Published by 学会事務局 on 10 10月 2022
本部企画シンポジウム – 2022年度大会(創立100周年記念大会)
産学連携委員会では、創立100周年記念第74回日本生物工学会大会(2022年10月17~20日、オンライン開催)にて、以下3件の本部企画シンポジウムを開催します。
未来産業の創造に向けた産学官連携プラットフォーム
- オーガナイザー:林 圭(三和酒類)・岡 賀根雄(サントリーホールディングス)
藤村 朋子(サントリーホールディングス)・明石 貴裕(白鶴酒造)
- 日時:2022年10月18日(火)13:30~15:30
⇒プログラム
【趣旨】第4産業革命は、産業界において同質的なコスト競争から付加価値の獲得競争への構造変化をもたらし、その変化は複雑、高度、そして速くなり続けている。産・学・官が、イノベーションの創出による新たな価値の創造に貢献していくためには、それぞれが互いを対等なパートナーとして認識し、新たな価値の創造を志向した本格的な連携が重要となっている。こうした背景を受け、産学官連携のプラットフォームづくりに第一線で関わっている先生方をお招きし、ご講演を頂くことにより、その認識を深め、未来産業に向けた新たな価値創造への一助としたい。
健康長寿に貢献するこれからの醸造発酵技術
- オーガナイザー:赤尾 健(酒類総研)・秦 洋二(月桂冠)・章 超(霧島酒造)
- 日時:2022年10月19日(水)16:00~18:00
⇒プログラム
【趣旨】醸造発酵食品の健康への寄与は、近年、社会に広く浸透している。今後、健康長寿がより一層希求される中で、醸造発酵技術の役割は、「効率的に産物を得る」という旧来の枠を超えて広がりつつあり、それに対する期待も大きい。本課題では、基礎レベルと商品開発の両面から、醸造発酵食品、機能性分子、関連微生物の生体作用に関する最近の成果を紹介し、健康長寿に寄り添った、これからの醸造発酵技術の可能性について考える機会としたい。
産学連携シンポジウム(培養・計測)
- オーガナイザー:児島 宏之(味の素)・今井泰彦(野田産研)
- 日時:2022年10月20日(木)13:30~15:30
⇒プログラム
【趣旨】培養・計測に関わる産学連携の取り組み事例をアカデミアと産業界のそれぞれの立場から紹介し、生物工学会が拓く未来社会に向けて達成すべき課題について議論する。
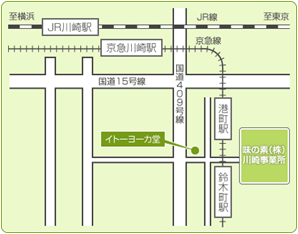
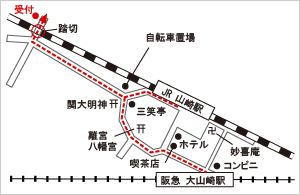



.gif)