Published by 学会事務局 on 26 5月 2025
【ご挨拶】100年先も輝く生物工学会の基盤を築く – 清水 浩

第25代会長
清水 浩
このたび、2025年度より日本生物工学会第 25代の会長を拝命することとなりました大阪大学情報科学研究科バイオ情報工学専攻の清水浩です。私が本会に最初に参加したのは大学院生の大会の時でした。熱い議論に感銘したのを覚えています。以来、35年あまり私の研究人生は本会活動がその中心にあります。微力ではございますが、副会長の青柳秀紀先生(筑波大学)、安原貴臣先生(アサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社)をはじめ強力な理事メンバーとともに学会の発展に努めたいと思います。
本会は、2022年に100周年を迎え、多くの皆様のお力添えを持ちまして無事100周年記念事業を終えました。改めて心よりお礼申し上げます。本会は1923年に大阪醸造学会として設立され、醗酵工学会を経て日本生物工学会と改名し現在に至っております。100周年記念誌に記されているように醸造に端を発し現在は生物工学の中心学会としての地位を築いています。次の100年後も輝く学会であり続けるために活動の継続と発展を進めたいと思います。
英文誌 Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)は 2023年の IFが2.3となり、生物工学分野の先端研究成果を発信する国際誌に発展しました。そのことは、日本の生物工学分野のプレゼンスを世界に示しております。皆様の引き続きの積極的な投稿をお願いします。和文誌はさまざまな特集や企画を通じて、読み応えのある記事を掲載発信し続けています。速報性が重要な情報はホームページへ移し、読み物としての魅力を大きくしたいと思います。
本会の大きな特徴の一つは、産学官の会員が情報交換を行うことにあり、大会や SBJシンポジウム、和文誌企画、さらには研究部会の活動を通じて新規研究分野のコミュニティの形成、活性化を支援したいと考えています。100周年を機に韓国生物工学会(KSBB)や台湾生物工学会(BEST)のみならず、ASEAN諸国の生物工学関連学会とも交流が始まりました。今後も大会の国際性など運営方法を議論していきます。
2025 年は改正公益法人法が施行されます。2011年公益法人として認可されて以来その趣旨に沿って着実な活動を行っており、公益事業としての活動や財政基盤の安定化が図られました。この度の改正にともなって外部理事・外部監事の任用など、より公正で開かれた学会として活動してまいります。
本年は学会事務局の体制が変化する時期でもあります。事務局長の定年退職をはじめ事務員が数年の間に異動するため、新たな事務局長、事務員を迎えました。また、これと同時期に会員情報管理システムや大会運営システムの更新などにも取り組み各種活動の効率化を図っています。このような取組みは本部のみでは達成できませんが、すでに各支部のご理解も得て着手しております。今後も本部と支部が協力し、皆様の活動が行いやすくなるインフラを整え、本部・支部を問わず快適な運営につながっていければと考えています。人やシステムが変わる時期にあたり、ひと時ご不便が生じる可能性がありますが、皆様の温かいご支援をお願いします。
100年後の生物工学会はどのように発展しているでしょうか。現在の地球規模の問題や医療、健康、食糧などの社会課題を乗り越えるため、生物工学は日本や世界を支えるキーテクノロジーの一つとして期待されています。基礎および応用研究において分野の垣根を越えて AI や情報、分析科学、ナノテクノロジー、ロボティクスなどなど、さまざまな分野との融合が起こりつつあります。イノベーションは分野どうしの境界で生まれ、発展するとも言われています。これらを生み出す源泉は会員皆様の中にあり、学会内外の分野とのネットワーク形成にあると思います。本会が生物工学分野の魅力のある学会であり続けられますよう、尽力したいと思います。会員の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
2025年5月
日本生物工学会会長
清水 浩
【歴代会長挨拶】
- 秦 洋二(2023年6月)
- 福﨑 英一郎(2021年6月)
- 髙木 昌宏(2019年6月)
- 木野 邦器(2017年6月)
- 五味 勝也(2015年6月)
- 園元 謙二(2013年6月)
- 原島 俊(2011年6月)
- 飯島 信司(2009年6月)
- 塩谷 捨明(2008年9月)

 2021年度より、日本生物工学会会長を拝命することになりました大阪大学大学院工学研究科の福﨑英一郎です。思い起こせば、大学院学生だった1984年に日本生物工学会の前身である日本醱酵工学会で口頭発表させていただいたことが当学会との出会いでした。それから数えて37年間お世話になり続け、御恩のある本会が、2022年には創立100周年という節目の時を迎えます。めぐり合わせに感謝するとともに、恩返しのために粉骨砕身努力する所存です。
2021年度より、日本生物工学会会長を拝命することになりました大阪大学大学院工学研究科の福﨑英一郎です。思い起こせば、大学院学生だった1984年に日本生物工学会の前身である日本醱酵工学会で口頭発表させていただいたことが当学会との出会いでした。それから数えて37年間お世話になり続け、御恩のある本会が、2022年には創立100周年という節目の時を迎えます。めぐり合わせに感謝するとともに、恩返しのために粉骨砕身努力する所存です。
 この度、日本生物工学会会長として選任されました早稲田大学理工学術院の木野邦器でございます。醸造・発酵工業のパイオニアとして世界のバイオ産業を牽引してきた我が国にあって、100年に近い歴史を誇る伝統ある日本生物工学会の会長を拝命致しますことは、誠に光栄なことではありますが、その使命と重責を担うことに身の引き締まる思いがします。高木昌宏、川面克行の両副会長をはじめ、理事、支部長、代議員、そして会員皆様のお力添えをいただきながら、先人達の築いてこられた本会の一層の発展に尽力して参りたいと存じます。
この度、日本生物工学会会長として選任されました早稲田大学理工学術院の木野邦器でございます。醸造・発酵工業のパイオニアとして世界のバイオ産業を牽引してきた我が国にあって、100年に近い歴史を誇る伝統ある日本生物工学会の会長を拝命致しますことは、誠に光栄なことではありますが、その使命と重責を担うことに身の引き締まる思いがします。高木昌宏、川面克行の両副会長をはじめ、理事、支部長、代議員、そして会員皆様のお力添えをいただきながら、先人達の築いてこられた本会の一層の発展に尽力して参りたいと存じます。 この度、日本生物工学会会長という大任を拝することになりました東北大学大学院農学研究科の五味勝也でございます。あらためて私と生物工学会との関わりについて思い起こしますと、大学院修士課程修了後に国税庁醸造試験所に配属になった30数年前に、大阪の日本生命中之島研修所における年次大会に参加するため本会(当時は日本醗酵工学会)に入会してからのお付き合いになります。中之島研修所は宿泊所も兼ねており、自分の部屋から直接会場に行くことができて非常に便利だったのを懐かしく思い出します。その当時はまだ大会での発表数や会員数もそれほど多くなかったかと思いますが、その後のバイオテクノロジー関連の研究分野の拡大に伴い、年次大会の発表数は750件、会員数は一般会員・学生会員合わせて3000名を越えるような大きな学会に発展してきました。
この度、日本生物工学会会長という大任を拝することになりました東北大学大学院農学研究科の五味勝也でございます。あらためて私と生物工学会との関わりについて思い起こしますと、大学院修士課程修了後に国税庁醸造試験所に配属になった30数年前に、大阪の日本生命中之島研修所における年次大会に参加するため本会(当時は日本醗酵工学会)に入会してからのお付き合いになります。中之島研修所は宿泊所も兼ねており、自分の部屋から直接会場に行くことができて非常に便利だったのを懐かしく思い出します。その当時はまだ大会での発表数や会員数もそれほど多くなかったかと思いますが、その後のバイオテクノロジー関連の研究分野の拡大に伴い、年次大会の発表数は750件、会員数は一般会員・学生会員合わせて3000名を越えるような大きな学会に発展してきました。.jpg) この度、日本生物工学会会長に就任いたしました九州大学大学院農学研究院の園元謙二でございます。90年を超える伝統を誇る由緒ある日本生物工学会の会長の重責を拝命し、身の引き締まる思いがいたします。理事、支部長、代議員をはじめ会員の皆様のお力添えをいただき、本会の発展に微力ながらお役に立ちたいと思っております。
この度、日本生物工学会会長に就任いたしました九州大学大学院農学研究院の園元謙二でございます。90年を超える伝統を誇る由緒ある日本生物工学会の会長の重責を拝命し、身の引き締まる思いがいたします。理事、支部長、代議員をはじめ会員の皆様のお力添えをいただき、本会の発展に微力ながらお役に立ちたいと思っております。.jpg)
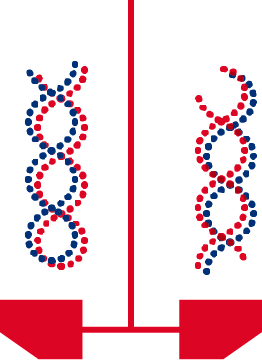
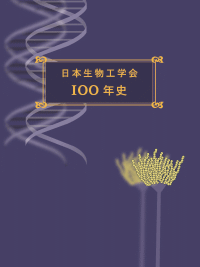
 本学会は1923年大阪で日本醸造学会として誕生し、爾来さまざまな変遷を経て、1992年現在の学会名、日本生物工学会となりました。学会としては古い歴史を持ち、2002年には創立80周年記念を祝うことができました。最初の学会名が示す通り、当初はアルコールや味噌醤油などの発酵食品を対象としていましたが、わが国のバイオ産業の発展につれ、微生物生産のみらず酵素、生理活性物質、植物、動物細胞や環境バイオテクノロジーなどが学会の守備範囲となってきました。21世紀、バイオの時代になるとポストゲノム、ナノバイオ、再生医療や組織培養を含む医薬バイオ、なども当学会の対象となってきています。
本学会は1923年大阪で日本醸造学会として誕生し、爾来さまざまな変遷を経て、1992年現在の学会名、日本生物工学会となりました。学会としては古い歴史を持ち、2002年には創立80周年記念を祝うことができました。最初の学会名が示す通り、当初はアルコールや味噌醤油などの発酵食品を対象としていましたが、わが国のバイオ産業の発展につれ、微生物生産のみらず酵素、生理活性物質、植物、動物細胞や環境バイオテクノロジーなどが学会の守備範囲となってきました。21世紀、バイオの時代になるとポストゲノム、ナノバイオ、再生医療や組織培養を含む医薬バイオ、なども当学会の対象となってきています。

.gif)