Published by 学会事務局 on 26 5月 2025

第25代会長
清水 浩
このたび、2025年度より日本生物工学会第 25代の会長を拝命することとなりました大阪大学情報科学研究科バイオ情報工学専攻の清水浩です。私が本会に最初に参加したのは大学院生の大会の時でした。熱い議論に感銘したのを覚えています。以来、35年あまり私の研究人生は本会活動がその中心にあります。微力ではございますが、副会長の青柳秀紀先生(筑波大学)、安原貴臣先生(アサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社)をはじめ強力な理事メンバーとともに学会の発展に努めたいと思います。
本会は、2022年に100周年を迎え、多くの皆様のお力添えを持ちまして無事100周年記念事業を終えました。改めて心よりお礼申し上げます。本会は1923年に大阪醸造学会として設立され、醗酵工学会を経て日本生物工学会と改名し現在に至っております。100周年記念誌に記されているように醸造に端を発し現在は生物工学の中心学会としての地位を築いています。次の100年後も輝く学会であり続けるために活動の継続と発展を進めたいと思います。
英文誌 Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)は 2023年の IFが2.3となり、生物工学分野の先端研究成果を発信する国際誌に発展しました。そのことは、日本の生物工学分野のプレゼンスを世界に示しております。皆様の引き続きの積極的な投稿をお願いします。和文誌はさまざまな特集や企画を通じて、読み応えのある記事を掲載発信し続けています。速報性が重要な情報はホームページへ移し、読み物としての魅力を大きくしたいと思います。
本会の大きな特徴の一つは、産学官の会員が情報交換を行うことにあり、大会や SBJシンポジウム、和文誌企画、さらには研究部会の活動を通じて新規研究分野のコミュニティの形成、活性化を支援したいと考えています。100周年を機に韓国生物工学会(KSBB)や台湾生物工学会(BEST)のみならず、ASEAN諸国の生物工学関連学会とも交流が始まりました。今後も大会の国際性など運営方法を議論していきます。
2025 年は改正公益法人法が施行されます。2011年公益法人として認可されて以来その趣旨に沿って着実な活動を行っており、公益事業としての活動や財政基盤の安定化が図られました。この度の改正にともなって外部理事・外部監事の任用など、より公正で開かれた学会として活動してまいります。
本年は学会事務局の体制が変化する時期でもあります。事務局長の定年退職をはじめ事務員が数年の間に異動するため、新たな事務局長、事務員を迎えました。また、これと同時期に会員情報管理システムや大会運営システムの更新などにも取り組み各種活動の効率化を図っています。このような取組みは本部のみでは達成できませんが、すでに各支部のご理解も得て着手しております。今後も本部と支部が協力し、皆様の活動が行いやすくなるインフラを整え、本部・支部を問わず快適な運営につながっていければと考えています。人やシステムが変わる時期にあたり、ひと時ご不便が生じる可能性がありますが、皆様の温かいご支援をお願いします。
100年後の生物工学会はどのように発展しているでしょうか。現在の地球規模の問題や医療、健康、食糧などの社会課題を乗り越えるため、生物工学は日本や世界を支えるキーテクノロジーの一つとして期待されています。基礎および応用研究において分野の垣根を越えて AI や情報、分析科学、ナノテクノロジー、ロボティクスなどなど、さまざまな分野との融合が起こりつつあります。イノベーションは分野どうしの境界で生まれ、発展するとも言われています。これらを生み出す源泉は会員皆様の中にあり、学会内外の分野とのネットワーク形成にあると思います。本会が生物工学分野の魅力のある学会であり続けられますよう、尽力したいと思います。会員の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
2025年5月
日本生物工学会会長
清水 浩
⇒歴代会長・副会長
【歴代会長挨拶】
【生物工学会誌 巻頭言】
- 清水 浩 [第104巻第1号(2026年1月)]
- 秦 洋二 [第102巻第1号(2024年1月)]
- 福﨑 英一郎 [第100巻第1号(2022年1月)]
- 髙木 昌宏[第98巻 第1号(2020年1月)]
- 木野 邦器[第96巻 第1号(2018年1月)]
- 五味 勝也[第94巻 第1号(2016年1月)]
- 園元 謙二[第92巻 第1号(2014年1月)]
- 原島 俊[第90巻 第1号(2012年1月)]
- 飯島 信司[第88巻 第1号(2010年1月)]
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧はこちら
学会について
Published by 学会事務局 on 25 12月 2024
生物生物工学会誌 第102巻 第12号
近藤 昭彦
月日の経つのは本当に早いもので、筆者も今年65歳、本年度末に大学を定年退職となる。「光陰矢の如し」「少年老いやすく学成り難し」を実感する。40年弱、大学や国立研究機関で研究を続けてきたが、感想を一言で言えと言われるなら、「面白かった」である。確かに寝る時間を惜しんで研究や申請書作成に使った時間を単純に楽しんだわけではないが、やはり「面白かった」である。苦労をすればするほど、良い論文ができあがった時や、大きなプロジェクトが採択されて研究が始められる時の喜びは一層大きなものである。幸せの定義は、実は単純であると読んだことがある。「一番幸せな瞬間は、苦労を重ねた結果として当初の思いが達成されて、周囲の人からも賞賛される時である。楽して手に入れたものは、大金であれ名誉であれ、真に幸せを感じるわけではない」と。まさにこうした幸せの瞬間を多く味わってきたが、多くの研究者で共通の感想ではあると思う。その中で多くの大切なことを学んできたが、若い人の参考になればとの思いで、自分の研究者人生の中で大切だったと思う三つのトピックス(学び)を書いてみた。
一つ目は、幅広い海外での体験の大切さである。幸いにも30代前半に、一年間ストックホルムのスウェーデン王立工科大学に留学できた。その後も、多くの二国間交流事業などに加えていただき、世界を回って研究の議論や文化を楽しむことを身に着けることができた。現在までに 200回を超える海外渡航をし、世界中で学会参加や研究機関・企業訪問を行い、議論や会食を楽しんできた。村的な研究に陥らないよう、視野を広げていくという意味で、研究面にも大きなプラスとなっている。また、世界で認められるためには、研究のユニークさとインパクトの大きさを追求し続けなければならないが、その感性を磨くことができた。さらに、研究成果を英語でインパクトのある形で発表することを追求することは、プレゼン能力のブラッシュアップにも大いに役立ったと思う。
二つ目は、各種大型研究に参加させていただいたことである。30代後半に、当時としては破格の大きさのNEDO産学官連携プロジェクトに参加する機会を得た。ここで、基礎研究だけでなく、基礎研究から社会実装までを産学官で連携して行うことの楽しさやプロジェクトマネジメントの重要性を学んだ。また、自分の手元だけの小さな研究構想だけでなく、社会の変革をどうすれば実現できるかという大きな視点から研究プロジェクトを構想することの重要性を学んだ。さらに、新しい研究課題に大胆に挑むという挑戦者の神を得たと思う。社会課題の解決には、どうしても新しい研究課題に大胆に挑まなければならないが、この時、よく言われるように、「少し鈍感に、また限定的ないい加減さを持って、失敗を恐れずに挑戦する」ことは大事だと思う。
三つ目は、研究人生の後半でアントレプレナーシップの大事さを学んだことである。50代中盤に神戸大学で科学技術イノベーション研究科を立ち上げて研究科長として運営する任務を与えられた。社会科学系の先生とともにアントレプレナーシップを兼ね備えた理系人材の育成を目指した。アントレプレナーシップの重要性は現在では広く認識されているが、当時の私には新鮮であった。スタートアップ(SU)の起業や、企業での新規事業創出のみならず、大学の研究者にも大事だと思う。なぜなら、「少ないリソースで、信じられないほど大きなインパクトを創出する」理念は、研究でもとても大切と思うからである。研究科の学生に実例を見せる意味からも、筆者は今まで6社のSUを立ち上げてきたが、現在も新たな SU の起業を構想中である。日本が世界と伍していけるように産業競争力を上げる観点から、グローバルSUを如何に増やすことができるか、まさに正念場である。
昔、65歳では引退的な雰囲気になっているのかと思っていたが、想像とはまったく異なり、アントレプレナーシップを持って新たな仕事に挑戦しようという楽しい気分である。大事なのは「熱量」と「ハングリー精神」!人生100年時代と言われて久しいが、面白いと思うこと、ワクワクできることを可能な限り続けていきたいと思っている。
著者紹介 神戸大学(副学長)、神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科(教授)、
理化学研究所環境資源科学研究センター(副センター長)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 11月 2024
生物生物工学会誌 第102巻 第11号
髙木 博史
いきなり私事で恐縮だが、今年(2024年)5月下旬に1週間近くNew Yorkに滞在し、企業在籍時(1986年)の海外派遣でご指導を受けた井上正順教授(当時New York州立大学Stony Brook校)の最終講演を含むシンポジウムに出席した。基本的にアメリカの大学には教授職の定年はないが、井上先生も今年90歳を迎えて正式にRutgers大学Robert Wood Johnson医学部を退職され、家族でHawaiiに移住される予定である。先生のようなCuriosity-driven Scientist(学部長に就任後も「大腸菌はどれくらいのサイズのタンパク質まで生産できるのか?」というワクワクする実験をされていた)を理想としてきた筆者も年齢を重ねたことに改めて気づいた。
筆者は昨年3月末に本学の教授を定年退職したが、特任教授として数名のスタッフと新しいラボを立ち上げ、企業との共同研究を中心に発酵科学に関する基礎・応用研究に取り組んでいる。また、産官学連携を推進する部門の役職も継続し、本学や本学会に微力ながら貢献できればと考えている。個人的には研究成果の創出と社会への還元とともに、若手・中堅の人たちの仕事やキャリアパスをサポートしていきたい。一方で、定年退職を機にいわゆるセカンドキャリアのステージに入ったが、教育(研究指導、授業など)の恒常的業務がなくなり一抹の寂しさはあるものの、PIとして研究費を獲得し、ラボの運営に奔走する状況は変わらず、その実感はない。
「人生100年時代」のセカンドキャリアは人それぞれである。筆者の場合、これまでの研究・技術シーズや人的ネットワークを活用した社会実装の経験をもとに、「シニア起業」への挑戦を考えている(恥ずかしいのでここだけの話です)。折しも、政府が「スタートアップ育成5か年計画」を策定し(2022年11月)、スタートアップに対する支援が加速している。本学においても情報科学系の教員や学生は起業意識が高く、筆者は大学発スタートアップの認定に関する規程を作成するなど起業を推奨する立場にある。また、本誌では筆者より若い先生が大学発ベンチャーや副業の経験を紹介されており、その意欲と行動力には敬意を表する。しかし、いざ自分が起業に向けた検討や準備を始めると容易ではない。「案ずるより産むが易し」かもしれないが、若い人にアドバイスを求められると、人生は自分で決めた道が正解、行動する勇気・行動しない勇気、仕事はどこで行うかではなく、何を行うかが大切、「今がふるさと」の気持ちが大事、などと偉そうなメッセージを送ってきた自分が情けない。
ベンチャーとスタートアップの大きな違いはビジネスモデルである。ベンチャーは既存のビジネスモデルをもとに、売上や収益性を拡大していくが、スタートアップは革新的なアイデアで新しいビジネスモデルを構築し、短期的に成長する企業である。また、スタートアップには事業の革新性・成長率・EXIT(出口戦略)・資金調達法などに工夫や計画性が求められる。そのためには、起業マインド・明確なビジョン・冷静な決断力・高い先見性・優れた統率力・前向きで柔軟な発想力・強靭な精神力などの資質を備えたうえで、目的・目標・課題を設定する能力および人・物・金・情報などの経営資源を動かす能力を有する経営者人材の確保と育成が必須である。また、研究開発型のスタートアップを目指す場合、事業化のための研究開発を先導する若手・中堅の研究者・技術者の確保と育成が重要である。さらに、アメリカのようにベンチャーキャピタルやアクセラレーターからの投資を積極的に受けるためには、研究者は常にアンテナを高くして人脈を広げる努力を行うとともに、大学側も利益相反の制限を緩和し、研究者が失敗を恐れず起業しやすい制度や雰囲気になればと、甘い?考えを持っている。
長々と書いてしまったが、セカンドキャリア後のサードキャリアについてはしっかりと設計している。アメリカ野球を愛する者として1)、来年(2025年)は日本人初のアメリカ野球殿堂入りに選出される可能性が高いイチローの表彰式が行われ、また日米の150年以上に渡る野球交流史を紹介する企画展も始まるアメリカ野球殿堂博物館(National Baseball Hall of Fame and Museum)を約30年ぶりに訪問し、自らの就職活動?を頑張りたい。
1) 高木博史:化学と生物,59, 417 (2021).
著者紹介 奈良先端科学技術大学院大学研究推進機構(特任教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 10月 2024
生物生物工学会誌 第102巻 第10号
芦内 誠
小職は高知大学生命環境医学部門に所属しています。当方部門の名称にもある「生命」「環境」について自らが理解できているか(正直にいえば)不安に思うところがありました。今回の「巻頭言“随縁随意”」は思い切って「いのち」をテーマにします。サイエンティフィックな哲学“おちこち”にお付き合いいただければ幸いです。
ところで、「生命」と「生物」、また「環境」と「生態」について本質的な違いを認識したうえで表現することを意識されていますか?いわゆる「理系」的なフィールドにいると何やら曖昧になって、ともすると「同一性」のバイアスに支配されることも少なくないように思います。小職が偶々参加したセミナーの席での件、講師からの『生物にはどのような特徴がありますか?』との質問に対し、参加者の一人から『自立的に増殖する存在』との答えがあったのを記憶しています。セミナー講師は地球微生物学を専門としていましたので、すかさず『深海底生命圏には10万年、ひょっとすると億年単位で時を経ても姿を変えず、増えようともしない生命体が存在する。このような存在を果たして生物と呼べるのか?』と問いかけました。私はこの核心的な問いから、大いなる気づきを頂いたように思っています。もう少し踏み込みますと、時間の長さに対する認知バイアスの存在、加えて「生命」ではなく「生命体」と表現したこと、まさに「言い得て妙である」と感服したことを思い出します。
釈迦に説法のようで恐縮ですが、ハイデガーの主著『存在と時間』は「生命」と「生物」の違いを言語化するうえで大いに役立ちます。生命は存在であって存在者ではありません。逆に生命体は存在者であって存在ではありません。その複製体を高速で作り出せるようになった特殊な生命体「生物」も然りです。存在者には実体があり、一方で存在そのものに実体はありません。ハイデガーの存在論がアインシュタインの一般相対性理論にも影響を与えたことは有名です。実際、『存在と時間』の主題は「存在を時間によって理解する」ことでしたので納得です。
ただし、生命(いのち)に潜在する「時間性」の意味をより理解するにはもう一工夫必要かとも考えています。ハイデガーなる真理の探究者(現存在)は「死」という絶対的可能性(時間性のなかに潜む結果)を傍らに置くことで「存在」することの意味を理解しようと試みます。小職は前出の問答から『生命(いのち)とは時(とき)に抗う存在』ではないかと気づきました。すなわち、「結果」ではなくそこに至るまでの「過程」にこそ、生命に足りうる本質が存在するのです。本件を理解するうえで格好の題材が「テセウスの船」と考えます。あまりにも有名な哲学パラドックスですので詳細は割愛しますが、たとえば、人体は60兆個の細胞でできており1日で約1兆個の細胞を入れ換えます。約2か月後、今のあなたは存在論的な「死」を迎え、生命の基本の細胞レベルで見れば、ほぼ完全に別人のあなたが「命」をつないでいることになります。それでも、あなた(現存在)は未来のあなたを自分だといえますか?逆に、先進再生医療技術によって現在の細胞から正確に生み出されたあなたのクローンは、それでも、あなた(現存在)と同一であるといえますか?存在論上の絶対的可能性に抗うからこその生命であり、故に、存在論は生命を理解するうえできわめて重要な哲学ではある一方、さらなる深化を求めるには不足しているといわざるを得ません。終局、新たな「生命論」を必要とする時代に突入したとの認識に間違いはないようです。
最後に、難培養微生物群の存在と環境保全の方向性についての考えを述べたいと思います。地球上に存在する微生物の総数は1030個といわれ、固定化された生物利用(循環)可能な炭素量(イエローカーボン)は植物が固定している炭素量(グリーンカーボン)に匹敵します。特に重要視すべきは、難培養微生物が大半(> 99 %)を占めるという事実です。したがって、微生物の生存戦略は大量のエネルギーやバイオマスを要する「増殖(バイオ異化)」ではなく「修復(バイオ同化)」に特化していることを意味します。現在、生分解性が環境保全の切り札とされていますが、炭素循環の主役である難培養微生物群への影響が不分明な段階での拙速な環境利用は避けた方が無難かと思います。
著者紹介 高知大学教育研究部総合科学系生命環境医学部門(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 9月 2024
生物生物工学会誌 第102巻 第9号
紀ノ岡 正博
シニアの教授の仲間入りをする年齢となり,自分が進めてきた研究はどの学問領域で,どのような貢献をなしてきたか,さらに,今後どこまで進められるのであろうかと問うことが多くなってきました.そこで,最近思うことを,自問自答しながら,語弊を恐れずに述べてゆきたいと思います.
私自身は,専門としての生物化学工学を,生物的な物事(対象)を系としメカニズムを仮定し解釈する活動と捉え,学問の体系化を進めつつ,研究としての技術構築(モノづくり),それを活かすための決め事(ルールづくり),そして,伝える努力(ヒトづくり)からなる「コトづくり」いわゆる社会実装に活かしてゆきたいと思ってまいりました.
昨今の社会実装では,産(民間企業),学(教育・研究機関),官(国・地方自治体),民間(地域住民・NPO)など,ステークホルダーの多様化により,大学における他との連携の在り方が大きく変わっております.たとえば,再生医療や細胞治療などの新たな医療技術の産業化では,私どもの研究対象である「細胞製造」が重要となりますが,学問が未熟で,学問構築と社会実装が同時進行する必要があり,人,情報,技術,分野をつなぐ仕組みを持つセンス良いチーム形成が不可欠であります.良いチーム形成には,受動的な活動ではなく,一人ではできないことを意識し,「良いお節介」ができる環境づくりが大切であると感じております.そこで,「良いお節介とは?」と問いながら,産学官民が協力し,教育・研究・産業化・生活に対する活動を可能とするエコシステムを形成することで,新技術産業領域に対して開発の方向性(ロードマップ)を明確にし,固有の概念・技術を構築ならびに迅速な産業化活動を行う必要があると思います.私は,教員として,学問の体系化の活動を怠ることなく,専門性を高め,次世代へつなぐことが重要な役割の一つであると思い活動しております.その際,諸先輩が築き上げてきた学問体系を読み解き,歴史を感じながら,新たな言葉や概念を加えようと挑むことは,至上の楽しみであり,同世代の仲間と,体系化の考え方を比較し,議論することで,楽しみを分かち合え,学問に磨きをかけるものと信じています.昨今は年齢層を超えたこのような活動が減ってきているように感じ,学会活動の中でも重視することを提案してゆきたいと思います.
さらに,研究を通し学問を進めることの楽しさを次世代へ紡いでいくことができればと思います.楽しみには,習うこと(学問の理解),見いだすこと(発見),創ること(技術創出),築くこと(技術構築),考えること(体系化),伝わること(技術伝承),変えること(変革),つかわれること(社会実装),育むこと(教育)などが挙げられ,各自が興味を持ち寄り醸成することで学問を育むことができると思います.
この楽しみは,時には苦に感じることもありますが,子供たちを育むことと同様,「楽しく思い挑み続ける能力」を身に着けた者が学問を育めるものだと思います.この能力は,やりぬいてこそわかること(グリット),いろいろ経験してうまれること(セレンディピティ),溢れる情報から取捨選択し,大切なことを留めること(鈍力・鋭力),負けたら再度挑戦すればよいこと(リベンジ),自分は無知であることを認め周りに聞くこと(頼る力),話にオチを考え,面白く,筋を通すこと(ひねる力)からなると考えており,日々の研究において意識していれば自然と身につき,学問の発展に挑み続ける原動力になると信じております.
最後に,思いのままに述べる機会を与えていただきました学会の皆様に感謝したいと思います.今後,私は,目の前の研究も大切ですが,学会活動を通して,自分の中で研究の流れを体系化し,次世代に伝えたいと思います.また,皆様におかれましては,よかったら一緒に,学問を楽しみ,発展に挑み続けませんか.日本生物工学会へ「良いお節介」をしませんか.
著者紹介 大阪大学大学院工学研究科(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 8月 2024
生物生物工学会誌 第102巻 第8号
阿座上 弘行
本誌第102巻第2号のBranch Spirit 1)でも触れましたが、筆者は2年前から山口大学の中高温微生物研究センターのセンター長をしています。皆さん、中高温微生物についてどのようなイメージをお持ちでしょうか?筆者らは通常の至適温度で生育する常温菌よりも5–10 °C高温で生育可能な微生物、すなわち概ね40–50 °Cで生育する微生物、あるいはその温度帯に対して耐性を持つ微生物が新規な微生物の一群を形成していることを見つけ、「中高温微生物」と名付けて、その研究を続けてきました。これまで多くの研究者は、常温菌以外では好冷菌や好熱菌、超好熱細菌などいわゆる極限環境微生物に注目してきました。本センターは、長年にわたる東南アジアの研究者との広範な共同研究・研究交流によって、熱帯環境から、我々ヒトの生活に密接に関わっている常温性の発酵・環境・病原微生物でありながら耐熱性や微好熱性を有する微生物を分離・蓄積し、日本でも有数なライブラリーを整備してきました。
本センターは、これらの「中高温微生物」群の至適温度特性を発酵の冷却コストの低減に応用する研究などを世界に先駆けて進めてきました。それと並行して、この特性のメカニズムについて基礎的・基盤的研究を進め、耐熱性細菌から「耐熱性遺伝子」群を発見するとともに、耐熱性酵母の中に高温において独自の代謝戦略をとるものがいることを見いだしました。したがって、「中高温微生物」が有する5–10 °C高温での増殖能は、熱帯環境で獲得された特別な生存戦略であると言えます。このように、「中高温微生物」はそのゲノムに常温菌とは異なる「環境適応」のための独特の分子メカニズムを獲得しており、これが「中高温微生物」の「耐熱性」の要因であることが明らかになってきました。非常に高温であった原始地球が次第に冷えてきたことで繁栄してきた常温菌が、熱帯環境に適応するために獲得した耐熱性とその要因である環境適応分子メカニズムは科学的に非常に興味深いものです。
しかし、常温菌の中には短期間での大幅な地球温暖化に適応できないものもいることが予想され、それらの淘汰は物質循環に悪影響を及ぼす可能性が危惧されています。したがって、これまでの進化の過程で「中高温微生物」が環境に適応してそのゲノム配列に刻んできた「環境適応能力」の利用をはじめ、人類にとってこれからきわめて重要となる「中高温」温度域での微生物研究の進展が注目されます。さまざまな分野で、その「環境適応能力」を基礎科学的に解明していきながら、「中高温微生物」研究で解明された知見を含めて広範な基礎科学分フィードバックすると同時に、応用科学分野にも利用していくことが期待できます。それ故、「中高温微生物」が持つ「環境適応能力」由来のさまざまな機能の解明やその利活用について、従来の微生物科学の領域に留まらない、新たな、かつ独自の研究領域の開拓が求められています。
当センターでは。東南アジアの熱帯環境から、発酵・環境・病原微生物を採集・分離・整理・保存・蓄積し、2,800株の耐熱性微生物を含む中高温微生物カルチャーコレクションを整備してきました。さらに、長年交流のあるタイのカセサート大学のバイオダイバーシティセンターと協力し、カセサート大学が保有する2,000株以上の熱帯性環境微生物を含むカルチャーコレクションの相互利用などが行えるシステムを構築してきました。現在、お互いのコレクションの情報をデータベース化することで、カルチャーコレクションとそのデータをONE-STOPで一体的に利用できるように整備を進めています。皆様のご研究に是非当センターの中高温微生物リソースをご活用ください。
また、近年、当センターでは、奈良先端科学技術大学院大学とMTA契約を締結して、森浩禎先生(奈良先端科学技術大学院大学名誉教授・現当センター客員教授)が作成された大腸菌網羅的解析リソース(KeioコレクションやASKAライブラリー、ASKAバーコード欠損株コレクションなどを含む)の保管・管理も始め、企業などを含めた研究機関への分譲体制も整えました。こちらのリソースの利用をご希望の場合も是非ご連絡ください。
1) 阿座上弘行:生物工学会誌,102, 86 (2024)
著者紹介 山口大学 大学研究推進機構 中高温微生物研究センター(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 7月 2024
生物生物工学会誌 第102巻 第7号
上田 誠
40年ほど昔、大学院博士前期課程1年だった私は、和文の学術誌で「バイオコンビナート」に関するコラムを読んだ。記事は、バイオテクノロジーの飛躍的な発展により、バイオマスを原料とした微生物によるエネルギー物質や化学品を製造するバイオコンビナートが将来実現するかもしれない、といった内容であった。
1980年代は組換えDNA技術が農学や工学系の大学や企業の研究室で普及し、大腸菌での有用タンパク質の異種発現など生物機能の改変や向上が注目されていた。そのコラムにおいても、華々しい生物工学の進歩により、供給に不安のある原油を原料(第二次オイルショック後であった)とする石油化学コンビナート(オイルリファイナリー)から再生可能なバイオマスを原料としたバイオリファイナリーへの原料転換の期待を込めたのであろう。私の修論テーマは「有機溶媒中の微生物反応」で、ヘキサンなどの有機溶媒中で水に混和しない脂溶性の物質の微生物変換を研究室で試行錯誤していた。リパーゼなどの加水分解酵素は有機溶媒存在下でも活性を示し、反応平衡をコントロールしたエステル合成やエステル交換といった産業利用例も後に開発されることになるが、多くのタンパク質を生理的でない疎水環境下で機能させるのは難しい課題であった。この経験から、生体中の多様な酵素を制御し、効率よく物質生産するバイオコンビナートの実現は難題だろうと学生ながら感じた。
博士前期課程修了で企業に就職することを決め、2年の春に三菱化成(現三菱ケミカル)の採用面接を受けた。面接の最後に「何か質問はありますか?」と聞かれたので、「将来、バイオコンビナートは実現するのでしょうか」と技術系面接官に尋ねた。「そりゃ無理だな…」と即答いただいたことが印象深く今でも覚えているが、その時、私は遠い未来への課題が自分に示された気がした。バイオコンビナートの実現に自分がどの程度貢献できるか予測できないが、少なくともバイオ関係の業務に就き「バイオものづくり」技術の進展を確認(ウオッチング)していくことを決めた。その後、私は、企業研究者からアカデミアに転職し、次代を担う人材育成が主なミッションとなったが、バイオプロセスに関する技術をウオッチングできる立場を継続している。
さて、この40年間でバイオコンビナートは実現したか? 1990年代のタンパク質の進化工学、2000年近くからの代謝工学、近年の生成AIを用いたタンパク質の設計など多くの要素技術は進歩しているが、代謝ルートを設計し、精密かつ柔軟な制御により微生物を望む状態で機能させることは現在でも難しい。日本の工業地帯は相変わらず石油化学コンビナートの風景だが、世界的にはバイオエタノールやバイオプラスチックの製造などのバイオリファイナリーが実現していることを前向きに受け止めたい(日本の貢献が少ないことが気になるが)。研究の進め方も大きく変わってきた。バイオプロセスでの微生物の育種というと個人的には斬新なアイディア、および粘りと頑張りの古いイメージがあるが、2000年以降のバイオプロセス開発においては、国家的な戦略と資本投下により先端技術を持つ技術者集団がロボティクスを活用してスマートセルを構築し、事業化を推進する時代となり、大学の研究室や企業が単独で技術開発できるレベルを超えている。
日本政府はスタートアップ人材の育成に力を入れている。私が所属する小山高専でも2023年度にスタートアップ教育環境整備事業に取り組み、学生が自由に活動できる起業家工房(試作スペース)と起業家マインドを熟成する教育プログラムを整備し運用を開始した。社会のニーズと政治・経済的な支援があり、社会的な課題にアプローチし解決のため行動する優れた人材により、バイオものづくり(=バイオコンビナート)が実現していくことと、日本生物工学会には、優れた若手が活躍できる社会的な雰囲気を醸す役割を期待したい。
著者紹介
京都大学 大学院農学研究科 産業微生物学講座(産学共同講座)(客員教授)
小山工業高等専門学校 物質工学科(嘱託教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 6月 2024
生物生物工学会誌 第102巻 第6号
章 超
「辰年」に入り、希望と機会に満ちた新たな始まりとなる。「辰年」は陽の気が動いて万物が振動し、活力旺盛になって大きく成長し「形が整う」年だといわれている。2023年までの長く苦しかった新型コロナウイルス禍がようやく明けた。貯め込んでいたエネルギーが爆発するかのように世の中が躍動している。日本生物工学会は2022年に創立100周年を迎えたが、辰年の2024年を次の時代へ向けて、明るく、楽しく、前向きに取り組み、学会の形をしっかりと整える1年としたい。
世界情勢や社会環境の変化が激しく、将来の予測が困難な現代は、volatility(変動性)、uncertainty(不確実性)、complexity(複雑性)、ambiguity(曖昧性)の頭文字をとって、「VUCAの時代」といわれる。このような時代において、我々(学会、企業、研究者)は急激な変化に対応して新たな価値を提供できるように変わっていく必要がある。そのために21世紀の経済社会における科学技術・学術の位置付けはこれまで以上に重要となる。技術の進歩とうまく付き合い、先端技術の実用化・商品化によって経済成長と新しい価値の創出を確実に実現していかなければならない。学会活動においては、情報共有・異業種との連携・技術の実用化および新しい価値の創造が求められる。私は産業界の人間であるが、学会活動を通してアカデミックの素晴らしい研究成果と優秀な人材に魅了されており、企業人として新しい技術の実用化・商品化への応用を大いに期待する一方、技術の産業転換と人材導入の難しさも深く感じている。本学会では、2023年度に産業界から初の会長が誕生した。これまで以上に研究者(学官)と企業(産)間の情報共有を密にし、お互いの課題解決を図ることを期待したい。私も理事の一人として産学官連携の架け橋として大切な役割を果たし、社会貢献に努めていきたい。
VUCAの時代に対応する一つの手段として、オープンイノベーションがある。2016(平成28)年に経団連が提言した「産学官連携による共同研究の強化に向けて」が背景となり、企業と企業だけでなく、企業と大学とのオープンイノベーションによる共創が加速している。この活動により業界や各立場を超えて革新的な製品やサービスを創造することができ、予測困難なVUCAの時代を生き抜くことが期待される。また国内市場の成長鈍化が見込まれる中、海外市場を急速に開拓し、グローバル化を進展させる必要がある。世界的レベルでの競争と共生のためには、海外への研究成果情報の発信、海外ニーズの把握が重要であり、さらにはコミュニケーション能力と新しい価値を創造する能力を持ったグローバル人材が必要と考える。こういう面においても学会には特に国外への技術交流・発信および人材推薦などに力を入れ、アカデミックや企業にとって価値のある活動をすることが期待される。
産学官それぞれの立場によって本質的に求めることは異なるだろう。産業界は新しい技術による事業課題の解決や競争的優位性を得ること、アカデミア関係者は企業が期待する技術・情報の提供と、研究成果の実用化による社会的・経済的な価値の獲得を求め、学生は自身が携わってきた研究成果が就職活動に役立つことを期待している。また公的機関においては科学技術の向上に繋がる研究基盤の構築や地域産業の活性化を求めている。学会としては産学官の架け橋として各関係者とうまく連携し、それぞれの期待に添うような手助けをしていきたい。そのためには理事会の力だけではなく、会員の皆様の協力が必要である。是非積極的に学会活動にご参加いただき、ご意見・ご助言を賜りたいと思う。
最後に、未来の学会活動の主人公となる学生の皆さんには大いに学会を利用していただきたい。学会で積極的に自身の成果を発表し、参加者と直接会話することで研究交流や情報収集を行い、自分の目線で企業の最新の技術や製品、サービスを体感しながら自分の将来像を思い描いて欲しい。
著者紹介 霧島酒造株式会社 研究開発部(課長)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 5月 2024
生物生物工学会誌 第102巻 第5号
田丸 浩
2023年はプロ野球が熱かった。WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)での14年ぶりの優勝に始まり、何といっても、故・新名惇彦先生が大好きであった阪神タイガースが38年ぶりに日本一になったのだ!俄かファンには申し訳ないが、大阪人にとって阪神タイガースは日常的に生活の中にある。39年前の1985年、当時、私は高校3年生であった。この年、阪神タイガースは初めて日本一になった。リーグ優が道頓堀川に投げ入れられた)。また2023年は、3年あまり猛威をふるった新型コロナウイルス感染症も5月8日に「5類移行」され、ようやく日常的な生活が戻ってきた。
さて、そもそも「プロ」はどのようにして生み出されるのか?「一芸に秀でる者は多芸に通ず」ということわざがある。何か一つの道に秀でる者は、他の道でも秀でるようになる、という意味である。将棋の藤井聡太8冠は将棋というゲーム、すなわち「一芸に秀でる者」の代名詞となっている。彼は若干21歳であるが、すでに前人未到の偉業を成し遂げている。一方、メジャーリーガー大谷翔平選手も2023年日本人で初めてホームラン王になるとともに、満票で2度目のMVPに選出され、これは大リーグ史上初の快挙であった。大谷選手の代名詞はご存知「二刀流」である。すなわち、メジャーリーガーの中で投打のバランスがもっとも良い選手、“ベーブ・ルース以来”の104年ぶりの偉業を成し遂げた訳である。まさに「投手大谷が勝つためには、打者大谷が打つしかない」と評されている。
さて、私が三重大学に着任して23年、教授に昇進して10年が経過した。カリフォルニア大学デービス校でポスドクをしていた時代は、「研究」だけできれば幸せであった。すなわち、研究者として「シングルタスク」が性に合うと今でも自負している。だが、2000年に帰国して、母校である三重大学の出身研究室に助手として採用されてからは、案の定“PAD: Post America Depression(命名:山中伸弥先生)”になった。つまり研究だけでなく、教育はもちろんのこと、管理運営、さらには社会貢献も要求される、まさに「マルチタスク」がプロの証という洗礼を受けた。今に思うと、この状況は三重大学に限った話ではなく、全国の大学で同じ状況になっていたと感じる。では、「マルチタスク」はただ大変なだけなのか?いや、そうとも言えない。現に、私は45歳で出身研究室の教授になれたし、「マルチタスク」は独創的な「二兎流の研究(二兎を追い、二兎を狩り、二兎を得る)」を実践する気づきを与えた。研究活動は自分自身が“面白い(おもろい)”と思えるテーマを見つけ出し、それに対して寝食を忘れて実験し、得られたデータから新規性や発見を見いだし、これらを考察した後に論文として発表する。すなわち、この一連の活動はまさに「マルチタスク」の成せる技であり、それが「プロフェッショナル(研究でお金を稼ぐ人)」に相当する職場であると考える。
そう考えると、ヒトの脳で処理していることは相当複雑なことであり、「シングルタスク」が楽であるとか、「マルチタスク」がしんどいとか、そう言う観念はもはやAIを超越した作業を長年にわたり繰り返すトレーニングのように思える。大学教員として、自分にしかできない研究を楽しんでやってきたと思うと、これまで歩んできた研究者としての人生はとても感慨深いものである。皆さん、感染症を克服して長生きしよう!
著者紹介 東北大学大学院工学研究科(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 4月 2024
生物生物工学会誌 第102巻 第4号
青柳 秀紀
私は、恩師の田中秀夫先生(筑波大学名誉教授)のご紹介で日本生物工学会とのご縁をいただき、大学4年生の時に第39回大会(1987年阪大)で初めて学会発表をいたしました。時が経つのは早く、約37年にわたり本学会にお世話になり続けております(長いようですが過ぎてしまいますとあっという間です)。非常に幸運なことに、本学会の創立100周年記念事業1)に参加させていただく貴重な機会を賜り、改めて、本学会の伝統と素晴らしさを感じると共に、本学会は、歴代の執行部、産官学の会員、事務局、関係する多くの皆様のご努力、熱い想い(愛情)、人と人とのつながりがベースとなり育まれてきたことを実感する場面が多くございました。生物工学の産官学に関わる最新情報を得るのみならず、本学会でのさまざまな活動を通じて、得られる経験、多様な世代、専門性、視点をもつ会員様とのご縁は素晴らしく、産学連携や共同研究にもつながることが多々あります。
1972年と2022年にローマクラブのレポート“The Limit to Growth”および“Earth for All: A Survival Guidefor Humanity”がそれぞれ発表され、SDGsが誕生しています。生命・環境・人間が調和した持続可能な未来社会の創造が必須であることは誰もが共通認識を持つようになり、バイオエコノミー社会の実現も謳われる中、次の100年に向け歩み始めた本学会が学界や社会に果たすべき役割への期待はますます大きくなっています。
2004年の独法化以降、講座制など大学の環境は変化し続け、現在、PIとして研究室運営をしている先生も多いと思います。私は講座制で11年間、PIとして16年間、大学に勤務しておりますが、PIには講座制とは異なる良い面がある一方で、課題もあるように感じております。また、研究(あるいは教育)では“ひらめき”が大切ですが、“ひらめき”は研究(あるいは教育)について考えに考えを重ね抜いた中で、「ぼおっとしている状態」の時に出ることが多いと言われています。もしかしたら日々に忙しい先生方には時間的、心の余裕がなく、“ひらめき”が出にくい面があるかもしれません。私は研究、教育にPI として取り組む中で、支部活動も含め、本学会で繋がりました多くの産官学の会員様にご相談に乗っていただき、ご助言をいただくことで、励まされ、助けていただきました(良いご縁に恵まれてまいりました)。
また、研究室の学生達と接する中で感じていることですが、最近は価値観が非常に多様化すると共に、さまざまな情報が簡単に手に入り非常に便利なのですが、逆にそのことについて深く考えて判断したり、推測したり、周りの人とそのことについて話す機会や、直接的な実験以外の議論(あなたはなぜ科学をするのか? 2))が年々、減っている感じがいたします。天然資源に乏しい日本において資源の一つは人であります。明治、大正時代の政治家 後藤新平(医師、拓殖大学学長)は「財を遺すは下、仕事を遺すは中、人を遺すを上とする」と遺しています。システムが変化しても組織や社会を構成しているのは人であり、その多様性が組織のポテンシャルに、考え方、目的意識や方向性のトータルが組織全体の活性に反映することに変わりはないと思います。このような現状の中、今後、生物工学に関する研究、教育、人材育成の面でも、本学会や支部が担う役割や重要性が増えてくると思います。また、他ではできないような長期的視点に立ち、議論できる場としての役割も重要だと思います。
私が大学院生の時に集中講義にいらっしゃいました著名な先生が、「オリジナルな研究をなさい。あまり流行を追わず自分が興味のあることをこつこつ続けるといつか花が開くものです」とお話しされていました。時代に合っているかはわかりませんが、個人的には大切だと想いますし、それが良いとも思っています。実際に、興味を持って実験に取り組む中で見いだした予期しない現象から研究が展開することが数多くあることも事実であります。実験中に予期しない現象に出会うことは、多くの研究者が経験していると思います。それを見逃さず、解明を進め、創造愉快に創意工夫してゆくと、新しい分野の開拓につながる場合が多いと思います。
以上、生物工学会とのご縁についてとりとめなく勝手な内容を書いてしまいましたが(ご無礼の段、お許しくださいませ)、ぜひ(特に若い皆様は)、今よりも一歩踏み込んで積極的に本学会に参加する(参加し続ける)ことをお薦めいたします(良いご縁に恵まれますよ)。今後ともご指導ご鞭撻、幾久しく宜しくお願い申し上げます。
1) 日本生物工学会「創立100周年記念事業」: https://www.sbj.or.jp/centennial/(2024/1/22).
2) Nature, Career Column (04 January 2024): https://www.nature.com/articles/d41586-024-00011-0 (2024/1/22).
著者紹介 筑波大学 生命環境系(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 3月 2024
生物生物工学会誌 第102巻 第3号
藤井 力
家族に高リスク者がいるので気をつけていたのに、ついに新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に感染してしまった。今年度再開し、楽しみにしていた「真核微生物交流会」にも行くことができなかった。
COVID-19が長く流行しているのは、ヒトに感染する機会が豊富で変異を繰り返しているからにほかならない。正確にいうと「変異を繰り返す」わけではなく、ウイルスは一定割合で変異するが、多くの人に感染し、いろいろな種類が生まれ、多様性が増え、最適株が増殖し、それまでの株に置き換わる。ウイルスは「次こうやって感染力をあげよう」と考えているわけではなく、ポンコツで淘汰される変異も多いが、免疫を偶然すり抜けやすくなったり、放出される時期が偶然発症前になったりするなどして、選択圧に対し最適な株に置き換わる。高校の生物の授業で、工業の発展に伴い、淡い色のオオシモフリエダシャクが暗色に置き換わる工業暗化という現象を習ったが、多様な種類から選択されたものが優占するという仕組みは同じ。多様性があれば、選択圧で最適株が選ばれる。オオシモフリエダシャクの多様性獲得(≒最適株の創出)の源泉は有性生殖であるが、ウイルスは突然変異。その時だけを考えるとポンコツも含めた多様性を持つことは非効率だが、多様性があることで環境の変化に強く、ロバストネス(頑健性)も高い。病原菌に抗生物質耐性菌が出現したり、驚くような環境に微生物が存在したりしているのも同じ原理か。
先日、学生とある工場を見学させていただく機会を得た。もっとも感銘をうけたのは、工場に貼ってあった行動指針「私は、今日の仕事を振り返り、誇りをもって家族に話すことができます」であった。効率アップとか安全とかではなく、「仕事を振り返り、誇りをもって家族に話せるか」が行動指針になっていた。この行動指針の場合、正しい効率アップ法が選択され、安全は守られ、問題は起きにくいであろう。昔なら「お天道さまはお見通し」か。うそやずるは短期的には得するように見えるが、人生100年かつSNS時代では必ずばれ、大手芸能事務所やマスメディア、中古車販売業者や保険業界、あるいは一部の政治家や芸能人の例を挙げるまでもなく、その人や組織を揺るがす。結果の確認に時間はかかるが、こちらも効率的な仕組みのように思える。
多様性を背景にした自然選択による最適化と「お天道さまはお見通し」による最適化。大学研究資金配分には活かされていないように思う。筆者は5年前に大学に来たが、基礎的経費はきわめて少額で、外部資金などを確保しなければ、卒論生や修士の学生の研究費を賄えない。乱暴でもぱっと見て伝わる文章が求められ、攻略本や攻略セミナーも開催されている。流行りの研究分野の方が取りやすいから「寄せに」行く者もいて、資金配布側の効率も悪い。その分野のブレークスルーより、確実に結果が出て報告書を書いてくれそうな人や分野を選びがちに見える。不正防止のために規制ができ、正直を証明するのに、ぱっとみてわかる文章を書くのに、膨大な応募を審査するのに、成果を出すための研究時間がどんどん削られていく。この選択圧は、科学技術発展のために正しいか。分野や手法の偏りを誘起し、多様性が生まれることを阻害していないか。
いまの仕組みが正しいかどうかも「お天道さまはお見通し」、歴史が証明する。短期的には効率が悪いように思うかもしれないが、研究時間を確保し、多様性を生み出すのに最小限の基礎的経費が出るようにならないと、社会が大きく変わった時に必要な研究成果は得られそうもないような気がする。いまの仕組みは本当に有効か。頑健性は高いか。成功するにはある程度の失敗と試行錯誤が必要なのである。多様性+自然選択による最適化と「お天道さまはお見通し」による最適化、信じてみませんか?
著者紹介 福島大学食農学類(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 2月 2024
生物生物工学会誌 第102巻 第2号
赤田 倫治
久しぶりの対面授業のせいなのか、ある日の微生物学の講義中、殺菌法や発酵現象の解明について話しているときに、ふとパスツールが私に降りてきて、なぜか岡山弁でしゃべり始めたんです。他でもない、生物がどこからともなく自然に発生することがあるという「自然発生説」の否定や、Chance favors only the prepared mindの名言で知られるあのパスツール先生です。
“そこら中に微生物がうようよおるってことをみんな知っとる? 肉汁を置いとったら生物が自然発生するとか言うとったやつらは間違っとるってことを言いたいんじゃ。肉汁を煮るだけで、目に見えん微生物が死んでしもうて、何も起こらんようになったのをみせたじゃろ。煮んと、肉汁にコンタミしとった微生物が増殖しただけじゃが。”
パスツールは、パスツールピペットと呼ばれるようになった細い管を持つフラスコを作製して、自然発生説を否定してみせたわけですが、それ以上に、殺菌が、目に見えない微生物たちを扱うことを可能にした本質的な実験法なんだということを、私に言わせようとしていると感じるわけです。
ところで、煮ればよい殺菌法は、科学の基礎でしょうか、それとも応用でしょうか?0から1を作り出すのが基礎で、1から100の量や種類を作り出すのが応用っていうイメージはどうなんでしょう? 科学の歴史で考えてみると完全な0はないのかもしれませんが。
最近、私たちは大容量PCR法という技術を近所のカニカマ機械メーカーの人と開発しています。PCR法は、新型コロナウイルス検査で広く一般に知られた技術となりましたが、多くの場合、微量のDNAを10~50μLの反応液中で増幅します。この技術を0辺りから1の基礎とすると、1mLの反応液で同じことをすれば、1から100への応用となり、1LができればDNAの新しい製造法となると思いつき、始めたわけです。でもこれが全然できない。そこであれこれ、0辺りに戻って実験してみることとなりました。そうしてわかったことは、DNAが不安定な物質だった、ということでした。ここでは煮過ぎがよくなかったのです。DNAはmRNAより安定ですが、それは程度の問題で、DNAは安定だという常識がすっかり邪魔になっていたのでした。現代は、情報が多すぎて、0辺りに戻ることや常識から距離を置くことが難しい時代なのかもしれませんね。
パスツールは、若くして光学異性体を発見したので、化学界を牽引して行けたはずと思われます。しかしながら彼は、一度、地方工業都市にあるリール大学に移り、そこで、アルコール醸造業者から品質管理の相談を受けて、アルコール腐敗の原因を探り始めました。
“困っとった会社の人をなんとか科学で解決してあげたかったんじゃ。せーでもなあ、それを解決するには、そこら中におる微生物を殺菌して、微生物がおらん空間を作らにゃおえんかったんで、煮りゃあええという方法を思いついたんじゃ。これが、論争じゃった自然発生説の否定に通じたんじゃが、それよりなあ、わしがうれしかったんが、煮る殺菌法でおいしいワインや牛乳を飲めるようになったことじゃが。”
“人の役に立つことは、幸せな気分にさせてくれるじゃろ。わしが科学に基礎も応用もねえと言うたんは、そんな議論より、人の役に立つことを目標に、根本からの解決を科学で図ってみることが重要じゃあと言いてーんじゃが。わしが晩年、流行り病やワクチンの研究をしとったいうのを知っとるか。未来でもコロナとかいうて困っとるらしいのう。mRNAワクチンとかいうのができたんか。頑張ったのう。でもなんでより安定なDNAでやらんのじゃ? 未来でもまだまだ科学で解決せんといけん課題がぎょうさんあるようじゃのう。0から100まで頑張りんさい。子供たちへの幸せが作れるからのう。”
The prepared mindとは、困っている人を科学で助けたいと思う心なんですね。パスツール先生、ありがと。
著者紹介 山口大学 大学院創成科学研究科 化学・ライフサイエンス系専攻(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 1月 2024
生物生物工学会誌 第102巻 第1号
秦 洋二
日本生物工学会の会長を拝命して、はや半年が経とうしている。SBJシンポジウムに始まり、名古屋での年次大会やアジア関連団体との協賛など大きなイベントをなんとか無事に終わらせることができた。これも清水先生、青柳先生の二人の副会長をはじめとする理事のみなさんのご支援、ご協力のおかげである。まだまだ力不足はぬぐえないが、学会発展のために尽力してきたい。
2023年は大谷翔平選手が、日本人初となるメジャーリーグでホームラン王を獲得した年となった。打者としての活躍だけでなく、投手としてもチーム最多の10勝をあげるなど、まさしく投打の二刀流の大活躍であった。当初は誰もが投打の二刀流などはあり得ないと考えていたが、大谷選手の卓越した能力と不可能に見えた二刀流に挑戦する強い精神力で、前人未到の偉業を達成した。我々には大谷選手のような二刀流は到底できないが、二刀流に挑戦する姿勢は見習うべきと考える。
日本生物工学会は、2022年に創立100周年を迎えた。1923年に大阪醸造学会として創立された当時は、醸造・発酵分野が中心となっていたが、この100年の間にカバーする研究領域は大きく拡大している。清酒醸造が中心であった微生物による物質生産は、対象となる物質や微生物が多種多様となり、研究対象も微生物だけでなく、広く動植物にまで広がっている。酵素工学、動植物細胞工学、さらには生物情報工学など新しい分野を次々と取り込むことにより、日本のバイオテクノロジー分野を代表する学会になることができた。
このような幅広い研究領域を包含する学会の役割としては、異なる学術領域の交流の促進があげられる。生物工学会では研究部会制度を導入して、異なる研究分野の融合やニッチな研究分野の育成、発展に努めている。現在13の第2種研究部会が活動しており、それぞれ魅力的で個性的なテーマで新しい研究分野に挑戦している。これからは異分野の研究者が役割分担をして領域を融合させるだけでなく、他の分野の研究を理解し実践できる「二刀流」に挑戦することが望まれる。たとえば、実際に生物実験を行って生命現象を解明するウエット研究者とバイオインフォマティクスに代表される情報処理で解析を進めるドライ研究者が、お互い協力するだけでなく、ウエット研究者がドライ研究を行う、ドライ研究者もウエット研究を実践する二刀流も必要だと考える。いままでは、そのような二刀流は難しい、かえって効率が悪いと考えられてきたが、大谷選手の活躍をみて二刀流の先には、新しい世界をみることができるのではと期待している。大谷選手のようなメジャーリーグでの投打の二刀流のような異次元の活躍はできないが、我々の身の回りにも二刀流に挑戦すべき課題はたくさん転がっていると思う。企業においても研究者が、マーケティングや財務の知識を持つことは必須要件で、さらにはその異分野の専門家になることも要求されている。まずは身近な異分野領域を実践する二刀流から始めてみてはいかがだろうか?ただ二本目の刀はどうしても自分の苦手な領域であることが多いので、ぜひ苦手な方の刀もしっかり練習して両刀使いになることが重要である。
私は日本生物工学会として初めて民間企業所属の会長となる。業経営のマネジメントと学会運営のマネジメントの二刀流をさせていただいているが、お陰さまで一刀流ではわからなかった多くの事を学ばせていただいた。特に今まで企業側からしか見えなかった学会について、アカデミアの視点、考え方を理解できるようになった。会社では、業務の効率、効果、銭勘定をまず先に考えてしまうが、学理の究明のためには多少遠回りをしても、真実を明らかにすることが重要であることを教えてもらった。まさしく両方向の視点でみえるようになったことは、二刀流に挑戦したからに他ならない。本来二刀流とは両手に刀や剣を持つ剣術法を指すが、大谷選手の活躍により、「同時に二つのことを行う」という意味の方が有名になった。スポーツ界だけでなく、我々の学術領域でも二刀流、三刀流の研究者が活躍することを望んでいる。
著者紹介 月桂冠株式会社(専務取締役製造本部長)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 12月 2023
生物生物工学会誌 第101巻 第12号
岡 賀根雄
2022年の創立100周年記念大会の成功、および記念事業の順調な滑りだしをお祝い申し上げます。私は募金担当として準備に携わらせていただきました。この厳しい社会・経済環境の中、ご寄付いただいた企業、団体、そして個人の皆様に心からのお礼を申し上げます。おかげをもちまして、当初予算を越える金額を頂戴することができ、学会の将来にとって喜ばしい結果となりました。募金集めにご尽力いただいた先生方にもお礼申し上げます。
さて本題です。自分自身はまだまだ若い、少なくとも年寄りだとは思っていなかったのですが、はや還暦を迎え、更にはこんな原稿を頼まれるようになり、現実に目を向けざるを得ない状況となりました。2019年に理事をお受けするまで学会活動とは無縁で来たため、私に語れることは限られていますが、将来を担う若者の皆さんに向けて、何某かの役に立てればと思って書き始めます。「人生の最大幸福は職業の道楽化にある」これは、本田静六さんの『私の財産告白』(実業之日本社文庫)に収められた『平凡人の成功法』という文章の言葉です。私がこれを知ったのは50代になってから。「もっと若い時に出会いたかった」と思いましたが、これまでを振り返って、「そうそう、そうだよな」とうなずくことしきり。「思った仕事と違った」「仕事に興味が持てない」と言って、好きで選んだはずの職業を何年も経たずに辞めてしまう若者が増えてきています。そんな中、多くの人に読んでもらいたい名著です。もう少し引用します。「職業を道楽化する方法はただ一つ、勉強に存する。」「あらゆる職業はあらゆる芸術と等しく、初めの間こそ多少苦しみを経なければならぬが、何人も自己の職業、自己の志向を、天職と確信して、迷わず、疑わず、一意専心努力するにおいては、早晩必ずその仕事に面白味が生まれてくるものである。一度その仕事に面白味を生ずることになれば、もはやその仕事は苦痛でなく、負担ではない。歓喜であり、力行であり立派な職業の道楽化に変わってくる。」
もう一つは遊び心を持ち続けるということ。ペニシリン、ダイナマイトなど、世の中の発見や発明に失敗や偶然がきっかけになったものは少なくありません。その失敗を意図してやってみようということです。企業で研究開発に携わっている人は、それが実用化に近いほど、最適値を求める実験を計画することになります。しかし小スケールの実験であれば、敢えて水準を大きく振ってみる遊び心を持ってもいいのかもしれません。私の職業であるビールの分野でも、現在普通に飲まれている淡い色合いのビールは、「色付けのための黒麦芽を入れ忘れてできたのだ」という伝説があります。意図して水準を大きく振ったのか、本当に入れ忘れたのかはわかりません。入れ忘れたとしても、失敗だとすぐに捨ててしまうのでなく、ビールにまで醸してみて、今までにない美味しさを発見したのだと思います。同じ意味で、意図しない異常点にも大きなチャンスが隠されているかもしれません。しっかり考察しておく必要がありそうです。
三つめは出会いを大切にするということ。自分の考えられる範囲なんて小さなもの。いろんな場所に出かけ、いろんな人に会い、経験し、それで気づかされることの何と多いことか。直接仕事に役に立つヒントになるかもしれませんし、新しい活動につながるかもしれません。また自分の価値観や人生に影響を与えてくれる出来事に出会うかもしれません。時間がない、興味がない、と言って捨てるのは簡単なのですが、「遊びで行ってみようか」これでいいのです。舞い込んできた情報やきっかけに少しの時間を割く。これが人生を豊かにしてくれるかもしれません。皆さんには大きな可能性があります。自分を小さく規定することなく、好きなことで大きな夢を描いて、突っ走ってください。夢大きく!明るく、楽しく、前向きに!
著者紹介 サントリーホールディングス株式会社(取締役専務執行役員)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 11月 2023
生物生物工学会誌 第101巻 第11号
髙下 秀春
年号が「平成」から「令和」になって久しいが、人々が美しく心を寄せ合うには程遠く、混沌とした先の読めない時代に突入した.酒類業界の中でも焼酎業界は、グローバル化を進める上で自分自身の強みが何であるのかを知ることが大事である。
最近の日本産酒類の輸出動向(https://www.nta.go.jp/taxes/sake/yushutsu/yushutsu_tokei/index.htm)によると、輸出金額は初めて 1,000億円を超えた 2021 年に引き続き、2022年分でも 1,392億円(対前年比+21.4%)と好調に増加している。品目別ではウイスキーが 561億円、日本酒が 475億円と大きく牽引している。これは、両者が長きにわたる海外へのアプローチを継続してきたからこその結果である。日本酒業界は、同じ醸造酒であるワインの世界展開に着目し、コンペティションとの連携や伝統的な日本食(和食)とのマリアージュなど、ワインの評価基準を通して輸出先のお客様に日本酒の価値の理解を促した。一方、焼酎の 2022年の輸出金額は 21.7億円で日本酒の 5%にも満たない。日本酒では 10年以上連続して過去最高を更新しているが、焼酎での対前年増減率は 2020 年以降にようやくプラスに転じて今に至っている。まだ、小さな兆しだがその上向きのベクトルをさらに推進する手段の一つとして、焼酎自身の強みを認識し、その価値をモノ・サービスに付与して世界に発信することが必要である。2022年に日本の國酒である日本酒、本格焼酎・泡盛、本みりんなどの「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産の提案候補として選定された。また、日本では蒸留酒である焼酎が食中酒として定着しているという、世界でも類を見ない飲酒文化がある。そこで、筆者の所属する三和酒類株式会社では焼酎を「麹文化の蒸留酒」として定義し、焼酎製造における麹を利用した「伝統的酒造り」のまだ解明されていないメカニズムを知ることを目指している。それが、焼酎に秘められた新たな価値を発見し、アウトプットとして世界標準の価値ある商品開発に繋がるものと確信している。
そのためのアクションとして、当社にて基礎に近い研究を自前主義で行うには限界がある。また、環境変化が激しい現在では、オープンイノベーションが重要となってきている。オープンイノベーションとは、組織内部のイノベーションを促進するために、意図的かつ積極的に内部と外部の技術やアイデアなどの資源の流出入を活用し、その結果組織内で創出したイノベーションを組織外に展開する市場機会を増やすための手段のことである 1)。
外部との連携を強化したい企業としては、共同研究など外部機関とのマッチングが最初の一歩となる。オープンイノベーションを促進するしくみとして、ニーズとシーズをマッチングさせる場の提供やプラットフォームを介したサポートなどがある。しかしながら、オープンイノベーションという言葉がない時代から、企業のニーズに対して自らが探索し、マッチングする研究テーマや研究技術を有する外部機関と共同研究するまで展開する場として学会が存在している。当社のような醸造・発酵関連の研究領域を探索する目利きを養う場としても日本生物工学会は重要である。初代三和研究所所長の故和田昇相談役から当社研究員は他流試合(学会に参加して学会発表、外部研究員との交流)をするように促された。筆者が入社した当時はネット環境が整っていなかったことから、醸造、発酵関連の学会に直接参加したことで最新研究の情報収集や人的ネットワークを広げることができた。外部連携を促進して「麹文化の蒸留酒」のアイデンティティを解明していくために、今後も学会参加を一つの足がかりとしたい。
最後に、オープンイノベーションのマッチングの場として学会を捉えたときに、発表時の導入部分で研究テーマがどのような課題に対して貢献できる技術であるかをニーズ側に立ってプレゼンしていただくことで企業にとってさらに価値のある学会になることを期待して筆を置きたい。
1) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「オープンイノベーション白書(第三版)」:
https://www.nedo.go.jp/library/open_innovation_hakusyo.html (2023/5/26).
著者紹介 三和酒類株式会社(取締役)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 10月 2023
生物生物工学会誌 第101巻 第10号
安原 貴臣
私が企業に入社した1991年当時、多くの消費財メーカーでは自社の保有するリソースをベースにした自前でのモノづくりが主流であったように思う。その後、新興国を中心とする人口増や情報化技術の普及による世界同時成長に伴い、化石資源依存経済が拡張を続けた結果、世界が持続可能な開発目標(SDGs)や、2050年のカーボンニュートラルの実現に向けた各国目標を定めたパリ協定などの国際合意に繋がっていることは周知のとおりである。特にSDGsにおいては、「誰一人取り残さない」との決意のもと、欧米を中心に新たな持続可能な経済活動パラダイムの主導権を握ろうと法令・規制の整備や産官学一体での技術プラットフォーム開発競争が急速に進んでいる。さらには、コロナ禍やウクライナ問題で露呈した地経学的リスクは化石資源脱却と資源自律の両立など、各国に強靭で持続可能な循環経済戦略を再考させている。こうして産業界は今、不確実な未来と経験のない事業環境の大きな変曲点を迎え、未来社会に受容、歓迎される事業への転換や再構築を迫られている。
こうした壮大な社会共通課題に対しては、産官学からの英知を総動員した質の高い技術開発と実証サイクルに加え、それらを国民理解と新制度の設計・発動を通して社会の行動変容にまで繋げる必要がある。すでに欧米では、ハード、ソフト面での総合知を結集する政策や積極投資が進められている。日本でもこの課題解決にはバイオの果たす役割はきわめて大きいとされ、「2030年に世界最先端のバイオエコノミー社会の実現」を掲げたバイオ戦略が2019年に策定された。本戦略は、世界環境の変化に伴い、毎年見直しが図られつつ、政府主導で産官学の共創での課題解決を誘導する施策が積極的に進められている。
一方で、「日本は技術で勝ってビジネスで負ける」との声や、社会変革に伴うルール形成において欧米の後塵を拝しているとの声を耳にする。この原因として、日本のビジネスモデル面での劣後が指摘されているが、その真因はどこにあるのだろうか? 2018年に実施された理事、代議員を対象とした生物工学会への参画目的と要望に関するアンケート(https://www.sbj.or.jp/wp-content/uploads/file/sbj/9711/9711_sangaku_survey.pdf)によると、学術界では成果発表と育成を目的とする意見が多い一方、産業界では成果発表と研究・情報発信に加え、ネットワークや有用技術・情報獲得が期待され、後者において不満足の意見が目立った。また、全体的に産官学が議論できる企画の充実を期待する声も多かった。こうした意見と現状から、産業界には連携・共創の意識はあるが、どう連携・共創するかの様子見、慎重な姿勢が感じられた。この背景には、日本の製造業が基本的に閉鎖的な枠組みでの生産で富を築けてきたこと、長期安定雇用もあり事業に必要な技術を内製化できたこと、および、業界ごとに優良な競合企業が複数共存する競争環境の歴史が関係しているかもしれない。いずれにしても、研究力や国際競争力の低下が指摘されているが、長きにわたって積み上げてきたナレッジと実直で連帯の精神が本国民の根底にあると信じており、個々の躊躇の先にある一歩が未来社会への競争優位なトランスフォーメーションと国力の復活に繋がると期待している。
近年、フードテック関連の研究会が複数立ち上げられ、そこにはITやエンターテイメント業界などに加え、多くのベンチャー企業も参画し、産官学の分野・業界を超えてバイオを起点としたSociety 5.0社会の高次の実現に繋がる共創議論が繰り広げられていると聞く。産も官も学も皆、持続可能なより良い未来社会の実現のために共存する公器である。それぞれの個人、組織、企業の存続と繁栄が大前提との相互理解の上、より多くの幅広い技術者が構想を恐れず掲げ、気付きや共感と連帯を生み、社会課題を解決する高次の競争価値を創造できる場として、100年の歴史を刻んだ今後の日本生物工学会の役割と繁栄を共に楽しみたい。
著者紹介 アサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社(社長付、担当部長(OI担当))
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 9月 2023
生物生物工学会誌 第101巻 第9号
小林 元太
「巻頭言“随縁随意”」の執筆依頼を安直に引き受けてしまったものの、さて何を書こうかとずっと悩んでおりました。そもそも「巻頭言」とは高名な大先生がお書きになるもので私が書くなど大それたことだと思いながらも、記憶と記録をたどりながら、学生の頃からお世話になっている本会で得たことについてご紹介してみます。
2022年末にコロナ禍でままならなかった九州支部佐賀大会を実行委員長として対面式で開催することができ、福﨑英一郎前会長にも遠路はるばる佐賀までご足労いただきご講演いただきました。その際に色々な先生方と久しぶりにお話しができ、お酒を酌み交わし(ここがとても大事です)、大変刺激を受け、やはり対面式の学会は良いな~大事だなぁと痛感したところです。さて、私自身が初めて参加した学会も、本会の前身である日本醱酵工学会大会(於 大阪国際交流センター)でした。遠い遠い昔の1988(昭和63)年11月(修士1年)のことでしたが、自分の番が来るまでの緊張感や話し終えた後の安堵感、そして会場いっぱいの聴衆に驚いたことなどを昨日のことのように思い出します。そして翌年に名古屋大学で開催された同大会でも発表をすることができ、それらの成果をまとめた初めての論文が掲載されたのも『Journal of Fermentation and Bioengineering(JFB)』でした。まさに私の研究者としての第一歩は日本生物工学会(日本醱酵工学会)から始まり、後に九州支部長となる恩師の故 石崎文彬先生(九州大学名誉教授)の生物工学に関する熱いご指導がなければ、今の私はありません。本学会とのご縁をとても感じています。その後、鐘淵化学工業(現 カネカ)を経て、1996(平成8)年に九州大学農学部助手として赴任しました。大学教員となった後は、前述の石崎先生が初代支部長として設立された日本生物工学会九州支部を中心とした学会活動を今でも行っています。
さて、本学会活動でもっとも楽しかった(有意義だった!?)のは何といっても「生物工学若手研究者の集い(若手会)」です。当時の吉田和哉若手会長から九州地区での開催を依頼され、手探りで開催したことも良い経験になり、参加・協力してくれた当時の若手(今はただのオッサン)の皆さんとは今でも交流が続いています。若手会の良いところは、お酒を酌み交わしながら、さまざまな分野の人たちと語らうことにより、将来的に役に立つ人間関係を構築できることにあると思っています。1999(平成 11)年に「休暇村 南阿蘇」で開催した若手会の巻頭言に吉田和哉先生が「夏のセミナー’99によせて ―ワイワイ騒ぐのがエエわ!」「インターネットフォーラムで酒は飲めませんもんね」と書いてくださっていますが、コロナ禍を経て対面式の良さを実感するにあたり、まさにその通りだと思っています。本学会の多くの方々とはその頃にお目にかかって以来お付き合いしていますし、最近では九州地区で「若手だった会」という任意部会(笑)を設立し、遠い昔に若手だったメンバー達と今でも熱い議論を戦わせています。
その若手会は、若い人たちだけでなくさまざまな人たちが交流をはかる場として非常に大事だと思いますが、今の学生さん達を見ると違和感を覚えることがあります。最近は趣味・嗜好が多様化しており、私の若い頃とは少し考え方が変わってきており、飲んで楽しいというだけでは、なかなか理解してもらえないようです。その最近の学生さんたちへの思いを少しだけ述べさせてもらえればと思います。私が企業から大学に移ったときに、なかなか大学に来ない学生さんが多くて、いったい何のために大学に入ったのかなと思ったことがあります(今でもそう思っています)。もし大学が面白くないのであれば、もっと面白いことを探せば良いのになぁと思いますし、自分のテーマに興味を持てない場合でも、それをどう受け取るかは自分の考え方次第だと思います。ほとんどの学生さんは自分自身の卒論や修論テーマの実験・研究を社会に出てからやることはありません。だからこそ、いま何のために実験・研究をするのかということを自分自身で考えてみて欲しいなと思います。たぶん、テーマは何だって良くて、その問題を解決するプロセスを学んでいるのだと気付けば少しは気持ちも変わるのでは…。
私は、彼らに、実験「を」教えるのではなく、実験「で」教えることが大事なんだと常日頃から思っていますが、それも日本生物工学会のさまざまな分野の皆さんとの交流で学んだことであり、今でも大変感謝しております。
著者紹介 佐賀大学農学部生物資源科学科生命機能科学コース(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 8月 2023
生物生物工学会誌 第101巻 第8号
関 実
バイオへの追い風が強く吹いている。しかし、順風がいつまでも続くわけではない。2020年度から、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の通称「バイオものづくり」プロジェクトのプロジェクト・リーダーを拝命している。正式には、「カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発」という長い名前のプロジェクトである。直接的には、2019年6月、内閣府から発表された「バイオ戦略2019」という政策方針を受けたものである。国が、バイオテクノロジーに関連する方針を発表するのは、2002年の「バイオテクノロジー戦略大綱」とそれを補完する2008年の「ドリームBTジャパン」以来である。このときは、どちらかと言えば、基礎研究のフロンティア開拓に軸足を置いていたため、社会還元の遅れが懸念されていた。今回の戦略では、出口指向がさらに強まり、目標は「2030年に世界最先端のバイオエコノミー社会を実現すること」になっている。
加えて、「バイオ戦略」策定後に発表された菅首相(当時)の「カーボンニュートラル宣言」(CN宣言)に呼応する形で、2020年12月に経済産業省が主導して「グリーン成長戦略」という政策方針も発表されている。CN対策を「成長の機会」と捉え、「経済と環境の好循環」を作っていく産業政策である。その主眼は、エネルギー転換である。再エネ、電化・蓄電、水素関連の新たな産業の発展が期待できるとして、14の重点分野が選定された。「バイオものづくり」も含まれている。
「バイオものづくり」のCNに対する貢献は必ずしも大きいとは言えないが、より重要なことは、循環型で持続性のある産業構造への転換(SX)である。石油化学製品のバイオマス原料への転換だけでなく、省エネルギー・省資源型のバイオプロセスを目指した技術開発は、バイオエコノミーの発展にも寄与する。NEDO「バイオものづくり」プロジェクトのミッションの一つでもある。
私の学生時代は、第二次オイルショック後の経済低迷の中で、石油代替エネルギーとしての太陽光、地熱、風力、水素、バイオマスなどの自然エネルギーの開発が注目された時期である。私自身がバイオに足を踏み入れるキッカケの一つでもあった。また、NEDO設立もこの時期(1980年)であり、当初より「新エネルギー開発」が目的の一つだった。その後、総合化学会社に入社し、当時の通産省が主導した次世代産業基盤技術研究開発制度の下で実施された大型のナショプロに参画する機会を得て、「次世代バイオリアクター」の開発に取り組んだ。コンピュータ自動制御による汎用化学品のバイオ生産を行うというもので、40年近く前の技術開発ではあるが、目指していたところは、現在のそれに通じるところもあった。
40年前の第一次バイオブーム、約20年前の第二次ブームは、それぞれ、遺伝子操作技術、ゲノム解析技術とその成果を中心とするバイオとその関連科学および技術の発展に裏打ちされたものである。そして、数年前からのバイオへの追い風も、情報技術やゲノム編集技術、そしてロボティクスの進展などの科学・技術の深化に後押しされている。同時に、経済発展の起爆剤としての「バイオエコノミー」に対する世界的な期待があることも大きな要素である。これまでのブームでも、それなりの成果を挙げて来たものの、社会実装・変革が大きく進まないと、10年も経たずにフェードアウトして行くことが繰り返されて来たとも言える。
「2050年CN実現」は、困難で時間の掛かる目標である。目標が大きければ、循環型のバイオプロセスの価値は益々高まって行くはずではあるが、追い風が続くかどうかは分からない。バイオエコノミーの発展に繋がる新たなバイオプロセスの社会実装を加速し、同時に、バイオ関連の情報解析技術や自動化システムなどの共通基盤の構築を急ぐ必要があるのだろう。
著者紹介 千葉大学 大学院工学研究院(名誉教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 8月 2023
生物生物工学会誌 第101巻 第7号
梶山 慎一郎
年初から暖かい日が続き、例年雪がちらつく大学入学共通テストも今年は穏やかに過ぎたと思っていたら、昨日から10年に一度という寒波が襲ってきた.私立大学の一般入試も始まっており、受験生に影響がでなければよいのだが……。毎年この時期になると自身が受験生だった頃を思い出す。当時は未だバブル崩壊以前で、周りもなんとなく将来に対する期待感みたいなものがあったように思う。受験生であった私もバイオテクノロジーをはじめとする科学技術の進歩に、これからどんな素晴らしい未来が待っているのだろうと胸躍らせていた。大学に入学し、研究室に配属されてからも、誤解を恐れずに言うなら、自分の興味に素直で心底研究を楽しんでおられる先生方や先輩が多かったように思う。あれから30有余年の年月が流れ、社会環境は大きく変化した。特に情報処理技術の進歩は目覚ましく、今やチャットAIがMBAに合格する時代である。生命科学の分野でも、あらゆる情報に簡単にアクセスし、データ横断的な解析やさまざまな予測・診断にAIが用いられるようになってきている。この状況は、ある意味科学者にとって夢の時代のはずだが、何となく昔のようにワクワクしないのはなぜだろう。
先日たまたまNatureに気になる投稿を見つけた。お読みになった諸氏もおられると思うが、さまざまな科学分野の過去60年に発表された膨大な数の論文や特許、さらにはアブストラクトの解析から、最近の科学技術研究の革新性が著しく鈍化してきている事を指摘した論文である1)。もっとも、発表論文の数自体は増えており、論文の質も特に低下しているわけではないのだが、多くは既知の知見の組合せや漸進的展開にとどまり、いわゆる常識を打ち破るような真に創造的で革新的な研究(原著ではdisruptiveとなっており、巷では「破壊的科学技術」と訳されるようであるが、なんとなくしっくりこないのでここではあえて、革新的研究とし)の割合が科学のあらゆる分野で減ってきているというのである。この論文ではその理由として、近年、研究者がより狭い分野の知識に依存して研究を行う傾向にあることを挙げている。また、このような傾向は、個々の研究者のキャリアには利益をもたらすが、より一般的な科学の進歩には結び付きにくいと指摘している。真に革新的な研究には、分野を超えた幅広い知識との関わりが必要であるというのである。
ただ、なぜそのような傾向になってきたかについてはあまり述べられていない。そもそも技術革新に学際的な視点が重要であるという指摘は従前から行われてきたし、大学の学部や研究科もそのことを意識して組織化されてきている。問題は研究者が異分野に興味を持つ余裕が無くなってきていることではないだろうか。
ここでいう余裕とは、時間的あるいは制度的な制約が少ないという事ではなく、いろいろなことを面白がる「心の」余裕である。言い換えれば、研究者の心理的安全性が低くなってきているのではと思うのである。日本だけでなく世界的に見ても、人類の持続可能性への危機感から、差し迫った問題に対してより即効性を有する研究に重点が置かれ、研究者に対する社会的要請も、シビアになってきているように感じる。必要は発明の母であるから、このような雰囲気は必ずしも疎まれるべきではないのかもしれないが、無駄を許容しない状況は研究者を萎縮させ、結果としてパフォーマンスが低下するのではないかと思う。
気象問題やエネルギー問題、食料問題など人類が直面する難題の解決に資するキーテクノロジーやこれらを乗り越える知性を生み出すためには、逆説的ではあるが研究者の遊び心や心理的安全性の確保が重要ではないだろうか。もちろん、状況のせいばかりにしてはいられない。研究者もつとめて異分野の知識に興味を
持てるよう、自身の心のマネジメントの努力が必要だろう。今年の受験生の中にも科学を背負って立つ人材がいることであろう。上記の論文でも今後科学政策が変わるかもしれないと書かれていたが、彼らが2045年にも訪れると言われるシンギュラリティを迎えた後も、自分の興味に素直に研究できる事を願う。
1) Park, M. et al.: Nature, 613,138 (2023)
著者紹介 近畿大学大学院生物理工学研究科(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 6月 2023
生物工学会誌 第101巻 第6号
英文誌編集委員長 井藤 彰
この度、英文誌編集委員長を拝命しました名古屋大学大学院工学研究科化学システム工学専攻の井藤彰です。就任にあたり、自己紹介方々、会員の皆様にご挨拶申し上げます。
私は1997年に名古屋大学工学部生物機能工学科の小林猛先生の研究室に配属され、機能性磁性ナノ粒子を用いた、がん温熱療法に関する研究に従事しました。当時、小林先生は日本生物工学会の会長を務めていらっしゃったので、当然、私も日本生物工学会に入会し、以来四半世紀が経過します。英文誌 ‘Journal ofBioscience and Bioengineering(JBB)’ への私の初めての投稿論文は2000年に掲載されました。それ以降、2004年、2008年、2014年とJBBの論文賞受賞論文に選んでいただき、これらの学術的成果は私のキャリア形成に大きく貢献しました。JBBに投稿して貴重な査読意見を頂戴するだけでなく、2001年に名古屋大学の助手となってからは、JBBへの投稿論文の査読を依頼されるようになりました。恩師である小林猛先生、本多裕之先生、上平正道先生から、学会誌であるJBBにおけるpeer reviewの厳しさと温かさについてご指導いただき、査読しながら多くのことを学びました。若い研究者には査読が多く回ってくるもので、自分が投稿した論文の数よりも圧倒的に多くの査読を依頼されると、他人の評価ばかりしているような卑屈な気持ちにもなりますが、ある日Elsevier から‘Top Reviewer’と書かれたボールペンが送られてきたことは、驚きとともに、ちょっとやる気が出たりしました。
2011年から2015年は、JBBの編集委員をお引き受けすることになり、髙木昌宏編集委員長にジャーナルの編集に関わる責務と意義についてご指導いただきました。特に、後半の二年間は副編集委員長として、編集委員長の仕事をサポートする貴重な機会を頂きました。若い頃から編集に携わる機会を与えるとともに、国際誌の副編集委員長を務めた実績をプロモーションに利用して欲しいという髙木先生のご厚意であり、大変感謝しております。編集委員であった当時、JBBのインパクトファクターを上げるための方策として、‘NOTES’として掲載されている論文の被引用回数が低いことからNOTESのカテゴリー廃止を提案しました。髙木編集委員長のご英断でNOTESは廃止されましたが、学生の学位取得のためにNOTESは残すべきだという意見に対して、「JBBは会員の駆け込み寺ではない」と仰った髙木先生のお言葉が心に残っています。
さて、直近4年間の英文誌編集作業は、神谷典穂編集委員長をはじめとする編集委員や事務局の方々の献身的なご尽力に支えられてきました。インパクトファクターも3を超え、JBBは日本、引いてはアジア圏のバイオテクノロジーを世界に発信する日本生物工学会のフラッグシップジャーナルとして益々発展し続けております。一方で、これからの10年は学術情報にとっての非常に大きな変革期であるといわれています。国などの研究資金提供機関の要請で、オープンアクセスのジャーナルが急増しており、学術の成果が社会へ広く公開されて誰もが利用できるようになるオープンサイエンスの一層の発展が見込まれています。こういったデジタルトランスフォーメーションが起こっている最中に、学会誌としてのJBBの未来をどのように描いていくか、編集委員長としての私の重責は非常に大きいのですが、その時代の渦中にあることは大きな挑戦であるとともに新たな学びの機会であると捉えています。今後4年間、編集委員および事務局の皆様と協働し、会員の皆様のご意見やご叱正を賜りながら、この変革期におけるJBBの在り方を考え、会員の皆様に愛され続けるJBBを目指していく所存です。会員の皆様にはご指導とご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
著者紹介 名古屋大学大学院工学研究科化学システム工学専攻(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
生物工学会誌
Published by 学会事務局 on 25 5月 2023
生物生物工学会誌 第101巻 第5号
堀 克敏
本学会の会員にも起業経験者や起業を検討している方が少なからずおられるであろう。ここでは、自身の経験をもとに起業に対する思いを述べたい。私は、2017年 6月に名古屋大学発ベンチャー、(株)フレンドマイクローブ(以下 FM 社)を起業した。名称には「微生物を友達に」の意味が込められている。商品・サービスとしては、微生物と酵素、バイオリアクターおよび受託研究が中心である。FM社の事業は、排水中の動植物油脂を強力に分解する微生物からスタートした。このテーマは、企業との共同研究から始まり、NEDOやJSTの複数のプロジェクトを得て発展してきた。現在 FM 社は、微生物と酵素でSDGsを実現することを掲げ、事業展開している。
さて、起業は、自身の研究開発の成果を社会実装する一つの手段である。しかし、起業以外にも、企業との共同研究や技術供与、知財のライセンスなど、社会実装の手段は複数ある。起業が他の社会実装とまったく異なる点は、通常、自己資金を投入する必要があるということである。私は約1千万円を自ら投資している。これには、事の他、大きな決心がいる。自分の研究成果が、近い将来に絶対に売れる自信がなければできることではない。失敗すれば、投資したお金を失うことになる。他者から投資をしてもらって起業することもできるが、それでは自分の会社にはならない。逆に言えば、自分の会社にこだわらなければ、他者に投資してもらえばよい。自己資金を出すだけの自信もない技術に投資してくれる人を探すのは容易ではないが、研究成果に惚れ込んでくれて資金を出してくれる人を見つけられるかもしれない。しかし、投資家の考え方次第で、いつでも退場させられてしまうリスクがある。研究者と投資家の意見が合わずに対立することは、ベンチャーではよくあることである。そうなったら仕方がないと腹をくくり、当面の研究費を稼ぐことを目的に起業する場合もあろう。起業は民間資金を得るための有効な手段であることには間違いない。しかし、真の起業とは、自ら投資して会社を興し、それを自己投資額の何百倍以上にも成長させてキャピタルゲインを得ることを目指すものである。自分の研究成果でそれを目指せるところが、大学発ベンチャーの魅力である。
私の起業の目的も自分の会社をもつことであった。その場合、もっとも重要なことは資本政策である。完全な議決権を有する51%、拒否権を有する34%をどの段階まで保持し続けるかが最重要事項である。そうなると、多くの資金を集めればよいということにはならない。多すぎる金は自らを滅ぼしかねない。資本政策で失敗した大学発ベンチャーは数知れない。
無論、会社をもつ目的は、利潤を追求し、会社の価値を上げるだけのことではない。私も定年が見えてきた頃であり、科学者として何を後世に残せるかと考えることも多くなってきた。もちろん、新しい発見や発明を後世に残したいと考えているが、如何に画期的な発明であろうと、その寿命はどれくらいであろうか?20年以上使われる発明は、どれぐらいあるだろうか?発明した技術が次の世代の技術の土台になれば、間接的には残ることになる。他方、会社を興し、それが発展すれば、技術と共に後世に残るであろう。また、ベンチャーには研究成果の社会実装の場としてだけではなく、教育成果である人材の活躍の場としての意義もある。人、金、技術で日本に革新をもたらすバイオベンチャーに発展させられれば、本望である。発明王エジソンは世界的大企業ゼネラル・エレクトリック社の創始者であったことは言うまでもない。バイオの世界でそんなことを実現したい、そんな大それた夢を見られるのも起業したからである。ベンチャーは、まさに我が子のようであり、苦労を伴いながらも育てることは楽しいものである。
資本政策上、これまで外部資金を入れてこなかった FM社も、実績が上がり、第一期の資金調達の時期に入った。調達目標はなんとか達成できそうである。バイオベンチャーで世の中を変えようという挑戦は、第二幕に突入する。
著者紹介 東海国立大学機構名古屋大学(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報,過去の学会行事
Published by 学会事務局 on 25 4月 2023
生物生物工学会誌 第101巻 第4号
吉田 聡
2020年以降、特にコロナ禍になってから、さまざまな職場で働き方改革の議論がなされてきている。オンライン会議の浸透で在宅勤務が普通に行われるようになり、通勤時間が節約でき、その分仕事ができるという話もよく聞く。また、本学会を含めて学術大会がオンラインで行われることが主流となり、遠くまで行かなくても自宅や勤務先で学会に参加できるというメリットもある。一方で、オンライン会議では複数人が同時に発言することができず、またシステムの負荷を考えて画像を出さずに行うことが多いため、参加者の表情が読み取れないといったコミュニケーション上の不便さも指摘されている。さらに、顔を合わせての懇親の場がないため物足りなさを感じたり、特に新しい人脈を作る機会が減ったりしている。今後、会議などはハイブリッドが主流になっていくと思われるが、それぞれの業態にマッチした進化をしていくのだろう。
このように、コロナ禍によりハード面で大きな働き方の変化がみられた。一方、ソフト面、すなわち働く人達の考え方も数年前から変化がみられ、特に若い20、30代の人達は終身雇用に拘らず、仕事が自分に合っていなければ退職して新たな職場に勤めることが普通になってきた。この傾向はコロナ禍により急速に加速してきている。変化する状況を受けて、働く人達のキャリアパスやモチベーションの維持、向上を推進するために、副業を解禁する会社も多くなってきた。以前より大学では優れた発明をした先生がスピンアウトして起業したり、会社でも社内ベンチャーの提案、推進がなされたりしている。会社によっては提案制度があり、採用されればその仕事を本業として行うことができるところもある。ただし、このような会社でも採用されなかった場合はアイデアとしてお蔵入りさせざるを得ない。しかし、副業が認められることで、会社が許可する範囲内であれば、就業時間外で自分のやりたいことを仕事として行うことができるようになった。
不肖、私も2022年2月に技術士(生物工学部門、総合技術監理部門)の資格を活かそうと一念発起して(血迷って)、個人事業主として技術士事務所を開設した。人生100年と言われる時代であり、定年後に年金をいただける歳までは働きたいと考え、会社に在籍中にセカンドキャリアの準備も兼ねて副業を開始した次第である。始めてみてわかったことは、人脈の大切さ、仕事を見つけてくることの難しさとお金(の計算)の大切さである。会社にいれば後者2つは別の部門の方々に担当していただけるが、個人事業主ではすべて自分で行わなければならない。間接部門、事業会社の方々への感謝を身をもって感じている。副業を始めるにあたり、本を読んだり、技術士会が主催する研修に参加したりしてそれなりに準備をしたつもりでいたが、いざ始めてみると準備不足に落ち込んだ。青色申告にすると65万円までの控除が受けられるということ、開業の書類の出し方などは知ってはいたものの、いざ青色申告の勉強会に参加してみると領収書の取り扱い方、経費の分類、帳簿の付け方など知らないことだらけである。ところで、仕事の内容について副業の難しいところは、技術の秘密保持を含めた本業との線引きである。コンサルティングをするにしても、本業の情報はもちろん副業では出せない。本業にも活かせて、ほかの人がやっていないようなニッチな領域を見つけられるか、同業者との差別化がこれからの副業の課題である。いろいろ副業でやりたいことはあるが、もちろん自分一人ではたいしたことはできない。よって、自分にはないものを持っている同業者や同じ考えを持った関係者との協働が必須である。会社内でやりたいことができなかったり、副業を始めるべきかどうか迷っていたりで悩んでいる読者の方がいらっしゃれば、私と同じことをやられてしまうと困ってしまうので複雑な心境ではあるが、まずは副業を始めてみてはいかがだろうか。きっと今まで経験したことのなかった世界が拓けると思う(と信じている)。そして、本業ではできないこと、何か面白いことを一緒にやりましょう。
著者紹介 キリンホールディングス株式会社飲料未来研究所(リサーチフェロー)、SYT吉田技研(所長)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 3月 2023
生物生物工学会誌 第101巻 第3号
大政 健史
2022年10月から第6代目のAsian Federation of Biotechnology(AFOB)の会長を仰せつかっている。
AFOBは、2008年に発足したアジア各国を代表するバイオテクノロジー関連学会の連合体である。初代の会長は吉田敏臣先生で、私は日本からの2人目の会長となる。会長の下に、14か国(バングラデシュ、インド、インドネシア、日本、韓国、中国、マレーシア、モンゴル、ネパール、パキスタン、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ、ベトナム)からの副会長を置き、Secretary Generalとして、韓国Inha大学のChoul Gyun Lee教授にご就任いただいている。学会の本部は韓国Incheon市に設けられているが、直接のRegional Branch Officeが、インド、インドネシア、韓国、マレーシア、パキスタン、タイに設置され、約6000名の個人メンバーも登録されている。また、各国のバイオテクノロジー関連学会をInstitutional Member として受け入れており、日本生物工学会をはじめとして、日本からの計5学会を含む20学会が加盟している。AFOBは、European Federation of Biotechnology(EFB)と活発に交流しており、1年おきにEFB主催European Congress on Biotechnology(ECB)とAFOB主催Asian Congress on Biotechnology(ACB)で合同セッションが開催されている。
国際学会のACBは、AFOBのもっとも大きな活動の一つであり、その前身のAsia Pacific Biochemical Engineering Conference(APBioChEC)から引き継いで2022年はインドネシアにて15回目の開催となった。
ACB以外に各国で開催されるAFOB-Regional Symposium(ARS)も重要な活動である。ARSは毎年開催で、すでに12回目を迎えており、生物工学分野のアジア各国での活性化に貢献している。
さらにAFOBでは、Divisionでの活動を推進している。現在、(1)Agricultural and Food Biotechnology、(2)Applied Microbiology、(3)Biopharmaceutical and Medical Biotechnology、(4)Biocatalysis and Protein Engineering、(5)Bioprocess and Bioseparation Engineering、(6)Bioenergy and Biorefinery、(7)Environmental Biotechnology、(8)Marine Biotechnology、(9)Nanobiotechnology、(10)Biosensors and Biochips、(11)Systems and Synthetic Biotechnology、(12)Tissue Engineering and Biomaterials、(13)Bioindustry Promotion and Bioeducation(Formerly Bioeconomy and Biobusiness)の分野を設定し、各国から委員を出して、それぞれ活発に活動を行っている。
すでに27年も毎年実施されている日本・韓国・台湾・中国の50歳以下の若手の博士号をもつ研究者の集い、Young Asian Bioengineers’ Community(YABEC)の活動もAFOBの重要なミッションである。これに加えて、2022年、インドネシア、シンガポール、マレーシア、ベトナム、フィリピン、タイの6か国からなるYABEC-Southが発足し、各国での自主的な交流活動も広がっている。
近年のバイオテクノロジー分野やバイオ産業の目覚ましい発展に伴って、AFOBの活動も非常に活発になり、新しい分野を積極的に取り入れ、対象とする研究分野もさまざまに増え続けている。一方、AFOBが行っている多様な活動における日本人研究者のプレゼンスや貢献は年々低下しているように思われる。我が国の生物工学(バイオテクノロジー)分野を代表する日本生物工学会は、バイオテクノロジーの発展と共にもっと発展すべきであり、是非新しい分野を積極的に取り入れ、アジアにおけるプレゼンスを発揮して欲しいと切に願っている。
AFOBの活動の状況はホームページ(https://www.afob.org/)を参照されたい。
著者紹介
大阪大学総長補佐・大学院工学研究科(教授・副研究科長)、Asian Federation of Biotechnology(会長)
日本動物細胞工学会(会長)、バイオインダストリー協会バイオエンジニアリング研究会(会長)
日本生物工学会関西支部(支部長)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 2月 2023
生物生物工学会誌 第101巻 第2号
山田 修
「巻頭言“随縁随意”」の執筆依頼が来て「学会への提言や若手、学生へのエールなど」を書くようにといわれました。しかし、そもそも、ものを書くほどの実力も実績もありません。そこで改めて、これまでの来し方を振り返ってみると「まったく仕事ができていない」ことに愕然とするとともに、世の中の移り変わりやデジタル界隈のうつろいの早さに驚いてしまいました。特に他に思いもつかないので、爺ぃの昔話を記してみることにします。
大学を卒業して1年間ブラブラした後、国税庁に技官として拾ってもらいました。9か月ほど国税庁醸造試験所で研修を受け、翌年1月に仙台国税局鑑定官室に配属となりました。変則的な時期の異動だったため、醸造指導の真最中、出張で部屋には誰もいなかったことが印象に残っています。また、メーカーに泊まり込みで清酒造りを実地に教わる機会を与えられたものの身につかず、今さらながらきちんと勉強しておけばよかったと悔やんでいます。当時はまだ、国税庁への計数報告は紙テープに打ち出し、切ったり張ったりして行っていました。また、鑑定官室のPC-9801には8インチフロッピーディスクドライブが接続され、そこからMS-DOSやアプリを起動して使っていましたので、広大な20MBのハードディスクが設置された時は感動したものでした。
仙台で数年間勉強したり、醸造試験所で1年間研修を受けたり、霞が関の国税庁酒税課へ1年間実査官として勤務した後、東京国税局鑑定官室分室というところで、全国の鑑定官室から送られてくる計数の集計などに携わることになりました。分室では、紙テープをハードディスクに記録し直して捨てたり、お役御免となったHITAC 10IIというオフコン(オフィスコンピュータ、事務処理用中型計算機)の廃棄を手伝ったりと、片付けに精を出しました。世の中ではWindows 3.1が出回り、DOS/V、PHSなどという話題も出はじめていたような気がします。
その後、首都機能分散というかけ声の余波による醸造試験所の引越しのお手伝いをすることとなり、荷物を送り出しては受け取ったりと、東京と広島とを行きつ戻りつしていました。古いラベルの剥げた試薬や用途もよく分からない機器の廃棄など、ここでも片付けにハリキリました。また、巷ではインターネットという言葉がちらほらと聞こえてきており、移転を機に試験所もインターネットに接続させようと、JPNIC(日本ネットワークインフォメーションセンター)にドメイン名を申請したり、こっそりDNSサーバを立ち上げてもらったりしていました。世の中はWindows 95前夜といったところでした。
引越しが終わると福岡国税局鑑定官室へ鑑定官として配属されました。しかし、鑑定官としての能力がかけらもなく、とある清酒酒造メーカーの社長からは「うちの社員なら即日クビ」と言い渡されたこともありました。福岡は清酒の他に焼酎メーカーも多くあり、初めて蒸留酒造りや黒麹菌などに触れることもできました。MS嫌いからノートPCへLinuxを入れてみたり、HP-200LXを雪山へ担ぎ上げたりしていました。また、PCで組んだツールがそのままMacで動くのを見てJava VMの威力を実感したりしておりました。
福岡で4年間、人様の邪魔にならないようにと過ごした後、独立行政法人化のどさくさにまぎれて醸造研究所へと異動となりました。しかし、ここでも研究者としての経験も力量もまったくなく、不惑を前に途方に暮れてしまいました。なにしろ、初めてPCRという技術を知らされて度肝を抜かれている体たらくでした。研究室では黄麹菌EST解析だ、ゲノム解析だ、と難しい言葉が飛び交っており、なんとか勉強して喰らいついて行こうと四苦八苦していました。このころ福岡で触れた黒麹菌の勉強をほそぼそと始めたのでした。しかし、世の中は、やれプロテオームだ、トランスクリプトームだ、メタボロームだ、携帯だ、スマホだ、5Gだ、Twitterだ、Instagramだ、クラウドだ、テレワークだ、などと怒涛のごとく流れていき、もはや理解不能、とうの昔に追いかけるのを完全に諦めて現在に至っております。
こんな奴でもここまで続けてこられたのは、「なんとかなるさ」という、いい加減さの賜物かもしれません。
著者紹介 独立行政法人 酒類総合研究所 品質・評価研究部門(部門長)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 1月 2023
生物生物工学会誌 第101巻 第1号
酒井 康行
人体応答の理解や予測手法として、生理学性の高いヒト培養細胞系の重要性が急激に増している。この背景には、幹細胞技術に加え、オルガノイドなどの各種三次元培養や共培養、Organ on-a-chipなどの培養技術が揃って急激な進歩を遂げていることがある。最近ではこれらの先進的培養系は、“Micro-Physiological System = MPS”という用語で括られつつある。最近、米国食品医薬品庁(FDA)の動物実験代替法ワーキンググループが、MPS および Organ-on-a-chipについて新たな定義を提案した。これによれば MPSは、オルガノイドや Organon-a-chip といった先進的な細胞培養系をすべて含むきわめて広いものとなり、マイクロ流体デバイス技術を用いる Organ-on-a-chip は、MPS の一つとして位置づけられた。MPS でない培養系は、今や二次元の単一細胞培養ぐらいである。
MPSの研究コミュニティーも急速に整備が進んでいる。欧州では2018年にEuropean Organ-on-a-chip Society(EUROoCS)が、米国では 2021 年から MPS World Summit が組織され、2022 年の初夏に米国ニューオーリンズにて第 1 回のオンサイト会議が開催された。今後は international MPS Society(iMPSS)の設立が予定されている。以上の米国・欧州がリードする流れの特徴は、MPS 研究者とベンダー、ユーザー(医薬品や化学物質・食品など)、規制当局といったステークホルダー間の協調が開発初期からの担保されていることであり、これは当然、近い将来の MPS の規制導入という意向を反映している。他方の背景として、欧州や米国での動物実験代替という社会的要請の高まりも大きい。
さて、多様な臓器構成細胞と広義の MPS 培養技術とをフル活用し、インビボと同様な環境下で細胞を培養することができれば、原理的にはインビボにあるのと同等の機能や応答を発現するはずである。その実現に必要な知見と技術とを現代の我々は手にしつつある。しかし、未だインビボの再現にはほど遠いのが現状でもある。個別臓器の MPS についてでさえ、現代のさまざまな技術は現時点では個別の必要条件に過ぎず、それらをどのように組み合わせれば必要十分条件になるのか、あるいは、まだ足りない条件があるかなどが、依然として明らかでない。これは、ビボを正面から目指す系統的な研究がなされていないためである。我々もプレート培養における酸素の拡散律速の問題を解決することで、専ら嫌気呼吸支配となっている現代の培養系の抜本的な解決の方向を示せたが、それは基本的であるとは言え必要条件に過ぎない。たとえば、成熟機能を人体内臓器細胞のターンオーバーに相当するぐらい長期に培養し、徐々に進行する臓器炎症などの慢性疾患を再現できるかと言えば未達成である。
「適切な細胞群を生体内と同じ環境で培養すれば、原理的には生体内と同様の機能や応答を発現するはず」である。しかしながら、上述の系統的検討の不足という科学的な問題に加え、生物科学コミュニティーの中には多かれ少なかれ「所詮はビトロ」という認識が厳然として存在することも大きな問題に思える。一見完成度が高く見える現代の細胞培養手法体系について、ビボの再現を本気で目指し、科学的根拠に基づく抜本的な改善に乗り出すための道具立てに目途は立った。これを基礎に生物工学者は、「所詮はビトロ」という認識の背後にある現象を科学的に解明し、ビトロとビボの乖離の克服に正面から取り組むべきであるし、我々はそれを可能とする時代に生きている。
著者紹介 東京大学 大学院工学系研究科 化学システム工学専攻(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 12月 2022
生物工学会誌 第100巻 第12号
黒澤 尋
今年(2022年)の大河ドラマは『鎌倉殿の13人』ですが、主人公の北条(江間)義時は、事が起こる度に「なんとかせよ」と面倒を押しつけられる役回りで、困惑しながらも懸命に対処し、難しい局面をなんとか切り抜けていきます。
私は、「なんとかする」というのは、どう対処していいのかわからない事案について、画期的な解決策を見いだして「けりをつける」までには至らずとも、最悪の事態を回避して、状況の改善につながる成果を得ること、と解釈しています。「なんとかせよ」と言われるような事案は、「なんともできませんでした」では済まされない状況下での対処案件ですので、これを引き受けるにはそれなりの覚悟が必要です。
野球で言えば、9回ツーアウトの状況で監督から「なんとかしてこい」と言われて代打に出されたら、監督の意図(期待)は「アウトになるな」ということです。監督の期待に応えるには、デッドボールでも良いので、とにかくアウトにならず、次につなげなければなりません。甲斐なくアウトになりゲームセットということになれば、自分のせいで負けたような印象を持たれてしまう損な役回りです。
どの職場でも同じだと思いますが、誰もやりたがらないが、誰かがやらなければならない面倒な仕事が存在します。そういう仕事というのは、労力のいる割に成果に対する評価が低い(コスパが悪い)か、既成の対処法がなく成果が得られそうにないものです。一方で、上司が「なんとかしなくては」と思っている仕事は、局面打開につながるキーポイントであるといえます。上司に「なんとかしてくれないか」と頼まれる人は、それなりの力量と実績があり、期待がもてる人ということになります。ですから、もしそのような仕事の機会を与えられたなら、引き受けるべきであると思います。
さて、面倒な仕事を引き受ける時の心構えですが、まず「やればできる」という楽観的な気持ちをもつことです。そして「失敗しても命を取られるわけじゃない」(少し大げさですが)と開き直ることです。さらに、報酬(見返り)を求めないことです。「やればできる」というのは、お笑い芸人(独立リーグで野球もしている)の高岸宏行さんの口癖(芸)です。彼は『鎌倉殿の13人』では仁田忠常を演じており、ドラマの台詞としてもこの言葉が使われています(脚本・三谷幸喜)。よく成功した起業家が「ポジティブシンキング」「決してあきらめない」などのキーワードを挙げて話をされますが、「やればできる」というのは、同類のポジティブワードで、一歩踏み出すときの勇気を与えてくれる言葉です。
私は縁あって1990年に山梨大学に助手として採用され、以来、定年まであと数年という歳になる今日まで勤めております。大学教員の仕事は教育研究ですが、この他に(表現は適切ではありませんが)いわゆる雑用があります。大学が新しい教育課程を新設するときには、通称「設置審」というものを受ける必要があります。教育課程の新設は、構想力と各方面との調整・説得が必要で、作成する書類も多いので、膨大な時間を費やすことになる面倒な仕事です。私は学部(学士課程)、修士課程、博士課程における新課程の設置に関わり、3回の設置審に対応することになりました。そして、この経験を通して、物事を「なんとかする」には、己を虚しくして淡々と努力を継続することと、未知の状況に対応する柔軟性と創造性が必要であることを学びました。つまり、私利私欲を捨てて(見返りを期待せず)目標達成に向けた努力を継続する中で、ちょっとした創造的なアイデアをひねり出せば「なんとかなる」ということを自分なりに頓悟しました。これは、「努力をすれば物事はなんとかなる」という単純なことではありません。努力するのは当たり前で、努力をしたら成果が出るというのは幻想です。それに、面倒な仕多事のくは、とっかかりが見えず、どう努力していいかもわからないものです。しばらくの間は、努力というよりは「もがく」という感じだと思います。
人が嫌がる面倒な仕事は重要な仕事なので、勇気をもって引き受けよう。そして、『胆力』をもって、『不撓不屈』の精神で、『虚心坦懐』かつ『機智縦横』に仕事に取り組もう。きっと「なんとかなる」と思います。
著者紹介 山梨大学 生命環境学部 生命工学科(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 11月 2022
生物工学会誌 第100巻 第11号
上平 正道
ヒトゲノムが完全解読された(Science, 1 April 2022 Special Issue)。今年は生物工学会100周年、新型コロナウイルスのパンデミック克服(希望的観測)とともに記念すべき年となった。なぜ、今更ヒトゲノム解析の話題かと思われる読者もあるかもしれないが、約 20年前、2003年にヒトゲノム解読完了が宣言された際には、当時解析困難なリピート配列など、ヒトゲノム全配列(30億5000万塩基対)のうち 15 %が未解読であり、2017年の時点でも全体の約8%、2億塩基対が未解読であったが、それがついに完全解読されたのである。ヒトゲノムプロジェクトが開始されて約30年後の快挙だ。残っていた2億塩基対にはタンパク質をコードする遺伝子が115含まれており、ヒトの遺伝子は合計で1万9969個になった。ヒトゲノムプロジェクト開始当初10万と見積もられていた遺伝子数が、ドラフトシーケンス解析後に3万数千と見積もられ、結局は約2万であったという事実に、他の生物種と比べて意外と少なかったというのが大方の見解となっている。完全解読はされていなくとも2003年以降、ポストゲノムが叫ばれる時代になってヒトゲノム配列情報が医療に与えた影響には絶大なものがあり、個人のゲノム情報に基づいたゲノム医療が現実のものとなってきている。いうまでもなく、配列自体は情報であり機能を示すものではなく、ヒトゲノムの完全解読によって生物学や医学に新しい何かが見えてくるかは未知である。しかし、我々自身を知るうえで重要な情報が加わったことには間違いない。
今回の快挙に配列解析技術の進歩は不可欠な要素であった。コストの低減に加えて、高精度で長鎖の配列解析が可能になったことによるものである。ポストゲノムの2000年代中ごろから始まった大規模シーケンス技術開発によって、1人のゲノム解析に1億ドルといわれたコストが、ムーアの法則を大幅にこえる勢いで低下して、この20年間で1000ドル以下にまで低減し、この流れは現在も続いている。この分野で日本の技術が具現化されていないことは悔しいところである。ゲノム解析の先にあるゲノム編集・改変の分野での技術開発競争の遅れも指摘されているが、生物工学会からの技術発信も含めてこれからの巻き返しを期待したい。
学会が創設された100年前には遺伝子の物質としての存在もわからなかったのが、今ではあたり前のように遺伝子の働きを意識しながら細胞の機能改変を行っている。つまり、細胞機能の遺伝子的改変を通して生物をデザインすることが可能になっている。過去の状況から考えてもわかるように、さらに20年、50年、100年後の未来に出現するであろう新たな技術によってどのような状況になっているか、 SFの世界観に立って想像をめぐらせても、予見することは難しい。生物としての我々自身についてもわからないことが多いのだが、いつか、意識、本能、進化といった生物の謎は解明できるのか、それらに共通する意志(魂)の働きを証明できるのか。一寸の虫にも五分の魂、1 μmのバクテリアにも魂の存在を確信しているのであるが、その実体を科学的に説明することができるようになるのか。ものごとの根源である量子物理とのシームレスな関係性は見いだせるのか。現在との接点として量子コンピュータ、人工知能(AI)、仮想現実(VR)技術の進展により時空をこえた解析が可能となり、いつの日か人類が生み出した科学が生物の謎を解明することを夢見ている。
著者紹介 九州大学大学院工学研究院(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報,生物工学会誌
Published by 学会事務局 on 25 10月 2022
生物工学会誌 第100巻 第10号
大城 隆
年号が昭和から平成に変わった頃、全国の工学部にバイオ系学科が数多く設立された。私の所属している学科もその一つで、1989(平成元)年に鳥取大学工学部生物応用工学科は発足した。私は、入学1期生が卒業研究に着手する前の1991年、ちょうどバブルがはじけつつあったころに、6年余り勤務した民間企業から赴任した。それからもう30年以上になる。翌1992年、生物工学会は創立70周年を機に、醱酵工学会から名称変更し、現在に至っている。年次大会は1967年からは長らく、大阪の日本生命中之島研修所で開催されていたが、私が大学院を修了した1985年(昭和60年:この年の出来事は、本誌「キャリアデザイン」に書かせていただいた1))に大阪を離れて東京大学教養部で開かれ、それ以降は全国で実施されるようになった。私も企業在籍中に大会で発表する機会に恵まれ、会員番号は1000番台である。このように、私が大学院を修了してから5年余りの期間に、生物工学会はダイナミックに変化を遂げ、年次大会も規模が大きくなり、研究対象を大きく広げて展開していった。バイオテクノロジーと呼ばれ始めた技術の発展は目覚ましく、学会の体制もそれに呼応して変わっていったのは当然のことである。ここ数年の年次大会では毎回、アジアの研究者を交えたシンポジウムが企画される一方、地域に目を向けた取組みも行われ、いわゆるグローカルな視点を持つ学会へ変貌を遂げている。
私自身はというと、大学へ赴任してからいろいろな研究テーマに関わり、学生さんの指導を行うとともに、自らもピペットマンを握り、日々実験に勤しんでいた。修士課程から企業に就職し、学位を取得していなかったため、当初は研究成果が出れば、学会発表、論文投稿というサイクルを繰り返し、少しずつではあるが学術成果を積み重ねていた。また、赴任時から、海外の大学との共同研究を複数行っており、オランダの大学に2か月、フランスの大学に半月、イギリスの大学に1週間ほど滞在させてもらったことがある一方、何人かのポスドクの研究者がオランダから鳥取へ来たこともあった。海外の研究者の考え方は新鮮で、当時の学生さんに強い影響を与えたと思うし、私自身もいろいろな面で感化された。それから10年ほど時が経ち、2004年の国立大学独立法人化後の2006年からは、文科省の地域を対象とした科学技術振興プロジェクトに参加させていただいた関係で、海外とのつながりよりも、地域の中小企業や鳥取県との接触が増えてきた。その後、2016 年から始まった国立大学の第3期中期目標期間において、全国86の国立大学法人のうち、本学も含め55大学が“地域のニーズに応える研究”の推進に対して重点支援を受けるようになった。本年度からの第4期においても、私自身、地域資源を生かした研究およびそれを社会実装へ展開する試みを行うつもりである。地域での活動は、時間がかかることが多いのを実感しつつも、微力ながら感触が掴めつつある今日この頃である。以上、振り返ってみれば鳥取へ赴任してから、前半は海外へ、後半は地域へ目を向けた研究を行ってきたことになる。
最後になるが、地方大学の学生さんの就活について……地方大学ではどうしても移動のデメリットがあり、4年生と博士前期2年生は春先から夏場にかけて研究活動が停止することが常であった。しかし、コロナ禍により企業による選考の初期段階の大部分がオンライン開催になった。もちろん、オンラインであれ面接対策に時間は要するため、学生さんは研究室に来ていても実験の手が進まないことが多いが、関西圏、首都圏に移動する必要がなくなったので、この時期の研究室の様子はかなり変わったと思う。コロナ後も、是非この形式での選考が続くことを望んでいる。
そして、入社後のポストコロナの時代では是非海外へ目を向けた行動をしてほしいものである。
1) 大城 隆:生物工学,98, 259 (2020).
著者紹介 鳥取大学 研究推進機構 未利用生物資源活用研究センター(センター長)
鳥取大学 工学部 化学バイオ系学科(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 9月 2022
生物工学会誌 第100巻 第9号
上田 宏
コロナ禍にもようやく明るさが見えてきた栄えある100周年である。しかし、発酵反応よりも発光酵素に興味があるような私がここで何を書くべきかと悩んだ結果、今回は自分の研究者としての原点を振り返りつつ考えたことを少し述べてみたい。
もともと筆者は、高校生の頃は、生物や化学よりも物理や電子工作に興味がある、いわゆる秋葉系少年であり、その応用として色々なセンサーにも興味があった。ただ、大学ではこれらのある意味確立した世界で飯を食うのも面白くないと思い、進学振り分けでは大いに悩んでいた。忘れもしない2年生の夏、恥ずかしながらある授業の試験日を一日早く勘違いし、呆然として大学生協に向かったところ、そこに平積みされていた恩師西村肇東大名誉教授の書かれた著書『冒険する頭―新しい科学の世界』(ちくま書房、1983年、絶版だがネットで読むことが可能)に出会った。元々彼が行っていた「環境問題研究法」という、土曜日の全学研究ゼミナールという授業に何回か出席して興味を持っていたことと、環境問題の解決のためにプロセス工学の手法を用いるという斬新さ、さらに、これからバイオに挑むという話に知的冒険心をくすぐられて化学工学科を選び、4年生で西村研に所属した。
そして修士課程で現在の研究の原型である、抗体に信号伝達能(その時はタンパク質チロシンリン酸化活性)を与えるという、恩師の発想による奇想天外なテーマを選んだ。当時の利根川進、本庶佑らによる免疫系と、Weizmann InstituteのJ. Schlessingerや山本雅らによるタンパク質チロシンキナーゼの分子生物学研究のめくるめく発展を目の当たりにしつつ、最初はディープフリーザーさえも他研究室に借りに行くような限りある研究環境で悪戦苦闘しながら、時間はかかったが何とか目的(抗原結合依存的に2量体を形成して活性化する酵素)と博士の学位(これ重要)を得ることができた。
その後、恩師がその成果をアメリカの分子認識に関する国際会議で発表したところ、幸い、ある診断会社(ベーリンガーマンハイム、現Roche Diagnostics)の目にとまり、新しい診断法の開発に関する国際共同研究へとつながった。さらに数年の悪戦苦闘の末、幸いにも、これが抗原結合による抗体の安定化を原理とする免疫測定法であるオープンサンドイッチ法の開発と、共同研究先であった英国MRCのGreg Winter研への留学へとつながった。
Winter先生は当時からファージ提示法を用いたヒト型抗体構築法の開発で著名であったが、最近(2018年)、分子進化法のテーマでノーベル化学賞をF. Arnold、G. Smithと共同受賞されている。留学中は周囲にかなりの迷惑をかけたと自覚しているが、福﨑会長はじめ多くの方にラボを訪問していただいたり、10年に1つ会社を立ち上げるイノベーターでもあるWinter先生とは帰国後も仲良くさせていただいている。
Winter先生には、本年、東工大の生命理工学院と学術振興会が主催するHOPE meetingでのオンライン講演なども快く引き受けていただいたので、多少の役目は果たせたかもしれない。また、オープンサンドイッチ法は、その後多くの低分子の非競合的な検出に応用することができ、ここから派生した蛍光バイオセンサー(クエンチ抗体)の創出と関連ベンチャーの創業にもつながった。
これらを思い返すに、独創的な研究や開発における重要な要素として、野心的だが本質を突いた、斬新で魅力的な発想の果たす役割が大きいと感じる。我々はそのような発想とそれを与えてくれた人物に憧れ、訪れるはずの成功を信じて試行錯誤を繰り返し、運も味方にしつつ、それを次の研究や開発、さらに次世代につなげる使命を負っているのではないだろうか?先達を良いお手本としつつ、彼らに追いつき、全部は無理でも部分的には追い越す気概が、結果として日本の科学技術の再活性化にもつながる気がしてならない。私レベルの人間が言うのも面映いが、その為にも、老若男女問わずに最低5年位は周囲の声を気にせず無謀な挑戦が許される研究環境が、経済的には昔より厳しいかもしれない今後も、最優先で維持されて欲しいと強く願うものである。
ちなみに、卒寿を目前とした恩師は未だお元気で、この秋にはクラウドファンディングによる新著の発売を予定されている。一連の100周年記念行事と共に、楽しみにしているところである
著者紹介 東京工業大学科学技術創成研究院化学生命科学研究所(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 8月 2022
生物工学会誌 第100巻 第8号
魚住 信之
新型コロナウイルスで世の中が右往左往しているためか、ウイルスという言葉から心に浮んだ思い出がある。学生の時、『蛋白質 核酸 酵素』という月刊誌(2010年1月号にて休刊)が研究室においてあった。毎月、ぱらぱらとめくって、その時の分子生物学分野の流れやキーワードを拾っていたように思う。ある時、珍しく、バクテリオファージの総説を読み始めたことがある。実は、そのウイルスに興味があったわけではなく、内容がとても面白かったからである。『蛋白質 核酸 酵素』はまじめな科学雑誌であるので、笑みを浮かべて読むような雑誌ではない。私が笑いながら読んでいるので、「大丈夫か?」と研究室の友人にからかわれた。
その総説1) は、当時としては珍しく、ふた月にわたって林多紀(Masaki Hayashi)先生が一人で執筆されていた。林先生は、ファージの分子機構を解明し、再構成系を構築した分子生物学の先駆者であり、ノーベル賞を受賞された利根川進博士の大学院時代のアドバイザー(指導教員)でもある。この総説の前半では、林先生自身が経験した研究にまつわる出来事がユーモアを交えて記述されており、主題であるはずのφX174ファージに関する内容は記述されていなかった。しかし、大学院生の私は研究生活を垣間見たようで、とても参考になるものであった。「子供の時に憧れを抱いていた博士論文を書くことが、やってみるとこんなにつまらない作業で、それよりも研究がしたかった」という内容は心に残っている。体裁を整える作業よりも、研究にワクワクしていることが伝わった。思い描くことと現実は違い、実際に体験しないと分からないのだろうと想像した。
私は他学部の助手になり博士の学位を頂いた後、海外の研究室を探す際に大学時代の恩師に相談した。数年間外国でポスドクをされた経験にもとづいたアドバイスは貴重であった。「研究者は一匹狼なのだから、希望する研究者に手紙を出すことです」と教えていただいた。この「一匹狼」という言葉が心に沁み、面識もコネもなく単に興味がある異分野の専門家に手紙を出したところ、採用いただいた。この研究室は、偶然にも林先生と同じ大学であった。そして、ふらりと先生の研究室を訪ねたことがある。林先生はちょうどご在室であったが、ご迷惑であろうから挨拶だけさせていただいて帰ろうと思っていたところ、「妙な日本人がやって来た」と思われたのか、オフィスでお話をさせていただいた。「あなたと同じように、他の人にもあの総説を褒められた。“私”という言葉を、わざとあの和文総説では使用しなかった」と、隠れたこだわりを教えていただいた。さらに、林先生はご自身の学生時代を振り返り、「異国における初めての講義で分かった内容はすでに知っていたことだけだった。つまり、何も英語で理解できていないことが分かった」と思い出を述べられた。秀でた科学的成果をあげた研究者の、大学院における「はじまり」を教えていただいた。
あれから年月がたち、お会いした時の林先生の齢に私も近づきつつあるが、かっこいい研究者の像は変わっていない。分子生物学の黎明期から、生命現象の巧みさに驚嘆し、真に良い研究を遂行しようとする林先生の姿に美しさを感じた。また、黎明の頃から脈々と流れる科学的知見は、競争というよりも、時間と空間を超えた研究者による共同作業の賜物であるとつくづく感じる。さて、自分自身はどうなのだろうか。科学の世界の端くれで没落していないか。紙一枚、一枚とわずかであっても新たな研究結果の積み重ねに参加しているのかと、自戒するのである。
1) 林 多紀:蛋白質 核酸 酵素、4, 363 (1988).
著者紹介 東北大学大学院工学研究科(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 7月 2022
生物工学会誌 第100巻 第7号
髙木 忍
大学の研究に「出口」として社会実装が求められるようになったのは、 いつの頃からだろう。個人的には、 大学にこそ基礎研究を行って欲しいと考えているので、 上記の方針はいかがなものかと感じている。一方で、 サイエンスは我々の生活を豊かにしてくれると堅く信じているので、 日本の大学から世界を救うイノベーションが起こることを願い、 期待している。現在、 世界における社会課題をみつめ、 地球規模で目指すべき17の目標、 SDGsが示されている。本学会会員により近い分野としては、 内閣府が「バイオ戦略」を策定し取り組むべき市場領域を示しているほか、 経済産業省1)や農林水産省2)も今後重点的に取り組む課題分野を示している。これらの分野でイノベーションを起こすことができれば、 社会へのインパクトは大きい。
世界経済フォーラムによるイノベーションランキングによれば、 日本は研究開発における産学協業が他の先進国に比べて劣っているらしい(2018年18位、 2019年25位)。発酵工学をはじめとする生物工学分野の歴史をみると、 かつては学界が産業界を牽引していた時期があったが、 その後、 企業が自社の開発力を向上させ、 大学に頼る機会が減少した。このため、 大学と企業との間に距離感が生じ、 大学側も産業界の「ニーズ」を拾える機会が減ったのではないだろうか。国内の大学における研究テーマは、 他国に比べて「基礎原理の追求」に偏り、 「問題解決」の視点に乏しいという指摘もある。企業のニーズは、 ほぼ問題解決に直結しているので、 企業ニーズを念頭においた研究は、 産業の発展により反映しやすいと言える。近年、 大学の「シーズ」をなんとか企業にマッチングできないかという努力が見受けられるが、 大学のシーズが企業のニーズに合うもので、 かつシーズが十分公開・宣伝されていれば、 企業の方からアプローチされるに違いない。アプローチのないシーズは、 残念ながら今の産業界では出番がないということになる。大学のシーズと企業のニーズが噛み合うような仕組みができれば、 国内のイノベーション力も強化できるのではないだろうか。
シーズとニーズが噛み合った産学協業を増やすには、 双方の歩み寄りが必要であろう。本学会が取り組んでいるように産学官の交流を増やし、 日頃から互いの強み・弱みについて理解し合えば、 互いに分業し開発に取り組む協業の芽が生まれてくると期待できる。諸外国では企業が大学に資金提供をし、 学術研究を支えているが、 残念ながら国内ではそのような資金提供は限られる。2015年のOECDのデータ3)によれば、 大学の研究資金のうち企業から提供された資金の割合は、 中国、 ドイツでは15.5%、 13%であったのに対し、 日本は2.6%である。双方の歩み寄りにより協業体制が増えれば、 資金の流れも変わってくるであろう。一方で、 現在は技術革新の過渡期にあるため、 産学協業にとってはチャンスかもしれない。コロナ禍など社会情勢による生活様式の変化、 気候変動や地球環境汚染の深刻化、 デジタル化・AIの利用が進んだ第五次産業革命など、 新規事業や技術革新が今後益々重要となり、 企業側も変革を求められている。このようなときこそ企業は新たな技術・知識を必要とし、 大学の存在感が増してくる。産学協業の絶好のチャンスではなかろうか。
誤解のないように付け加えると、 国内の大学と企業との共同研究は、 件数・金額共に増加している4)。その上で、 尚イノベーション力が低いという汚名を払拭できるような活躍を本学会員に期待したいのである。最先端の研究成果を収めているアカデミアと産学官の連携があれば、 きっと可能であるに違いない。
1) 経済産業省 バイオ小委員会 報告書「バイオテクノロジーが拓く『第五次産業革命』」(2021年2月)
2) 農林水産省「緑の食料システム戦略」:
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/index.html (2022/4/22).
3) 日本学術会議「学術の総合的発展と社会のイノベーションに資する研究資金制度のあり方に関する提言」(平成29年8月22日), p. 10:
https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-t248-3.pdf (2022/5/11).
4) 金間大介, 高野里紗:研究 技術 計画, 35, 339 (2020).
著者紹介 千葉大学(非常勤講師)、 STグローバル バイオ・ネット
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 6月 2022
生物工学会誌 第100巻 第6号
湯本 勳
毎年、大学に入学したばかりの1年生に2コマだけ講義を行っており、その一方で修士の学生さんにも何年かに一度集中講義を行っています。また、大学に在籍する海外からの留学生と一緒に研究を行っています。このようなスナップショットでのみ接している立場から学生さんに対する思いを記述させていただきます。
1年生の講義のテーマは「極限環境微生物学入門」であることから、講義の最後に「極限環境微生物に関する内容であればなんでもOKで、できるだけ自分の頭で考えたことがわかるようなレポートを作成してください」とお願いしています。こちらの意図は、頭を使って企画して独自の考えを書いてもらうことにあります。受け取ったレポートのうち、毎年10 %強は非常に興味深いものや後々まで印象に残っているものがあります。たとえば、講義で説明した核心部分を分かりやすく、より身近な例を使ってたとえ話に置き換えて説明しているものや、レポート以外の選択肢として簡単な設問に簡単に答えるという形式を提示していますが、それに対して講義の内容を含めたかなり詳細な解説を加えた解を作成したものなどがありました。印象に残るレポートを提出してくれた学生さんは講義の内容をよく理解し、レポートに上手に反映させていたことになります。モチベーションも高く、発想力も豊かな学生さんもいる中、素晴らしい個性が伸びるように誘導していくことは、重要なことだと考えています。
一方、修士の学生さんにも講義の終了後、同じような条件でレポートの提出をお願いしています。修士の学生さん達は皆それなりのベテランであることから、レポートのことを説明する際には「できるだけ自分の頭で考えたことが分かるようなレポートを作成してください」とはお願いしていません。このようなこともあってのことかもしれませんが、私にとって目を引くようなレポートの数は1年生の場合よりもかなり少ないのが現状です。修士の学生さんにとって私の講義やレポート提出に対する新鮮さはほとんど無く、単位をもらうために講義を受け身の姿勢で受け、仕方なくレポートを提出しているようにも見えます。こちらとしては、明らかにモチベーションの誘導に失敗しています。学生さん達の本当の実力を見るために、今後は修士の学生さんにはこちらの意図を十分説明するなど、嬉々として頭を使って取り組むための方策を考えなければならないと感じています。
最後に、海外から来る留学生の大学院生ですが、将来自立していかなければならない立場にいる意識が低いように感じられることが多いです。大学院では学部とは異なり「自分に合った良い問いを発見する能力」と「良い問いを解決する能力」や「トライ&エラーと思考を繰り返すサイクルにより可能性を少しずつ詰め、結果を手繰り寄せる能力」を伸ばすことが重要であることを分かってもらわなければならない場合が多いと感じています。プレゼン資料を見ると、得られたデータから何が言えるのかを考えやすいように情報整理をしたうえで、引き出せる事実は何なのかを真剣に考えた形跡はあまりみられないことが多く、自分で経験を深化させることの重要性や考えることは楽しいことをもっと分かってもらわなければならないと考えています。
大学に入学すると高校までとは異なり、さまざまな面で自由度が高まるわけですが、その自由度をうまく利用すれば独創性の高い「問い」を発見し、考える能力を養うことは可能だと思われます。それぞれの段階に応じたモチベーションの維持を通じて経験を深め、独力で「解」を発見する喜びを経験できるような頭の鍛え方を実践していくことが有意義な学生生活を送るために重要なのではないかと考えています。指導教官は学生との対話や研究に関する議論を通じて、学生が既成概念にとらわれず、答えが無いかもしれない「問い」に対しても嬉々として挑戦し、自らの夢や目標に向かって積極的に経験を重ねていくように誘導していかなければならないと考えています。
著者紹介 産業技術総合研究所(つくば第六事業所長)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 5月 2022
生物工学会誌 第100巻 第5号
村田 幸作
新型コロナウイルス感染症は大学の教育と研究にも影を落とした。講義は専らオンラインであったと聞く。私の学生時代(1970年頃)と似ていなくもない。大学紛争の煽りを受けて講義も疎らになり、時にはキャンパスも封鎖された。そのため故郷で過ごすことが多かった。彼のニュートンもそうであったようだ。黒死病の流行で大学が閉鎖されたため故郷に帰った。ただ、彼はそこで重力の発見など重要な仕事をした。私は野良仕事をした。あれから50年、今、体力勝負の運命的な「巣篭り」の中にある。
その中で自分の研究を振り返ると、その内容は三つに集約される。有用物質(NADP、グルタチオン他)の生産、巨大物質(多糖、DNA)の輸送機構、およびそれらに関連するタンパク質の構造生物学である。その中にピカッと光る(と、自分が思っているだけの)発見が幾つかあった。二、三拾ってみる。NADP生産の研究では、ヒトのミトコンドリアに初めてNADキナーゼ(1980年に発見した細菌型酵素)を発見した1,2)。多糖輸送とタンパク質構造の研究では、鞭毛タンパク質フラジェリンは多糖アルギン酸の結合タンパク質であり、細菌の細胞表層に局在することを証明した3)。また、細菌に巨大物質を丸呑みする動物まがいの口を発見し、その口は他の細菌に移植できることも示した4)。独創的な研究を……、と意気込み、何か変わったことを意識して追い求めていた訳でもない。目的からはみ出たこれらの成果は、研究過程で偶然に行きついたものである。
中でも細菌の口の発見は偶然にして印象的であった。この細菌はアルギン酸を大の好物とする。しかし、細胞外でこれを細かく切る手段を持たない。生物は奥の手というか、容易には分からない策を秘めているものである。アルギン酸を食べる口を隠し持っていた5)。それだけではない。鞭毛を使ってアルギン酸の在りかを探り、身の周りにはフラジェリンをまとってアルギン酸をかき集めていた。細胞表層分子を動かして口を開け閉めし、アルギン酸を丸呑みしていたのである。どうしてもアルギン酸を食べたい!この一念が、私をしてこの口の発見に至らしめたのかもしれない。この真っすぐな意志が物質に介入し、化学反応を誘い出し、情報量を増やし、多くのタンパク質をリクルートしてこのシステムを創り上げたのかもしれない。そんな感じさえした。細胞には表と裏がありそうにも思える。アルギン酸とフラジェリンの密接な関係も気になる。この偶然の発見は、知識や論理の枠組みにも影響を及ぼし、新たな微生物学の途を模索する一つのアプローチになるかとも思えた。
しかし、セレンディピティと云う言葉が意味するかもしれないこうした偶然的な発見は、求めて求められるものではない。そこでは偶然を引き出し、偶然を見逃さない力が働いているのであろう。それは関連科学への広い関心力は元より、脳科学が示唆する“ぼんやり状態”での創造力のようなものまでも含むであろう。その意味に於いて、偶然はもはや偶然ではない。それはそのような力によって準備されたものである。育むべきは偶然の現象への敏い観察力と、たとえそれがノイズのようなものであろうとも、それを科学的に検証する意欲であることを実感させられる。
2021年、世界における日本の高頻度被引用論文数の占有率ランクは、2018年にはインドにも抜かれ、一桁から二桁に急落したと報じられた。こうした評価の意義はさておき、独創的な論文が減りつつあるのだろうか。
“どのような研究の中にもノーベル賞に値する現象が一つか二つはあるものだ”とも聞く。そうした偶然の現象に分け入り、独創的な面白い研究を展開したいものだ。コロナ禍の恩恵でもあろうか、そうしたことを運命的な「巣篭り」の中で考えている。後の祭りだが。
1) Ohashi, K. et al.: Nat. Commun., 3, 1248 (2012).
2) Murata, K.: Proc. Jpn. Acad., Ser. B Phys. Biol. Sci., 97, 479 (2021).
3) Maruyama, Y. et al.: Biochemistry, 47, 1393 (2008).
4) Aso, Y. et al.: Nat. Biotechnol., 24, 188 (2006).
5) Maruyama, Y. et al.: Structure, 23, 1643 (2015).
著者紹介 京都大学名誉教授、本会功労会員
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 4月 2022
生物工学会誌 第100巻 第4号
民谷 栄一
2022年を迎え 、新型コロナウイルスオミクロン株の大流行に世界中が再び悩まされる状況になった 。そのコロナ禍のため1年遅れで開催された昨年の東京オリンピックであったが 、筆者の年代になると前回の東京開催の1964年のことを思い出す 。筆者は当時小学生であり 、学校に導入されたばかりのカラーテレビを教室で見ながら日本人選手を応援した 。それから半世紀余りが過ぎたが 、その当時からライフスタイルは大きく変化した 。
今日 、ほぼ全員がPCやスマホを持ち 、インターネットを通じてさまざまな情報にいつでもアクセスができるようになり 、それを行動のベースとするような生活様式も一般的になってきている 。さらにAIも積極的に活用されるようになった 。これらのことは 、物理学や情報分野における科学技術の発展が基礎となっている 。1920年代に提案・確立された量子力学は 、今日のエレクトロニクス 、フォトニクスの基礎ともなり 、半導体を用いたトランジスタ(1948年)の発明 、半導体レーザーの開発(1970年) 、Intelによるマイクロプロセッサー(1971年) 、Apple社のPC(1977年) 、光ファイバー通信(1981年) 、インターネット標準化(1982年) 、携帯電話事業(1985年)へと展開された 。さらに 、iPhone(2007年) 、4G開始(2010年) 、AI AlphaGo(アルファ碁)(2016年) 、5G開始(2020年)と今日に至っている 。こうした怒涛の如く進展した情報技術が今日の我々の日常生活の基盤となっているのは言うまでもない 。
一方 、バイオサイエンス・テクノロジー分野においても華々しい進展があった 。従来の発酵などに代表されるオールドバイオテクノロジーから 、遺伝子(組換え技術1972年)やタンパク質(モノクロナール抗体1975年)など分子レベルでの設計や操作を可能としたニューバイオテクノロジーが生まれた 。新型コロナウイルスの診断で毎日ニュースにも出てくるPCR技術(1983年)やDNAシーケンシング技術(1977年)も開発された 。ファイザーやモデルナのワクチンで用いられているmRNAからタンパク質への翻訳に関しても1980年代に明らかとなっている 。筆者の専門とするバイオセンサー分野においても 、酵素センサー(1967年) 、ELISAイムノアッセイ(1971年) 、SPRバイオアッセイ(1986年) 、DNAチップ(1989年)などが開発された 。
以上のように 、この100年の間に人類史上において 、爆発的に科学技術が進展した 。人類史をホモサピエンス出現からとすれば数10万年の歴史があるといわれている 。その最後の100年というきわめて短い期間での出来事である 。もし 、100年前に生まれていたなら 、こうした科学技術の恩恵は受けられなかった事になる 。
今日のコロナ禍と100年前のスペイン風邪(1918–19年)はよく比較されている 。科学技術の観点から見ると 、100年前の状況は今日と相当に異なる 。スペイン風邪は 、その原因はインフルエンザA型であることが後になってわかるが 、その当時は 、ウイルスの存在自体まだ認知されていなかった 。
第1回ノーベル賞候補にもなった北里柴三郎は 、コッホの研究室で微生物学を学び 、破傷風菌の純粋培養に成功し 、抗毒素の発見や血清療法の開発などの大きな業績をあげた 。スペイン風邪の時にも原因を探ろうとしたが、ウイルスの発見には至らなかった 。その当時は光学顕微鏡では見えないウイルスの存在は確認できなかったためであろう 。1930年代になり電子顕微鏡が開発されると 、ウイルスを実像として目にすることができた 。電子顕微鏡に限らず 、計測技術の発展は科学の進歩に大きな貢献をした 。
ところで 、武漢から始まった新型コロナウイルス感染症の実体であるウイルスの塩基配列が 、Nature誌に報告された1) 。それによれば 、2019年12月26日に入院した患者の6日間の病状の変化を追跡すると同時に塩基配列を解析し 、論文原稿は2020年の1月7日には投稿された 。このように1–2週間程度でウイルスのゲノムが明らかにされている 。これには次世代シーケンサーや蓄積された遺伝子データーベースの貢献が大きい 。また 、その配列をもとにPCRのプライマーも設計され 、迅速診断を可能とした 。ワクチンもスペイン風邪の時はまだ開発されていなかった 。今日 、高い有効性を示すと報告されたファイザーやモデルナのワクチンはRNAを脂質膜に包括したものである 。このように 、科学技術の進展によりスペイン風邪の時とはまったく異なり 、病原体の原因を探り 、対処するための術を我々はいくつも手にしている 。
今日に生きる我々は 、こうした科学技術の恩恵をリアルタイムに受けていることを再認識するとともに 、さらなる発展のためには 、次世代を担う科学技術人材の育成を強力に推進すべきと思う次第である(2022年1月13日執筆) 。
1) Wu, F. et al.: Nature, 579, 265 (2020).
著者紹介
産業技術総合研究所 先端フォトニクス・バイオセンシング オープンイノベーションラボラトリ(ラボ長)
大阪大学 産業科学研究所(特任教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報,生物工学会誌
Published by 学会事務局 on 25 3月 2022
生物工学会誌 第100巻 第3号
中濱 一雄
京都市の比叡山西麓に紅葉と霧島つつじで名高い曼殊院がある。門跡寺院であるため格式が高く、築地塀に5本の横線があるのはその証である。その境内に微生物を供養するための「菌塚」がある。
今から約40年前に、食品用・工業用酵素を製造・販売していた大和化成株式会社の取締役社長であった笠坊武夫氏は、社長退任を機に「人類のため多大な貢献をし、犠牲となった菌類に感謝し、また供養する」ため、菌塚を建てることを思い立った。菌塚の建立について相談を受けた発酵研究所の長谷川武治所長は、発酵研究所の理事で発酵・醸造学の世界的権威であった坂口謹一郎東京大学名誉教授を笠坊氏に紹介した。
菌塚は自然石の石碑で坂口名誉教授の揮毫による「菌塚」の題字が彫られている。1981年5月16日に菌塚の除幕法要が行われ、多くの関係者が参列した。その後、曼殊院では毎年5月に法要を行っていたが、知名度が低く、参列者は少なかった。
2013年5月に曼殊院の松景崇誓執事長から「久しぶりに多くの方に参列していただいて菌塚の法要をしたいので協力してほしい」との依頼があり、発酵研究所が全面的に協力することになった。2014年5月26日に33年ぶりに盛大な法要が執り行われ、雨天にもかかわらず、大学や企業の微生物研究者および京都大学の大学院生・学生を含めて約100名が参列した。法要の願主は菌塚を建立した笠坊武夫氏のご子息である笠坊俊行氏。法要は当院の藤 光賢門主の読経から始まり、参列者の焼香で滞りなく終了した。菌塚は微生物の「供養塚」であるが、この下に枯草菌の遺灰が納められていることから「お墓」でもある。
このようなものは外国にはない。おそらく欧米人には理解できないであろう。これは次のような宗教観の違いによるものと思われる。日本では古来「万物に魂が宿る」とあるように、すべての生き物には人と同じく命があると考えてきた。この生き物には、当然、微生物も含まれる。一方、キリスト教の聖典である旧約聖書の創世記に「すべての草、すべての木、すべての生きて動くものはあなたがたの食物となろう」とあるように、欧米では「人間以外の生き物は人間のためにある」と考えるので、これらを供養することはあり得ない。同じ創世記のモーセの十戒には「あなたは殺してはならない」とあるが、これは「人を殺してはならない」という意味である。一方、我が国の支配的な宗教である仏教の五戒にある「不殺生戒」では、あらゆる生き物を殺してはいけない。この生き物とは、人間は当然のこととして、動物、植物および微生物も含まれる。
このようにモーセの十戒よりも仏教の五戒のほうが厳格に思える。しかし、人間が生きていくためには、生き物である動物、植物、微生物を食べることは避けられない。五戒は「これらの生き物を食べる(殺す)ことはやむを得ないが、そのかわり、これらに対して贖罪の思いをこめて感謝することが大切である」と教える。五戒の「不殺生戒」の意味を理解すると、菌塚が建立された趣意がよくわかる。私たちは納豆や漬物を食べることによって、枯草菌や乳酸菌を殺すことになる。醸造や発酵工業では、発酵生産が終わると殺菌・滅菌する。微生物を扱う大学の研究室では、実験後には微生物をオートクレーブで滅菌することが義務付けられている。このように、食品、生産、研究など人類にたいへん役に立ち、犠牲となった微生物に感謝するために、この菌塚がある。京都大学では発酵関係の講義で菌塚について説明し、大学院生・学生に参拝させている。素晴らしいことである。
微生物を扱う研究者には、「よい研究ができるのは微生物のお蔭である。ありがたい」と微生物に感謝するとともに、研究で得られた貴重な微生物株を死滅させないよう大切に保存することを心掛けていただきたい。微生物をこよなく愛し、大切にしてほしい。
著者紹介 公益財団法人発酵研究所(理事長)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
FAQ,新着情報
Published by 学会事務局 on 25 2月 2022
生物工学会誌 第100巻 第2号
東 雅之
大阪市立大学工学研究科の東です。所属につきましては現在大阪府立大学との統合の準備を進めており、2022年4月には大阪公立大学として開学予定です。実現すれば学生数約1万6千人規模の公立総合大学となります。新大学におきましても引き続きご指導よろしくお願い致します。巻頭言のお話を頂き、大学の小さな研究室で長年研究しているだけですので躊躇しましたが、稀にはそのような立場からの話があっても良いかと開き直りお引き受けさせていただきました。
これまでの一会員としての日本生物工学会での活動を振り返りますと、年次大会を研究室の主要な発表の場として利用し、学生さんには研究室所属期間中に少なくとも1回は発表するように指導しています。今はコロナ禍ということで懇親会は開催されていませんが、醸造メーカーなどで開催される醗酵学懇話会に毎年学生さんを連れて行き、お酒を飲みながら楽しんできました。『生物工学会誌』のバイオミディアにも長年お世話になっており、大学院講義での学生の調査発表に利用しています。また、JABEE特別部会や研究部会において諸先生方と交流させていただき、年会費11,000円で十分元をとり楽しんでいます(小研究室なのであまり他学会に浮気できないという事情もあります)。関西地区では発酵(生物工学)野球大会が行われ、学会でお馴染みの大学関係者の皆様とも交流させていただいています。台風やコロナ禍の影響でしばらく開催できず、直近の大会で優勝してから長年優勝カップを研究室に置いています。再開を楽しみにしています。
少し研究室の話にも踏み込みますと、運営資金は毎年の悩みで、大型資金は難関ですので、小口資金を複数集めながらの運営で何とか凌ぐことを長年続け、修士課程の学生さんを中心に研究を回しています。研究室では微生物の細胞表層構造に着目し、それらの改変による工学的応用を目指しています。最近では、酵母の表層に化学修飾を加えた機能性材料を開発し1)、その応用を目論んでいます。それに関連してということもありますが、毎週行われる雑誌会でリチウム硫黄電池に酵母を活用するという論文の紹介がありました2)。リチウム硫黄電池は二次電池であるリチウムイオン電池の後継として注目を集めています。負極と正極に各々金属リチウムと硫黄を利用するリチウム硫黄電池は、大容量かつ低コストという面で期待される一方で、多硫化リチウムが電解液に溶け出し電池寿命が短くなるという課題があります。その解決に向けて、マンガンを吸着させた酵母を水熱・焼成処理し炭化して、セパレータのコーティング剤に活用しようとする内容でした。まだ検討段階の内容ですが、酵母を炭素の殻にして最新の二次電池に利用しようという発想が、酵母=エタノール発酵のイメージから抜け出せない人間には新鮮でした。対象を大きくは変えずに視点を変えて新たな土俵を見いだすやり方は、小研究室にとっては必須の作戦で、もっと頭を柔軟にということを考えさせられました。優秀な学生さんのお陰です。研究室の安定した運営、特に修士課程の学生さんが中心の研究室では、研究に魅力を感じている学生さんが集まってくれる研究室の空気感の維持が何よりも重要と思っています。当たり前のようで難しいところです。
学会においても、集まってみたくなる、少し楽しみにしているような空気感のある活動があると思います。国内の学会で会員減が続く中で、個人的には、忙しい中でも会員を継続する一線と思います。その辺りを大切にすることで、学会をうまく活用する仲間が増え、お酒好きの仲間ももっと増え、日本生物工学会が益々活性化することを祈願しています。
1) Ojima, Y. et al.: Sci. Rep., 9, 225 (2019).
2) Feng, G. et al.: J. Alloys Compd., 817, 152723 (2020).
著者紹介 大阪市立大学大学院工学研究科(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 1月 2022
生物工学会誌 第100巻 第1号
会長 福﨑 英一郎
我々の学会は、工学に軸足をおき、バイオテクノロジーの発展の一翼を担いながら、2022年に学会創立100周年を迎えます。その節目に学会長を務めることの責任の重さを痛感しております。何とか学会員各位の思い出に残る、素敵でかつ今後のさらなる学会発展の一助となるように100周年事業を成功させたいと願っています。学会員の皆様のご協力、ご支援を期待する所存です。最初に100周年に向けた覚悟とお願いを申し上げた上で、ポスト100周年において生物工学会が進むべき道についての個人的な所感を述べたいと思います。
さて、みなさんご存知のように我々の学会は、1923年に創立された大阪醸造学会をルーツとしています。当時は国税に占める酒税の割合がきわめて高かったこともあり、醸造技術(特に清酒醸造技術)を発展させることが国益に資することであり、我々の先輩達の使命感も如何に大きかっただろうと思います。第二次世界大戦後、研究対象として抗生物質発酵、アミノ酸発酵、核酸発酵などの非アルコール性発酵の重要さが増すにつれ、我々の学会の研究課題は微生物を用いた有用物質生産に広がりを見せました。そして、学会創立40周年を迎えた1962年に日本醱酵工学会と改称しました。さらに前世紀末のバイオテクノロジーの革命的発展を受けて、学会創立70周年の1992年に日本生物工学会と改称し、現在にいたっております。
酒造りの技術研究集団が100年かけて、生物アクティビティーの有効利用の最大化研究を行うまでに発展したと言えます。研究対象は、微生物から動植物まで広がり、酵素や遺伝子、タンパク質、代謝物の網羅的解析も視野にいれる広大な研究領域をカバーするにいたっております。学会の研究範囲が広がるということは、当該学会のコアコンピタンスの一般性と拡張性が期待されたからに他なりません。ただ学会員数の漸減の中での急速な研究範囲拡大は、局地的に見れば研究者層の薄さを露呈する一因になりかねません。また、急速な技術の発展に伴う研究必要経費の増大は、若手研究者から、研究室を主宰するシニアまでも苦しめる要因となっています。生物工学という学問は、「社会ニーズにバイオテクノロジーで応えるサービスサイエンス」と考えることができますが、応用を志向する研究分野で高額研究費を得ようとすれば、社会実装を強く意識した研究計画にならざるをえません。「バックキャスティング」という言葉に悩んでいる研究者が如何に多いことでしょうか?ある著名な計量経済学者が「絶対成功する研究などそう多く無い。『選択と集中』よりも、『ばらまき』の方が期待値は高い」と発言されていました。奇しくも我々が若手と呼ばれた当時は、研究者に対しては短期的成果を求めない大らかな雰囲気があったと思います。優秀な研究者が世界中から集まる米国では、継続性よりもチャンスの平等を優先し、競争により優秀な研究者を選りすぐることができるのでしょう。ただし、激しい競争の敗者に対する復活戦も用意されていると聞きます。
しかしながら、資源や場所や言語の制限がある日本に同様のことが成り立つとは到底思えません。「選択と集中」「競争原理」が本当に日本の科学技術発展のための最良のシステムかはデータに基づき検証する必要があると思います。さて、日本は少子高齢化が進みますが、アジアでは発展を続ける国が沢山あります。それらの国々と対等の関係でWin-winの協業が今後一層必要になってくると思います。そのために必要な国際化も100周年を契機になお一層進めていきたいと思います。
最後に、数年前、小職が尊敬する先生が英国ケンブリッジ大学の旧友と会われたときの会話についてお話したいと思います。私の先輩は、「日本では、最近、大学を良くするために様々な改革を行っている。ケンブリッジ大学はどのような改革を試みているのか?」と尋ねたそうです。それに対してケンブリッジ大学の先生は「ケンブリッジ大学のシステムは基本的には数百年間変わっていない。しかし、世界中から優秀な人材を集めているし、研究力も落ちていない。日本は改革によって何が良くなったのですか?」と問い返したそうです。英国が良くて日本が悪いと短絡するつもりは毛頭ありませんが、考えさせられました。「変化こそチャンス」と良く言います。ただ、「変えるべきでないことを変えない見識」「変わるべきでないときに変わらない勇気」も重要だと思います。以上雑駁ですが、巻頭言とさせていただきます。
著者紹介
大阪大学大学院工学研究科(教授)
大阪大学先導的学際研究機構産業バイオイニシアティブ研究部門(部門長)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 24 12月 2021
生物工学会誌 第99巻 第12号
橋本 篤
新型コロナ感染症が世界中で猛威を振るい、我々のほとんどの活動に深刻な影響を及ぼしている。それは、教育・研究活動も例外ではなく、大学教員である我々の日常も大きく変化した。大学教員としての職務は教育と研究、それに管理・運営などであるが、どの業務においても、人と人との接触頻度を下げる工夫がなされるようになった。その特徴的なものの一つがオンライン会議システムの普及である。オンライン会議システムは以前から存在しており、海外の研究者とのやりとりなどに関してはこれまでも利用されていた。しかしながら、オンライン会議システムが学内外における日常的な会議や授業などにおいて頻繁に使用されるようになったのは、コロナ禍以降といえる。このように、我々はコロナ禍をきっかけとして、これまであまり意識してこなかった事柄を無理することなく省けることに気付いた。大学の授業においても、必ずしも対面で行う必要がなく、むしろオンライン(オンデマンド)形式を活用した方が適した特性の授業もあった。
情報伝達・交換などの側面だけを考えると、移動時間や設備の利用料を節約することは効率的で便利ではあるが、物足りなさを感じるのも事実である。昭和のアナログ人間であるために感じる部分は多々あるかもしれないが、それだけではないとも思う。コロナ禍において、我々はこれまでの無駄に気付いた一方で、効率的な側面からの「無駄」の重要性を感じることができたのではないか。学生たちは巧みにオンライン授業を活用しているが、やはりキャンパスライフを望んでいる。現在、会議や授業などだけではなく、さまざまな事柄がデジタル化され、利便性が向上している。私自身も食・農分野における情報化に関わる研究を進めている。マスコミでもDX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉が躍っている。しかしながら、DXとは、ITにより人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させるという概念であるので、単純なデジタルシフトではないはずである。
ところで、欧州連合(EU)の「欧州グリーンディール(European Green Deal)」の取組みは、EUからの温室効果ガスの排出を実質ゼロにするとともに、経済や生産・消費活動を地球と調和させ、人々のために機能させることで温室効果ガス排出量の削減に努める一方、雇用創出とイノベーション促進することを目指している。また、現在ではSDGs(Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標)という単語を耳にしない日がないほどである。私の研究と関係する食・農分野においても、日本の農林水産省が「みどりの食料システム戦略~食料・農林水産産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現~」を発表している。どれも問題を抱えているのは確かだと思うが、多面的な意味で「持続性(sustainability)」がキーワードとなっている。
大学教員の本務である教育・研究に関して持続性は重要であるとともに、研究遂行の上でも欠かせない概念のひとつとなっている。しかしながら、見かけ上の効率化が求められることが多く、評価にも入ってきている。これまでの自分の研究活動に目を向けてみると、最短距離よりも筋の良さに主眼を置いた場合の方が、その後の研究活動に役立っていると思われる。最近はそのようなことを無駄と考えられることが多いが、極限まで無駄を省くと目の先のことしか考えなくなり、結果として脆弱性が増すのではないだろうか。コロナ禍は日常生活から研究活動までさまざまなベクトルから無駄ではなく、ゆとりの重要性について考える機会を与えてくれた。我々は、この機会を「無駄」にせず、教育・研究活動のみならず日常生活においても効率の意味を再考する時ではないかと考える。
著者紹介 三重大学大学院生物資源学研究科(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 11月 2021
生物工学会誌 第99巻 第11号
尾関 健二
麹菌研究と初めて出会ったのは、24歳の時に日本酒メーカーの研究所で「乾燥麹」のテーマを貰ってからである。麹の酵素活性を毎日のように測定し、酸性カルボキシペプチダーゼ活性をニンヒドリン反応後、比色法で定量するのだが、当時は手袋もなく指先が紫色になり、毎日の通勤電車で他の乗客に気づかれないようにしていた記憶が残っている。この研究は、今だから話しても問題ないと思うが、アメリカ工場で「乾燥麹」にして日本に輸入し、日本酒造りのコストダウンにつなげようというものであった。しかしながら、当時の食糧管理法に触れる可能性あるということでこのストーリーはストップになった。その後、国内の醸造資材メーカーが「乾燥麹」を商品とし、意味のある研究だったと気が付いた。
35歳から2.5年間、当時東京にあった国税庁醸造試験所(現酒類総合研究所)に出向し、麹菌の分子育種技術を勉強する機会に恵まれた。ここでの経験については、研究やその成果よりも、各先生や、同じく醸造メーカーからの出向者、研修生の方々との人脈づくりの印象が深い(他の役割も担っていたが)。当時は所属先の日本酒メーカーにも基礎・応用の研究をする余裕があり、出向から戻った後には「麹菌の遺伝子研究」分野を立ち上げた。麹菌のAMA1配列を利用したショットガンクローニング、有用なプロモーターの取得などが可能であることを実した。このショットガン方式は別の日本酒メーカーに技術を教え、麹菌の優性マーカー系の実用化として引き継がれているが、まだまだ各種展開があり得るところかと考える。
47歳の時、大変お世話になった日本酒メーカーを辞め、金沢工業大学のゲノム生物工学研究所に転籍した。まさに麹菌の菌糸が結んでくれたような、不思議な縁で新たな麹菌研究の場に出会うことができた。この大学初のバイオ学科の設立に際し、教育体制の構築と研究所での研究の立ち上げに忙しい毎日で、さしたる実績も上げられないまま数年があっという間に過ぎた。ようやく、バイオ学科の3期生目の卒論として「日本酒のα-エチルグルコシド」を発酵で高めるテーマに取り組む余裕ができた。麹菌研究では恩恵もたくさん受けているが、痛い目にも遭っている。その一番の例は、あるコーヒーメーカーとの取組みの中で起きた。麹菌のDNAマイクロアレイ解析により、アクリルアミドで誘導された49の遺伝子を、アクリルアミド分解能を持つアミダーゼ候補遺伝子として選別した。DNAマイクロアレイ解析で発現量がもっとも増加した2つのアミダーゼ候補遺伝子について、それぞれの高発現麹菌を育種したが、いずれも分解能に変化がなかった。他方、両候補遺伝子を破壊するとアクリルアミド分解能が低下することが判明し、その後の解析から、この2つの候補遺伝子は1つのORFを形成していることが判明した。この確認には、実に2年間も時間を余分に費やすこととなった。
60歳になったころから、研究が朝日新聞の教育の紙面で取り上げられるようになった。同時に、地元の偉人である高峰譲吉博士にちなんで行われていた、麹菌を利活用する実験を、大学生から地元の小中学生に教える(お手伝いする)役割を担うようになり、麹菌研究により一層ハマった感がある。麹菌の一番複雑な並行複発酵物である「日本酒」と、一番単純な発酵物である「甘酒」の機能性を研究しつつ、これまでの40年以上にわたる麹菌研究をもう少し続けながら、後継者を育て、日本酒復権や甘酒のステータスを高めるなどのテーマに取り組みたいと考えている。麹菌が固体培養の特殊な環境で菌糸を伸ばしながら有用物質を生産する如く、その産物の研究はまだまだ可能性があると確信している。
著者紹介 金沢工業大学 バイオ・化学部 応用バイオ学科(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 10月 2021
生物工学会誌 第99巻 第10号
後藤 雅宏
今年は沖縄の大会参加を楽しみにしていたが、それも叶わなかった。正直、新型コロナ感染症(以下コロナ)の影響がここまで長期に及ぶとは予測していなかった。2020年の4月7日の緊急事態宣言以来、オンライン会議が定着し、今や誰しも3大Webツール(Zoom、Teams、WebEx)を使いこなす時代になってきた。
コロナがもたらした半ば強制的なIT改革は、今世紀最大の変革をもたらしたと言えるのではないだろうか。おそらく、コロナが収束しても元の形には完全に戻らないことは予想に難くない。今後は対面とオンラインの相互補完による新しい学会モデルが構築される可能性が高いと考えられる。
さて、振り返ってみると、コロナ収束のためには、ワクチン接種が一番の鍵だったことになる。ワクチンとは、病原体の特徴を前もって体の免疫システムに記憶させるものである。うまく記憶させることができれば、体内に危険ウイルスが侵入してきた時に、その記憶を基にウイルスを攻撃する抗体を作り出すことができる。
ワクチンには、以前から弱毒化および不活化したワクチンが用いられてきた。コロナワクチンの内、中国製の2つのワクチンはこの旧来型の不活化ワクチンである。日頃身近なインフルエンザのワクチンが代表的な不活化ワクチンであり、その予防効果は40~60 %と言われている。日本でもKMバイオロジクス社
(旧化血研)はこの不活化の手法でコロナのワクチン開発を進めている。
一方、現在コロナワクチンの主流は、次世代型ワクチンと言われるメッセンジャーRNA(mRNA)ワクチンである。従来、RNAは分解されやすく、実用化はとても困難とみられてきた。しかし、そのmRNAの炎症性を低下させタンパク質の変換効率を飛躍的に改善し実用化にこぎつけた技術が、“ウリジン”の“シュードウリジン”変換のアイデアである。この技術の提案者は、本年4号の巻頭言1)でも広島大学の黒田先生が記されているように、ハンガリー出身の女性研究員カタリン・カリコ博士である。同氏のインタビューを収録した2021年5月27日にNHKで放映された“新型コロナ世界からの報告”の中で、この発明は、2005年彼女がペンシルベニア大にいた当時、同大のドリュー・ワイスマン教授との共同研究の成果と報告されている。この2人が、まさに今年のノーベル医学生理学賞の最有力候補であることは間違いない(本稿が掲載された頃にはその答えが出ていると思われる)。多くの研究者がその可能性に気づかない中、ドイツのBioNTech社は、この技術に注目しカリコ博士を2013年に副社長として迎え入れている。同社は、この技術を基にファイザーと2018年にインフルエンザのmRNAワクチン開発に着手したが、その後、この技術はコロナワクチン開発に転用されたと考えられる。今回の鍵となる“シュードウリジン”に関しては、2013年の本誌5号のバイオミディア2)に冨川千恵氏の解説記事がある。米国のモデルナも基本的には同じ原理のmRNAワクチンである。一方、英国のアストラゼネカ社のワクチンは、同じ次世代型ワクチンでもウイルスベクター型のワクチンであり、その仕組みが少し異なる。
日本のワクチン開発は遅れを取っているが、その主な原因は、臨床試験の困難さにある。臨床試験では、ワクチン投与群と偽薬(プラセボ)群との有効性比較データが必須となるが、現在の日本の状況下でプラセボ群を確保することは容易ではなく、薬事申請の大きな障害となっている。
最後に、ワクチン接種の副作用に触れておきたい。ワクチン接種の副作用について、若い女性の方がその割合が高いことが報告されている。その原因は明らかにされていないが、一説には化粧品に含まれているPEG(ポリエチレングリコール)の影響が疑われている(まだ、科学的に実証された例はない)。私達は、2016年からフランスの大手化粧品メーカーC社との共同研究を開始した。その際、研究所トップのM氏から、当社ではPEG系界面活性剤が免疫系に影響を及ぼす疑いがあるため、PEGの使用は禁止されていますとの説明を受けた。個人的には、C社の高級化粧品しか使用していない女性群のデータを検証してみたいと思っている。
1) 黒田章夫:生物工学、99, 161 (2021).
2) 冨川千恵:生物工学、91, 259 (2013).
著者紹介 九州大学大学院工学研究院(主幹教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 9月 2021
生物工学会誌 第99巻 第9号
金森 敏幸
あちらこちらで書いているが、19世紀は化学の時代、20世紀は物理の時代で、21世紀はバイオの時代だそうである。このレトリックは、化学が物理(主に量子力学と熱力学)で説明できるようになったのと同様に、複雑な生命現象も化学や物理で説明できるようになった、と捉えることができる。一方で、そういった、いわば還元主義に対するアンチ・テーゼとして自然現象を複雑系として扱おうとする研究が半世紀ほど前に盛んになったが、その対象の最たるものが生命であって、少し前に福岡伸一先生がこの視点を再度取り上げて、『世界は分けてもわからない』(講談社現代新書、2009年)などの一般図書が話題になった。
○○の時代云々は、勃興する産業分野と対応すると考えることができる。言うまでもなく、製造業は科学技術によって成り立つので、新しい産業は新しい科学技術によって生み出される。筆者の印象では、確かに1990年頃から、化学、材料、機械、電子などの化学と物理によって成熟した産業分野の企業がバイオ分野への進出をより積極的に検討するようになった。本学会は日本生物「工学」会であって、工学の存在意義の第一と筆者が考える「社会への実装」の観点から、今こそ、その意義が問われているのではないだろうか。
筆者はこれまでの経歴、あるいは、現所属のミッションから、どうしても社会実装の点から研究開発を考えてしまう。悲しいかな、純粋に知的好奇心から研究開発に取り込むという素養・能力がないとも言える。
なので、筆者の意見は少し偏っているであろうことを認識しつつ、バイオの研究成果をどうしたら産業に結びつけられるか、について、少し愚考を開陳させていただきたい。
機械や電子部品、材料などの無生物製品と、バイオが対象とする生物製品との大きな違いは、前者が均質・同一を保証できるのに対して、後者はきわめて多様である(均質・同一は期待できない)ということであろう。
バイオの研究成果の社会実装先の一つである医薬品については、世界中でprecision medicineに向かっていることは衆知である。たとえば、iPS細胞が樹立された頃に提唱された、患者さんの体細胞からiPS細胞を経て「その患者さんの」疾患モデルを樹立し、それによって最適な治療法(治療薬のみならず、放射線治療なども含め)を見つけ出すというストーリーが、時間的にも費用面でもSFでなくなりつつある。
均質・同一の製品でのビジネスモデルは少品種・大量生産、およびそれによるコストダウンに立脚する。一方で、バイオ製品は超多品種・少量生産が前提であり、当然コスト高にはなるが、販売戦略上、価格には限度がある。つまり、バイオ製品は、基本的に小商いである。他分野の企業がバイオ分野への進出を検討し始めた頃、多くの企業の皆様と意見交換の場を持たせていただいたが、その際彼らの多くがバイオ分野に抱いていた印象は、ハイリスク・ハイリターン(代表例はブロックバスター医薬品)であって、当時世界的に珍しい成長を遂げていた新興バイオ企業のインビトロジェンの事業内容を例に取って、バイオ分野の特徴、すなわち、超多品種・少量生産、小商いについてご説明した。この特徴は本質的な問題ではあるが、少なくとも米国では、アカデミアの研究成果をスピンアウトベンチャーで製品化し、ヘルスケアあるいはバイオ製品の大手企業(たとえば、ベクトン・ディッキンソンやサーモフィッシャー)にM&Aされるという形で社会実装されるスキームが確立されている。一方我が国では、米国ほどM&Aは盛んではないし、四半世紀ほど前に話題になった「社内起業」が大成功を収めていると筆者は聞かない。また、経済産業省が掲げた「大学発ベンチャー1000社計画」が有効に機能したかどうか、検証してみる必要があるだろう。いずれにしても、本質的に小商いにしかならないバイオの研究開発成果を社会実装する「仕組み」こそが、バイオの時代を花開かせる鍵だと考えている。
学問としての生物工学を深化させるために、還元主義が良いのか、俯瞰的、あるいは構成論的アプローチが良いのか等々、浅学な筆者には分からないが、「工学」の意義が「社会実装」にあるとしたら、深掘りばかりではなく、どうしたら社会実装できるのか?という議論も必要ではないか、と考えている。
著者紹介 国立研究開発法人産業技術総合研究所細胞分子工学研究部門(招聘研究員)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 8月 2021
生物工学会誌 第99巻 第8号
鈴木 徹
2011年の内閣府による「高齢者の経済生活に関する意識調査」によれば、60歳以上の高齢者が優先的にお金を使いたい項目は、一位が健康維持や医療介護、二位が旅行、三位が子や孫のための支出であった。なるほど、近年の健康科学=長寿科学は最大多数である高齢者のニーズを正確に捉えている。政府のGoToキャンペーンも、辛口批評家たちが批判するよりずっと的を射た政策だとも言える。2020年の時点で国内の健康産業の規模は26兆円、GDPの約5 %で、10年後には37兆円になると予測されている。長寿科学はこれから益々の発展が期待される。健康長寿は全人類のアプリオリな願望だから。
しかし、生物学者の端くれとして冷静に考えると、人間以外にこれほど長寿を希求する種はいないことに気付く。種が維持され、あるいは発展していくために繁殖し、次世代を確実に残せない種は絶滅し淘汰される。寿命は、そのために最適な長さに自ずと収斂していく。たとえば、鮭は数年間の海洋生活の後、生まれた川を遡上し、産卵・受精の直後にすべて死ぬ。植物は基本的にクローナルな増殖が可能であるが、環境によっては毎年種を作り枯れていく一年草と言う戦略を選ぶ種もある。
ヒトにもっとも近いチンパンジーのメスは、死の直前まで排卵があり出産が可能であるそうだ。つまり、ヒトという種は「おばあさん(+おじいさん)」という、孫の世代の養育に特化した新たな生の在り方を、進化のうえで獲得したのである。ほとんどの女性は、生後15年以内に初潮を迎える。そして、妊娠・出産・子育てで15年。その後、孫の養育と子世代のサポートに15年。
織田信長は、桶狭間の戦の折「人間五十年、下天のうちを比ぶれば、夢幻の如くなり」と謡ったが、当時の結婚年齢は15歳。明治期には20歳で成人し結婚、寿命は60歳位。1970年代は25歳までに結婚し、75歳が寿命。現在は30歳が結婚適齢期で女性の平均寿命が89歳。人生は、幼年期、子育て期、孫育て期を経て寿命となる。結婚適齢期と寿命には1:3の法則があるようだ。
ところで、結婚と寿命のどちらが関係性を支配しているかというと寿命の方であろう。童謡「赤とんぼ」の歌詞には「十五で姉やは嫁に行き」とあるが現在ではこれは違法。今の親世代の感覚では、子供が大学卒業後すぐに結婚したいと言えば「少し早いのでは」と嗜める。若者を幼弱化させ自立を妨げているのは親世代。子供の結婚と出産が早すぎると親の老年期に自分の生きる目的がなくなってしまうから。
が、もしこれ以上寿命が伸びると女性の適齢期が出産可能年齢を越えてしまう。現に日本の出生数は1950年には約240万人であったのが、2000年には120万人に半減している。日本人はすでに絶滅危惧種だそうだ。対処法は、早い出産を奨励すること、つまり1:3の呪縛を解き放つことである。具体例として、フランスのように出産と育児に対して公的扶助をして早く子供を産む方が寧ろ有利になるようにする。婚姻に拘る必要もない。出産と子育てをした後でも高等教育が受けられるよう大学も企業も変わる。いや、それ
以上に出産年齢×3以降の新たな人生の役割を創出するべきか。“1:4”の新しい人類の誕生である。健康科学、社会制度、政治、哲学、宗教すべてを総動員し、国やコミュニティごとにさまざまな可能性に挑戦することが必要であろう。多くの失敗の中から数十年かけて新しい次の千年を生き抜くためのライフスタイルを見つけられれば未来は明るい……多分。しかし、最近ではこういった発想は人権問題と受け取られ、きついバッシングを受け、政治の世界ではタブーとなってしまった。
長寿科学は、ゲノム解析を皮切りに、再生医療、ゲノム編集、ビッグデータと人工知能の誕生と共にこれまでにないアグレッシブな進歩を歩み始めた。大袈裟にいえば17世紀に錬金術が化学に止揚した時代のまばゆさに匹敵する光を放ち初めている。これは、もう止められない。
アダムとエバは善悪の木の実を食べエデンの園から追放された。その理由は、神が、人がその次のステップに手を出すことを阻止するため。「見よ、人はわれわれのひとりのようになり、善悪を知るものとなった。
彼は手を伸べ、命の木からも取って食べ、永久に生きるかも知れない(創世記3:22)」。
長い寿命の代償に、人類は新たな荒野を突き進む。
著者紹介 岐阜大学応用生物科学部(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 7月 2021
生物工学会誌 第99巻 第7号
新城 雅子
パンデミックに遭遇し、物理的に制限される中、時空を超えて多面的に想いを馳せるようになった。COVID-19について、人類とウイルスの戦いという切り口で報道される中、日々医療現場で尽力されている医療従事者の方に心より感謝の気持ちをお伝えしたい。
大学での活動においてもこの一年余、学生も教職員も不便な思いをしながら、さまざまな工夫をし、新しい社会状況への適応模索元年となった。私は在宅勤務の時間が増え、過去の自身の研究を思い起こし異なる切り口で生物の悠久の営みを考えている。現時点での私の想いは、ウイルスを含む外来遺伝因子と良いバランスで共存するのが賢明というもの。生物としてのヒトが他の生物と共存して今後百年、千年、万年生き続けるために必要なことは、今地球上で宇宙で最強になることではないと思う。限りある資源を宇宙全体の変化に応じて、恒に未来の生物、非生物に想いを馳せ利用させてもらうという謙虚な気持ちになる。
大学時代、故江夏敏郎先生の講義「醗酵生理学」で、ジャック・モノー著『偶然と必然』を題材とするレポート課題があった。当時、哲学的なフレーバにむせながらも、その論理の切れ味が骨身に沁みた。その後40年余り、偶然と必然のパワーバランスとその時々の結末を見ることになった。修士研究の中で、Bacillus licheniformisのバクテリオファージを電顕観察した。このファージはバクテリアの表面にまるで月面着陸する様相で、DNAをバクテリアに注入する。この感染ファージDNAは宿主内に隠れ(溶原化)、環境の変化による緊急事態を感知すると誘発され、宿主内で激増し、宿主を破壊し環境に飛び出し、次の宿主に感染しまた隠密生活を始める。感染直後から宿主で増幅して宿主の命を奪う攻撃(ビルレント)タイプもあるが、すぐ周囲に宿主が途絶えてしまう。
同じく修士研究で、トリプトファン高生産菌育種目的で大腸菌のトリプトファンオペロンをセルフクローニングした。ところが、培養中に人間の都合で同居させられた組換えプラスミドから、お仕着せのトリプトファンオペロン配列が、ある確率で中立的に起こるトランスポゾン由来の繰り返し配列関与の組換えで欠失し、その株は身軽になり、より速い増殖能を得た。“偶然に”生じた欠失株は、みるみるうちに大腸菌社会の優占種になった。この現象を就職先の製薬企業の研究室でも追体験した。ビタミン製造前駆体生産菌の育種研究において、長年工業レベルで使用されていた菌株は時々ファージ感染に見舞われたことを知った。その株のゲノム配列から、環境変化との闘いが壮絶であったことが想起された。過酷な環境変化に対応する武器は、過去に偶然遭遇し自己ゲノム内に侵入していたファージ、トランスポゾン、IS因子由来配列であり、それらが誘発する“偶然”の遺伝子(構造)変異が、生き残りに貢献したことを想像させる。COVID-19は、より劇症だったSARSと比較し、人間を宿主として賢く利用しているという見方もある。私はウイルスに意思があるとは信じていなかったが、Bacillusのファージ間で情報交換をしているという報告が2017年にNatureに発表された。ファージ間の宿主の密度を知らせる情報伝達だというから驚きだ。この自己増殖制御機構を地球で存続する戦略として備えてきたと想うと感銘すら受ける。
大学教育現場ではSDGsをコアコンセプトとする「科学技術の社会実装」という英語授業を担当している。留学生と日本人学生が国境を越え、研究領域(バイオサイエンス、情報科学、物質創成科学)を超えて、各国の課題共有後、グローバル視点で課題解決案を討論し、スタートアップのピッチプレゼンをするという模擬授業だ。私自身のグローバル勤務(日米欧)経験から、「均一な環境で順風満帆の人生を送るより、修羅場を経験した異分野の人生経験者の連携が激動の時代の荒れ狂う波を乗り越える力を生み出すと思う」と伝えている。留学生は自国の課題意識があり、「自身の課題のソリューションは日本ですでに整っているのでそれを自国にも展開したい」と提案する。それを聞いた日本人学生は驚き、嬉しく思い、日本人だからこそグローバルに貢献するアンメットニーズがあると知る。日本人学生および外国人学生である本誌の若い読者の皆様には覚悟と勇気を持って、“偶然という必然”(想定外とも言われる)から学び、地球・宇宙規模の共存を意識し、ボーダーを超えた協働を発展させ未来を「共創」して欲しいと願っている。その背中を押す役目をもう少し果たせると嬉しい。
著者紹介 奈良先端科学技術大学院大学 教育推進機構(客員教授)、MS BioConsulting(個人事業主)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 5月 2021
生物工学会誌 第99巻 第5号
池 道彦
水を中心とした環境の保全と修復を目的とする環境工学分野での研究開発と教育を生業にしている。元来、環境工学は、製品の生産やサービスの提供、その消費において生じる廃棄物や排水、排ガスをどうにか片付けるという役割を担うもので、利を生まず儲からない「負の技術」である。良い技術でも、コストが安くなければ実用化されず普及しないさだめなので、大きな富を生むメディカルバイオやアグリバイオの成功事例を見ると、つい拗ねたくなる。それでも、SDGs(Sustainable Development Goals)に示されたように、さまざまな環境問題の解決こそが人類の目標なのだから、自らの環境技術がいずれ社会に貢献すると信じて研究を行っている。古い言葉になってしまったが『環境革命』が起こりつつある、あるいは我々が起こすのだという気持ちが、その一つのよりどころである。環境革命は「エコロジーの原則に従って世界経済を再構築する」世界の大きな変化を示す概念であり(レスター・R・ブラウン)、産業革命、IT革命に続く新たな産業の革命ともいえよう。これにより、健全な水や空気や土に対して正当な対価が払われるようになり、環境問題への取組みが「負」から「普通」になる。
産業革命は蒸気機関の発明を契機とした産業の機械化により、またIT革命は高性能コンピュータによる情報技術の急伸により、いずれも画期的な新技術が主導する形で世界の価値観、社会や文化を変えた。これに対して環境革命は、これらとは逆に、地球温暖化をはじめとした環境問題が人類に突き付けられた結果としての価値観の転換が、技術の進展を主導する革命であろう。技術の波及効果が時代を変えるような成り行きにまかせてはおけず、『終末時計』の残り「100秒」の日限に間に合うように成し遂げるという制約がある。
この革命は一つの技術で実現できるものではない。温暖化対応を例にいえば、クリーンエネルギー開発だけでは日限には間に合わない。CO2 吸収源である森林やサンゴ礁の保護・再生、化石資源を使わないプラスチックなどのモノ創り、超省エネ型の製品群や住宅、都市創り……等々、あらゆる分野での取組みが必要である。
また、SDGsに示されたように、温暖化だけではなく対応しなければならない無数の環境問題があり、それらの解決が互いにTrade-offの関係になり得ることも十分理解する必要がある。私の領域でいえば、水環境を守るために高度な排水処理をすればするほど、エネルギーや資源の利用が増え、温暖化を助長し資源枯渇を早める。革命の担い手となる環境技術者は、あらゆる分野の先端科学技術を駆使し、しかもそれら相互の関係を理解しつつ、地球-人間システムの中で適正に組み合わせ、実装するという仕事を大急ぎでやってのけなくてはならない。
そこに新型コロナウイルスのパンデミックである。環境問題とは異なり直接に人の命を脅かすコロナ対応に人類の英知を集めてあたるのは当然のことであるが、環境革命はまた後回しになるのだろうなとも思う。
一方、私の感覚でいえばコロナの問題は環境問題と類似している。コロナ流行が人の生活様式や文化、価値観を一変させ、特効薬やワクチンなど最先端医療分野での開発を誘発する問題主導の技術革新が進みつつある。また、高性能マスク、消毒薬、ウイルス粒子拡散のシミュレーションや換気装置、感染者との接触可能性を知らせる情報システムなど、あらゆる領域での技術開発が行われ、実装が進められている。さらに、感染防止と経済活動に代表されるような、多くのTrade-offを考慮した対応が求められることも同じである。
コロナを克服するなかで得る、多分野連携型の科学技術の進展とそれを実装する社会変革の経験が人類の新たな学びとなり、アフター・コロナには案外、環境革命がすんなり進むことになるのかもしれないなどと夢想する。早い終息(収束)を願う。
著者紹介 大阪大学大学院工学研究科(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 4月 2021
生物工学会誌 第99巻 第4号
黒田 章夫
この原稿が掲載される頃には、新型コロナウイルスに対するmRNAワクチンの接種が始まっているかもしれない。いま人類を救おうとしているこの技術も、最初はまったく相手にされなかったそうだ。カタリン・カリコ博士は、このmRNAワクチンの開発者の中心人物である。カリコ博士のmRNAワクチンの申請書はことごとく却下され、当初まったく研究費がつかなかったとある。今でいう「選択と集中」から外されていたのである。100年以上使われている従来のワクチン技術(弱毒化したウイルスなどを使う)があれば、わざわざ未知のmRNAワクチン技術を採用する必要があるのか?という理由もわからないわけではない。しかし、mRNAワクチンは配列さえわかれば素早く設計して生産できるというメリットを持つ。さらには細胞性免疫を増強剤に依存せず誘導できるというのも強みであるようだ。カリコ博士はmRNAワクチンの優位性を信じて改良を重ね、さらにはベンチャーを作って実用化に邁進してきた。今回、新型コロナウイルスによる世界的なパンデミックにより、突然パラダイムシフトがおこった。いち早く設計して生産できることがワクチン技術の価値観を一変させたわけだ。
東京大学の石川正俊先生が「大学における工学、特にICT分野の教育改革の現状と未来」と題して文部科学省で発表された中に、「独創性の本質」について説かれた部分がある1)。この中で、私は「マーケットがない技術、欧米に競争相手がいない事業、科学技術基本計画にない分野を推進できているか?」という部分が特に好きだ。mRNAワクチンのように、未来のニーズは把握できない。石川先生が述べられているように、研究開発は投資的行為であり、多くは失敗するものであると考えるべきである。新しい研究開発は時として莫大な価値を生むので、ほとんどが失敗に終わっても全体としてはプラスになる。日本人は「投資=ギャンブル」という感覚を改めて、理性的に捉えるべきである。言葉でわかっていてもそのような考えが常には意識されないので(あるいは多人数による選考会になると説得しにくいので)、価値が見通せる無難な研究や聞いたことのある研究が採択される。また同資料の中の「研究段階では社会的価値は見えない、価値が見えるようであれば独創性は低い」という記述は多くの研究者をハッとさせるのではないだろうか。しかし、価値が見えなければ何でもOKであるわけではない。そこが難しいところだ。ある他の先生の話の中で「なぜNatureを読むのか?その理由は自分と同じアイデアでないことを確認するため」と聞いたことがある。すなわち、誰もやっていないことが重要であるということだ。未来はわからないのであれば、少なくとも「誰もやっていない研究」であること、さらにはカリコ博士のように自分でベンチャーを作ってでも「続ける研究」て投資されれば、全体としてプラスになるのではないだろうか。
今、研究者の評価が論文数や引用数というわかりやすい数値に偏っている。若手の研究能力評価としては仕方ないのかもしれないが、テニュアをとった後も同じ基準というのでは日本の将来が危ぶまれるのではないだろうか。大学の校費があまりにも少なくなり、科研費などがもらえないと研究が続けられない。研究員を抱えているとなおさらだ。「独創性」の高さは論文数や引用数とは必ずしも相関しない。恐らく研究初期は相反するので、どうしても「誰もやっていない研究」を始めるのに躊躇するだろう。しかし、テニュアをとった暁には、安寧とした研究ではなく、ある種のリスクをとって「誰もやっていない研究」を始め、さらに論文や特許を出したらそれで終わりではなくゴールまで「続ける研究」を目指して欲しい。
1) 文部科学省 大学分科会(第138回)・将来構想部会(第9期~)(第7回)合同会議(平成29年10月25日)
配付資料1 石川 東京大学情報工学研究科長 提出資料
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2017/10/27/1397784_01.pdf
(2021/01/27).
著者紹介 広島大学大学院統合生命科学研究科(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 20 4月 2021
こちらでは生物工学会誌第87巻(2009年)~第98巻(2020年)の『巻頭言 ”随縁随意”』に掲載された記事がご覧いただけます(第99巻(2021)以降はこちら)。
|98 (2020)|97 (2019)|96 (2018)|95 (2017)|94 (2016)|93) (2015)|92 (2014)|
|91 (2013)|90 (2012)|89 (2011)|88 (2010)|87 (2009)|
⇒生物工学会誌 –『巻頭言 “随縁随意”』
⇒過去号掲載記事(記事種別)一覧へ
記事種別
Published by 学会事務局 on 25 3月 2021
生物工学会誌 第99巻 第3号
竹山 春子
慣習的になりすぎて改革できなかったことが、まったくの突発的事態によって可能になるのを目のあたりにすることになりました。コロナ禍によって遠隔会議がこの1年でデフォルトになってきました。デメリットもありますがメリットも大きいと感じます。分野や業態にもよりますが、IoTの超進化した社会では、仕事場を自由に選んで働くことが当たり前として描かれていましたが、それが今回加速されてきています。多様なライフスタイルを実現することが現実味を持って社会に受け入れられつつあります。それに伴い、システムのセキュリティ強化など技術の高度化も必須であり、遅れ気味であった日本も独自の路線を模索することが課題となっており、技術開発が活発化するかと思います。日本の技術力は高い評価を受けている割には、有事の際に素早い活用がなされていないと感じます。対症療法的なコロナ対策研究費が拠出されていますが、他分野の研究も含め継続性を是非担保してほしいと思います。社会の頑強さ、柔軟性を担保するためには科学技術政策の転換が必要であり、基礎研究も含め先行研究投資をより真剣に考えるべきかと思います。
昨年、内閣府のムーンショットプログラムが各目標のもと始動しました。各省庁の元施策にリンクする必要はなく、今までにはなかった大胆な発想を、というコンセプトが原点にあったはずのものです。私も、農水系の目標5においてPMを務めることになりました。「そんなこと本当に可能なの?」と驚くような発想が必要だと思っています。JSTの未来食糧プログラムでアドバイザーを務める機会もあり、一次生産である水産・農業に関していろいろ考える機会がありました。養殖を陸上で行うという発想は新しいものではありませんが、日本ではコスト面での課題もあり規模は大きくありません。一方、ノルウェーでは、環境汚染対策としてサーモン養殖を陸上で行うシステム開発が進んでいますし、中国でも大規模に進んでいます。陸上での養殖が可能ならば、海上での農業はどうだろう?休耕田も多く存在しますが、規制にとらわれない海上農業は新しい価値を生む可能性があるのではないでしょうか。移動型の海上農業は台風を回避でき、さらには温度帯を選ぶこと、洋上エネルギーを利活用することで独立型にもすることが可能かと夢想しています。何でだめなの?ということを恐れず行うことが、予想しない未来を拓くかもしれません。
既成概念にとらわれない価値の創造を、今後育っていく若手研究者に担ってほしいと思っています。現在、若手研究者には偏重気味と言われるほど手厚い研究環境をつかみ取るチャンスが提示されています。その風潮はどんどん加速していて、博士後期課程からすでにその競争の場に出陣することが可能です。科研費での若手研究と基盤研究Bとの重複申請が可能になったことから若手の採択率は飛躍的に高くなっていますし、JSTも次々と若手対象の砲弾を撃ち込んでいます。女性研究者も10年前と比較すれば、大学でテニュアに残っている割合は少しずつ増加していますが、彼女らが教授になるまでにはあと10年、もしくは20年かかる気がしてなりません。ダイバーシティーの重要性は、最近身をもって感じています。女性ばかりでも、男性ばかりでも研究室はうまく回っていかないことを経験しています。性差だけでなく、個性、年齢の多様性も重要だと痛感します。ダイバーシティーの高い環境で育った研究者には縦割りではない横広がりのネットワークで研究する力が備わるのかもしれません。生物工学会では、男女共同参画やダイバーシティーの組織立った活動は今まで多くはなかったかと思いますが、今だからこそできることもあるのではないかと思っています。
古本屋で見つけた五木寛之の『林住期』(幻冬舎)という本を、時々読み返しています。ヒンズー教の「四住期」に「学生期」「家住期」「林住期」「遊行期」がありますが、働き盛りの研究者は「家住期」にいて、私はすでに「林住期」にいます。人が本来なすべきことは何か、を研究の場から再度考え直したいと思っています。
著者紹介 早稲田大学理工学術院(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 2月 2021
生物工学会誌 第99巻 第2号
坂口 正明
この度2020年9月30日をもちまして定年退職いたしました。同社で非常勤の再雇用で継続勤務いたしますが、会社人生の区切りとして入社以来40年の「想うこと」を紹介させていただきます。
★1980~1992年:発酵の技術開発(モルトやグレーンウイスキー、酵母増殖代謝とその発酵制御など)
★1992~1997年:工場での生産管理・開発(焼酎、アルコールの製造管理、現場技術開発、TQC活動など)
★1997~2020年:蒸留の技術開発(連続蒸留機、単式精留蒸留機での蒸留酒全般の技術開発など)
★2002~2016年:日本生物工学会関西支部、本部(実践的な交流ができる産学連携活動など)
蒸留酒の技術開発における40年を通じて、1) 種々の技術開発・現場改善の体験による新たな発見によってのみ本当の力が身に付く、2) 美味しい、安心・安全な品質にこだわる、3) 凛々しく品格のある設備設計をする、4) 仕事が楽しい、ことがキーであったと思っております。あっという間の40年間でした。テーマ、時間、良い先輩や仲間に恵まれたと思います。
最初の12年間は、酵母の増殖代謝と発酵制御に関係するテーマを実施し、原因と結果の因果関係を普遍的に深掘り解析することにより問題点を解決してきました。その基礎的な成果を「酒類におけるエステル生成に及ぼす要因とその調節機構」(バイオサイエンスとインダストリーの解説)1)、「酵母の増殖・代謝に及ぼす減圧の影響」(発酵工学会誌)2) などに投稿しました。
次の6年間は、生産工場(臼杵工場、大阪工場)での生産管理、改善活動、技術開発をおこない、研究開発で経験してきた普遍的な技術を現場で実践することができ、生産や製造の実践活動の楽しさを体験いたしました。
その後の22年間は、蒸留酒の技術開発、アルコールの品質保証に関係しました。専門外の分野でしたが、見様見真似ながら独自の蒸留理論の構築、蒸留シミュレーション技術と、それに裏付けられた実践的な技術開発ができるようになっていきました。「スピリッツ蒸留の理論と実践」や「連続蒸留酒の開発」(社内刊行)、「実用蒸留技術」(分離技術会編)などで蒸留理論とその応用技術を体系的にまとめることができました。
今となっては、蒸留技術で大きな成果を出したことになるのですが、当初は専門外の分野なのでやりたくはなかった仕事でした。仕事は「やりたい」「やりたくない」で決めるのではなく、まずはやってみてから「できる」「できない」で決めることであると身を持って体験しました。このことを社員教育の場などでお話しすると、体験した者が教える迫力が伝わっているようです。
40年の会社生活の中で、創業者鳥井信治郎から伝わり、社内の恩師から影響されていることがあります。たとえば、【やってみなはれ】まあ、そういわずに、とことんやってみなはれ。やらなわからしまへんで。莫大なエネルギーによる積極果敢な行動と挑戦をする。【陰徳】人に施しする者は、感謝を期待してはいけない。必ず良いことがある。【信用第一】売れるとか売れんとかの問題やない。一番大事なことは信用や。嘘をついてはいけない。【品質】これより上はない、飛び切りええもんを造っとくなはれ。表面的な看板ではなく、真にこだわりのある中身品質を造りだす。【仕事】楽しくやることこそが正義だ。
産業界のみならず学会関係者皆様方のご支援のおかげで日本生物工学会での活動も本当に楽しくやることができました。
1) 坂口正明:バイオサイエンスとインダストリー,47, 32 (1989).
2) 坂口正明ら:醗酵工学,68, 261 (1990).
著者紹介 サントリー(株)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 29 1月 2021
生物工学会誌第99巻第1号掲載
中野 秀雄
新型コロナウイルスの突然の出現により、世界の風景がまったく変わってしまってから、はや半年が過ぎようとしている(令和2年9月執筆時点)。
この新型コロナウイルスによるパンデミックの試練は、丁度幕末期の黒船到来と同じような効果を日本全体に及ぼしているように思える。奴国が金印をありがたく頂戴して以来のハンコ至上主義が、いつのまにやら社会全体でIT化を遅らせ、それらがパンデミック対策に必要な迅速な対応の障害になっているという、不都合な真実が明々白々になった。筆者が勤める名古屋大学でも、総長が「世界1のデジタルユニバーシティーを目指す」と宣言された。生命農学研究科だけでも年間1000万円以上の非常勤職員の人件費をかけてチェックしている経理関係の紙書類と印鑑が(53研究室に分配されている講座費は7500万円程しかないのであるが)、今後この宣言で一掃されるとすると、新型コロナウイルスの恩恵は思いの外大きくなるのではないかと、日々事務に提出する紙と印鑑に埋もれている筆者は密かに期待している。
新型コロナウイルスの問題だけでなく、食料、資源、環境、エネルギーなど、世界が直面しているさまざまな課題の解決には、生物工学の貢献が必要不可欠である。しかしそのための公的な研究資金は、残念ながら我が国において十分とは到底言い難く、しかも「効率化」の名のもとに、年々着実に減らされている。このような状況下で、現状をポジティブな方向に動かすことができるのは、より積極的な産学連携であり、またリスクマネーを科学の領域に導くことができる大学発バイオ・スタートアップを、生み出し育てることであろう。
筆者自身は、無細胞タンパク質合成系を用いて、ヒトや動物から短時間でモノクローナル抗体を探索できる技術を開発し、大学発のバイオ・スタートアップであるiBody株式会社の立ち上げに関わった。単に検査薬や治療薬の抗体をスクリーニングするだけでなく、うまくビジネスモデルを構築すると、免疫系に深く関係する抗体分子を網羅的に獲得・解析することで、これまでにない事業展開が可能だと思っていたのであるが、資金調達でVCなどを回ると、「おたくの会社は、『試薬』『受託』『創薬』のどれですか?」とよく聞かれ、答えに詰まったことが度々あった。米国ではこの無細胞タンパク質合成系と合成生物学・インフォマティクスなどの技術を組み合わせた大学発バイオ・スタートアップも立ち上がっている。この分野でのスタートアップは、従来の枠にはまらないビジネスモデルを展開でき、バイオサイエンスとインダストリーを「リノベートする」役割を果たすことになるのではないかと大いに期待している。
大学発スタートアップの質と量において、日本は米国より大きく遅れをとっているのは歴然たる事実である。よく知られているように、米国では政府資金による研究開発から生じた特許権などを民間企業などに帰属させることが1980年に制定されたバイ・ドール法により可能になったが、日本でそれが導入されたのは、米国に遅れること22年後の2002年である。さらに米国では「失敗することを恐れない」チャレンジャーであることを尊ぶ精神が幅広く共有されているのに対し、日本では「失敗することは許されない」風土で変化より安定が好まれるという、精神文化的違いも指摘されている。
しかし日本はこれまで、短期間に急激な社会的変化を複数経験し、なんとかその変化うまく対応してきた。明治維新や、先の敗戦からの戦後復興などが典型である。その成功に秘訣があるとすると、高い倫理観に裏打ちされた合理的精神を皆が共有していたことではないかと、個人的には思っている。変化の時代を生き抜く術を我々は有している。老いも若きも変化を楽しんで欲しい。
著者紹介 名古屋大学大学院生命農学研究科(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報,生物工学会誌
Published by 学会事務局 on 23 12月 2020
生物工学会誌 第98巻 第12号
清水 浩
ご存知の通りのコロナ禍である。3月に、イタリアの友人とメールで話す機会があった時には「ロックダウン」という言葉の響きに驚き、大学は数か月すべてWeb講義をしているという話を、まだ遠い世界の話として聞いていた。最後に彼は「Stay home」と言ってくれた。そのあと、あれよ、あれよという間に日本全体が「緊急事態宣言」「休業要請」という濁流に飲み込まれていった。4月に講演受付を開始する予定であった本年度の生物工学会大会は、受付開始をひと月延期するも及ばず、本学会の長い歴史の中で初めての中止に追い込まれた。ご準備いただいた北日本支部実行委員会の先生方をはじめ関係各位の思いは察するに余りある。自然が我々の暮らしに大きな影響を及ぼすとき、いつも人間の無力を思い知る。今度もまたそうであった。しかし、その中でもWeb開催による本年度学会受賞者の講演とシンポジウムの開催決定は会長や実行委員長の英断と思う。
100年前にはスペイン風邪が流行ったのだと色々知らされ、その時も今もワクチンがなければ自粛して閉じこもるのが人類の知恵だと教えられた。各国の対応が日々比較され、強制力のない自粛要請が限界ですとのこと、最終的には自己判断、自己責任と現場の判断に委ねられ、「そんなに私たちいつも自由だったっけ」と多くの人々がフラストレーションを感じた。私たちの研究室も大学の要請が日に日に厳しくなっていく中、何度も考え、ルールを更新したが、最後はやむなく全員自宅での活動となった。ウイルス感染拡大が6月にやや収まってみると、医療従事者のがんばり、医療体制の整備、高齢者福祉の充実などなど、西欧諸国に比べても我が国のレベルは高く、また、色々な意見はあろうが、一人一人がこの程度の要請で見識を持って行動し、ウイルスの活動を一旦封じ込めることに成功したのはこの国に生きる人たちの矜持と言うべきである。これから、ファクターXの科学的理由も解明されていくではあろうが、一因として、この国の人々の行動様式があると思う。本稿を書いている7月には再び感染者数が急上昇しており、先はまったく見通せないが、このウイルスに関する情報も集まりつつある。今後もしばらくwithコロナを覚悟すべきと思う。
ひとたび、ウイルスの緊急事態制限が解除されると今度は、経済の命が大変だという。何年もかけて経済状況が持ち直してきたのに、たった2、3か月間、経済が止まるとこんなに影響を受けるというのは素人に信じがたいことである。金融、情報、物流、すべてがICTによってグローバルネットワークにつながっており、全体が止まった今、動き出すには大きな時間の遅れをともなう。現代社会という巨大なネットワークで流れ続けてきたフラックスがウイルスという外敵によって急ブレーキを踏まざるを得ず、もんどりうってひっくり返った状況だ。この後、どれくらいの厳しさが私たちを待っているのか誰にも分らない。世界中がネットワークでつながってしまっている以上、世界全体の活性化という方策しか道はなく、分断や利己的な振る舞いでは安定な状態はもたらされないということはおそらく間違っていない。コロナ禍の過ぎた世の中では新しい技術や行動様式も定着するだろう。
大会は開催されないが、先生方のご尽力で、この原稿を書いている間にWebシンポジウム開催の準備がされている。この拙文が会誌に掲載される頃にはシンポジウムはとうに終わっているはずである。何しろ初めてことだらけで心配は尽きないが成功裏に終わることを祈っている。一方、オンラインの開催には強みもある。要旨をダウンロード形式にするので講演者はいつもより字数を多くすることができるし、締め切りまでの時間に余裕がある。会場数のアレンジも比較的容易に調整できる。このような利点は物理的なスペースや時間の制限が少ないからできるのであろう。チャットなどのツールを使って、講演中に聞き手が考えていることを発信しておけば、座長はそれを見ながら聴衆の考えていることが分かって講演がより盛り上がるかもしれない。もちろん直接会って話をすることはかけがえがない事だけれど、同じものでなくても長所を生かして楽しみたいものだと思う。
著者紹介 大阪大学情報科学研究科・教授、日本生物工学会 庶務・会計担当理事
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 24 11月 2020
生物工学会誌 第98巻 第11号
大利 徹
筆者は修士課程修了後、民間会社に約10年、新設地方公立大学に約15年、現在の北海道大学に所属して10年になる。この35年を振り返ってみると、多くの方々から頂いた多種多様なご助言が色々な場面で大いに役立った。この経験を、上下関係に代表される「縦」のつながりと、上下関係がない「横」のつながりの観点から、特に学生会員や若手の会員の方々に紹介したい。
「縦」と「横」のつながりの始まりは学部、修士の学生時代で、先生や先輩から現在の礎となる多くのスキルをご指導いただいた。この研究室における「縦」の関係は強く、卒業後もOB会などを通じて継続され、多くの場面で役立っている。他方、「横」のつながりでは、色々な意味で刺激をくれる同級生が数人いる。しかし、いずれも母集団が小さく、数は限られる。
やはり、筆者が刺激を受けた方々は社会に出てからが圧倒的に多い。民間企業では研究所勤務となり、「縦」の関係といえる上司から与えられた課題をひたすらこなしていた。数人の上司に仕えたが、各々に独自な研究スタイルは、その後大いに役立った。また、大学時代の基礎研究とは異なり、出口戦略に基づく企業における研究というものを学ぶことができた。「横」の関係では、研究所には出身大学・研究室が異なる多くの研究員がいたが、先輩社員が独自の手法で課題解決するのを目の当たりにし、豊富な知識に基づく発想力の大事さを痛感した。このように企業では、「縦」と「横」の両方のつながりで多くの方々から刺激を受けたが、一企業内の人脈であり、まだ母数は限られていた。
その後、大学教員に転職し、再度、母集団が小さい組織に属することになった。「縦」の関係では、新設大学設立のために招聘された重鎮の先生方から大局的に俯瞰する重要性を学ぶことできた。「横」のつながりでは、小規模大学ゆえに個々間では強かったが、数は知れていた。しかしそのころ、いくつかの学会活動に誘われ、初めて学会運営なるものに携わる機会を得た。それまでは、年次大会で細々と成果を発表する程度であったが、学会活動を通して他分野の先生方と交流する機会が増え、得られた幅広い知識や情報は、その後の研究に大いに役立った。このように、限られた人員の組織では、「横」のつながりが如何に重要であるかを実感した。
還暦を迎える年齢になると、助言を頂く「縦」関係は少なくなり、「横」のつながりがもっとも重要になっている。この「横」のつながりを広げるのにもっとも適しているのが学会であろう。筆者はいくつかの学会に所属しているが、生物工学会は多様なバックグラウンドを持つ会員数約3,000からなり、個々の会員がつながりを持つには最適な規模だと思う。そこで、若手会員の方には、年次大会はもとより、研究部会、シンポジウム、支部活動などにも積極的に参加し、多様な「横」のネットワークを構築することをお勧めしたい。また、若いうちから海外留学や海外の研究者との交流を通して、グローバルな「横」のつながりも積極的に構築していくべきだと思う。筆者の経験では、これらのつながりは、将来必ず役立つはずである。
最後に、中島みゆきの「糸」(作詞・作曲:中島みゆき)の歌詞の中に、「逢うべき糸に出逢えることを、人は仕合わせと呼びます」という一節がある。意味合いは違うかもしれないが、若手会員の方々も、逢うべき「横」の糸と多く出逢えることで、良い仕合わせ(めぐりあわせ)が多数あることを願う。
著者紹介 北海道大学大学院工学研究院(教授)、日本生物工学会(理事)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 24 10月 2020
生物工学会誌 第98巻 第10号
児島 宏之
2020年2月頃までは対岸の火事だったCOVID-19,3月末から始まった在宅勤務が今日現在まで続いています。ゴールデンウイークもずっと在宅で過ごしました。皆さまがこの巻頭言をお読みになる頃の状況も何となく予測・想像できるようになってきました。
決して手放しで喜んでいるわけではありませんが,COVID-19 が2019年12月に発生し,ウイルスのゲノムが次世代シーケンサーを使って一週間程度で決定されました。ウイルスが変異しつつ世界各地に広がっていった様子もゲノム情報をもとにトレースされています。得られる限りの科学的知見を総合し,診断方法,ワクチン,治療薬について,さまざまな取組みが行われています。ネット上では不確定なものも含む多くの情報が飛び交っていますが,京都大学の山中伸弥先生の見識の高いWebサイト(https://www.covid19-yamanaka.com/index.html)や,日経バイテク元編集長の宮田満氏の質の高い情報(https://twitter.com/miyatamitsuru)に無料でアクセスすることもできます。いまだかつてない急速な勢いで罹患数が増える状況下で,感染拡大を防止しつつ崩壊寸前の医療現場では患者さんを治癒する努力が続けられる一方で,このような先端科学を駆使した取組みが世界的規模で行われていることに感銘と感謝の念を抱くとともに,生物工学会の会員としても個人,組織,学会として何ができるか,何をすべきかを考えています。
短期的には,崩壊寸前の医療を支え,不足している資材の供給を可能にすること,食料をはじめとしたライフラインを確実なものにする取組みが優先されます。その後は一旦停止しているさまざまな活動とその活動に従事する人の生活を軌道に乗せ経済的基盤を確保しつつ,学校教育のように将来にむけての取組みを再開させる必要があります。
今改めて意識すべきことは「COVID-19の前の状態に戻らない。現状を回復するだけではなく,新たな仕組みを作り,いち早く成長に向けて進んでいかなくてはならない」ということでしょうか。失われたり棄損されたりした仕組みに従事されていた方々への最大限の配慮が必要ですが,「以前の仕組みを再構築するよりも,過去のしがらみを捨て去って,より良い仕組みを構築する」良い機会とも言えます。コロナウイルスとの闘いは長期にわたると予想されています。マラソンランナーの山中先生もマラソンに例えています。取組みの積み重ねによって,将来に大きな差が生じる可能性があります。今は日々の活動に色々な制限があり,実験,実習,試作,製造に大きな制限を受けています。この状態は皆さんの努力によって少しずつ回復していくでしょうが,状態が回復することをただ待ち望むのでなく,将来について考え,計画を立て,実行するためのさまざまな準備をすると考えれば時間はいくらあっても足りないでしょう。
今こそ私たちが実現すべき未来の価値,姿を改めて考え,それに向かって何をすべきかをしっかり考えておきたいと思います。後ろを振り返って嘆き悲しむのではなく,明るい将来を信じて頑張りましょう。
まるい地球の水平線に
なにかがきっとまっている
くるしいこともあるだろさ
かなしいこともあるだろさ
だけどぼくらはくじけない
泣くのはいやだ 笑っちゃおう
進め
ひょっこりひょうたん島……
その昔のNHKで放送された人形劇『ひょっこりひょうたん島(作詞:井上ひさし・山元譲久,作曲:宇野誠一郎)』の主題歌より。是非YouTubeでご覧ください。モーニング娘。も歌っています。
著者紹介 味の素株式会社(専務執行役員)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 9月 2020
生物工学会誌 第98巻 第9号
川瀬 雅也
和文誌の巻頭言を書くようにとの話を頂き、引き受けたまではよかったが、何を書こうかと悩んで、文章を書いているうちに、何となく以下の文章ができた.さて、タイトルをつけなければと思い、辞書を引いてみると、「とりとめもなく思いつくままに書いた文」を「漫文」というらしく、この言葉をタイトルとした。
今、新型コロナウイルスの流行で、大学も企業もテレワークとなっているところが多いと思う。この文章を書いている私も、自宅待機の身である。講義はweb配信なので、動画を作り、放送大学の真似事をやっている。動画を作った後、少し時間ができたので、本でも読もうと思い、本棚の中をいろいろと探ってみた。
ファインマンの本(ファインマンが著者ではなく、周りにいた者が、その発言などをまとめたもの)が目についたので、もう一度読み返してみると、いろいろと考えることがあった。ご存知のように、ファインマンは量子電磁気学における功績で、日本の朝永振一郎と一緒にノーベル物理学賞を受賞した人物である。非常に好奇心旺盛で、いろいろな逸話を残している人物でもある。その一方で、スペースシャトルチャレンジャー号の爆発事故の調査員として原因の究明を行ったことでも有名である。
今のように立ち止まって考える機会がなければ、おそらく考えなかったと思うが、今の自分はファインマンのように、いろいろなことに好奇心を持てているだろうかと考えてみた。自分の本棚を見てみると、自分の研究分野以外のジャンルもあり、まだ、かろうじて興味の広がりは残っていると思えた。学生に、「視野を広く持て」とか、「自分の分野だけでなく、他の分野にも目を向けろ」などと、偉そうに言っている本人が、そうでなければ話にならないので、内心、ホッとしている。皆様は如何であろうか。
確か、何の結果が出なくても、長い時間、焦らずに考え続けるというようなことが書いてあったと思う。興味の広さに加え、もう一つ、我慢も必要だということだ。成果を急げば、成果の出そうなことしかできなくなる。こうなれば、本当に、科学的に大事なことはできない。このことは、多くの人が同意するだろうと思う。たとえば、ある学生が卒論でポジティブな成果がほとんどなく、修士課程でも成果がなかったとする。皆さんならどうするだろうか。きっと、ファインマンなら、ネガティブな結果も大事な結果だと言って、ネガティブな結果を堂々と修士論文として提出させたのではないかと思う。我々もこのような度量を持ちたいと思う。ネガティブデータの重要性を認めて、また、多くの人に価値ある内容だったら学会誌などに掲載するようなことは可能ではないだろうか。今後の学会の発展を考えると、次を担う人材の育成が重要な課題であることは多くの人が同意するだろうし、ネガティブデータを生物工学の財産だとすることも、人材の育成にプラスになるのではと思う.
『ローズ』という映画をご存知だろうか。この映画の主題歌「The rose」(歌:Bette Midler、作詞・作曲:Amanda McBroo、1980年)の最後に、
“Just remember in the winter
Far beneath the bitter snows
Lies the seed that with the sun’s love
In the spring becomes the rose”
という歌詞がある。
次を担う人材に、春を届ける方策も、学会として議論してほしいと思う。
著者紹介 長浜バイオ大学(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 22 8月 2020
生物工学会誌 第98巻 第8号
今井 泰彦
「おいしさ」というのは五感で感じる総合的な感覚とされ、さまざまな側面から科学的な研究が行われている。「おいしい」ものを食すると、なぜ幸福を感じるのだろうか。享受できるのは人類だけなのだろうか。日頃、漠然と疑問を感じていたが、先日、人類はどのようにして「おいしさ」を感じる能力を身に付けたか、という大変興味深い番組があったので、ぜひここでご紹介させていただきたい(NHKスペシャル「食の起源」)。
それによると、人類は今まで生き残るために数多くの危機、環境の変化に適合してきたが、食に関しても数々の変化への適合があったらしい。その過程で「おいしさ」に関する3つの特殊能力を手に入れたという。我々の先祖はアフリカで約30万~10万年前に出現した。そして、約6万年前に気候変動により寒冷化が起き、食べ物を求めてアフリカから新天地に移動した。しかし、そこにある食べ物は今までとはまったく種類が異なり、生き残るために色々な物を食べる必要が生じた。その中には苦味を持つ食材もあった。それまでは苦味を持つものは排除すべき食材であったという。それは、植物の葉などに含まれる毒物に苦味を持つものが多かったためで、敏感に苦味を感じとり、これを排除していたらしい。しかし、偶然、苦いが食べても安全な食べものを見つけられ、さらにこれに栄養があったことで、生存のチャンスを高めることができた。そして、苦味のある物を食べるということの積み重ねにより、苦味が次第に積極的に食べたくなる味として認識されるようになり、遂には「おいしい」とまで感じられるようになったという。人類は苦味も「おいしい」と思うことで他の動物にはない独自の味を手に入れ、食べ物の範囲を広げていった。これが第1の特殊能力である。
次に、さらに遡るが、かつて人類の祖先であった哺乳類は夜行性だった。約6600万年前に巨大な隕石が地球に衝突して恐竜が滅んだ後、次第に夜行性から昼間に活動するように生活スタイルを変えていった。その結果、目が発達して顔の骨格が大きく変化、長く突き出ていた鼻が退化して、鼻と口を隔てる骨がなくなり、食べ物の香りが直接鼻に抜けて嗅覚を刺激するようになったという。人間は嗅覚細胞が1000万個もあるが、これに対して味覚細胞は100万個しかなく、食べた際には、舌で感じる味の情報に比べ、桁違いに多くの「におい」の情報が脳に届く。加えて、火による調理を始めたことで、さまざまな香り成分が立ち上るようになり、香りが激しく脳を刺激し、味だけではなく、香りも加えて食べ物の風味を楽しむ能力を手にした。その結果、人類は味をより楽しめるようになり、「おいしさ」に結びつけて記憶するようになった。これが第2の特殊能力。この結果、おいしそうな香りによって過剰な食欲をかき立てられるようになったという。
そして、最後に、味覚も嗅覚も上回る第3の特殊能力を身に付けたことで、異次元の「おいしさ」感覚を得られるようになった。それは「共感・共有」する能力。人類はアフリカから出て旅をする間に、次第に前頭葉(腹内側前頭前野)が発達して、他の人と「共感」するという劇的な能力を身に付けることができた。その結果、今までは自分の経験で食べる価値があるかどうかを判断していたのが、たとえば「仲間が新しい食材を見つけておいしそうに食べている」という姿を見ると、これに「共感」して、自分も食べてみようという好奇心が芽生えるようになったという。仲間が食べているものは自分も食べる価値があるものと判断して「おいしさ」を共有するようになった。この仲間との「共感能力」の結果、人類はさらに生き延びるチャンスを高めることができるようになった。自分の好みだけではなく、自分と違う味覚を持った仲間と食べ物を「共有」していく、味の楽しさ、「おいしさ」を共有するという第3の特殊能力を身に付けたことで、人類は連帯感が深まり、生き抜くことができたと考えられているという。
さて、現在、世界中で感染拡大している新型コロナウイルスは人類史上、最悪のウイルスと言われている。一昔前ならば、発生した国や地域の風土病で済んだかも知れないし、さらにもっと昔だったら、固有の生物の中だけに閉じ込められていたものだったかも知れない。グローバル化が進んだ故に、あっと言う間に世界中に感染が拡大してしまった。まさにパンドラの箱を開けてしまったのである。しかし、いまこそ科学者が正確な情報を提供し、一人ひとりが行動に責任を持って、進んで協力することが必要である。一つの地域、一つの国で回復しても意味はなく、世界中で回復してはじめて終息する。コロナから身を守るのは、人類の持つ共感・共有能力を働かせた「連帯感」である。大切な人のために、三密を避け、外出を自粛して、一体となって危機を乗り越えることが必要である。
人類は今までに幾度となく苦難に出会い克服してきた。我々が身に付けてきた「おいしい記憶」をたどることが、コロナへの特効薬となるはずである。
著者紹介 公益財団法人 野田産業科学研究所(専務理事)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 23 7月 2020
生物工学会誌 第98巻 第7号
片倉 啓雄
Well-beingということばをご存知でしょうか。直訳すれば「よく存在する(生きる)こと」ですが、福利、幸福と訳されることが多いようです。ここでは、もっとも身近に感じられる「幸せ」と訳すことにします。
1998年にアメリカの心理学会の会長に就任したMartin Seligmanは、well-beingを科学として研究するポジティブ心理学を提唱し、その成果は世界に広く浸透しつつあります。それによると、well-beingは測定可能であり、Positive emotion、Engagement、Relationship、Meaning、Achievementの5つの要素からなるといいます。また、高い幸福度を得るにはMeaningが必須であることが科学的に検証できています。学生や社会人に、あなたが「幸せだ」と感じた状況のベストスリーは、と問うと、美味しいものを食べた、楽しい時を過ごした、ぐっすり寝た、などPositive emotion に分類されるものが圧倒的に多くなります(表1)。論文が受理された、ポジションを得た、合格した、優勝した、などの何かを達成する幸せ(Achievement)、パートナー・肉親・友人・知人と良い関係を保てる幸せ(Relationship)、時を忘れるほど趣味や仕事に没頭できる幸せ(Engagement)がそれに続きます。しかし、以下に例示するMeaningに相当するものをあげる人はごくわずかしかいません。人に感謝された、誰かの役に立てた・必要とされたことなどがMeaningであり、学生の場合だと、チームに貢献できた、ボランティアや文化祭の企画に感謝された、塾のアルバイトで「先生!成績が上がったよ」と言われた、などが、社会人の場合だと、自分の仕事が世に出た、自分の仕事・話が人の役に立った、家族に感謝された、部下の成長を見ることができた、などが具体例としてあげられます。つまり、Meaningとは、価値を認めるものに貢献する幸せ、ということができます。
ところで、研究・開発とは、まだ誰も知らないこと/できないことを解明/解決することであり、私たち研究者・技術者はこれを生業にしています。では、私たちにとってのwell-beingにはどのようなものがあるでしょうか。特に、もっとも重要なMeaningにはどんなものがあるでしょうか。「価値を認めるもの」は人さまざまですが、一つの見方を紹介したいと思います。
工学にはさまざまな定義があり、工学における教育プログラムに関する検討委員会は「数学と自然科学を基礎とし、ときには人文社会科学の知見を用いて、公共の安全、健康、福祉のために有用な事物や快適な環境を構築することを目的とする学問」と定義しています。また、筆者は、担当している技術者倫理の講義で、工学を「安全性・経済性・利便性のよりよいバランスを実現する学問」と定義し、「安全性が最優先であるが、ものづくりにおいてはこれらのバランスが重要である」と説いています。これらの定義には何れも「安全」というキーワードが含まれており、安全・安心・健康・福利は、誰もが「価値を認めるもの」と言えるでしょう。
私たち研究者・技術者は、楽しく過ごすPositive emotionはもちろん、研究・開発に没頭するEngagement、同僚・共同研究者・学生・取引先とのRelationship、製品化した・論文が書けた・ポジションを得たなどのAchievementを得ることができます。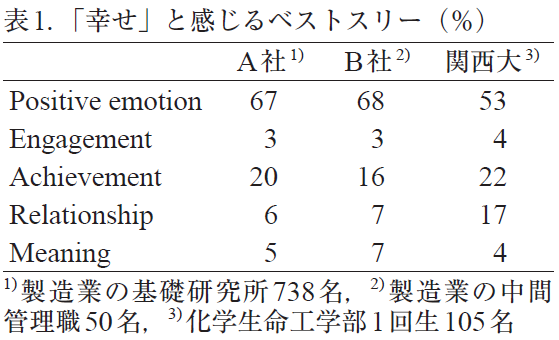 これらに加えて、私たち研究者・技術者は一般の人たちに比べてMeaningを得る機会に恵まれていることにお気づきでしょうか。自分の強みを活かして誰もが価値を認める安全・安心・健康・福利に貢献することができるからです。成果を論文化したり製品化したりすることだけで満足せず、自分の経験・知識・スキルで何に貢献できるかを考えてみませんか?そうすれば、皆さんの幸福度は間違いなく高まるはずです。筆者のMeaning?それは本稿によって皆さんの気づきに貢献できることです。
これらに加えて、私たち研究者・技術者は一般の人たちに比べてMeaningを得る機会に恵まれていることにお気づきでしょうか。自分の強みを活かして誰もが価値を認める安全・安心・健康・福利に貢献することができるからです。成果を論文化したり製品化したりすることだけで満足せず、自分の経験・知識・スキルで何に貢献できるかを考えてみませんか?そうすれば、皆さんの幸福度は間違いなく高まるはずです。筆者のMeaning?それは本稿によって皆さんの気づきに貢献できることです。
著者紹介 関西大学化学生命工学部(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 24 6月 2020
生物工学会誌 第98巻 第6号
後藤 奈美
輸出の現状 日本産酒類の輸出は、ここ8年増加を続けています。もっとも輸出額が高いものは清酒で約230億円、以下、ウイスキー、ビールと続き、酒類の合計は660億円(令和元年)を超えました。とはいえ、フランスワインの輸出額は約1兆円と桁違いで、日本が輸入するワインの約1,800億円と比較してもまだまだ低いことが分かります。一部のテレビ番組では、ニューヨークやパリで清酒がブームになっていると紹介されていますが、それはまだ一部での現象で、逆に言えば、大きな伸び代があると言えるでしょう。
楽しみ方の情報発信 海外で清酒や単式蒸留焼酎のような日本のお酒を楽しんでもらうためには、まず知ってもらうことが大切と思われます。話題を清酒に絞らせていただくと、インターネットなどでの情報発信とともに、海外の展示商談会などで試飲をしてもらったり、清酒の歴史や製造方法を紹介したりすることに加え、清酒と食事のペアリングを紹介することも有効かと感じます。当研究所の味覚センサーを用いた実験では、チーズ(実際は抽出液)の後に清酒をセンサーに浸すと、チーズの後にワインを浸した場合よりもうま味の値が高くなることが示されました。つまり、チーズに清酒を合わせるとチーズのうま味がより引き立ち、一方、チーズにワインを合わせると口中がリフレッシュされて食べ飽きないことを示すと言えます。また、和風の魚料理とワインを合わせると生臭さを感じることがありますが、これは魚に含まれる不飽和脂肪酸にワインに含まれる鉄や亜硫酸が作用して生臭さの成分であるアルデヒドを生じる(この反応は口の中で起こることになります)からと報告されています。一方、清酒と和風の魚料理の相性は抜群で、清酒には鉄分が少なく、亜硫酸もほとんど含まれていないことがその理由と考えられます。
品質の確保と評価と 清酒を輸出する場合、国内よりも流通に長期間を要し、高温に晒される場合も想定されます。このような条件では、清酒に老香[ひねか、タクワンのような香りのジメチルトリスルフィド(DMTS)が主成分]と呼ばれる一般にあまり好まれない匂いが出てしまうことが知られています。当研究所では老香の発生を抑制する研究にも取り組んでおり、酒造メーカーとの共同研究で開発されたDMTSの前駆体をほとんど作らない清酒酵母の試験販売が始まりました。国内向けはもちろん、輸出される清酒への活用が期待されます。現在のところ、清酒は海外の和食レストランを中心に消費されているようですが、今後その販路を広げていくには、ワインの流通やサービスの力を活用していくことが有効と考えられています。その際に気になるのは、ワインの目線や価値観による紹介や評価になっていくことです。地域によって異なる消費者の嗜好を尊重することは大切ですが、一方でオーセンティックな評価方法も情報発信していきたいと感じます。
今後に向けて 海外での清酒の消費が増えてくると、クラフトサケと呼ばれるような海外の人による現地生産も増えてくると考えられます。日本の技術を流出させないように、という考え方もありますが、個人的には日本で清酒醸造を学びたいという人に門戸を閉ざさない国でありたい、と感じます。海外の清酒ファンが増えれば、それだけ本場の日本酒(注:日本酒は国内産の米を原料に国内で製造された清酒を指す地理的表示)を楽しみたい、と思う消費者が増えるのではないでしょうか。日本も海外からビールやワイン、ウイスキーの技術を学び、今では海外からも高い評価を得るまでになっています。とはいえ、やはりフランスワインなどは一目置かれる存在です。さらに、清酒醸造を研究しよう、という海外の研究者も出てくるでしょう。海外のクラフトサケのお手本であり続けられるよう、研究開発や技術革新にも努めたいものです。現在、COVID-19の影響で酒類業界は苦境に立たされていますが、この困難を乗り越えた日には、国内はもちろん、世界中の人々に日本のおいしいお酒を楽しんでもらえるよう、当研究所も力を尽くしたいと思います。
著者紹介 独立行政法人酒類総合研究所(理事長)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 5月 2020
生物工学会誌 第98巻 第5号
田口 精一
スポーツ最大の祭典であるオリンピック・パラリンピックは、より速く、高く、遠くを目指し、人類は進化し続ける。ノーベル賞も、人類の叡智の象徴であり、その輝かしい業績は人類史として刻まれている。筆者が現職に着任早々、入学した学生相手に、ノーベル生理学医学賞・化学賞の受賞者を一人選んで深堀してください、という課題を出したことがある。最初は鈍かったが、彫刻を掘るように徐々に業績の理解が進み、同時に科学者本人の人物像が浮かび上がっていった。筆者はこれまで、数人のノーベル賞受賞者と出会い、そこに香る研究観に接し考えさせられた。ここでは、受賞以前の出会いとして年代順に紹介させていただく。
埼玉の県立高校時代、筆者は弓道部に所属し、日々の地味ながら厳しい活動に怠け気味だった。2年上に梶田隆章先輩が居られた。黙々と練習に励み、穏やかな口調で語る静かな方との印象が強かった。弓道は物理学の粋ともいえるが、何故か物理系に強い集団だったような気がする。ニュートリノ振動の観測は、大規模スケールでありながら粘り強い研究活動で、いかにも理論派で堅実な梶田さんらしい研究テーマのように思う。実用には遥か遠い基礎科学の大きな果実であった。今年、顧問をしている協会で講演をしていただく計画を立てている。久しぶりにいろいろとお話しできることを楽しみにしている。
国際会議出席に伴い、Frances H. Arnold博士に会うためにCaltechを訪問したことがある。ラボツアー後、アインシュタインの彫像が鎮座するカフェテリアで、彼女と話をした。酵素の触媒活性を100、1000倍に上げるとあっさり言いのける延長線上に、「K点越え」が出るのか。進化分子工学を駆使して生命システムの創成を目指すうえで、彼女の跳躍力や陣頭指揮ぶりはPI(独立した研究者)を目指していた筆者にとってとても眩しかった。生物進化の原理を、実践的な形で生体化学反応に応用した成果は圧巻である。日本からは、多くの企業研究者が彼女を慕って留学し、帰国後もFrancesファミリーとして仲良く交流していることは有名である。
助手の時代に、仏国のルイ・パスツール大学で研究をする機会を得た。自然免疫研究を微生物の観点から学びたいと思い飛び込んだJules A. Hoffmann研は、分子細胞生物学、分子遺伝学、生化学が効果的に統合されていた。Hoffmann博士の優れたマネージメント能力にも圧倒されたが、書き物の英文表現がとにかく美しい。あれほど精緻なロジックの上に上品が添えられた文体を観たことがない。科学と芸術が共結晶化している。仏国だから?
北大時代に、クロスカップリング反応で知られる宮浦憲夫先生と同じ部門に所属していた。伝統的に有機化学分野のレベルは高い。北大は、地域性から周囲の雑音が入りにくく、独創的な研究が生まれる風土があるように思う。ある日、宮浦先生にノーベル賞(恩師:鈴木章名誉教授)を受賞する予感はありましたか?と学食で質問したことがある。「まあね.でも、研究発表後は撤退することを考え始めたよ.原理がわかれば、優秀なポスドクを擁する研究室には敵わないからね。」正直、カッコイイと思った。新分野の開拓と発展、スタイルの違いである。
乳酸ポリマーの微生物合成は、筆者の悲願だった。機密情報を含んでいたので、大村智先生に内容を理解していただいたうえで、PNASのcontribution投稿をお願いしたことがある。興味を持っていただけたが、結果的にはタイミングが合わず自由応募になった。折角なので、北里研究所内を案内していただいたところ、抗寄生虫薬はじめ、多くの人類を救った功績の証が散見し、すくった土の中の微生物代謝物がこれほど大きな価値を生み出すのか!といたく感動した。ちなみに、審査中に親切に対応いただいた編集長Randy W. Schekman博士は、受賞後NやSのつく商業誌には論文を投稿しないと看破された。講演で来日されお会いした時、髭を蓄えた博士の笑顔はとても印象的だった。
真理を探究する科学研究は、人間味溢れる活動である。スポーツや芸術活動と一緒で、人間そのものがドラマチックに前面に出てくるようだ(原稿掲載時には、新型コロナウイルス問題が少しでも改善していることを願っている。命・生活あっての研究活動であることが身に染みている)。
著者紹介 東京農業大学生命科学部(教授)、北海道大学名誉教授
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 23 4月 2020
生物工学会誌 第98巻 第4号
横田 篤
先般、岡山大学で開催された本会第71回大会において、本部企画シンポジウム「持続可能な開発目標(SDGs)を生物工学にどう活用するか」に出席した。時宜を得た企画であった。6人の演者からの話題提供とパネルディスカッションがあり、筆者はバイオエコノミーに関わる後半を聴講した。巻頭言執筆を依頼されて久しく色々と理由をつけて逃げ回っていたが、これを題材として責を果たしたい。
話題の元となった「バイオ戦略2019」は、2019年6月に統合イノベーション戦略推進会議において策定された国の方針である。ただし、バイオの技術面ではなく、バイオを活用して国内外の人材や投資を呼び込んでビジネスを創出し、持続可能で健康に暮らせる社会を作るための戦略である.類似の方針策定が欧州連合や米国、ASEAN諸国で先行する中、我が国は後塵を拝する形になっている.国の持続可能な社会の形成に対する取組みが十分でなかったからであろう。
シンポジウムを聴講して、筆者は本戦略に上滑り感を禁じ得ず、絵に描いた餅になるのでは、との懸念を抱いた。この戦略の立案やシンポジウムに関わられた方々が大学の現状を十分ご存知ないと思ったからである。そこで、戦略の実施を担うべき大学の立場から、シンポジウム終了間際に次のような意見を申し上げた:
「法人化後15年を経た国立大学は弊疲し、大学の教育研究の持続性が大きく損なわれている。戦略の実現にはこうした状況の改善が必要なのに、これに関する言及はどなたからもなく残念だった。それぞれのお立場で正しいことを述べられたとは思うが、大学としては遠い話に聞こえる。」
大学の教育研究機能の健全化は「バイオ戦略2019」の大前提である。このことに関連して、戦略を読んで気になった点を3点あげる。
- 我が国の強みであった基礎研究力が低下したのは、従来型の研究スタイル(個別ラボの分散型・縦割り)が原因であるとし、将来の理想的な研究スタイルをデータ駆動型のビッグサイエンスに求めている。あまりにも短絡的である。私の研究室の腸内細菌叢解析では、次世代シーケンスは共同研究者にお願いし、そのデータ解析、動物の飼育、各種の分析は自前で行っている。泥臭い従来型研究を土台として学生が育つのである。その上に新たに必要となる教育研究を積み上げるのが筋であろう。
- 我が国の強みの一つとして、バイオ医薬等の生産基盤をなす微生物発酵技術をあげている。ちなみに私は学生時代から40年以上発酵生産の研究を続けてきたが、私の定年退職後は、法人化による定員削減のため、この分野の後継者を採用できなくなる見通しだ。このような現状でどうして戦略が実行できよう。
- 大学側の企業との連携意欲がいまだに低調であることを問題視しているが、私は企業側の責任も大きいと思っている。すなわち、バイオ・食品系の企業が博士課程修了者の採用に消極的であることが発端となり、学生が博士進学を嫌い、研究者人材の育成や学術・開発研究が停滞、産から学への投資が進まず、互いの信頼関係が深まらない、総じて連携の機運が盛り上がらない、と言う悪循環である。ここが欧米と大きく異なる。今こそ博士の採用を民間に一定割合義務付ける国の指導が必要と考える。
日本生物工学会にはこの戦略にどう向き合うかが問われている。学会は戦略を鵜呑みにすることなく、その実現を阻む要因を明確にして、打開のために関係方面に提言や働きかけを行う役割を担う必要があるだろう。この度のシンポジウムがその契機となることを願っている。
著者紹介 北海道大学大学院農学研究院(教授)、日本生物工学会監事
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 24 3月 2020
生物工学会誌 第98巻 第3号
三宅 淳
人工知能といえば、医療画像の自動判定や自動運転技術として注目の的である。医学領域では、その本質である「診断」が定性的・概念的方法であって人工知能の機能と相応することから、応用研究が急速に広がりつつある。生物工学の分野では、厳密な数値を求める工学の立場が強いだけに応用はまだ限定的である。しかし生物は単純なモデルでの解析が困難であり、個と全体が簡単に結びつかない複雑系である。人工知能が大いに役立つ分野である故に、早晩応用が進むであろう。
留意したいのは、ルネサンス以降発展してきた自然科学が可能とした定量性と、人工知能が提示する概念性という対極にある2つの方法が初めて揃ったことである。ギリシャに始まった科学哲学は我々の自然認識や方法の基礎ではあるが、自然科学がその唯一の子孫とは言えない。自然科学の特徴は物理学によく見ることができる。すなわち、長さ、重さ、時間という3つの要素を「人為的に」選択し、その関係を定式化するものである。問題は3つの要素だけでは森羅万象を記述しきれないことである。自然科学の体系は産業革命を経て形成され、発展を続けてきた社会・技術と相互作用しながら特定の方向へ形成されてきこともあり、もともと応用学との相関が深い。また、自然科学は体系性が特徴である。計測された事実を含むすべての空間における共通した構造を知ろうとする。現象は一旦体系に昇華され、そこから数的・精密な検証が可能となる。
自然科学だけを習ってきた我々は、専門性を研ぎ澄まし、範囲を狭めてキリのように深めていく細密さが自然を理解するための唯一の合理的方法と信じてきた。しかし、細密な領域での深堀りを続けると、我々の理解は、無限に小さな領域の、相関性の乏しい集合になってしまう可能性がある。エネルギーと物質の再帰を含む循環型社会のような複雑な対象になるとうまく扱いきれない。複雑系を扱う難しさは生命系・感性においてさらに顕著である。自然科学によって人間の感情・情動・アーティスティックな価値の扱いは困難であった。脳の中の構造や機能を分子のレベルから解明できればヒトの知性は再現できるという漠然とした期待があったが未だブレークスルーに至っていない。
これに対して人工知能は帰納的な方法である。ヒトの「考え方」の模倣であって、提示された現象から、自ずからなるカテゴリーを見いだし、個々の現象をそこへ分類する。がん組織や細胞をX線写真から見いだすのも典型的なカテゴリー分類である。写真に映った対象物をカテゴリーにわけて、がんが分類されたカテゴリーに属しているかどうかを判定する。ヒトよりも解析が詳細であるから診断はより正確になる。
経済、地球環境、疾患と原因などの多すぎる相関をどのように結びつけるか、環境負荷のない経済発展はあるのだろうか。人工知能はこのような超多量要素からなる問題を解くうえで役立つだろう。さまざまな要素の組合せを行ってカテゴリーを創出し、最良の現象につながるものを選び出すことができる。自然科学とは方法も対象も異なっていて、要素を限定せず、全体の特性=概念あるいはカテゴリーを抽出したり定義したりする。細部へではなく、上へ上へと階層を昇って行き、俯瞰する方法である。定量的な「法則」が存在しないので、精密性がないと誤解されるが、概念を扱う方法であって分担範囲は異なる。
生命体を構成する分子は、物質・エネルギー・情報を内包する三位一体の存在である。すでに生物工学は生命体の機能そのものとなる膨大な情報と制御に関わる多くの事象を扱っている;たとえば、細胞内の分子反応の連関、情報ネットワーク、遺伝的制御、細胞集合体の機能などである。しかし、情報は物質の特性に付随するものだと思われているところもある。情報によって形成される概念が「もの」の価値を超える可能性も遠い未来ではないかもしれない。我々は、システム全体を俯瞰した概念の形成とその利用を行う人工知能という、自然科学に基づいた厳密な工学と相補い合うものを見いだしつつある。それらをただつなぎ合わせるのではなく、より高次の理解と応用の方法を創造的に編みだすことができるなら、工学は感性やアートの世界も内包し、生命・複雑系をフィールドとする、これまでにない体系を持つことになるに違いない。
著者紹介 大阪大学国際医工情報センターおよび大阪大学工学系研究科Hitz協働研究所(特任教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 21 2月 2020
生物工学会誌 第98巻 第2号
柏木 豊
近年、夏の猛暑、豪雨、強力な台風などの気象災害が多発しています。おりしも国連気候行動サミットが開催され、わが国からは環境大臣が出席され演説をされました。地球温暖化は、人類の化石燃料利用から排出されるCO2などの温室効果ガスが原因であることは定説となっています。
今から40~50年ほど前、化石燃料資源の枯渇が叫ばれ、未利用バイオマス資源を燃料へと変換する研究開発に注目が集まったことがあります。これに呼応して、バイオマス変換技術への微生物・酵素の活用研究が強力に推し進められました。この時期に大学を卒業し、農林水産省の研究機関に採用された私は、バイオマス変換計画のなかで研究生活を送ることになりました。この当時、大気CO2濃度の上昇は観測されていたものの、地球温暖化や気候変動はまだ顕在化していなかったように思われます。むしろ、排気ガスによる大気汚染が大きく問題視されていました。同時に、微生物を利用した化石燃料代替技術の研究開発が進められ、多くの成果が得られましたが、実用技術としての普及はなかなか進まないのが実情であったと思います。しかし、この数年の気象災害の多発を見ると、CO2排出削減が目前の課題として突きつけられ、いよいよこれまでの技術発の結果と、さらなる研究に期待される時期が到来しているのではないでしょうか。
当時、取り組んだ研究課題は植物由来の未利用糖質の資源化というものであり、木質セルロースを食糧や燃料へ変換することを目的としたものでした。配属された研究室では、公設試験研究機関、企業(食品産業に限らず)からの研究員が多数在籍し、精力的に研究が進められていました。その中に混じって微生物探索から研究をスタートしましたが、新規のセルラーゼ生産糸状菌を分離することができ、酵素の特性の解明と酵素遺伝子の単離を行うことができました。もう一つは、非結晶性セルロースからセロビオースを特異的に生成する細菌におけるセロビオース生成要因の解明というものでした。すでにセロビオヒドロラーゼ(CBH)が結晶性セルロースからセロビオースを生成することは研究されていましたが、非結晶性セルロースに作用するCBHは未発見であり、新発見の可能性が期待されました。結局、該当の酵素はβ-グルコシダーゼの一種であるがセロビオースへの作用が低いために培地にセロビオースを蓄積することがわかり、新発見には到りませんでした。当時は、開発されたばかりのゲル板式の蛍光DNAシーケンサーやPCR装置が研究所に導入され始め、遺伝子の配列解析にようやく活用される時期でした。現在の研究環境からすると隔世の感があります。
その後、本省の研究行政部署に移動になり、続いて地方公設試験場に転勤になり、バイオマス変換の研究から離れてしまいました。1997年に研究所に戻った時には、発酵食品を所掌する応用微生物部の糸状菌研究室に室長ポストとして配置されました。このころに、麹菌Aspergillus oryzae EST解析・ゲノム解析研究コンソーシアムに参画し、企業、国研、大学の皆様と自由闊達に大変に楽しく研究させていただきました。麹菌ゲノム解析コンソーシアムに参加したNITEのDNAシーケンスセンターの解析能力に後押しされて、当初の予想よりも短期間の3年ほどでドラフト配列が判明し、2005年に全塩基配列の解読に成功しました。同時に、アメリカ、EUにてA. fumigatus、A. nidulansのゲノムが解明され、海外勢力に遅れることなく、Aspergillus属3菌種ゲノムのそろい踏みが叶いました。
麹菌や発酵食品の研究のつながりで、縁あって、伝統ある東京農業大学醸造科学科にお世話になっています。研究機関から大学への転職となり、一番に気がついたのは、学生の人数と多様性の多さです。多いときには200人近くの学生に講義をしています。授業で受講生がどれだけ満足してもらえたのか、未だに判然としないままですが、醤油醸造学などの講義をしています。現在は、新原理のNGS(次世代シーケンス)が次々と開発されてゲノム解析研究が身近になり、また測定機器が発展し、分析技術が充実しています。若い研究者の方々は、このような研究環境を活かして、これまでの研究から大幅に前進した研究成果を得られていることと思います。社会からの注目度により研究が促進されることよくあることですが、冒頭の話題のように、地球環境の観点からも発酵や生物工学の研究の進展が大いに期待されていると思います。
著者紹介 東京農業大学 醸造科学科(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 27 1月 2020
生物工学会誌 第97巻 第6号
和文誌編集委員長 岡澤 敦司
この度、生物工学会誌編集委員長を拝命いたしました大阪府立大学大学院生命環境科学研究科の岡澤敦司です。就任にあたり、会員の皆様にご挨拶申し上げます。
期せずして、新元号への切り替わりという歴史の節目に、伝統ある生物工学会誌(以降、和文誌と記します)の編集委員長を任せられることになり、大変名誉に思うとともに、一層の重責を感じております。任を与えていただいた前執行部役員の先生方に、まずは心よりお礼申し上げます。
私は、園元謙二先生が編集委員長を務められていた時に和文誌編集委員に加えていただき、幸運にも木野邦器先生、藤原伸介先生という3名の編集委員長の先生方と和文誌の編集に携わることができました。園元先生は、学会誌として、「学問情報の伝達」「学会活動の伝達」および「会員の相互交流」を使命に掲げられ、木野先生は、さらに「産学連携の強化や民間研究の発信」にご尽力され、前任の藤原先生は、それまでの方針を継承しつつ、「会員が欲する情報の発信」という視点での編集に努められました。その甲斐もあり、「特集」「バイオミディア」ならびに「生物工学基礎講座―バイオよもやま話―(現在は続編として継続中)」といった、和文誌の基幹といえる記事のダウンロード件数は、依然右肩上がりとなっています。また、「プロジェクト・バイオ」「生物材料インデックス」「バイオ系のキャリアデザイン」ならびに期間限定連載のバイオインフォマティクスや統計解析に関する講座なども、他に類を見ない、あるいは、他に先駆けて取り組んだユニークな記事として、大変好評を得ております。これもひとえに、編集委員、バイオミディア委員、ならびに、支部編集委員の皆様と執筆者の先生方、事務局の連携の賜物であり、ひいては、学会誌に期待を寄せていただいている学会員のご支援によるものと感謝しております。新体制においても、これまでの編集委員会の基本方針を踏まえ、より魅力的な誌面作りを進める所存です。
平成は、科学技術という側面では大変な飛躍を遂げた時代であり、特にバイオ関連の技術革新には目を見張るものがありました。和文誌においても、時流に乗った先端のバイオ技術を「特集」や「バイオミディア」で積極的に発信することができました。一方、社会に目を向けると、度重なる自然災害や、宗教あるいは政治的な対立が激化し、あらゆる分断が生じた時代でもあり、科学技術の進展が世界平和につながると信じる楽観主義者にとっては、試練の時であったかもしれません。令和への切り替わりを一つの機会として、和文誌から発信する科学技術について、あるいは、科学者や科学そのものについて、社会との関係を改めて根本的に考えてみる必要があると感じています。醸造、醗酵から連綿と続くバイオテクノロジーを、どのように社会に受容また活用してもらえるかについて、特には哲学的にも考えなくてはいけない時代になりつつあると思っています。生物工学会は、数ある学術団体の中でもずば抜けて自由闊達な雰囲気をもち、若手からシニアまですべての年代層の活力に満ちている学会だと思います。和文誌が、学会員の皆様の多様なご意見を頂戴し、広く発信することで、学会内外での対話を促し、学会活動を社会に還元するための一端を担うことができないか模索したいと思います。
新体制では、長森英二先生(大阪工業大学工学部)に編集副委員長を務めていただきます。前期より継続していただく9名の委員に加え、4名の企業の方を含む8名の新任の委員の皆様、10名(内4名が新任)のバイオミディア委員の皆様、各支部編集委員の皆様、事務局の皆様とともに和文誌の編集を進めて参ります。ご存知のように、和文誌のほとんどの記事は、学会内外の執筆者からのご寄稿によっています。執行部、各支部、ならびに、若手の会を含む各研究部会とも連携を取りながら、充実した誌面作りを目指して参りますので、引き続き会員の皆様のご支援とご協力を賜わりますようお願い申し上げます。
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
生物工学会誌
Published by 学会事務局 on 27 1月 2020
生物工学会誌 第97巻 第6号
英文誌編集委員長 神谷 典穂
この度、英文誌編集委員長を拝命しました九州大学未来化学創造センターバイオテクノロジー部門兼工学研究院応用化学部門の神谷典穂です。就任にあたり、自己紹介方々、会員の皆様にご挨拶申し上げます。
私と本会の出会いは、20年以上前に遡ります。1995年に第47回大会が九州大学工学部で開催された修士2年の秋、私にとってはバイオの専門家が集う学会での初めての発表に、たいへん緊張したことを覚えています。これがきっかけで、当時の指導教官である後藤雅宏先生より投稿を勧められ、本誌への初投稿論文はJournal of Fermentation and Bioengineering(JFB)に受理されました。工学部の片隅でバイオに関する研究を始めたばかりの学生にとって、掲載可否もさることながら、生物工学の専門家からどういった評価が下されるのか、期待と不安を抱きながらの投稿作業でした。結果として受理に至りましたが、率直で建設的な査読意見を頂戴し、その後の学位論文の執筆に大いに役立ちました。学術誌への投稿に際し、自身の研究を客観視し、誠実なreviewに伴う厳しさと温かさ、次の展開に繋がるヒントを求める気持ちは、当時と今であまり変わりはありません。
改めて英文誌の歴史を紐解くと、前身の醗酵工學雑誌には1973年から1976年までは奇数月が日本語、偶数月は英語の論文が掲載され、1977年に和文誌「醗酵工学会誌」と英文誌‘Journal of Fermentation Technology’が誕生します。その後、1989年にJFBへ、1999年にJournal of Bioscience and Bioengineering(JBB)へと変遷を遂げ、現在に至ります。JBBへの名称変更により、本誌のスコープがより幅広い分野の研究者に対して浸透し、新たな研究発表の場として本誌を選択するモチベーションを高める契機となったのではないかと拝察します。
さて、直近4年間の英文誌編集作業は、加藤純一編集委員長と20名の編集委員、7名の海外編集委員、英文誌を担当する編集事務局の方々の献身的なご尽力に支えられてきました。国内編集委員の任期は4年、2年ごとにその半数が入れ替わり、次の担い手に襷が渡されます。私自身は、大竹久夫編集委員長に編集委員としての責務を、髙木昌宏編集委員長に学術誌の編集作業に関わる意味をご指導頂きながら、編集委員を4年間務めました。その後、化学工学会英文誌(JCEJ)、Biochemical Engineering Journal(Elsevier)の編集に携わってきましたが、アジア各国からの投稿の増加に比べ、日本からの論文投稿数の減少を実感・危惧しています。Elsevier社による直近数年間の分析結果によると、本誌への投稿数、掲載論文ダウンロード数の何れも中国が日本を上回っている状況にあります。インパクトファクターが2を超えたJBBへの年間原稿受付数は約850報に至る勢いです。編集委員の多くは若手・中堅の本会会員であり、ご自身の研究と教育に対するエフォートに加え、本誌の編集業務に携わっていることをどうかご理解頂き、査読依頼が届きましたら積極的にお受け頂きますようお願いする次第です。
昨今、非常に多くの電子ジャーナルが乱立している状況にあり、皆様のお手元にも投稿依頼のダイレクトメールが届いているかと思います。なかには一見JBBと見間違うような名称を冠した雑誌もあり驚くこともありますが、JBBはその歴史と伝統から新興雑誌とは一線を画します。科学(Bioscience)と工学(Bioengineering)の両面に向き合い、これらをバランス良く取り扱える点は、国内外の関連学会英文誌や関連商業誌と競争・共奏するうえでの特徴にもなります。最近は産の研究者からの投稿も増えていると聞いており、この点もJBBの強みになると考えます。産官学の会員の皆様からの投稿論文が起点となり、新しい学術や研究開発に繋がる思考の種を与え続けるジャーナルにしていくことが、結果として本誌の価値をさらに高めていくものと思います。
最後に、本誌編集委員長の重責を負うことは、私にとって大きな挑戦であり、新たな学びの機会でもあります。編集委員・事務局の皆様と、著者・査読者・読者として関わってくださる皆様のご意見ご叱正を賜りながら、JBBが日本、引いてはアジア圏のバイオテクノロジーを世界に発信するフラッグシップジャーナルとしてさらに成長するよう、精一杯尽力する所存です。令和元年からの4年間、何卒宜しくお願い申し上げます。
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
生物工学会誌
Published by 学会事務局 on 27 1月 2020
生物工学会誌 第98巻 第1号
会長 髙木 昌宏
新年明けましておめでとうございます。
お正月を代表する料理に、お雑煮があります。皆さんが召し上がったお雑煮は、どんなだったでしょうか?周囲の人に尋ねると、「家のお雑煮は、普通の……」と答えつつ、その中身は、ずいぶんと異なっていたりします。興味のある方は、お雑煮マップ(https://chefgohan.gnavi.co.jp/season/ozoni/)をご覧ください。あまりの種類の多さに、驚かれることと思います。お雑煮に限らず、当たり前だと思っていることを、詳しく調べて考えてみると、思わぬ発見があり、自分の先入観の危うさに気づかされるものです
我々は(少なくとも私は)、子供の頃から、「よく考えろ」「ちゃんと考えろ」と言われ続けてきました。皆さんは、「考えなくては……」と思いつつも、いったい「考える」とは、どういうことなのだろうかと疑問に思ったことはありませんか?
【考えるとは?】
「考える」を要素に分解すると、次の4種類になるそうです。
- 「より深く」考える。
- 「より広く」考える。
- 「分けて」考える。
- 「筋道を立てて」考える。
このことを知るだけでも、考えるプロセスが整理できそうで、基本は「もれなくダブりなく事柄を洗い出す」「事柄について、基本軸を明確にしつつ、全体像を把握する」「解決法を優先順位をつけて策定する」ということになります。しかし、我々が思い浮かべる「考える」となると、ほとんどの場合、結局、「深く考える」しか頭になくて、「広く」「分けて」考えることを忘れてしまっています。いい大人が集まって議論する、大学や会社の会議でもよくありそうな話です。「広く」「分けて」考え、そこから筋道を見つけ出すには、たとえば図にしてみるのも有効な方法で、その代表が、「ロジックツリー」です。詳しくは述べませんが、興味のある方は、ぜひ調べて、使ってみてください。
【演繹・帰納・アブダクション】
「筋道を立てて考える」というのは、まさに論理的思考です。この論理的思考は3つに分けられ、「演繹」「帰納」「アブダクション」です。「演繹法」は、一般的に正しいとされることと、ある事象から妥当と考えられる結論を導き出す手法、「帰納法」は、複数の事象をもとに一つの結論を導き出す方法で、これらについては、御存知の方も多いと思われます。多くの日本人が、知らないか、使いこなせていない手法に、「アブダクション」があります。これは、「仮説形成」とも言われる論理展開法で、起きた事象に対する仮説を立てて、検証する手法です。仮説は、あくまでも仮説なので、間違っている可能性もあります。失敗を極度に怖れる日本人は、特にこの「アブダクション」という思考方法は、苦手だと思われます。
【応用基礎研究とアブダクション】
哲学者の西田幾多郎は、「生きるために便利だから真理なのではなく、逆に真理だから、我々の生活にとって、有用にされ得るのである。」(哲学概論)と述べています。本誌97巻6号の会長挨拶で、望遠鏡から幾何光学が、蒸気機関から熱力学が発展したことを例に、応用基礎研究(応用が先で、基礎が後)について紹介させていただきました。見方を変えると、応用研究は、我々を真理に導く「アブダクション」を与えてくれるのです。欧米の先端科学に追随する状況、つまりは正しい仮説(ゴール)が与えられている状況から日本が抜け出すカギは、独創的な「アブダクション」にあると思います。そして我々の個性、人生もまた、いかなる「仮説」を設け、それをいかに証明するかで決まると言えるのではないでしょうか?
研究はもちろん、人生においても、今年は「仮説」を立て「証明」を試みる思考法を実践したいものです。
「プロならプロであることを証明しなければならない」(広岡達朗:野球解説者)
「各人はいわば一つの仮説を証明するために生れている」(三木 清:人生論ノート)
著者紹介 北陸先端科学技術大学院大学(教授)、日本生物工学会(会長)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 23 12月 2019
生物工学会誌 第97巻 第12号
高木 睦
漠然とではあるが、「大学卒業後は人の役に立ちたい」と願っていた高校生の私は「工学部では産業に直結した技術を学べる」と聞き、工学部に入学した。卒業し、「やっと世の中の役に立てる」と喜んで、ある総合化学会社で13年間勤め、一仕事終えて退職して、大学(工学部)の教員になった。
工学は(狭義には)サイエンスを応用して大規模に物品を生産するための方法を研究する学問であると思う。だから、講義や研究指導では「サイエンスも大事だが、ここではエンジニアリングをやる」と学生達に再確認するとともに、「エンジニアリング(工学)は研究結果の実用化、事業化、社会実装を目指すことが前提だから、実用化までのしっかりした(仮説を含む)道筋、すなわちロジックが工研究には大事だよ」と説明するようにしている。言い換えれば「どのような経済的・社会的価値をどのように創出するのか」を十分に調査して組立ててから工学研究を始めるということだ。
実用化までのロジックはさまざまな要素を合わせて組み立てられる。たとえば、反応主原料を輸入する場合、日々変動する為替レートは重要な要素である。この他、その産業分野の状況や流れ、商品の機能やコンセプトの新しさ、コンペティターの状況、製造原価の目標、律速技術打開の可能性などもロジックの要素に含まれるだろう。
現在私が所属している大学の化学系専攻(バイオも含む)だけの大学院には、工学部出身学生と理学部出身学生がほぼ半数ずつ所属している。その中でほとんどすべての理学部出身学生の修士論文発表には、実用化に関するロジックはなく、ひたすら化学反応のメカニズムが追及される。サイエンスはこれでいいのだと思う。
ところで、昔の話だが、私は上記の総合化学会社に入社後も年に数回は工学関連の学会で、特にアカデミアの工学研究を聴講させていただいたが、中にはロジックはあるが具体性が弱く「実用化は難しいのではないか」と思う発表もあったと記憶している。他に、「実用化までのロジックがなくても、特許出願や企業から頂いた奨学金が実用化の十分条件との思いこみ」を感じさせる発表もあった。これらに対して、実用化に至るまでのしっかりしたロジックを工学研究者自らが組み立ててから始めた工学研究を少しでも増やすことができれば、アカデミアの工学研究の産業への貢献が高まるのではないかと思う。
ではどうすれば、少しでも多くのアカデミア工学研究者が、実用化までのしっかりしたロジックを組み立てる力を発揮できるようになるか、たたき台として考えてみた。まず、企業の中堅技術者の実用化までのロジックの考え方を、アカデミアの若手工学研究者がスクール形式やe-ラーニング形式で理解できるようにならないだろうか。もう一つは、アカデミアの若手工学研究者が研究発表する会を設ける方法である。主として実用化までのロジックに関するコメントを、発表を聴講した企業の中堅技術者が紙に書いて(必要ならブラインドで)オーガナイザーに発表会場で渡していただき、オーガナイザーから研究者に訊ねるというのもいいかもしれない。
そして、「(他人のことは偉そうに言う反面自分のことは見えていないかもしれない小生も含めて)大規模な研究にしても小規模な研究にしても、アカデミアの工学研究もちゃんと地に足がついている」と企業の方にもっと言ってもらえるようになれば幸いである。
著者紹介 北海道大学(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 11月 2019
生物工学会誌 第97巻 第11号
本多 裕之
自身のことをつぶやいて恐縮である。私の本務は名古屋大学予防早期医療創成センターである。大学のセンターで“予防”を標榜しているセンターは全国的にも珍しい。このセンターは、2015(平成27)年7月に名古屋大学の全学センターになり、医学研究科から1名の教授、工学研究科から1名の教授(小生である)、産業界から1名の特任教授、センター専任の准教授を学内の管理定員で措置していただいて4名体制で運営している。センター定員とは別に医学研究科長の門松健治先生をセンター長に迎え、松尾清一総長にもサポートいただき、産学連携、医工連携の研究拠点として運営している。
センターのミッションは多分野産学官連携による健康寿命の延伸への貢献である。人生100年時代が到来し、健康寿命と個体寿命の差をいかに少なくするかが問われている。日本の高齢化は世界の最先端にあり、高齢化のための社会システムの構築や予防に向けたモノづくりは世界が注目する最先端事業である。センターの研究の一つに、高齢者の健康維持・増進のためのコホート研究がある。この研究は、企業の現役従業員や退職者をリクルートし、過去から現在までの健康診断データ、リストバンド型の活動量計を使った現在の運動習慣情報やアンケートなどを駆使した食習慣情報、さらには健診の残余血液を使ってDNAを採取し、200 SNP程度の遺伝情報も収集し、過去の健診情報から将来の疾患予測を試みるという研究である。具体的には、メタボリックシンドロームからの脱却を促すため、個々人の体質にあった健康増進アドバイスを解析で得て、それらを特定健診の特定保健指導の一助にしていただくことを考えている。
さて、この研究で、課題は何だと想像されるだろうか?1)エントリーする対象者数、2)体質情報としてのSNPタイピング数、3)健診情報の入手方法の確保、4)レセプトなどを使った疾患発症情報の入手、5)現在の運動習慣・食習慣の正確な情報収集、6)それらを組み合わせた精度の高い推定モデルなど、どれも重要な問題である。しかし、あまりに不正確な入力情報は解析から除いて、データ数の少ない入力情報であれば少ないなりに、アドバイスを出すことはできる。難しいアウトカムを設定しなければ、それなりの疾患発症の関連性は得られる。我々も、たとえばGHRL遺伝子のrs696217のSNPのMajor Alleleを持っている人はカロリーを控えて体重を減らすことが重要といった知見を得ている。誤解を恐れずに言えば、上記の課題を一つずつ解決していけば、より精度の高い関連性が得られるし、複雑なヒトの体質や疾患発症の機構を理解する研究につながる。研究は続けられるのだ。しかし、それだけでいいのか?
生活習慣を変えることを行動変容という。実は一番大きな課題は、特定保健指導をしても生活習慣を変えない、すなわち行動変容につながらない方が多いということである。つながらなければ研究しても意味がない。リアルワールドでの実証こそ何よりも重要である。我々の研究では、自分の体質情報、健康診断情報、運動習慣情報などを掲載したマイページを用意し、対象者個人だけが閲覧できるセキュアな仕組みを作って、データを見える化し、健康意識を高めてもらうようにしている。だがしかし、それでもなお、健康意識の低い方は何も変えない。変える方は元来健康意識の高い方である。メタボリックシンドロームは痛くもかゆくもないため、行動変容につながりにくい。
さて、我々大学教員にとっての“リアル”は学生の教育である。社会に出るまでの最後の教育機関として、その責務は決して軽くない。「もっとどん欲に広い知識を得るようにせよ」「もっとアグレッシブに発言すべし」「しつこくデータを見る努力をせよ」「顕微鏡下で起きていることを想像力で理解せよ」……。指導はしてみるが、行動変容につながっているであろうか。自身のことで恐縮だが、それでもなお、「この子(学生)は、どう言えば(指導すれば)変わってくれるのか」を考える“実証研究”を楽しんでいる。ヒトが一番面白いのだ。陳腐に聞こえることを恐れずに書けば、情熱をもって語りかけ続けることが何よりも大事、である。
著者紹介 名古屋大学予防早期医療創成センター(工学研究科兼務、教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 10月 2019
生物工学会誌 第97巻 第10号
加藤 純一
1988~1990年、ポスドクとしてイリノイ大学シカゴ校のA. Chakrabarty先生の研究室でお世話になった。Chakrabarty先生は面白い実験データが出ると、しばしば“my hunch is …”と頭にひらめいた解釈を意見として述べ、「それを検証してみたら」とアドバイスしてくれた。しかし、その“hunch”の多くはとてつもなく飛躍していたり、突拍子のないものであったりしたので、アドバイスされた方は困惑してしまう。幸いなことに、その日の夕刻までにChakrabarty先生はhunchを忘れてしまうため、研究室の学生とポスドクはhunchを聞き流すのを常としていた。今振り返ると、hunchを引き出させる事象に遭遇すること、その直感を実験的に実証するに至ること(さらに言うと実証したことが次のhunchへと連鎖反応的に拡がっていくこと)が研究の大きなモチベーションになっていることに気づく。そしてそのためにはChakrabarty先生のように、ことあるごとに“my hunch is …”と意見表明していかなければならないとやっと気づくようになった。
細菌の多くは好ましい化合物には集積し、好ましくない化合物からは逃避する走化性という行動的な環境応答を示す。病原菌や重要な環境細菌の挙動(走化性)の制御を目指し、これまで何種類かの細菌の走化性を測定してきた。アガロースで検定物質を固め入れたガラスキャピラリーを菌体懸濁液に挿入し、キャピラリーの開口部への応答(集積、忌避もしくは無応答)を観測することで走化性を評価する。Pseudomonas aeruginosa(緑膿菌)、Pseudomonas putida、Enterobacter cloacaeではクリアな走化性測定を行うことができたが、Ralstonia solanacearum(青枯病菌)では悩ましい事象に遭遇した。R. solanacearumは時としてコントロール(アガロースのみ)にも集積応答を示してしまうのである。厄介なのはR. solanacearumのコントロールへの応答がばらついていることである。コントロールに対し強い応答を示した日には他の化合物への走化性応答を評価することはできない。ともかく、コントロールへの応答がないか微弱な時の日のデータのみを使うことでこの問題を棚上げしていた。とある日、“my hunch”が頭に浮かんだ。「ガラス由来の化合物に応答しているのかも」早速ガラスキャピラリーの成分に対する走化性を調べたところ、R. solanacearumはホウ酸を誘引物質として感知し、走化性を示すことが判明した。そしてその後すぐにホウ酸走化性のセンサーも特定することができた。興味あることに、ホウ酸走化性センサーのホモログは属を超えた種々の細菌に分布するが、それらはすべて植物病原菌なのである。ホウ酸は植物の細胞壁のペクチンの架橋に使われており、植物にとって生育必須成分である。ホウ酸走化性を介した植物病原菌に共通な感染メカニズムがあるのではないかと、ワクワクしている。
士郎正宗原作の「攻殻機動隊」はSF漫画・アニメである。このSF世界では人類は自らの脳を電脳化し、コンピュータネットワークと直接接続できるようになっている。電脳における個々人の個性、自我、意識、霊性の本源は「ゴースト」と呼ばれている。攻殻機動隊の主人公である草薙素子少佐が直感を得た時につぶやく有名なフレーズが「私のゴーストがそう囁く……」である。今でも科学的な「ゴーストの囁き」を聞ける機会がある。ゴーストの囁きが聞けなくなった時が引退の時期なのだろうか?
著者紹介 広島大学大学院統合生命科学研究科(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 9月 2019
生物工学会誌 第97巻 第9号
鈴木 健一朗
微生物分類学といえば、以前は分類学者だけの専門分野であった。しかし、今では細菌/アーキアの場合、16S rRNA遺伝子の塩基配列(以下16S rRNAと略す)を決定することにより、誰でも自分の分離した菌株の同定が客観的な基準でできるようになり、微生物学者に身近なものになった。16S rRNAが共通の物差しで分類体系が構築されているため、塩基配列に基づいて菌株を地図上にプロットすれば、その株の学名がわかるとともに、比較の対照にすべき近縁な菌も的確に選定できる。これには国際的なデータベースの利用環境と微生物株保存機関の整備が大いに貢献している。
しかし、異なる株を同一種と決定するハードルはまだ高い。解像度が高くない16S rRNAだけで種は決定できないため、1960年代から使われている染色体DNA交雑による類似度(DNA-DNAハイブリダイゼーション、DDH)が必要である。DDHで70%を種の境界とするという「コンセンサス」がいまだ基準になっている。そうなると、16S rRNAでどのくらい離れていたらDDHをせずに別種にできるかの基準も重要である。これは経験的に16S rRNAの類似度で97%以下とか98.7%以下とか言われている。DDHは、比較する菌株双方からDNAを抽出し、交雑反応を行うウェットな実験として行われてきたが、最近では、全ゲノム塩基配列(ドラフトゲノム)(WGS)の決定が安価で行えるようになり、それを用いてDDHをパソコン上(in silico)で行う方法も普及してきた。
そこで、2018年から国際原核生物分類委員会(ICSP)は、細菌とアーキアの新種の発表の際にはその基準株のWGSの決定をほぼ義務化した。すべての種の基準株のWGSがデータベース化されれば、分離株のWGSを決定するだけで種レベルの同定が可能となり、さらに機能性遺伝子の情報も利用できるようになるため、分類学だけでなく、応用微生物学にも大きく寄与することが期待される。分類学は学問であると同時に、コミュニケーションツールであることから、新技術の導入と命名のルールの調和がますます重要になってくる。
「国際原核生物命名規約」の改訂版が2019年1月に発行された1)。前の改訂が1990年なので、29年ぶりとなる。命名規約では国際微生物学会連合(IUMS)の公式誌『International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology(IJSEM)』への掲載のみを学名の正式発表としているので、そこでそのすべてが把握できる(2017年現在で約3000属17,000種)。命名規約では新種発表に際し、「生きた菌株」のみを種の分類学的基準(基準株= type strain)として指定し、微生物系統保存機関(カルチャーコレクション)へ寄託・公開することが規定されたため、標本、スケッチは不可となった。
さらに2000年からは、基準株の寄託は異なる国の複数の保存機関に行うよに厳格化された。これは生物多様性条約(CBD)による生物資源の国際移転が厳しくなっている現状への対応を見直す良い機会である。分類学は適切な生物資源の管理にとってもっとも基盤となるべき知識と技術のひとつであり、CBDにとっても重要な科学である。そのために、生物遺伝資源への適切なアクセスは研究成果を担保し、発展的に利用できる国際的に公平な学術環境の維持に必要である。分類学は世界共通であり、新種の発表には既知種との比較が不可欠である。生きた基準株へのアクセスの重要性はますます高まっている。
最近ではMALDI-TOF MSが微生物の迅速同定に利用され、そのためのデータベースも市販、あるいは公開されている。マイクロバイオームの解析もゲノムベースで体系化された分類学があるから可能となったと言うことができようこれらの新しい技術が新しい知見を蓄積し、相互評価することで微生物の分類学がますます意味のあるものになっていくことに期待したい。
1) Parker, C. T. et al. (Eds.): Int. J. Syst. Evol. Microbiol., 69, S1 (2019).
著者紹介 東京農業大学応用生物科学部醸造科学科
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 23 8月 2019
生物工学会誌 第97巻 第8号
西村 顕
今、米国でクラフトサケが人気なのはご存じでしょうか?クラフトサケとは、現地の小さなサケ・ブリュワリーで醸造される日本酒のことで、2018年にニューヨーク州で初めて開設された“Brooklyn Kura(ブルックリンクラ)”で醸造された日本酒は、現地の日本酒ソムリエたちに絶賛されました。米国内には多くの小規模な蒸留所やビール醸造所があります。一方、サケ・ブリュワリーは、Brooklyn Kura を含めて約15か所と少ないのですが、今後参入者が増加すると言われており、クラフトサケがブームになりつつあります。また、米国のみならず世界中で、日本酒の品質・味わいに対する評価は高く、その特異的な醸造技術にも熱い視線が注がれています。
日本生物工学会には賛助会員として多くの発酵・醸造関係の企業が属しています。筆者も大学卒業以来36年にわたり日本酒メーカーに勤務し、現在は、研究部門から離れて経営企画部門にいますが、企業生活の半分を研究開発部門で過ごしました。冒頭に述べた米国での日本酒醸造への熱い視線は、元技術者(研究者)として喜ばしいとともに、世界に発信できる現状の日本酒に関する技術的側面の研究成果が少ないことが気がかりです。
「清酒醸造の歴史は、たゆまない技術革新の歴史」と先輩諸氏から教えられてきました。室町時代の「菩提もと(乳酸発酵の利用)」や「火入れと呼ばれる低温熱殺菌技術(pasteurization)」、江戸時代の「寒造り」、明治時代の「速醸もと」、大正・昭和時代の「醸造協会酵母」の整備、「四季醸造工場」の建設、「連続蒸米機」「大型製麹機」「自動圧搾機」などの開発、昭和から平成にかけては、「生酒劣化防止技術」「高香気生産性酵母」の育種、「発酵制御技術」「麹菌の機能」や「清酒酵母の高発酵能」の遺伝子レベルでの解析など、まさしく技術革新の歴史でした。技術革新のたびに、日本酒の品質が向上し、おいしくなり、さらに安心・安全が付加され、大いに愛され消費されてきました。
しかし、平成から令和に時代がかわるとき、日本酒の現状には寂しいものがあります。30年近く毎年消費量が減少し、日本酒業界全体が疲弊しつつあります。消費が減少した要因は多々ありますが、本学会に席を置き、業界で長く仕事をしてきた筆者には、世界に発信できる最近の日本酒に関する革新的な技術開発、研究成果の少なさが一因ではないかと感じています。
筆者が、研究開発部門のリーダーでいたころ、部下に以下のような言葉(ある本の引用だと思いますが、書名は忘れました)を贈っています。「普通は、研究が進展するにつれ問題が整理され、わかったこととこれから検討すべき点がはっきりしてくる。にもかかわらず、問題が徐々に複雑になる場合は、テーマの筋が良くないか、研究の進め方が良くないかのいずれかだ。良い研究テーマは、どこかすっきりした美しさ、簡明さを秘めている。進め方についても、複雑になるよりも、簡明になっていく方向を選択したほうがいい。さらに重要な要件として、テーマの懐の深さがある。アイデア自身のフレキシビリティ、展開が多様となる可能性を秘めたテーマが面白い。何を美しいと感じ、何を簡明だと受け止めるか、何を懐が深いと思うか、そこに研究者のセンスが問われる。テーマの良否は、そのテーマを考え出した研究者のセンスと切り離しては考えられない。自分のテーマの素性の良否を冷静に問う姿勢を持った研究者は、自分の研究を冷静に見つめることができる。」(これらの言葉が、少しでも若手研究者の一助となれば幸いです)
最後に、令和時代には、本学会の醸造(特に、日本酒)にかかわる技術者、研究者が発奮し、世界に発信できる研究成果を生み出し、そして、日本酒産業を活気づけてくれることを期待しています。
著者紹介 白鶴酒造株式会社(取締役執行役員 経営企画室長 兼 商品開発本部長
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 24 7月 2019
生物工学会誌 第97巻 第7号
金川 貴博
自然界では、どの種の生物も、他の種の生物との係わりあいの中で生活している。ヒトでは、他の種の生物を食して生きているという形での係わりあいだけでなく、ヒトの皮膚の表面や腸内には多種類の細菌が生息していてヒトの健康に係わっている。だから、皮膚表面や腸内に、どんな種類の細菌がどれくらいいて、どんな働きをしているのかを解明したいと思うが、複数種の細菌が混じった状態のものを解明するのは、ほぼ不可能である。したがって、皮膚表面や腸内にいる細菌の様子は、よくわからない。こう言うと「最新のDNA解析技術を使えば、かなりわかるはずだ」という反論が出てくるだろうが、本当にそうなのか。DNA解析を行えばたくさんのデータは出る。しかし、そのデータは試料の細菌相をどの程度に反映しているのだろうか。
細菌相解析上の最初の問題点は、試料中のどの細菌からも等しくDNAを抽出する手段がないという点である。DNAの抽出のしやすさは菌ごとに異なり、DNA抽出段階で大きな偏りが生まれる。DNA抽出後の操作としては、菌の同定の指標である16S rRNA遺伝子をPCR増幅することが多いが、ここでも偏りや誤りを生じる。この点について、私は総説に詳述した1)。この総説はELSEVIER社のMost Downloaded JBBArticles(最近90日間)に今もランクインしており、引用回数も増え続けて500回を超えた(2019年5月に確認)。微生物集団を解析したデータには偏りがあることが広く認識されつつあるようである。解析データはあまり当てにならない。
一方で、微生物集団の利用は大いに進んでいる。微生物の利用というと発酵食品や医薬品製造に目が行きやすいが、実際にもっとも微生物が利用されているのは廃水処理分野である。しかしながら、廃水処理分野に微生物の専門家は私以外にはほとんどいない。そもそも微生物学の基本は純粋培養であり、他の種の生物との係わりを断ち切った特異な環境で育つ微生物を対象にして出来上がった学問は、特異な環境(純粋培養系)にしかあてはまらない。自然界の微生物集団を扱うには、現在の微生物学とは異なる考え方が必要であり、微生物学者には不向きな分野と言わざるをえない。どの微生物にも当てはまるような共通事項は使えるが、使える事項はわずかしかない。
それでは、微生物学者は微生物集団にどう挑めばよいのか。ひとまず微生物学を忘れて、微生物集団を注意深く眺めることである。目の前で起こっていることが真実の姿である。微生物集団の中身を解析するのではなくて、さまざまな条件のもとで集団が示す行動を十分に見ることが必要であり、これには膨大な時間がかかる。これを自分で行うのは大変だから、こういう作業は他の分野の人に任せよう。他人の実験や現場のデータを眺めた結果、微生物学者の強みを発揮できそうな局面が来たら乗り出す。「先手必勝」ではなくて「後手楽勝」をねらってみよう。
微生物集団の利用は医学分野でも始まっている。「糞便移植」である。これは、お腹の調子が悪い人を治療するために、お腹の調子がいい人から便をもらって腸内に挿入する方法である。お腹の調子がいい人は、腸内の微生物相健全なのであるから、健全な人から出た新鮮な便を調子が悪い人に入れて腸内に健全な微生物相を作る。「善玉菌?」を入れるのではなく、微生物集団をそのまま使う。廃水処理分野の発想と同一である。
微生物集団の利用は今後ますます重要になるだろう。微生物集団に挑むには、微生物学の常識を捨てて、研究対象をよく見て、考え方を組み立てなおす作業が必要になる。
1) Kanagawa, T.: Bias and artifacts in multitemplate PCR, J. Biosci. Bioeng., 96, 317 (2003).
著者紹介 京都先端科学大学バイオ環境学部(特任教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 22 5月 2019
生物工学会誌 第97巻 第5号
太田 明徳
私は1971年6月30日卒業という、明治初期の大学9月入学時代のような履歴を持つ大学紛争世代の一員である。大学ストライキ、すなわち学生による授業放棄と大学の封鎖が始まったのは教養学部の2年次学生の時の7月頃であり、翌年1月のストライキ解除まで、長期の無為の期間を過ごしていた。それだけの期間があれば有意義に過ごすことができそうなものであるが、いつストライキが終わるかわからないので、結局、日時が経過するままであった。喫煙という悪癖に馴染んだのが後遺症で、30才直前まで止められなかった。
なんとか無事に学部に進学できたのは、紛争収束のために、さらにいい加減になった単位認定のおかげと思う。農学部農芸化学科に進学したが、この学科を選んだ理由は、微生物に惹かれたためと、受験時にお世話になった家の子息がビール会社の社員で、学科の先輩であったことである。進学決定後は慌ただしく2年次後半と3年次の短縮された課程を済ませて、卒業研究の研究室に配属された。微生物に関心を持ったのならば、伝統があり、人脈も豊かな研究室を選べば良かったのであるが、当時の私はうかつにも卒業研究の研究室の選択によってその後の人生が大きく左右されるなんて思いもしなかった。単純に酵素学が新鮮で先端的な学問分野に思われたので、今堀和友教授の酵素学研究室を志望したのである。
今の私は学生たちに、目指す分野を真剣に考え、調査することを勧めている。若い未熟な人間が慎重に考えても、必ずしも思うようにはならない。しかし、最上の選択ではなくとも人生に対して肯定的で積極的であるかぎり、有意義な人生を送ることができるであろう。どのような分野が自分に向いていて、おもしろいか、また重要であるかということを懸命に考え、選択することが、自分の人生を生きるということでもある。私自身はあまり流れに逆らわず生きてきたように思うが、同時にそのことによって研究者として失ったものも多かったのではないかと振り返ることがある。良い研究者であるということと円満な人生を送ることとはあまり関わりがない。時に研究者となることを人に勧めることにためらいを感ずるのは、それが人生に大きなひずみを生ずることがあるからである。
今堀教授は教養学部基礎科学科の助教授から農芸化学科教授に異動して来られ、私は2代目の農芸化学科卒論生であった。研究室には教授についてきた基礎科学科の優秀な大学院生がいて、農芸化学科の卒論生には必ずしも馴染みやすい雰囲気ではなかった。博士課程院生のなかにはノーベル生理学・医学賞を受賞された大隅良典先生がいたのであるが、先生は自ら望んで京都大学にいてほとんど不在であり、酵母研究の仲間としておつきあいが始まるのは10年近く後のことである。当時の今堀研究室では助手2名が留学中で、残る当時の太田隆久助教授、大島泰郎助手、そして私を指導した松澤洋助手は、てんでに自分の持ち込んだ研究をしていた。私はこれが当たり前の大学の研究室だと思っていたが、今時の研究室とはだいぶ違ったようである。
卒業研究では松澤助手が分離した大腸菌の形態変異(短桿菌が丸くなる)に関する遺伝学を始めることになったが、酵素学とは関わりのないこのテーマは私に合っていたらしく、楽しかった。今堀研究室の当時の酵素学は一種の分光学で、酵素の円偏光二色性の測定により、酵素の構造を調べる仕事が中心であった。これにはあまり興味が持てず、旋光の数式にも困惑していたので、松澤先生についたのは私にとってまことに幸運なことであった。
後に分子生物学的な手法による研究に向かう大きな契機にもなった。卒論の発表会で今堀教授から、吸光度と濁度の混同を指摘されたが、これが唯一の教授からの直接の教えであった。酵素学研究室に卒論配属の希望をしながら、大学院では志望しなかったのであるが、その理由はもう一つある。当時の今堀研究室には、理学部生化学科の学生も卒論生として来ており、大学院生をチューターとしての「Enzyme Physics」(Volkenstein)の英語版を読む卒論生の読書会があった。そこで生化学科出身の卒論生が教養学部時代にロシア語の原書で読んだと言った。ストライキの期間を有意義に過ごした学生がいたのである。これで今堀研究室に残るという気持ちがきれいに消えてしまった。
結局、私はなんとなく自分に向いた世界に向かって進んでいたのだと思う。もし私が勤勉な勉強家で、当時の酵素学にまともに向き合っていたら、苦しかったに違いなく、博士課程を志望しなかっただろう。若者にとって研究は何より楽しくなくてはならず、新しい発見が伴えばもっと楽しい。楽しくない研究はやらない方が良いと今の私は言うことができる。
著者紹介 中部大学応用生物学部(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 23 4月 2019
生物工学会誌 第97巻 第4号
宇多川 隆
産業界から大学へ、そして公設研究所と異なる文化の中で勤務する機会を得た。その間にバイオものづくりの研究・開発・生産に従事し、それぞれの立場でその面白さを経験してきたので一端を紹介する。
最初にバイオものづくりの面白さを知ったのは、入社して間もなく取り組んだ抗ウイルス剤の製法研究においてである。生産菌の探索を1年近く続けたが、ポジティブな結果がまったく得られず諦めかけていたところ、ある時、発酵(酵素反応)に使用していた培養器の温度が上昇するというトラブルに見舞われた。失敗かと思われたその発酵(反応)液を分析すると、なんと目的とする抗ウイルス性化合物(アデニンアラビノシド:Ara-A)が生成していたのである。生産の最適温度は60°Cにあり、室温まで冷却するとAra-Aの結晶がキラキラと出てきた。その時の感激は忘れられない。ヘルペスウイルスに効果的で、多くの関係者の尽力で工業化され、商品名アラセナAとして上市された。60°Cでは生産微生物の生育はおろか完全に死んでしまう。なぜ当該微生物は死ぬほどの温度で抗生物質を作るのか不思議であり、興味の尽きないところである。
他にも、高温で強い活性を示すアミラーゼやプロテアーゼなども中温微生物によって生産されることが知られている。生物の生育至適環境と酵素力価の至適条件が必ずしも一致しないところに生物触媒のスクリーニングの難しさと面白さがある。酵素活性の最適値の多様性は生物の進化と関係があるのかもしれない。一方、耐熱性DNAポリメラーゼは高温菌、アルカリプロテアーゼは好アルカリ細菌が生産するように生育環境と酵素の活性発現至適条件が一致するものは数多く知られている。
その後、地域資源をバイオの力で有効に活用するという研究に携わることになった。漁業が盛んな地域では、魚加工場から大量の副生物(アラ)が生成し、その多くは有償で廃棄されている。この副生物には良質なタンパク質とそれを分解する酵素が含まれている。分解酵素の最適温度は55°Cにあり、タンパク質は速やかに分解されてアミノ酸を遊離する。この性質を利用すると、魚加工副生物から短時間で魚醤を生産することができる。サバやブリの加工副生物を原料にした場合、1~3日で発酵が完結し、精製して得られる魚醤は旨味を呈していることから調味料として販売するに至っている。廃棄されていた副生物を短時間で有用物に変換するバイオの力に感動である。55°Cではサバやブリは生存できないが、体内の酵素が生きているところに生物の驚異を感じる。
高温発酵では速度が速くなるだけでなく、雑菌の生育がほとんど認められないので、都合の悪い化合物が副生しないことも大きな利点である。雑菌が汚染すると、Ara-A生産の場合アデニン部位がヒポキサンチンに分解されて抗ウイルス活性は弱くなる。魚醤では、ヒスチジンが分解されてアレルギー物資であるヒスタミンが生成する。
有用物質の生産研究において微生物などをスクリーニングする場合、中性・常温条件で実験することが多いが、温度やpHなどの条件を大胆に変えてみると、思いもよらない新しい反応や物質の発見につながる可能性がある。
現在の地球上に生存する生物は、過去のさまざまな環境を生き延びてきた生物の末裔であり、過去の過酷な環境に対応してきた能力がその遺伝子の中に隠されていると考えられる。この能力を引き出し、有用物質の生産に利用することは、バイオによるものづくり研究者の重要なミッションである。
常識にとらわれず、だれもが思いつかないような条件において発現される生物の力を利用し、有益なものを生産するバイオものづくりの面白さを味わってほしい。
著者紹介 福井県食品加工研究所(特別研究員)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 3月 2019
生物工学会誌 第97巻 第3号
秦 洋二
日本生物工学会の始祖は、1923(大正12)年に設立された大阪醸造学会である。名前の通り、清酒醸造などの醸造・発酵分野が中心となった学会である。当時は国税収入の中に酒税が占める割合が2割近くに及び、酒造業の発展は安定な税収確保のためにも重要な課題であった。また単なる「お金」だけの問題ではなく、酒造りのテクノロジーは、当時の微生物学で解明するに非常に魅力的な研究対象であったに違いない。
酒造りにおいては、西洋に先んずること300年以上前から低温加熱殺菌法「火入れ」が導入されていたり、複数の微生物を巧みに操りながら清酒酵母のみを純粋に培養する技術「生もと」が確立されていたり、先人たちの努力により多くのテクノロジーが組み込まれていた。ただ、これら先人たちが苦労して発明したものについて、国際的には我が国が発明者になりえていない。低温加熱殺菌法の発明者は、火入れの完成から300年後のルイ・パスツールである。なぜか?それは、清酒製造におけるテクノロジーについて、その理屈が解明されていなかった点があげられる。ヨーロッパのような多民族で構成される地域においては、人種、言語が異なる相手を納得させるために「理屈」で説明することが要求される。まさしくパスツールは、低温加熱により混入する乳酸菌が死滅することを理屈で明らかにした。一方我が国のように、ほぼ単一民族で同一言語を使用する地域においては、理屈もさることながら「情緒」を含む人間同士の信頼関係で他人を説得することが多い。酒造りをはじめ、日本の伝統的技術においては、当時の世界に先んずる発明が多数見いだされているが、残念ながら理屈の解明がなされずに、その多くについて世界の中で発明者の名称は与えられていない。
このような「宝の山」であった清酒醸造技術を当時の最新の科学理論で次々と解明していった原動力が大阪醸造学会であった。大阪醸造学会の学会誌である『醸造學雑誌』の創刊号には、清酒醸造におけるさまざまな問題点を技術的に解決する論文はもちろんのこと、「清酒醸造上の持論」のような論説記事や、「南シナにおける酒類」といった国際色溢れた論文まで掲載されている。また同年は関東大震災に被災した年でもあり、下半期の学会誌には、「大震災と諸味仕込用タンク」といった時事に迅速に対応した記事も紹介されている。学会誌として、清酒醸造の技術的な学理の解明だけでなく、さまざまな分野で酒造産業の発展に貢献した雑誌であったことがうかがえる。
生物工学会は、4年後の2023年に創立100周年を迎える。醸造・発酵が中心となってスタートしたが、現在は生物化学工学として微生物が関係する幅広いプロセスに応用されるようになり、さらに酵素工学、動植物細胞工学とその研究対象が広がり、近年は生物情報工学など新しい分野との融合も図られ、幅広い研究領域を網羅する学会となった。設立当初の大阪醸造学会が対象とする産業分野が醸造・発酵産業に限られていたものが、いまでは食品産業はもちろんのこと、医薬、医療分野、環境分野など、学会が貢献すべき産業分野も大きく広がっている。かつての大阪醸造学会が酒造業の発展に大きく貢献したように、現在の生物工学会もその波及する産業界の発展に大いに貢献して欲しいと願う。そのためには何が必要か?その一つに「枠を超える」「壁を取り除く」ことがあげられる。『醸造學雑誌』が、学術誌として単なる技術・研究報告にとどまっていたならば、酒造業への影響力は限定的であったかもしれない。学術誌の枠を超え、酒造業の発展に必要な情報提供を進めたが故、業界への貢献度は飛躍的に向上したのではないだろうか。先述のように生物工学会が関係する研究領域は非常に多岐にわたっている。この多様な研究領域の枠を超えて、異業種の壁を取り除いて、さまざまな産業に貢献できる技術シーズを学会から発信し続けることを期待する。
著者紹介 月桂冠(株)総合研究所
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 2月 2019
生物工学会誌 第97巻 第2号
栗木 隆
産業界では、常に「誰に」「何を」「どのように届けるか(売るか)」を考えて活動している。こんな中、paradigm changeはdisruptive changeとも思えるほどの近年の産業構造の変化についていけず、消滅していく会社は多い。最近のdisruptive changeの例は、従業員わずか3千人余りのAirbnbの時価総額が、すでに従業員1万7千人の世界的ホテルチェーンのHiltonを超えたことである。HiltonはMarriottと競争している場合ではなくなったのである。顧客の解決して欲しい問題をいかに解決するかを突き詰めて考えると「立派な建物」「行き届いたサービス」は必ずしもすべての顧客に必要ないことがわかる。Airbnbは顧客が想像も認識もしていなかった問題解決法を提供したことが成功の鍵であったと思える。こんな風に「イノベーション」に必ずしも研究や技術開発は必要がない。では、これからの産官学の研究機関はいかにして生き残っていけば良いのであろうか。
「マーケティングは顧客から出発する」とはP・F・ドラッカーの有名な言葉であるが、産業界だけでなく学術界の研究者も「顧客」を意識せず自分の仕事を進めることは困難な時代になったと考えねばならなくなったと私は思う。最高水準の科学によって、未知の現象を解き明かす、あるいは誰も目にしなかった技術やモノを生み出すことは学術界の研究者が第一に目指すことであろう。研究者のモチベーションは「その研究がいかに自分にとって面白いものであるか」「世界の誰もがまだ成し遂げていないか」などであり、この点は学術界であろうと産業界であろうと同じであると考える。しかしここで「顧客は誰か」を考えることもまた同じく必要になったと皆さんも思われないだろうか。
学術界においての顧客は、その研究に喜んで資源を投入してくれる納税者や社会そのものであると思う。2015年にスーパーカミオカンデでニュートリノ振動の発見によりノーベル賞を受賞した梶田隆章博士は受賞後、「何の役に立つのですか?」という質問に「何の役にも立たない」と答えた。人間だけが持つ高度な知的欲求を満たし、100年後かも知れないが人類に恩恵をもたらすであろう、このような最高水準の科学であれば「顧客」は喜んで資源を投入する。山中伸弥博士は、最高水準の科学でありかつ医療に直接大きく貢献するiPS細胞を開発した。「顧客」はこの成功に歓喜し、これを利用した医療を待ち望んでいる。しかし多くの研究は、その域にははるかに達しない「そこそこのレベルの研究」に終わる。顧客はそれらの研究に今後も資源を投入してくれるだろうか?
一つ目の解はその時点で「何の役にも立たない」と思われても、顧客すなわち人類ならではの知的好奇心と夢を満たす喜びを与えるほどの「世界でダントツ」の研究を行うことである。こんな研究は100年後には必ず「大変役に立つ」研究になるものである。二つ目の解は、レンガを高く積み上げるには横方向にも積まなければならないことを研究者が理解し、顧客も納得させることである。素晴らしい研究の周辺領域にはその研究を支える分析技術の開発や実験方法の開発が必要であり、また「ダントツを目指して」切磋琢磨し競争することにより抜きんでた研究は生まれる。最高水準の科学を支えるこんな裾野も必要である。三つ目の解は学術界でも産業界でも「顧客のニーズ」に応えることであると思う。顧客のニーズはその研究によって産業競争力が生まれ、雇用が創出され、世の中が豊かになることに尽きると思う。そんな研究には間違いなく大きな資源が投入されるであろう。これに関連して、産業界では「顧客ニーズ」に応える時代から、顧客さえもニーズと認識していない「インサイト」を探索しこれに応えないと市場で勝てない時代になっている。これら三つに当てはまらない研究は、「顧客の投資効率に合わない」研究として今後淘汰される覚悟が必要である。ただ、この覚悟さえできていれば、かく言う私も四つ目の解はあると思う。長い間注目されず、大きな研究費も安定した地位ももたず、細々とコツコツと「動く遺伝子」の研究を続け、81歳でノーベル賞を受賞したバーバラ・マクリントックの研究者としての生き方に、私は強い共感と魅力を持つ一人である。
著者紹介 江崎グリコ株式会社(取締役常務執行役員)、グリコ栄養食品株式会社(代表取締役社長)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 24 1月 2019
生物工学会誌 第97巻 第1号
山本 秀策
デジタル革命の急速な進展に立ちすくむだけのそんな日本に、労働人口の減少という国力衰退の始まりが重なり、再生を期して国を挙げての「生産性向上」「イノベーション創出」のかけ声も、ただ虚しく響くだけ。今こそ大学は、その「知」を生かし、日本の再生に貢献すべき時ではないか。古くて新しい喫緊の課題である。
知財の視点から私見を述べたい。
2017年3月のネイチャー特別企画冊子は「日本の科学研究は失速か」という問題を提起した。日本の研究論文数が世界で相対的に減少している。特に物理、生物学、免疫学、コンピュータ科学で、いずれもこれから最重要視される領域である。日本政府の科学への資金が停滞し、各大学は研究者の雇用を短期契約に舵を切らざるを得なくなったなど、要するに研究費がないのがその理由ではとのこと。
表1は日本の大学のライセンス収入トップ5を示す。表2の米国に比べて日本は2桁少ない。日本の全大学の合計額も米国のそれより2桁少ない。いったいこれは何だ。
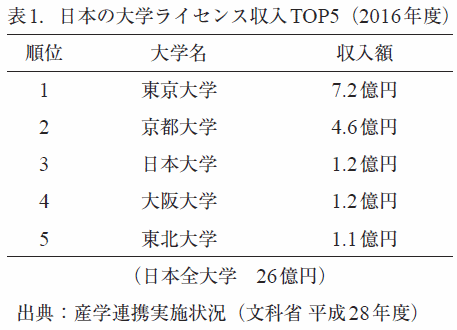
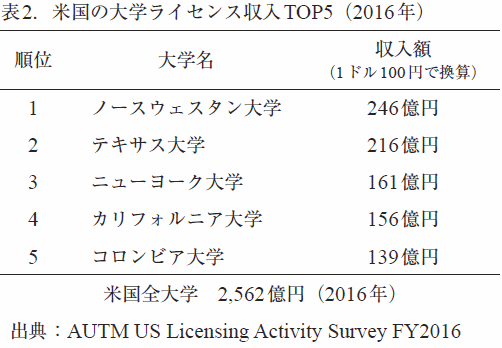
2017年8月のネイチャー・インデックスがイノベーション・ランキング・トップ200を示した。トップ30までが米国の大学。31位に初めて日本の大阪大学が登場。日本の2位が理研、ランキングにして39位。日本の3位が京大、ランキングにして53位。特許に引用された研究論文の引用回数から研究論文を評価したとのこと。
表3は米国の大学の特許出願件数トップ10を示す。そこに示すノーベル賞受賞者数と高い相関を示し、同時にライセンス収入とも相関している。この出願件数トップ6位までの大学にノーベル賞が集中し、ライセンス収入も多額、しかも上記イノベーション・ランキング上位30内にすべて入っている。
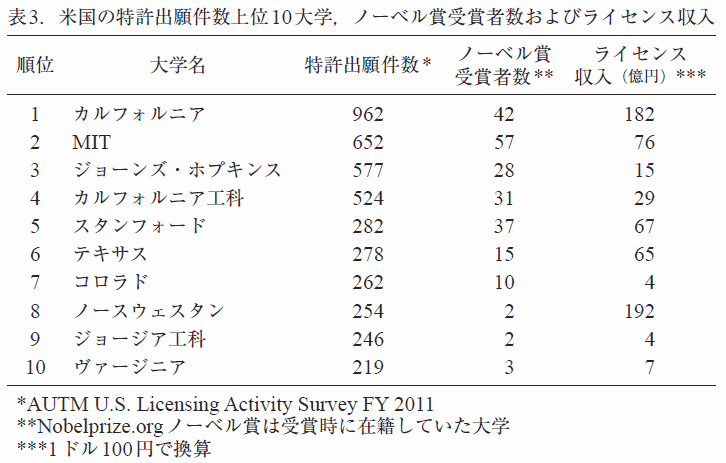
つまり、イノベーションの観点から高いランクに評価される研究論文の出る大学にノーベル賞が集中し、特許出願が多くライセンス収入も多額ということである。
この事実は、これら大学は、特許などの知財に対する認識が高く、かつ上流側に位置する基礎研究から民間企業に魅力的な下流側の応用研究に至るまで広範にわたって優れた業績を上げているということである。
米国の大学はその存在意義を「社会への還元」と周知していることから、企業への協力という点が重視され、それが同時に研究者の評価の指標となる。研究の方向は必然的に社会に向かう。ゆえに大学発ベンチャーが多く輩出され、多額の投資がそれになされる。投資競争は過熱気味で、投資側は少しでも有利なポジションを占めようと、上流側の基礎研究にも投資対象を広げる。研究者は基礎研究に没頭できるというわけだ。魅力的で優れた研究をする大学には必然的にお金が集まり、大学はそれを独自に運用し、運用益は研究費に使われる。
日本は、研究者が伝統的に下流側に位置する応用研究を嫌う。大学発ベンチャーという発想がそもそもない。ゆえに民間企業には、その研究成果は魅力的でなく興味もない。その結果、企業にも大学にも研究成果に対するお金が入ってこない。大学の存在意義に日米間で差はないはず。学問の府にいつまでもとどまっていては「社会還元」という使命を果たすことは難しい。
「武士は食わねど高楊枝」という古い表現がある。「清貧と体面を重んじるのが武士」という意味である。もはや「武士」を「研究者」と読み代えて納得している時代ではない。研究費を国に頼る時代も終わっている。
自分の研究費は自分で稼ぐべきで、主体的戦略的に研究活動を立案し実行すれば可能なことである。知財の威力、特許の威力をしっかり認識し、生かすことだ。
日本政府は、この度、交付金の一部を成果重視で配分する意向を示した。成果の評価はベンチャー設立や企業との連携とのこと。当然の施策である。大学人は真剣に社会に目を向け、その「知」で研究費を稼ぐことを視野に研究に向うべきで、それが今、社会が大学に求めていることである。それこそが大学が果すべき「社会への還元」の第一歩であり、日本の再生への貢献ということではないだろうか。
著者紹介 山本特許法律事務所 弁理士
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 20 12月 2018
生物工学会誌 第96巻 第12号
倉根 隆一郎
筆者はこれまでに産官学と3つの職場を経験してきました。次世代を担う研究者にエールを込めて3つの キーワードを贈りたいと考えています。①女神様の微笑みを見逃さないように! ②知識、文献などは重要だが、これらを超えた発想と展開力を! ③トータルで考える! これらを頭に入れて諦めずに努力することが読者の方々の将来につながると考えています。
①女神様の微笑みを見逃さないように! 女神様はすべての人々に等しく1~2回は微笑んでくれます。 筆者が伯東(株)野畑靖浩氏との共同研究成果として生物工学技術賞を受賞した微生物の生産する高機能性バイオポリマーは女神様の微笑みの賜物です。バイオポリマーは微生物が菌体外に生産する多糖類で、1gで2Lの水を吸水保持する吸水保水性バイオポリマーです。国内外の多くの有力化粧品メーカーにて乳液やクリームなどに保湿剤として広く使用されています。粗精物に水溶液を加えたところ、溶けずに吸水し始めた時に、突如、かわいい赤ちゃんが紙オムツをはいて歩き出した姿が目の前に現われました。きっと女神様に微笑んでいただいたと確信しています。
②知識、文献などの枠を超えた発想と展開力を! この事例の代表例はノーベル賞に輝いた山中伸弥教授です。筆者のつたない2事例を記します。
(1)有害な有機塩素化合物TCE(テトラクロロエチレン)の塩素呼吸細菌によるバイオレメディエーション。従来の知見では完全嫌気性塩素呼吸細菌を用いて一つずつ脱塩素して最終的にエチレンにするものですが、分解途中産物にTCEより強い発がん性があり、脱塩素スピードが遅く年単位を要します。テーマ設定にあたり、TCEより一つ塩素が嫌気的にはずれたトリクロロエチレンで止まり、かつ、ある程度の酸素耐性を有する塩素呼吸細菌を探し、その後は好気的処理法などにより処理することを考えました。1か月後には目的塩素呼吸細菌が世界で初めて見つかり、能力は年単位から3日に大幅にスピードアップし、リスクのない脱塩素工程が完成しました。これにより、経済的に優れかつリスク管理型となり、我が国のバイオレメディエーション指針の大臣認定第1号となりました。
(2)医療現場での抗生物質耐性腸内細菌の感染拡大を防止。伊勢志摩サミットでオバマ大統領から、抗生物質耐性菌の拡大に手をこまねいていると、人類はやがては中世時代の医療環境に戻る恐れがあるので、第4世代の抗生物質の開発とともに耐性菌の拡大防止策を各国協議すべきとの提案がありました。この事案はサミット宣言に書き込まれ、日本でもアクションプランになりました。筆者は愛知県衛生研究所の鈴木匡弘先生、山田和弘先生とサミット前より共同研究を開始しており、従来法では遺伝子タイピングの検出に約1週間必要であったのに対し、同精度で、わずか4時間で遺伝子タイピングが可能な新規検出法を開発しました。サミット後1か月には関東化学(株)よりキットとして販売されるに至り、全国の医療現場で抗生物質耐性菌の感染拡大防止に役立っています。
③トータルで考える! 生物工学分野では木質・草本系バイオマス利用がエネルギー課題です。糖化およびエタノール生産工程は各々優れた多くの研究報文があります。しかし、現行の脱リグニン工程は酸などによる物理化学的処理によりなされ、結果として生じる廃液(黒液)処理に必要なエネルギーは、エタノール として得られるエネルギーの数倍以上必要と報告されています。私共の研究室では新規取得した糸状菌などにより、短時間での直接、脱リグニン・糖化を可能とし、まだ実用化には至っていませんが、稲ワラなどよりビール程度のエタノール生産に至っています。研究課題の産業への展開を図る時などに何らかのトータル の指標(例、エネルギー)を入れると独自性のあるテーマにつながると考えられます。
筆者のこれまでの狭くつたない経験からですが、何らかの参考にしていただければ幸いと存じ、次世代を担う方々にエールを込めて3つのキーワードを贈ります。
著者紹介 中部大学客員教授
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 26 11月 2018
記事種別
Published by 学会事務局 on 22 11月 2018
生物工学会誌 第96巻 第11号
堀内 淳一
本学会の会員には、大学教員はもちろんのこと、民間企業の研究者も多く含まれている。筆者は大学院の修士課程を修了後、民間企業に約15年勤務し、その後大学に転じ約20年勤務してきた。ここでは、これらの経験をもとに、企業研究者と大学教員について思いつくままに比較し、読者の参考に供したい。
本学会会員の仕事は主に研究である。問題を解決するために文献を調べ、仮定を立て実験を行う研究の進め方そのものに、企業と大学で違いがあるとは思えない。しかしながら、研究の動機には大きな違いがある。企業における研究活動は、経営目標を達成するための手段の一つである。したがって、研究テーマは企業戦略の中で重要な、優先度の高い課題が選択され、そこに研究者の趣味が入る余地はない。一方、大学教員の研究の原動力は、特定の領域に関する強固な知的関心であり、本質を明らかにしたいという個人的欲求である。解くべき問題は、企業研究者の場合は社会やマーケットにあり、大学教員ではその人の心の中にある、と言っていいかもしれない。
研究成果は、企業では商品やサービスとして社会や消費者に提供される。研究成果が目に見える形で世の中に出ていく醍醐味は、企業研究者の特権だろう。大学では、研究はオリジナリティにより評価され、論文数が重要になる。大学で継続的に論文を出し続けるためには、研究に対するモチベーションに加え、強いメンタルが求められる。以前に比べ、大学教員の論文数は大幅に増加しており、ポストの減少と相まって企業研究者の大学への異動が難しい時代である。企業における研究は組織的に行われ、大学での研究は個人的に進められる。企業では、あるテーマを誰が担当するかは会社の都合で決まり、チームで研究が行われ、多少休んでも研究は支障なく進んでいく。大学の研究は個人の意思と責任に基づいて行われ、本人が休むと進捗は直ちにゼロになる。組織人として歩んできた企業研究者が大学に異動することは、大企業のサラリーマンが自営業者になるのに似ており、それなりの覚悟が必要である。
大学教員の重要な仕事に講義や研究指導などの教育がある。実は企業研究者は、仕事として教育を考える機会は余りない。筆者も大学に転じた時、若い学生たちに何をどのように教えていくべきかについて、深く考えたことがなかったことに気づかされた。会社にいた時のペースで学生に厳しく接し、見兼ねた上司の教授から「先生、教育は忍耐ですよ。」と諭され未熟を恥じたものである。せっかちな企業出身者には、誘導期にある学生の成長を辛抱強く見守ることが難しかったのである。実際、日々学生から教えられることも大変多く、その成長を身近に見ることは、大学教員でなければ得られない貴重な機会であろう。
企業研究者のキャリア形成には難しい面がある。企業のキャリア育成システムは、研修や海外勤務、ローテーションなどにより、バランス感覚や広い視野を持った経営中枢を担う人材の育成を目的としていることが多い。残念ながら研究をいくら一生懸命やっても大組織の運営能力は身につかない。このため企業研究者は一定の年齢で、このままスペシャリストとして進むか、マネジメントに進むかを決断する必要がある。筆者は結果的にこのタイミングで大学に異動したことになる。一方大学では、指導教員の下、専門分野を深く極める教育が行われるが、かなり若い段階で人材を絞り込み、その将来性を見極めねばならない点が大変難しい。テニュアのポジションが得られれば一般に定年まで研究を継続する環境が保証される。
最後にお金の話をするが、国立大学法人では、教員一人に配分される研究予算は旅費込みで概ね年100万円以下である。学生の人件費がタダであることを考慮しても、企業で使える研究費の1/10以下と考えてよい。このため研究室の維持に外部資金の導入は欠かせない。ちなみに筆者の場合、30代後半で民間企業から大学に移った際、年収で約2割減少した。大学教員は蓄財には向かない職業である。
著者紹介 京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 24 10月 2018
生物工学会誌 第96巻 第10号
中山 亨
最近、イタリアのカターニア大学のプルチーノらによる「才能か運か」と題する興味深いアーカイブ(arXiv)論文1)が出版された。世の中の富の分布には「パレートの80:20の法則」というものがあり、富の8割は人口のわずか2割で所有されるという。世界でもっとも富める8人の財産の合計は、世界の貧困層36億人の財産の合計に等しいという計算もある。このように、世の中の富の配分は「べき乗則」に従う不均衡なものだという。
IQなどの人の能力は統計的にガウス分布を示すのに、富の配分はなぜそうならずに「べき乗則」に従うのか?プルチーノらはコンピュータモデルを用いてその理由を解析した。その結果、成功と才能との間には必ずしも相関がなく、富の不均衡な配分を生んでいる要因は、ひとえに「運」であることが示された。彼らの結論は、富める人々は幸運に恵まれた人々でもあり、貧しい人々は運に恵まれなかった人々であるというものだった。
この論文が特に興味深いのは、研究費の配分にかかわるこの種の問題の解析にも取り組んでいることである。科学的発見に関わるさまざまな逸話が示しているように、科学的発見に「運」が果たす役割は大きく、これをセレンディピティという。プルチーノらは、いくつかの研究費配分モデルを設定し、セレンディピティを考慮した場合にどのモデルが最大の効果を生み出すかを調べた。設定したモデルは、「すべての科学者に均等に研究費を配分する」、逆に、極端な配分格差をつけて「過去に高い業績を上げているごく一部のエリート科学者のみに配分する」、および、それらの中間の配分方法からなる19パターンであった。シミュレーションの結果、最大の効果を与えたのは「すべての科学者に均等に研究費を配分する」であった。
翻って、わが国の大学への研究費の配分はどのようになっているのだろうか?この点に関しては、日本学術振興会学術システム研究センターの黒木登志夫顧問による興味深い分析結果がある2)。それによれば、研究費配分には大学間格差があり、これも「べき乗則」に従うという。すなわち、大学への研究費配分額(教員あたり)の対数を、配分額に基づく大学ランキングの順位の対数に対してプロットすると、右下がりの直線関係が成立する。この負の傾きが大きいほど大学間格差が大きいことを意味する。
この「べき乗則」はわが国のみならず、英米独の3か国についても成立する。重要なことは、この「べき乗則」の成立においては研究費配分に関するその国の施策の特徴が明確に反映されていることである2)。日本も含めた4か国間の比較では、この負の傾きはわが国がもっとも大きく(–0.92)、次いで、英国(–0.64)、米国(–0.27)、ドイツ(–0.25)の順である。すなわち、わが国の研究費の配分のされかたは4か国の中ではもっとも不均衡で格差が大きい。一方、ドイツでは上述のプルチーノらの結論にもっとも近い、格差の小さいやり方で研究費が配分されていることになる。わが国の科学研究が低迷し、世界におけるその相対的地位を下げつつあるなかで、近年ドイツの科学研究が存在感を増しているという最近の新聞報道3)は、プルチーノらの結論に照らして納得がいく。
ルイ・パスツールは、「幸運は準備された心のみに宿る」と述べた。「準備された心」はたゆみない研究によって培われるのだから、そのための基礎体力となる研究費くらいは皆になるべく均等に配分した方が全体的にはより多くの幸運の女神が微笑むことになるのだ……プルチーノらの結果はそのようなことを意味するように思われる。国立大学の場合、1990年代までは積算校費がそうした財源の一部として機能していたと思われるが、積算校費に代わる現在の運営費交付金はそのような状況にはない。国レベルで見た場合、研究費の極端な配分格差は研究や研究者の多様性を失わせるとともに、科学の発展に不可欠な研究者層の厚みも失わせる。わが国の科学研究の力量を高めるための方策を考えるうえで、プルチーノらの論文の結果は示唆に富んでいる。
1) Pluchino, A. et al.: arXiv:1802.07068v2 (2018).
2) 黒木登志夫:IDE 現代の高等教育, 589, 17 (2017).
3) 朝日新聞 2018年3月1日付.
著者紹介 東北大学大学院工学研究科(教授)、日本学術振興会学術システム研究センター(専門研究員)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 9月 2018
生物工学会誌 第96巻 第9号
朴 龍洙
私は、二つの国で生物工学を学び、この分野の位置付けについて非常に悩んだ覚えがある。韓国で修士課程の時、米国MITから赴任されたDewey Y. Ryu教授の下で発酵工学を学んだ。1980年代の韓国では、この分野は最先端であり、新鮮さとおもしろさに魅了され、私は一生この分野に身を投じる決心をした。その後4年間、学んだことをもとに韓国最大の発酵企業で、核酸発酵、発酵工場の建設、試運転まで携わり、発酵工学の随を経験した。日本に渡り、東京大学応用微生物学研究所の戸田清先生と名古屋大学工学部の小林猛先生の両恩師の下で生物工学分野のイロハを学んだ。その後、静岡大学の岡部満康先生の研究室(当時の培養工学)に移り、より実践的な生物工学を学んだ。
学問として生物工学はどのようなものなのか。修士課程では発酵が至極の学問だと思ったが、その後、高密度細胞培養、遺伝子産物の効率的生産および放線菌による抗生物質の生産を研究課題にして取り組んでいるうちに、私は、生物工学は時の流れに密に関わりながら変化し続けるものだと理解するようになった。醸造学から始まった生物工学は、発酵工学、生物化学工学、生体情報工学、環境工学、酵素工学、動物細胞工学および生体医用工学分野に至る広範囲をカバーしている。
私は、この広範囲な分野でどのような研究をすればよいか相当悩んだ。しかし今振り返ってみると、対象は変わったが、自分が物質の生産性向上を常に追い求めてきたことに気がついた。細胞の密度を高めて培養する「高密度培養」のコンセプトで、遺伝子操作が可能で、かつ自由に飼育できる生物としてカイコに辿り着き、蚕糸学会の主役であるカイコを生物工学会に持ち込んだ。カイコは、溶存酸素もpHの制御も要らない、きわめて高い高密度培養が可能であり、スケールアップの心配も不要なため、生体バイオファクトリーに適していると確信している。発酵工学に魅了され、最後にはカイコバイオファクトリーをライフワークとして挑戦するとはまったく想像もしなかった。
時の中で生物工学の目指すものは何か。時代の変化に伴い姿は変わっていくものであるが、人類のために何をすべきかは不変の課題である。地球規模で進んでいる温暖化、そして、日本社会の異常なほど急速に進む高齢化・少子化は人類が経験したことのない最大の危機であり、知恵を絞って対応していかなければならない。私が所属している静岡大学では、このような問題の解決のためにグリーン科学技術研究所を2013年に設立し、あらゆる分野の研究者を集めて未来課題の解決に向けて研究を進めている。生物工学は、微生物、動物および植物を対象に、さらに物事をシステム的に考える工学的思考の上に成り立っているので、21世紀の諸問題の解決に貢献できる絶好の機会と考える。第5期科学技術基本計画(平成28~32年度)の経済・社会的な課題への対応として、
(1)持続的な成長と地域社会の自律的な発展、
(2)国民の安全・安心の確保と豊かで質の高い生活の実現、
(3)地球規模課題への対応と世界の発展への貢献、
があげられている。特に、(1)では資源の安定的な確保と循環的な利用、超高齢化・人口減少社会などに対応する持続可能な社会の実現、(2)では食品安全と生活環境安全の確保、(3)では地球規模の気候変動に対応した温室効果ガスの大幅削減などが、重要課題として設定されている。
このような課題は、まさに、生物工学者が大いに貢献できる分野である。このような地球規模の課題は、日本の国内学会だけでは解決が不可能である。そのためには、国際的な会合の場を増やし、高いポテンシャルを有する海外の学会と学会間のネットワークを構築することが求められている。国際共同研究プロジェクトへ参加すると同時に、優れた外国人研究者が本学会に入って活躍できるようになれば、本学会のポテンシャルをより一層強化することになる。これによって、国ごとの地域特性を活かし多様な視点や発想に基づく解決策を共有できる仕組みが本学会を中心にできあがるのではないだろうか。
学会として、21世紀の重要課題の解決に向けたロードマップを策定し、国の政策決定に提言できるように、また生物工学会は、これから学会を担っていく多くの若手研究者がこのような課題に果敢に挑戦していく場であることを願っている。
著者紹介 静岡大学グリーン科学技術研究所(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 23 8月 2018
生物工学会誌 第96巻 第8号
養王田 正文
研究者としてSurvivalするには、Impact Factorの高いJournalに論文を発表し、Citation数の多い論文を出すことが求められている。渾身の研究成果をまとめてNatureなどに投稿しても、数日も経ないでEditorによりRejectされた経験をお持ちの方も多いだろう。NatureなどのEditorも雇われの身であり、JournalのImpact Factorを上げることで評価されている。その結果、Citationが多くなることが期待される論文を選別することになる。Citationが高いということは、内容が読者にとって面白いだけでなく、そのテーマに関わる研究者が多いことを意味している。必然的に、流行のテーマに関わる論文を選別することになる。
私は学部学生の時、学生実験が大嫌いだった。学科の学生全員が、一斉に結果の分かっている実験を行うことに意義を感じることができなかった。同じ課題で考察することなど、バカバカしくやる気にならなかった。学生実験に関してまったくダメな学生だった私が変わったのは、4年生の卒業研究からである。自分だけのテーマを自分独自の考え方で研究することに醍醐味を感じ、研究者の道を進むことになった。学生時代に指導していただいた西村肇先生が『冒険する頭―新しい科学の世界』1)という本の冒頭で以下のようなことを書かれている。
“研究というのは、どんな場合も、今まで人のやらなかったことをやることですから、研究をやるにはまず、人の前にでなければなりません。ハイウェイのように、みんなが走っている時はたいへんです。自分はもっとはやく走って列の先頭にでなければなりません。”
なぜか大学院でタンパク質の研究を志すことになった私が、テーマとして選んだのはF1-ATPaseだった。生化学研究の素人である私がどうせ後から追いかけるなら、当時もっとも重要で複雑なタンパク質の一つと考えられていたF1-ATPaseを研究するのが良いと考えたからである。F1-ATPaseの反応機構の解明にはX線結晶構造の解明が不可欠だったが、当時の技術では不可能であると考えられていた。そこで私は、各サブユニットを単独で解析して全体の構造を再構成するというアプローチを取ることにした。その実現のために、博士課程で好熱性F1-ATPaseのサブユニットの大腸菌発現系と再構成系を構築した。そのままF1-ATPaseの研究を続けるという道もあったが、指導していただいた吉田賢右先生らが私のアイデアで研究を行ってくれることになったので、独自のテーマを求めて企業に就職した。ご存知のように、後にJ. Walkerらが牛心筋ミトコンドリア由来F1-ATPaseの結晶構造解析に成功し、さらに吉田先生たちがF1-ATPaseが回転することを示し、J. Walkerと回転のモデルを最初に提唱したP. Boyerがノーベル化学賞を受賞した。私が意図した方向ではなかったが、F1-ATPaseの反応機構解明に貢献することができたのは私の誇りである。
企業から理化学研究所を経て、現在の東京農工大学までさまざまな研究を行っているが、研究に対する考えは変わっていない。流行のテーマで多くの研究者と同じ方向で研究を行えば、Citationの高い論文を出せることは分かっているが、どうしてもMotivationが上がらない。他の人が研究するなら、自分がその研究をする必要はないと思うからである。さらに、多くの研究者と競争して先んじて独創的な研究をすることは、ほとんど不可能である。あえて、ハイウェイを降りて、他の研究者が走らない独自のルートを探して進む独走的研究を考えながら研究を行って来ている。論文を出すときは苦労し、期待した程Citationが上がらないことも多いが、自分が満足のできる研究を進めることができている。さて、西村先生の本当に言いたかったことは先の引用の後にある。字数の関係で少し修正して紹介する。
“ハイウェイで追いつくには、ブロイラーのようになんでもすばやく吸収してしまえば良いです。しかし、本当の研究をするには、みんなが走りたがるハイウェイを降りて、まだ人が通ったことのない大地を歩く野生のにわとりになる必要があります。”
ハイウェイでは決まった方向にしか進むことができない。野生のニワトリのように自由に走り回る独走的な研究こそ科学技術の進歩につながると信じている。
1) 西村 肇:冒険する頭―新しい科学の世界、筑摩書房 (1983).
著者紹介 東京農工大学(教授
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 7月 2018
生物工学会誌 第96巻 第7号
伊藤 伸哉
SGUは、文部科学省のスーパーグローバル大学(SGU)創成支援事業の略号で、現在、最長10年間の長期プロジェクトの中間審査時期を迎えています。この事業に参画している大学(タイプA 13校、タイプB24校)に所属する先生方は、英語での授業、留学生の勧誘、学生の留学サポート・英語力アップなど、さまざまな負担を感じておられると思います。私の専門は、生体触媒化学やバイオプロセスですから、こうした専門分野の研究費や事業の評価委員を担当することが度々ありますが、ひょんなことからこのSGU事業の審査部会委員を、以前の大学の世界展開力強化事業から務めています。自分でもこの役は適任かどうか少々疑問ですが、おそらく国公私大・公的機関・民間、地域、理系・文系のバランスの関係から選ばれたのだと思います。もちろん、SGU事業には批判もあります。私自身、採択時、これほどまでに細かい数値目標を採点化する必要があるのか、文部科学省の誘導が強すぎるのではないかと疑問を持ったことも事実です。また、世界大学ランキングは英米が外貨獲得の手段として利用しており、画一的な和製グローバル化では通用しないという論評もあります1)。ちなみに、本来のグローバル人材は、国境を越えて高等教育を受け学位を取得した人々が、出身国に関わらず国際労働市場で活躍する、こうした高度人材を指します。共通言語は英語です。
一方、最近の日本においては、若者人口の著しい減少、特に18才人口の減少が2018年問題として大学人には強く意識されています。若者の減少が、大学の統合や淘汰を推し進めるのは仕方なく、淘汰されないまでも学生の質低下や経営悪化など大学に与える影響は甚大です。しかし、最近のニュースでは、東京のある区の成人式では、20%近くが外国人で占められていたなど、東京圏を中心に非常に多くの外国人留学生が見受けられます。日本に住む外国人は、直近の2017年6月時点で247万人と過去最高であり、正社員やアルバイトなどの形で働いている外国人就労者も108万人に上っています。移民受け入れの是非はともかく、今や日本社会がこうした労働力を必要としているのは明らかです。この内、留学生は2017年にこれも過去最多の26万7000人(内訳:中国 10.72、ベトナム 6.17、ネパール 2.15、韓国 1.57、台湾 0.89、スリランカ 0.66万人)に上っています。この波はゆっくりですが、いずれ地方にも訪れるはずです。
したがって、これからの大学・企業や学会には、日本人の若者の減少を外国人の高度人材で補う(取り込む)努力が、求められるのではないでしょうか。そのために成すべきことは、まず留学生を増やすことですが、これは順調に増えています。また内向きと言われていた日本人留学生数も短期留学が多いのですが増加に転じています。こうした数値の変化は、前述のSGU事業などの後押しによるものであることは明らかです。次に、留学生に質の良い効率的な日本語教育を提供することが大切です(日本語のアドバンテッジを与える)。また、多くの日本人がコミュニケーション手段としての「英語の壁」を完全に払しょくすることはできないまでも、この壁を低くする努力を、個々のレベルも含めてこれからも続けて行くべきです。
昨年の早稲田大での大会のポスター発表でのエピソードですが、観客のほとんどいない外国人留学生に話しかけたところ、実に流ちょうな英語で熱心に答えてくれたのが私には強く印象に残っています。彼らのためにも、大学での英語による教育プログラムやコースの提供はやはり必要だと思われます。また、学会での英語のシンポジウムや情報の提供も引き続き実施・強化して行くべきだと思います。10年後の大学や学会の姿は、グローバル化の流れによって今とは相当変わっているのではないか、もしくは変わらざるを得ないのではないでしょうか。
1) 刈谷剛彦:オックスフォードからの警鐘 グローバル化時代の大学論、中公新書ラクレ (2017).
著者紹介 富山県立大学工学部(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 6月 2018
生物工学会誌 第96巻 第6号
稲垣 賢二
『生物工学会誌』(和文誌)を毎号楽しく読ませていただいています。歴代の編集委員長、編集委員の皆様のご尽力に心から敬意を表したいと思います。各号の「特集」はとても面白く、「バイオよもやま話」は為になる話も多いし、「バイオミディア」も興味深い、本当に読みやすく学会員の為になる和文誌です。バイオサイエンス系のいくつかの学会で理事などを務めた経験から、会員への和文誌の無料配布が「学会本部、支部と会員との橋渡し役」として、きわめて重要であると痛感しています。
現在、さまざまな事情により、学会誌の無料配布の停止や、オンラインジャーナル化がトレンドとなっていますが、以前からこれは考えものだと思っています。一例として、日本農芸化学会では、以前『日本農芸化学会誌』と言う名称の学会誌(1924–2004)と現在も継続発行されている『化学と生物』(1962年発刊)という一般啓蒙雑誌の2種類を刊行していました。『日本農芸化学会誌』は会員に無料配布され、『化学と生物』誌は希望者のみ有料配布でした。学会として2種類の毎月発行が負担となり、2誌を統合し、どちらかの刊行をやめる決断が迫られました。評議員会でその話が出たときに、個人的には『日本農芸化学会誌』を残して欲しいと思いましたが、理事会での議論の結果、統合誌として『化学と生物』という名称が残されました。さらに経費削減のため、オンラインジャーナル化(2015年2月から)と会告欄の廃止が決まりました。
またほぼ同じ時期に、日本生化学会でも学会誌『生化学』のオンラインジャーナル化に伴い、会員への無料配布が中止され、会告欄は廃止されました。現在、『生化学』誌の冊子体は、希望者への有料配布となっています。こうした状況を経て現在冊子体として発行されている日本農芸化学会の『化学と生物』誌、日本生化学会の『生化学』誌ともに会告欄はありません。つまり、学会本部から会員への案内はホームページや電子メールが中心で、和文誌にはほとんど掲載されていません。一方、『生物工学会誌』には年次大会やSBJシンポジウムの案内はもちろん、7つある支部からの行事情報も頻繁に掲載されており、学会を大変身近に感じますし、他支部主催の行事に参加するきっかけともなっています。さらに学生の教育にもなるので、是非無料配布をこの先も続けて欲しいと思います。
さて、ここで現在の『生物工学会誌』の素敵なところを見てみてみたいと思います。まず、「カレンダー」を見れば当面の学会、支部の行事が一目で分かりとても便利です。そしてこの「随縁随意」、学会に長く関わってこられた先輩諸氏のさまざまなご意見は、若い会員の傾聴に値すると思います。そして多くの号で「特集」が組まれ、最近の研究動向を知ることができます。
続いて「続・生物工学基礎講座―バイオよもやま話―」、この実験に関わる基礎講座は、本当に研究者や院生学生の為になります。前身の「生物工学基礎講座―バイオよもやま話―」は、学会創立90周年記念事業の一環で書籍化され『生物工学よもやま話―実験の基礎原理から応用まで―』として市販されていますし、学会のホームページ上でも2011年89巻4号–2013年91巻3号分がPDFとして公開されています。日本のバイオテクノロジー技術、研究の進展や一般市民への知識の普及に大きく貢献していると思います。
「バイオミディア」は、さまざまな研究トピックをミニレビュー風にまとめてあり、こちらも参考になります。「バイオ系のキャリアデザイン」は、OG、OBが歩んできた道を振り返るコーナーで、若い読者すなわち院生、学部生のキャリア選択の参考になるので、是非とも読んでいただきたい。各支部回り持ちで担当する「Branch Spirit」、会告欄に相当する「本部だより」等々、こうしてみるとさまざまな企画があり、読み応えもあります。編集委員に積極的に若手、女性や企業会員を登用してきた成果も現れているように思います。
実は小職、昨秋から日本生化学会の編集担当常務理事に就任したので『生化学』誌を担当する立場となりました。『生物工学会誌』の優れた取組みにも学んで、会員の為になる和文誌になるよう努力したいと思います。最後に『生物工学会誌』の益々の発展、充実を祈念して筆を置くことにします。
著者紹介 岡山大学大学院環境生命科学研究科(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 5月 2018
生物工学会誌 第96巻 第5号
日野 資弘
巻頭言を書くという大役を仰せつかった。さて何を書こうかと迷った。そこで、なぜ自分は生物工学会員になったのか、会員として得たことは何か、本会の特徴や魅力について改めて考えてみた。
私は、大阪大学の醗酵工学専攻を卒業後、藤沢薬品工業に入社し、醗酵産物から医薬品の種探しを約25年、その後、醗酵産物や動物細胞が生産するタンパク質の工業化を担当した。私は大学院時代の研究を発表するために本会の前身である醗酵工学会に入会した。約40年も前のことである。その間、本学会に参加して得たことは、発表の機会、技術情報の入手、人材交流の場であり、入会して30年が過ぎた頃より人材育成の場にもなった。
近年はバイオ医薬の最盛期であり、さらに再生医療の時代を迎えつつある。創薬技術の多様化から、入会する学会や研究会を決める際には、先端技術分野に特化したものを選ぶ傾向にあるように感じている。それに対して、本学会は、生物を起源とした幅広い有用物質の産業化について、工学的な視点で、基礎、応用を研究開発する研究者の集まりである。所属する研究者は、醸造、バイオマス利用、環境、バイオ医薬、再生医療などを研究開発する産官学の部門出身である。本会の大会はまさに異業種交流会である。ここが専門的な学会や研究会とは大きく異なる点であろう。
近年の学会選択の方向性からすると、扱われるテーマの分野が広範囲なことはメリットと感じられないかもしれない。しかし、個々のテーマを見ると、遺伝子、核酸、タンパク質、糖質、低分子や中分子代謝物などの生物由来の機能性分子が研究対象であり、微生物や動物細胞がその中心にある。さらに、微生物や動物細胞の遺伝子操作技術、培養技術、その生産物の分析技術、生産物の濃縮・分離技術、代謝物や画像の解析技術やシミュレーション技術などが用いられ、各分野において共通性が高い。
私が関わってきた醗酵医薬やバイオ医薬分野の過去の事例をいくつかあげてみよう。いずれの事例も異なる分野で開発された技術が応用されたものであることがわかる。①アミノ酸発酵の育種技術は醗酵医薬品の生産性向上技術に応用された。②今を時めくバイオ医薬の抗体医薬は、主にCHO細胞のFed Batch培養法で製造されるが、微生物で種々の有用物質生産に実績を上げた培養技術である。③計測・解析技術の進展により、高質の培養技術が構築できるようになっている。大会のシンポジウムでも取り上げられているように、代謝物や培養環境を精度よく解析できる計測技術は、食品関連の有用物質、醗酵医薬やバイオ医薬製造プロセス開発に貢献している。
これからの時代を担うと期待される再生医療の製造プロセスでは、バイオ医薬の製造技術、とりわけ培養装置、培地開発、代謝解析技術、ハーベスト技術などが非常に参考になると思われる。
以上のように、生物工学会がカバーする領域の中で構築されてきた種々の技術開発の歴史や最先端情報を学ぶことは、研究遂行において、知識の強化とともに発想転換のよい機会になると思われる。同じ分野で切磋琢磨、試行錯誤している研究者の中で議論するのも有意義だが、まったく異なる分野で同じ技術領域を持った研究者との交流こそが、ブレークスルーに重要だと感じている。
私の研究生活は、微生物産物の探索研究にはじまり、発酵産物・動物細胞由来タンパク質や抗体の工業化研究へと続き、現在は再生医療の世界にいる。振り返ってみると、それぞれの転換点において、新たな分野でやっていけるかという不安もあったが、その世界に入ってみると共通点の多さに気づき、少し異なる視点からものが見えることが強みになったように感じる。
生物工学会が、生物を中心にした生産技術開発の先端情報の交換や議論の場として、また、異業種交流の場としてますます発展することを期待している。
著者紹介 (株)ヘリオス 神戸研究所
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 4月 2018
生物工学会誌 第96巻 第4号
下飯 仁
『生物工学会誌』の前身である『醸造學雜誌』が大阪醸造学会から創刊されたのは大正12年(1923年)である。大学図書館に創刊号があったので目次を見てみると、ほとんどが清酒(日本酒)に関する記事である。生物工学会はバイオテクノロジーの学会であるが、その中でも清酒醸造学はもっとも歴史のあるオールドバイオの一つであることは間違いないであろう。昔の酒がどんな味がしたのかを現物で確認することはできないが、明治初期の清酒の分析値をみると、非常に辛口で酸味も強く、まさに「鬼殺し」の味であったようだ。
明治以降の日本の近代化に伴い、清酒醸造にもさまざまな技術的進歩がなされて、現在の芳醇な清酒がつくり出されてきたのである。主な技術だけでも、高度精白米の利用、培養酵母の利用と酒母製造の合理化、主要な工程の機械化などがある。筆者が醸造学研究の道に進んだころ、ある先輩から「清酒醸造の歴史は、なりふりかまわぬ技術革新の歴史なのだ」と教えられたことがある。清酒醸造は日本の誇る伝統技術だが、一方で、その時々の最新の技術を積極的に取り入れてきたのである。
筆者の専門である清酒酵母にしても、変異株である泡なし酵母が実用化されたのは1970年であり、すでに50年近い歴史がある。清酒酵母はもろみで高い泡をつくる性質があるが、この高泡は発酵の指標となる一方で、もろみタンクの利用効率を悪くする。国税庁醸造試験所の大内らは、高泡をつくる優良清酒酵母から高泡をつくらない泡なし変異株を巧妙な手法で分離し、泡なし変異株を使用しても、できたお酒の品質には影響を与えないことを示した。その後、多くの泡なし変異株が優良清酒酵母菌株から分離され、広く使用されるにいたっている。アミノ酸の代謝制御発酵における変異株の使用には遅れるものの、醸造の分野にこれほど古くから変異株の利用がなされていたことは驚くべきことである。
また、生成酒の品質を向上させる変異株も多数取得されており、たとえば月桂冠株式会社による香気成分高生産変異株の育種は吟醸酒の品質を大きく向上させた。最近では、清酒の貯蔵にともなう劣化臭を出さないような菌株の育種も進められており、今後、清酒の品質保持に大きな貢献をすることが期待されている。
清酒発酵の特徴の一つは醸造酒の中でもっとも高濃度のエタノールを生産することであるが、清酒醸造における高濃度エタノール生産のメカニズムについては、いくつかの原因が考えられている。まず、清酒の発酵は麹菌によるデンプンの糖化と清酒酵母によるエタノール発酵が同時に進行する並行複発酵である。並行複発酵ではグルコースが蓄積しないので高濃度の仕込が可能となる。また、麹菌は糖化酵素以外にもさまざまな栄養素を生産することで酵母の増殖を助けている。さらに、清酒酵母自体も他の菌株に比べて高濃度のエタノールを生産することが知られている。清酒酵母の高い発酵力については、長い間、清酒酵母がエタノールなどのストレスに強いことが原因であると考えられてきた。しかし、筆者らは、清酒酵母は他の酵母に比べてむしろエタノールなどのストレスに弱いことを明らかにした。酵母が発酵で生産するエタノールは酵母自身にとっても増殖阻害物質であり、通常の酵母はストレス応答を引き起こしてエタノール発酵を停止する。しかし、現在使用されている清酒酵母はストレス伝達経路の遺伝子に多数の変異が入っており、エタノール濃度が高くなっても発酵を停止せず、結果的に高濃度のエタノールを作り出す。ストレス応答がむしろエタノール発酵を阻害することは大変興味深い。
ゲノム解析に基づいた最近の系統学的研究によると、清酒酵母はワイン酵母など他の系統の酵母から独立した「純系」であるとのことである。清酒酵母は日本という地理的に隔離された環境の中で進化してきたと考えられる。最近、自然界から分離した酵母を使用する試みが盛んであるが、それらの天然酵母は清酒酵母のような高い発酵力を持たない場合も多い。清酒酵母と同様に、ストレスに弱いが発酵力の強い酵母が元来自然界に存在していたのか、酒類製造という人間の営みがあって生まれてきた酵母なのか、興味は尽きない。
著者紹介 岩手大学農学部(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 26 3月 2018
生物工学会誌 第96巻 第3号
谷口 正之
学生や助教などの若手の時代には、指導教員や上司から研究テーマをいただくことが多いが、新しい一つの研究室や分野を担当することになると、新規性、将来性、革新性、波及性などがある研究テーマを自ら設定することが必須になる。若手の時代にやってきた研究を継続して発展させることは一つの方法であり、その分野をリードできる可能性が高いかもしれない。筆者も2人の恩師からいただいた研究テーマである「セルロース系バイオマス資源の有効利用」や「膜分離型バイオリアクターを用いた有用物質生産」に関連する研究を20年以上継続してきた。この間、「学位を取った後は、論文が先生だよ」「生産方法の研究であれば、おもしろい物質の生産を研究対象にしなさい」などのアドバイスを念頭に、その時々の教育研究環境を考慮して、どのような研究テーマを設定するかを常に考えてきた。
学会には、自身の発表以外に、新しい研究テーマの設定のヒントになる情報を収集するなどの目的を持って参加した。特に本学会では、数多くのヒントをいただき、また、多くの学会会員の方々と出会い、情報交換させていただいた。さらに、いただいたヒントなどをもとに新しいテーマの研究を開始する時には、厚顔も顧みず、研究材料の無償提供や新しい装置の借用などをお願いし、多くの学会会員の方々から多大なご支援をいただいた。もちろん、流動層型固体培養装置の開発など、多くの挫折や失敗もあったが、これらの支援のおかげで研究を継続してなんとか展開してきた。
研究室を主宰してしばらくは、研究テーマ間の相乗効果を期待して、またリスク分散のために、三つ程度の大テーマについて研究を同時に進めた。また、約15年前には新潟県内の企業や公設試を含めた「食品タンパク質の構造と機能」や「バクテリオシンによる清酒の火落ち防止」に関する共同研究なども開始した。その後、脱脂コメ糠や飼料用多収米を原料としたエタノールや乳酸の生産性を、稲わらなどのセルロース系バイオマスを原料とした場合と比較し、考察した。結局、セルロース系バイオマスを糖質などに変換する研究は中止することを決断した。さらに上記の共同研究を進める中で、「歯周病菌プロテアーゼを阻害するコメタンパク質由来ペプチドが抗菌活性を発揮する」という偶然の発見が、新しい研究テーマを立ち上げる契機になった。
約8年前からは、一つの大テーマ「食品タンパク質由来ペプチドの構造と機能」に集中して研究を進めている。この新テーマの研究の初期段階では、主に大学院生を所属大学内の他の研究室はもちろんのこと、他の大学(東京歯科大学、北陸先端科学技術大学院大学、京都大学など)や研究機関(国立医薬品食品衛生研究所など)に派遣して多くの実験手法を習得してもらい、研究の質のレベルアップに努めた。現在は、抗菌作用に加えて、ペプチドの抗炎症や創傷治癒などの機能に関する研究へと展開し、研究対象もタンパク質のアミノ酸配列に基づいて化学合成したペプチドから、食品タンパク質酵素加水分解物や発酵食品中の天然型ペプチドへと拡大し、三つ程度の中テーマを設けて研究を進めている。
研究テーマの設定は、研究者の存亡を左右する重要課題である。若手研究者がポジションを得た後は、いつもヒト、モノ、カネ、スペースなどの教育研究環境を熟慮して、これまでにやってきた研究を継続して発展させるか、その継続研究に関連する新しい研究テーマを立ち上げるか、まったく新しいテーマの研究を開拓するか、それらを決断するのは研究者の実力であるが、正解がない永遠の課題かもしれない。特に、重要なのは、やはり共同研究者、研究協力者、学生などのヒトであり、先輩・後輩はもちろんのこと、学会などでの新しい出会いを大切にし、活用してほしい。友達の友達も頼りにしたらよいと思う。以上、若手研究者が研究テーマを設定するときに、何かの参考になれば幸いである。
著者紹介 新潟大学自然科学系(工学部)(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 26 2月 2018
生物工学会誌 第96巻 第2号
辻 明彦
近年、大学からの校費は減少し、外部資金を獲得しないと十分な研究費を得ることはできなくなりました。申請書が採択されるためには、時代のトレンドに合致した研究、10年先の成果が見通せる研究、社会貢献、社会実装が期待される研究として上手にまとめる作文技術が必要で、社会ニーズに対応した最新技術を活用したスマートな研究計画、関連分野の実績が要求されます。私自身は酵素学が専門ですが、酵素の研究で外部資金を獲得しようとすれば、医学的な分野であれば、酵素の立体構造からの阻害剤の設計と創薬への応用、ノックアウトによる病因解析、生物工学的分野であれば、酵素の大量発現、機能改変、有用物質生産への応用に関する研究計画、そして実績が必要です。しかし、クローニングされたタンパク質が、すべて大量発現が可能ではなく、また大量発現しても、すべて結晶構造解析ができるわけでもありません。若い研究者の方は、高インパクトファクター(IF)の学術誌への論文発表や外部資金獲得状況で人事評価されるために、どうしても成果が確実に期待される研究に集中することになり、日本全体の研究の多様性が失われています。
私は長い間、ズブチリシンと相同性の高い哺乳類のズブチリシン様プロプロテインコンベルターゼの研究を20年ほど行っていました。生理活性ペプチドの前駆体の活性化を行うCa2+依存性セリンプロテアーゼですが、Furin、PC1/3、PC2、PACE4などが知られています。ただでさえ含量の少ない生理活性ペプチドの活性化を行う酵素なので、酵素の含量はさらに少なく、ウエスタンブロットで明快なバンドを出すことも非常に困難な酵素でした。siRNAを使った機能解析や転写調節に関する結果を加えて、なんとか論文を発表していましたが、費用対効果がきわめて悪い研究で、気づくと日本でこれらの酵素を研究しているのは私どものみという状況でした。定年まであと10年という時に、少しは生物工学で役に立ちたいと思い、このプロテアーゼからは撤退し、セルラーゼの研究へ移行しました。ところがこの間に海外では、特にがんとこのプロテアーゼとの関係が明らかになり、さらに近年では診断マーカーや創薬の研究が盛んになり、今では撤退したことを少し後悔しています。生物工学会大会でも酵素研究の発表件数は減少傾向ですが、生化学会や分子生物学会でも激減し、成果が出やすい酵素の研究に集中しています。このままでは、低含量で不安定な酵素を精製できる研究者がいなくなるのではと危惧しています。
大学院時代の恩師から、「泥の中からダイアモンドを探り出し、それを世界初の研究へ発展させなさい」という教えを叩き込まれました。その人しかやっていない研究を推進するには、大きな困難が伴います。しかし、大きな喜びもあります。私は学生時代には山岳部でしたので、研究を登山にたとえて考えますと、泥臭い研究とは初登頂をめざす登山であり、スマートな研究とは初登頂でなくてもより困難なバリエーションルートを登る登山なのではと思います。いくら航空写真があっても、初登頂の場合は、実際登ってみないとわからない地形が多くあり困難が伴うのに対し、バリエーションルートを登る場合は先行チームからのデータを利用できます。
1989年に米国ミシガン大学に留学していたころ、日本はバブル時代で、特にバイオの分野では大学にも多額の研究費が投入されていました。当時の米国の雑誌には、このままでは経済のみならずサイエンスでも米国は日本に追い抜かれると心配する記事もありましたが、逆に多様な基礎研究の分野では圧倒的に米国が優勢であり心配する必要はないという記事も多くあり、米国の優位性をあらためて実感した記憶があります。
研究資金や昇進のため、若い研究者が置かれた現在の状況が非常に厳しいことは十分に承知していますが、どうか初登頂を目指して、誰も手をつけていない領域に踏み出していただきたいと思います。科学や物理に比べれば、生物の領域は、まだまだ小さい研究室でも大発見できる未知の分野があると思います。また年長の研究者は、若い研究者の多様な研究を公平に多角的に評価し、支援するシステムの構築に努力しないといけないと思います。
著者紹介 徳島大学 生物資源産業学部 教授
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 26 1月 2018
生物工学会誌 第96巻 第1号
会長 木野 邦器
新年を迎えて今月号から表紙がリニューアルされた。生物工学が扱う素材や技術をイメージした魅力的なデザインは本学会をわりやすく紹介し、毎号変わるデザインは読者を楽しませてくれるはずである。
昨年も世界的に社会全体が落ち着かない不安定な一年であったように思う。温暖化による異常気象ばかりではなく、政治も社会も経済も地球規模で不確実で不安定な状況にある。もちろん、こうした状況はさまざまな人間活動に起因するものであることを強く認識しなくてはならない。ところで、昨今の企業における不祥事は何とも嘆かわしい。長年にわたり受け継がれてきた多くの経験や知識をもとに、さらに極みを目指そうとする熱意と工夫によってオンリーワン製品を作り出す高度な技術は、日本が得意とする生産技術改良によるものづくりとあわせて“技術立国日本”を支えてきた。これまでの日本の科学技術は匠の技に代表されるようにこだわりを持った研究者や技術者で支えられてきたが、利益を追求するが故に合理的な経営・管理手法に基づいた運営が主導的となり、優秀だが現場を知らないリーダーが多くなってきた。その結果、暗黙知で築かれてきた技術の継承が難しくなっている。グローバル化や標準化が進むとその傾向はさらに強くなるように思う。
日本の伝統的な匠の技があらためて海外から注目されているが、技術の本来あるべき姿やそれに打ち込む人間のこだわりへの理解が世界共通であることを示すものとして大変嬉しく思っている。日本では文化や芸事、武術に対して、茶道、華道、書道、剣道、柔道などと求道的な意味で「道」と名付けることが多い。それは、巧拙や勝敗よりも、自己の精神修養や他者への敬意、感謝の心を尊重する日本人固有の考え方に基づくもので、伝統的な匠の技のみならず自身に課せられた仕事に対する取組み方にも通じている。道を究めることにはゴールはなく、自分自身との戦いがより洗練された高度な技術を作り上げていくと信じている。しかしながら、この職人技とも言える伝統的な匠の技とその世界観を伝える後継者の不足はきわめて危機的な状況にある。
一方、政府は第5期科学技術基本計画において、人々に豊かさをもたらす「超スマート社会(Society 5.0)」を未来社会の姿とし、IoTやAIなどのサイバー空間と現実社会であるフィジカル空間を高度に融合させる取組みを推進することでその実現を目指そうとしている。とくに、OECDが生物資源とバイオテクノロジーを用いて地球規模の課題の解決と経済発展の共存を目指す「バイオエコノミー」を提唱していることもあり、アカデミアや企業に対する革新的な技術創出への期待は大きい。生物工学にとっては今がチャンスと捉えるべきで、その使命を果たす時を迎えている。
この大きな動きの中で、本学会としては枠にとらわれない自由な発想と挑戦的な取組みによって魅力的なテーマの立案とイノベーション創出に挑んでいきたい。こだわりを持った真摯な姿勢が新たな可能性と境地を切り拓くものと信じている。酒造りの工程にある“火入れ”は、パスツールが「低温殺菌法」というワインの腐食防止技術を開発する300年前から確立していた“経験的な知”に基づく匠の技である。“こだわり”から創意工夫により技術が洗練され、さらに研ぎ澄まされて技術の革新が起きるものと考えている。
最近、多くの分野で若い人の活躍が目立つが、その中でも、史上最年少で将棋のプロ棋士となった藤井聡太四段のデビューからの公式戦29連勝は、世代を越えて多くの人に鮮烈な印象を与えた。完璧ではない“人としての危うさ”の中で、運をも引き寄せる彼の精神的な強さと読みの深さに魅了された。しかも、AIを取り入れて自身の技術を高めるという今の若者らしい取組み方もしている。
デジタル化が進み、究極的な合理化の時代になっても人の知的・精神活動が社会の主体であると信じている。未来社会の良し悪しは、それを動かす人の資質に大きく依存することは間違いのない事実である。本学会においては、近未来の科学技術の主軸になるであろうバイオテクノロジーを専門とする次世代を担う人財の育成に注力していきたい。
著者紹介 早稲田大学理工学術院(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 21 12月 2017
生物工学会誌 第95巻 第12号
安部 淳一
日本の片隅で糖質の分解酵素を地味に研究していると、つい最先端の知識や技術からは遠ざかり気味になります。したがって、私に不向きなそれらの話は他の先生方にお任せし、これまでの大学生活で自分をもっと磨けば良かったことの反省を述べ、若い研究者とその卵の院生・学生の皆さんへのエールとしたいと思います。
各自の専門と近辺のできるだけ幅広い自然科学の知識を蓄えることは言われずとも行っておられると思いますが、ぜひ専門とまったく異なった分野にも興味を持つことを特にお薦めしたいと思います。最近では、総合科学、あるいは統合科学という言葉も頻繁に目にするようになり、幅広い教養を身につける重要性が指摘されています。国際学会や留学などで海外の研究者と話をする機会を得て、親しくなればなるほど会話が弾み、専門以外にさまざまな話題の会話がなされます。専門領域の最新の科学の話題はもちろんですが、野原を歩くときはさまざまな自然の風物について、町中では建物、道、交通機関、そして室内では政治、文化、歴史、絵画に音楽、文学、映画などの芸術、あらゆることが話題になります。時には、教育システムについても当然話題に上がります。これらについて、皆さんはどの程度興味を持っており、それらの話題を提供することができるでしょう?
私が尊敬する多くの先生方は、専門以外にも深い知識・興味をお持ちでした。物理学者であった寺田寅彦先生や朝永振一郎先生は随筆家としてとても有名で、科学、教育、芸術の分野で多くの作品を残しておられます。学生時代に所属していた研究室のある先生は、さまざまなジャンルをお読みの読書家でまた知識人でした。昼休みに読んでおられた本のタイトルを横目で盗み見て、へディンという探検家やさまよえる湖ロブノールという話を知り、私もシルクロードに興味を持ちました。同じ糖質分野のある先生は、ベートーベンのさまざまな年代における生活状況と心理状態からいくつもの曲の背景を論じ、ついに著書にまとめられました。留学先の仲間達からはよく歴史の話題に巻き込まれましたが、ヨーロッパの歴史はほとんど分からず、またアジアの歴史と対比して語ることもできず沈黙。もちろんその当時の西欧と東欧をまたいだ政治の話にはまったく歯が立ちませんでした。研究室のボスからはカズオ・イシグロの本を紹介されましたが、世界が認める日系イギリス人作家について当時はまったく知らず、また世界中にファンが多い黒澤明監督の映画についての背景や思想について尋ねられても答えられず、恥ずかしい思いをしました。日本の文化、歴史を、そしてそれらに対する私の理解を聞いてもらうチャンスを失しました。
各地で巡り合った教養のある人々の社会科学や歴史、文化の話題の豊かさは、とても豊かな精神性と深い人物像を感じさせ、印象が強く残っています。それらのいくつもの話題が次々に展開されるのが日常会話なのではないでしょうか?ぜひ日常会話に強くなりたいものです。芸術や歴史、文化について深く学べというのではありませんが、それらに接したときに心に留めると同時に感想を必ず言葉で表現し、感性を磨きたいと思いました。私が感じた彼らの豊かな精神性は、研究領域に重要な足跡を示す業績を上げると同時に、毎日の生活を本当に楽しんでいることから来るのではと察することができました。
今後、自然科学にとどまらず、社会科学、芸術、歴史、文化、多方面のことに興味を広く持ち、世界のあちらこちらで話題を提供できる研究者、技術者になって活躍されることをお祈りします。
著者紹介 鹿児島大学農学部食料生命科学科(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 27 11月 2017
生物工学会誌 第95巻 第11号
播磨 武
ベトナムのGMP(Good Manufacturing Practice)のレベルを引き上げようと思って、この地に来たのですが。想像していた以上に苦しんでいます。今回は生物工学から離れて、製剤の分野に移った人間のベトナム奮闘記を楽しんでいただければと思います。
さて、私は外資系の新薬メーカーであるファイザーで約30年(前半の20年間は生物化学工学をやっておりました)、日本のジェネリックメーカーである東和薬品で約8年、一昨年の2015年6月まで勤務しました。昨年(2016年)の正月明けに友人から電話があり、「退職して何もしていないなら、ベトナム国内企業でNo. 1の製薬会社であるDHG PHARMA社がコンサルタントを探しているので、ベトナムのために一肌脱いでくれないか」と言うのです。
環境次第ということになり、その年の2月にベトナムへ下見に行きました。ベトナムのGMPレベルがどれほどか知りたいのと、住居と食事が気になっていました。GMPのレベルは想像した通りでした。想像と違っていたのはベトナムではダイレクターレベルでも英語がほとんど通じないと言うことです。会社が準備してくれた住居はホテルでしたが、一軒家とメイドが希望であることと、自宅から会社まで通うのに運転手をお願いしたところ、すべて聞いてくれたのです。会社の会長の熱意が伝わってくる感じでした。もう一つ気になっていた食事はまったく問題なく受け入れることができました。2月にDHG PHARMAで2018年末まで働くことを決めましたが、書類の提出に時間が掛かり、実際にベトナムを再訪したのは4月の半ばでした。
ベトナムに着いて、まず工場見学を行い、工場の人達と話しました。驚いたのは、彼らが前のコンサルタントを盲目的に信じていることでした。以前に東和薬品で働き始めの頃のことを思い出しました。東和薬品の方々は、私の言うことを盲目的に信じてくれました。ただ、これでは私がいなくなった後で、何をするか自分達で考えられるようになりません。東和薬品で人を育てることの難しさを感じましたが、結局、彼らの成長を信じ、自分で考えることの大切さを教えました。ベトナムではもう少し状況は異なりますが、DHGの人々の成長を信じ、日本でやったように、自分で考えることの大切さを教えていこうと思いました。ただし、前のコンサルタントが必ずしも正しくないということを証明してからです。大変だったのは前のコンサルタントの協力がほとんど得られなかったことです。自分で自分のやった仕事や自分で承認した仕事を否定するのですから、無理もありません。このことによって前のコンサルタントとの人間関係が傷つかないことを祈るばかりです。
自分で考えることの大切さは、自由で活発な議論なくしてありえないと思います。しかし、自由で活発な議論をすることは中々大変です。ベトナム人は直属上司に対する信仰が厚く、その言葉に盲目的に服従することに慣れているので、自分で考えようとせず、すぐに答えを聞いてしまいます。答えをすぐに与えずに、根気よく、自分で考えることの大切さを教えていくのです。
私はよく人に“Be a reliable person.”「信頼できる人に成れ」と言いますが、信頼できる人とは約束を守る人だと思います。組織である以上、他人のした約束も守らないといけません。来た当初はAさんがやらないからとか、Bさんが遅れたとか言って、平気で約束を破ることに随分泣かされました。在任中にはReliable personを数人育てたいと思います。
ベトナムの人はある件の担当者を他の誰かに決めたら、その件が自分の担当の仕事と関係あるとしても、まったく無関心な人が多いと思います。また、新しい知識を身に着けようとしない人も多いようです。私は彼らの意識を変え、組織を見直し、必要があれば担当者を変え、DHGを他人の言葉を鵜呑みにせず、自分で考え、新しいことを積極的に学ぶような組織にしたいのです。難しいです。私が苦しむ理由が分かったと思います。任期までに完成は無理でも何とか目途を付けたいと思っています。
著者紹介 DHG PHARMA、 Senior Consultant
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 26 11月 2017
生物工学会誌 第91巻 第6号
和文誌編集員長 藤原 伸介
この度、生物工学会誌編集委員長を務めさせていただくことになりました関西学院大学理工学部の藤原伸介でございます。就任にあたり、会員の皆様にご挨拶申し上げたいと思います。
伝統ある日本生物工学会の学会誌(和文誌)の編集を担当させていただくことは大変光栄なことだと感じております。和文誌は新会長の園元謙二先生が編集委員長をされていたときに掲げられた三つの目標(学問情報の伝達、学会活動の伝達、会員の相互交流)を継承し、これまで活動を行って参りました。前任の木野邦器先生は民間の視点を重視され、産学連携や民間研究の紹介にもご尽力されました。日本の発酵産業の歴史にも注目され、特に90周年では、記念座談会(本年4月号掲載)を企画化され、黎明期の出来事を生物工学会の歴史を交えながら紹介されています。私は先生方の目標を継承しつつ、さらに「会員が欲する情報の発信」を意識して取り組みたいと考えております。
ご存知のように本学会は民間企業の研究者が会員の約4割を占め、民間企業、大学、あるいは公的研究機関の研究者が集うユニークな学術団体です。和文誌は、学生、教員に学問的価値の高い情報を発信するとともに、民間研究者が欲する情報も発信しなければならないと考えています。学生にとって企業が欲している情報を知ることは、将来の職業選択、キャリアデザインを考える上で大切なことです。また学生会員の方に知っておいていただきたい実験の原理、生化学の基礎なども生物工学基礎講座などを通じて提供して参ります。和文誌が世代を超え会員の皆様にとっての価値ある情報源になるよう務めて参りたいと思っております。
数年前から和文誌の内容もWEB上で公開され、パソコンや情報端末でもお読みいただけるようになっています。特にキーワード検索の機能が進歩したこともあり、冊子体ではなく情報端末の方が読まれているのではないかと感じます。中でも「生物工学基礎講座」「バイオミディア」はダウンロード件数も多く、補助教材としてもかなり活用されているのではないでしょうか。今年の4月号から新たに連載されている「科学者が知っておきたいビジュアルデザインの心得」も好評で、学会発表や学位論文発表などのパワーポイント作りに役立っているのではないかと思います。冊子体では表現できない写真やカラー図もWEBを通じた情報端末では可能です。これからは積極的にWEB媒体も意識し、「会員が欲する情報の伝達」を心がけて参りたいと考えております。
学会誌には大きく二つの使命があると考えております。一つはトレンドとなる学術性の高い情報を会員に知らせることです。和文誌には英文誌にはない親しみやすさがあると思いますが、バイオの最新トレンド、あるいはこれからトレンドになりそうなトピックスを日本語でわかりやすく提供して参りたいと考えています。もう一つは次世代を担う若手研究者の方に、忘れないでいただきたい情報の再発信です。最新の知見とともに、教科書から忘れ去られてしまいそうな内容も、継承すべき事柄は取り上げたいと思います。日本の発酵産業の中で産まれた技術、発酵工学を基礎として培われた先端技術も積極的にとりあげ、我が国の技術水準の高さを会員の皆様に再認識していただきたいと思っています。編集副委員長としては岡澤敦司先生(大阪府立大学 )にご尽力いただくことになっています。デザインセンス抜群の岡澤先生の力を借りて、視覚的にも訴えられる和文誌を目指したいと思います。新年度はこれまで和文誌の編集に携わられた多くの委員の方が去られました。同時に新しい委員の方が多数加わり、委員会全体も若返りしています。新しい力を活力として、他の学会誌に負けない内容の学会誌刊行が続けられるよう努力して参りたいと思います。
どうか会員の皆様のご指導とご鞭撻を、何卒よろしくお願い申し上げます。
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
生物工学会誌
Published by 学会事務局 on 25 10月 2017
生物工学会誌 第95巻 第10号
山田 隆
科学研究は絶え間なく進み、その成果たる知識と技術も絶え間なく増加し、進歩している。この進歩は、インターネットなど高度情報伝達技術によって全世界でほぼ同時に共有できる。全世界で共有された進歩は、それを基に更なる進歩につながる。しかし、この連鎖がどんなに加速しても、変わらないものは「科学の進歩は科学者によってもたらされ、科学者は人間だ」ということである。それぞれの科学者がさまざまな程度で進歩に貢献する。万有引力の発見や相対性理論、DNA構造解明などの飛躍的進展は、ごく一部の天才的科学者によってもたらされた。天才(ここでは飛躍的進展をもたらす人を天才と定義する)による飛躍が生まれるまでのその土壌は、凡人によって準備されるのが常である。チョッピリ土壌を耕すヒトや、かなり深く広く耕すヒトもいるが(耕す程度を本人は自覚していない)、大多数は天才とはなり得ない。如何に情報が速く広く全世界に流れてもこの土壌耕作者が増えるだけかもしれない。特に情報に敏感で影響を受けやすいヒトほど土壌を耕す側に回る危険がある。
(土壌を地道に耕し、確実に科学の基盤を固める作業を軽視しているわけではない。あらゆる仮説や理論は実証されねば意味がない。実証には多大のエネルギーが必要であり、実証された原理からの演繹で多くの成果が生まれる。天才が出るためにはそれなりの科学者コミュニティーの広がりが必要である。)
あるアイデア(科学情報・技術)が流行すると全世界が一色に染まる(しばらくの間)傾向が、最近特に気になる。これは音楽や映画などの世界では普通であるが、科学の世界では最近まではそうではなかった。科学の世界は基本的に保守的であり、新概念の受け入れには慎重であり、その広がりにも時間がかかった。最近の(軽薄な?)傾向にある情報技術と連動した科学価値観の変化を見逃すわけにはいかない。科学の成果は論文として科学雑誌に発表する。主要雑誌のほとんどはオンライン化され、投稿、査読、公開までインターネット上で行われる。公開された論文はウェブサイトで閲覧され、その頻度が記録される。このプロセスの中に新価値観が埋め込まれてしまった。流行のキーワードを入れておけば、被閲覧頻度が上がる。雑誌編集者、査読者の受けも良い(ただし、研究内容、質とは無関係であるが)。この風潮の影響は看過できないほど大きく見える。結果的に、一見加速されて見える科学の進展が、実は同じレベルでの高速空回りにしか過ぎないことに気づくべきである。この空回りは時に大きな波のうねり(後で無用とわかる)を引き起こす。
科学の進歩に飛躍的貢献をする天才(必ずしも天才でなくても良いが)となるためには、他とは違わなければならない。ボールに集まってボールと一緒に動く下手なサッカー選手たちとは距離を置いて、冷静に物事を見なければいけない。科学者コミュニティーの中では異端者扱いされるかもしれないし、研究費などの獲得競争でも冷遇されるかもしれない。研究成果も学会などでなかなか認められないかもしれない。ただし、意義の高い研究成果は必ず認められるし(昔に比べれば比較的速く)、意味のないものは膨大な論文の海に埋没してゆく。こうした状況で、科学者として如何に自らを鼓舞していくか。また、このような科学者をいち早く発掘して、きちんと評価する体制を整備できるのか。はたまた、このようなポテンシャルのある人材を現教育制度の中でどのように育成していけるのか。科学技術基本法に基づく科学技術創造立国の課題は多い。
著者紹介 放送大学広島学習センター(所長)、広島大学名誉教授
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 9月 2017
生物工学会誌 第95巻 第9号
浅田 雅宣
生物工学会の会員の専門分野は、私が会員になった醗酵工学会であったころから比べると非常に広がっており、会員数も増え、学会としては発展してきています。そこで複数の企業で研究を行ってきて大学に移った経験を踏まえて、学会のさらなる活性化と学術研究レベルの向上に関する私案を述べたいと思います。
総務省統計局の平成28年科学技術研究調査結果によると、2016(平成28)年3月31日現在の我が国の研究者(企業、非営利団体・公的機関および大学などの研究者の合計)は、84万7,100人であり、そのうち企業の研究者は50万6,134人で、約6割を占めています。企業の研究費は13兆6,857億円、大学などは3兆6,439億円、非営利団体・公的機関は1兆6,095億円となっています。すなわち、企業は研究に膨大なお金と人員を費やしており、実用化に向けた研究だけではなく、基礎的な研究でも非常に優れた多くの知見を有しています。もちろん、一口に企業と言っても、その規模やカバーする分野によって研究内容は多様であり、人員やデータの蓄積量も異なります。
私は、大学院時代には、企業は応用と商品開発研究を行い、大学は基礎から広範な研究を行っていると思っていました。しかし、実際に企業の研究所に入ると、実用化するために多くの基礎的な研究がなされていることに驚いたものです。企業が得意としている分野における研究手法や商品化に関しては、独特の技術やノウハウが蓄積されています。企業は発表するために研究をすることはなく、何らかのアウトプットを目的としていますが、その過程で多くの知見を得ています。企業には、企業秘密という囲いがあり、実用化したものを守らなければならないため、それに関連したキーとなる研究成果は一部しか発表していません。その他にもビジネスにつながらなかった研究が多くあり、特許以外には公表されず死蔵されているため、学会においても社会においても知られていないのが実情です。それらには、まったくの新分野であったり、既知のものや大学で研究されているものよりも数値的には上回っているものもありますが、大学や公的機関ではそれらを目にすることがないため、自分達のデータが一番と思っている時もあります。そこで提案です。企業としては、ビジネスにつながらなかった研究データの発表にお金もマンパワーも使いたくないというのが本音ではありますが、まずは死蔵データでも個々のデータが優れているものは、企業の研究レベルの高さを示す良い機会であるので、発表を促したいと思います。それだけでもかなりの数になります。
こうした発表は、携わった企業研究者の張り合いになりますし、交流会の話題にもなり、人脈を広げるきっかけになります。企業の高いレベルのデータが発表されれば、大学や公的研究機関の研究者にとっても刺激となり、新たなアイデアや共同研究の機会を生み、その分野全体の底上げにつながり、まさしくオープンイノベーションとしてより大きな発展をもたらすと思われます。
大学生、特に大学院生には、企業における研究者の仕事にも目を向けて欲しいし、圧倒的に多くの先輩たちは企業や民間研究機関で仕事をしており、そのレベルの高さを知って欲しいと思います。生物工学分野は、基礎研究だけでなく、応用あるいは商品化研究に特徴があり、学会を介して大学と企業の交流がより盛んになることで両者のさらなる発展が見込まれます。発表数が増えるということは、会員数も増えるということになり、学会が活性化し、価値を生み出す媒体としての意義が一層高まることになります。本学会の40%が企業の会員ということですが、研究者数からするともっと企業の会員が増える余地があります。学会としては、会員のメリットになる色々な企画をされていますが、企業に過去の研究データも含めて発表するように促す取組みもしてみてはどうでしょうか。
著者紹介 甲子園短期大学(特任教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 24 8月 2017
生物工学会誌 第95巻 第8号
駒形 和男
微生物の研究には、乳酸発酵の研究から、酪酸発酵、アルコール発酵、酢酸発酵、自然発生説の否定、狂犬病のワクチン治療まで広範な研究を行い、微生物学の基礎を開いたフランスのパスツールの研究の流れと、家畜の炭疽病の病因が炭疽菌という細菌であることを解明し、寒天培地の導入、結核菌の分離などいわゆるコッホの条件を確立し、医学細菌学の基礎を開いたコッホの流れがあると考えられる。他方、1800年代の後半から1900年代の半ばにわたり、オランダのベイエリンク(Beijerinck, M. W.)はデルフトのPolytechnicalSchool(現在のDelft University of Technology)の教授として微生物学研究室を開設し、基礎微生物学(generalmicrobiology)の基礎を築いた。最近、この学派についての記録が出版され、再評価の機運が見られるので、この学派(Delft School)について紹介したい。
Delft Schoolの創始者であるベイエリンクは、根粒菌の分離で知られているが、さらに増菌培養(集積培養、elective culture, enrichment culture technique)の手法を発展させ、1921年から1940年の間に、硫酸還元菌、硫黄酸化菌、硝酸還元菌、窒素固定菌、尿素分解菌、発光細菌、酢酸菌、乳酸菌、セルロース分解菌、水素酸化菌、メタン酸化菌などの細菌を分離し、研究の対象とする微生物の幅を拡大した。増菌培養は、微生物の成育環境に基づいて、生育因子を制限し、その環境に生育する微生物を増殖・分離するする手法で、環境に存在する少数の微生物を分離するのに用いられる。また、ベイエリンクは、タバコモザイク病の病原体は細菌ではなく、濾過性のもので、これをウイルス(virus)と命名したことで知られている。
ベイエリンクの後継者となるクライバー(Kluyver, A. J.)は1914年、酵母の発酵性を利用した糖の分別定量の研究で学位を取得し、その後、セイロン(現在のスリランカ)、ジャワ(現在のインドネシア)で農産物の調査をしていたが、1921年にベイエリンクの職を継いだ。彼は、就任に際しMicrobiology and Industryという講演を行い、その中で、微生物は人類にとって有用な働きをするもので、微生物と人類とのかかわりは病気だけではないと述べている。また、クライバーは、微生物の発酵などに見られる代謝の研究から、すべての生化学的反応は水素の受け渡しであると述べ、unity in biochemistryを提唱した。現在の生化学からすれば常識であるが、この考えを発表したのが1926年のことであるから、ほぼ90年前のことである。クライバーは、基礎微生物学は医学細菌学と異なり、科学のなかの独立した一分野であると強調するとともに、化学工学をはじめ他分野との協調を述べている。糸状菌の振とう培養、通気培養の原型と考えられるクライバー・フラスコは彼の研究室で開発された。彼の研究室の名称がLaboratory of general and appliedmicrobiologyというのも彼の研究方針を物語っている。また、彼が糖の分別定量に用いた菌株は、オランダのカルチャーコレクションの酵母部門の中核となっている。
ファン・ニール(van Niel, C. B.)は、クライバーの研究室で助手を務め、1928 年12 月米国に渡り、Stanford UniversityのHopkins Marine Stationで紅色硫黄細菌の研究を続けた。また、1930年から1962年にわたり、同大学に基礎微生物学のコースを開設した。微生物の形態学、分類学、酵母と細菌の生態学、微生物の生化学、光合成などに関する講義、集積培養の実験が行われ、密度の濃いコースであったといわれている。受講生は、米国のみならず世界各国より集まり、後日、彼らのなかから基礎微生物学をリードする優れた研究者が多数うまれた。
ベイエリンク、クライバー、ファン・ニールの系譜に属する研究者の一門をDelft School といい、このSchoolは、微生物学を生物学の一分野と位置づけ、常に微生物とは何かという視点から研究を続けた。また、Delft Schoolの貢献は、微生物学研究者の育成である。このSchoolに学んだ研究者は広く世界に分布し、その地で基礎微生物学を根付かせた。微生物を研究の材料として用いるだけでなく、基礎微生物学を教育・研究する学部とはいわないまでも、せめて微生物学科の設立を望みたいものである。
著者紹介 東京大学名誉教授
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 7月 2017
生物工学会誌 第95巻 第7号
遠藤 銀朗
宮城県美術館で開催されたルノアール展を観てきた。国内外の多くの美術館から集められたルノアールの絵は観る者を楽しく幸せな気持ちにさせてくれる。多くの芸術の中でも、フランス印象派の絵画はそれを観る多くの人を虜にする。それは、画家の絵画手法によるというよりも印象派の絵の根底にある「幸福感」の忠実な描出と、それを鑑賞する側に創出させられる「幸せの無意識的共感」にあるように思う。そして、ルノアールは特にその傾向を強く示してくれる印象派の画家だと思う。
自然科学や工学技術は絵画芸術や文芸、音楽、舞芸などの芸術文化活動から対極にある営みであるとみなされることがある。しかし、必ずしもそれは正しくないと思う。科学技術も印象派の絵と同様に「人間の幸福を主題とする」目的によってなされる活動であることに違いはない。個々の科学技術の研究や開発においては、それが基礎的なものであろうと応用的なものであろうと、その発端には「科学的真実」を見つけ出すという目的がある。そして最終的には、その科学的真実を人間の幸福につながるものとして使えるようにしたいという目的がある。自然科学の場合、科学的真実は少しずつ近づくことはできるが、同時にさらに理解しなければならない謎も深まる存在のように思える。その少しずつ近づくことができた真実を技術の形に仕上げ、人間の幸福を実現する手段として使えるようにするには、そのために必要なさらなる謎を解き明かさなければならない。多くの芸術が追い求める「人間の心象的真実」もまた、多様な謎の解き明かしと人間の幸福を理解するための努力によって近づくことができる存在なのだと思う。
絵画芸術は、必ずしも先に述べたフランス印象派の画家のように「幸福な主題」を描いたものだけではない。重い主題によって描かれたものも数多くある。観る者を暗く不幸な気持ちに追いやるそれらの絵画は、なにを目的に描かれたものであろうかと考えさせられる。しかし、それらの絵画も多様であろう人間と人間社会の心象を一つひとつ解き明かし、そしてそれらの心象的真実から、人間の本質とその本質によって組み立てられる人間の幸福を見つけ出すために必要な芸術文化なのだと思う。翻って、科学技術にもこれと同じ状況があるように思われる。私たち自然科学者・技術者は、人間と自然の幸福な存続のために役立つことを目指して、己が決めたそれぞれの科学や技術の分野で日々活動している。しかしそのために、多様であろう科学的真実の暗く不幸な側面も見いだし理解しておくことが必要なはずだ。この不幸な側面の理解という目標がなければ、さまざまなリスクが克服された状況の下で人間として安心して生きられるというような、科学技術における「幸せの無意識的共感」を得ることはできないように思う。
科学技術としての生物工学はどのような目的を持ってこれから先に進むべきなのだろうか。生命や生物現象をさらに正しく理解することと、それら理解した事柄を新たな科学技術の創造に役立てていくことは、これからも生物工学に必要な手段といえる。そして、より正しく理解できた科学的真実を人間や自然にとって「幸せの無意識的共感」に結実させることが、生物工学においても目的の一つになるのではないだろうか。その結実の手段を見つけ出すこともまた必要である。科学技術において「幸せの無意識的共感」を獲得することは、必ずしも簡単でないかもしれない。生物工学のこれからの発展の先に予測できない暗く不幸な側面はないのか、もしそれがあるとしたらその側面から新たな真実として(あるいは人間・人間社会と自然の本質として)学ぶべきことは何か。そしてそれらを学んだことから新たに組み立てることができる「幸せ」の存在様式はどのようなものなのか。このように考えてくると、生物工学を含む科学技術と芸術の目的の間には何の壁もないように思われてくる。
著者紹介 東北学院大学工学部(特別教授)、東北学院大学工学総合研究所(客員教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 24 5月 2017
生物工学会誌 第95巻 第5号
長棟 輝行
若手会員、学生会員の皆様は、アジア生物工学連合(Asian Federation of Biotechnology: AFOB, www.afob.org)をご存知でしょうか。AFOBはアジア地域におけるバイオテクノロジー関連研究者の相互理解・交流を促進するために2008年10月に設立され、アジアの14か国/地域から13のバイオテクノロジー関連学会が加盟している学術組織です。AFOBは、Asian Congress on Biotechnology(ACB)を2 年ごとに、Young Asian Biological Engineers’ Community(YABEC)を毎年開催しています。また、欧州生物工学連合(EFB)と2014年7月末に交流協定を締結し、それぞれが主催する国際会議であるACBとECBでジョイントセッションを開催しています。
若手会員の中にはACBやYABECに参加された方もいるのではないでしょうか。AFOBには当学会をはじめとして日本化学会バイオテクノロジー部会、化学工学会バイオ部会、環境バイオテクノロジー学会、日本動物細胞工学会も加盟しています。現在、AFOBには約3900名が個人会員登録していますが、日本でのAFOBの認知度はまだ低く、個人会員登録数は190名と、韓国、インド、マレーシア、中国の約1060名、740名、550名、400名を大きく下回っています。アジアでバイオテクノロジー分野の教育・研究・産業を牽引してきた日本の将来を担う皆様のアクティビティーをアジアに向けて発信し、また、同世代の若手と交流し、切磋琢磨するために、AFOBの個人会員に登録をしてみてはいかがでしょうか。ちなみに、個人会員の会費は無料であり、AFOBが主催・共催する国際会議やセミナーの参加費割引やAFOBが編集する『Biotechnology Journal』特集号の無料閲覧などの特典があります。
当学会の若手会が主催する夏のセミナーは約50年の歴史を持っており、合宿形式で熱い議論を交わすことができる若手交流の場として大きな役割を果たしてきました。先輩や同輩の方々と午前・午後はセミナー、夕方は野球、夜は懇親会、さらに深夜まで相部屋の方々との熱い議論を通じて、多くの方々と交流を深め、知己を得ることができたことを懐かしく思い出します。AFOBのYABECはまさに若手会の夏のセミナーにあたる合宿で、2~3日間寝食を共にしながら研究発表会や懇親会などを通して、相互啓発や情報交換、密度の濃い個人ベースの国際交流を図ることを目的としています。YABECは23年前にシンガポールで開催されたアジア太平洋生物化学工学会議に参加していた韓国の若手研究者達から、お互いにもっと深く知り合う機会を作ろうという呼びかけに日本、中国、台湾の若手研究者有志が賛同して、翌年に発足しました。その後、毎年この4か国の持ち回りで開催され、現在はAFOB若手会の役割を担っています。私自身、YABECメンバーとの共同研究、国際会議の企画、大学間交流など、さまざまな場面で、YABECで培った人脈の重要性やその恩恵を実感しました。
学会ホームページ国際展開委員会のサイトに掲載されている「国際展開諮問委員会報告」の中で、当学会の「アジア戦略」として、アジアとの交流・共同研究を行う若手研究者の支援、学会間の連携を推進する若手の育成による新学術分野の開拓の重要性が指摘されています。生物工学若手会の夏のセミナーと同様に、YABECへの参加や運営に主体的にかかわることで、単に学会で会う“顔見知り”としてではなく、生涯を通じて付き合える“友人”としての交流が生まれ、豊かな人脈が培えると思います。アジアにおけるバイオテクノロジーの将来を担う若手会員、学生会員の皆さんに、アジア若手国際交流の場への積極的な参加をおすすめします。
著者紹介 東京大学大学院工学系研究科化学生命工学専攻(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 4月 2017
生物工学会誌 第95巻 第4号
山本 憲二
生物工学という分野は非常に幅が広い分野であると思う。工学や農学のみならず理学や薬学、医学をも包含した分野で、生物工学会大会での発表者の所属を見ると非常に幅広い分野の研究者がいることに驚く。考えてみると生物工学という名前は少し奇妙で、曖昧でもあり、一体どのような研究が基本的に行われているのかイメージし難いところがある。生物を工学的な視点から見ることなのか、生物を技術的に扱うという意味なのか、わからない。英文ではバイオテクノロジーと訳されているので、その名前の魅力がいろいろな分野から研究者が集まる要因になっているのであろうか。
私は農芸化学の分野に立ち位置があり、応用微生物学が研究分野であるので、学生のころは、当時は醗酵工学会と称していた当学会の、醗酵という名前はともかく、工学という名前にやや違和感を感じ、学会との距離を感じていた。工学という領域はちょっとわからないなという感覚があった。しかし、バイオテクノロジーの学会といわれると私たちが応用微生物学の分野で研究していることはまさにバイオテクノロジーではないかと考えてこの学会に参加することに余りためらいはなかった。
よく考えてみると、生物工学という領域の中でも私たちはどちらかといえば、スクリーニングなどのローテクノロジーを操って有益なもの、実用的なものを天然界から見いだすことが主な仕事である。とにかくやってみないと分からないという世界である。一方、工学的な視点では、ハイテクノロジーを用いていかに実利的なものを早く、多く作り出すことに重点がおかれているように感じる。要はいかに合理的な方法でもの作りをすることが重要であるかという世界のように思える。一見、両者はきわめて違った手法によって目的を達成しようとするように思えるが、どちらもバイオテクノロジーには変わりないでしょということで同朋意識が芽生える。バイオテクノロジーという言葉は魔法のような言葉である。魔法のような言葉であるが故にわからないところも沢山あるけれども、同朋意識を芽生えさせる不思議な言葉でもある。
私が若い頃の工学部出身の方々は、まるでブルドーザーのような方々が多く、活発で頭脳明晰で、少しこわもてのような人が多いと感じていた。だから、工学の分野に入ることには一種の恐れのような気持ちがあった。しかし、私が専門領域としている「糖鎖」の世界で、糖鎖工学はグライコテクノロジーと訳されているが、その工学の本質は私たちが農学の領域で行っている微生物の酵素を使って糖鎖を自在に切ったり貼ったりすることに他ならないということに気付いた。すなわち、私たちがやっていることはまさしく工学だということに気づいて、生物工学をより身近に感じるようになった。ただ、生物工学会では大会の講演セッションとして「糖鎖工学」があるものの、演題数が例年わずかであって風前の灯火のような状況にあるのは残念である。
最近の生物工学会大会で発表されている内容からは従来の工学のイメージを抱く発表や講演が少なくなっているような気がする。いわゆるバイオテクノロジー的な内容が多くなり、工学に関わりのある学会という色彩が薄くなっているように感じる。私はこれを良い傾向であると思っている。私が若い時に感じたように、工学という言葉に少し距離感を感じる若い方々にも、その研究分野の内容の多彩さがわかってもらえれば、もっと門戸が開かれるような気がする訳である。生物工学よりもバイオテクノロジーの学会と認識してもらえるようになる方が良いのではないだろうか。
バイオテクノロジーという言葉は不思議な言葉であり、まさしく魔法のような言葉である。
著者紹介 石川県立大学生物資源工学研究所(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 26 3月 2017
生物工学会誌 第95巻 第3号
清水 範夫
大学を卒業して企業の研究所で研究開発を担当し、その後、大学に奉職して教育と研究に従事したことから、企業と大学の両方の事情を経験しました。その経験から、研究を推進し、研究成果を社会に出して貢献するにはどのようなシステムが良いかについて考えるところを述べたいと思います。
企業の研究開発では経営方針に基づいた研究テーマが上長から与えられます。企業に就職した1970年頃は、公害が大きな社会問題でしたので、大型培養槽を高濃度有機性排水処理に適用する研究開発を行いました。小スケールから大型試作装置による実験を経て、営業活動を支援して製品化することができました。
1980年頃には、コンピュータ制御培養装置の研究開発に従事し製品化しました。当時の企業の研究は、このように研究から製品まで自社開発で、研究開発に投資して製品化していくという大きな自信があり、自前主義にいささかの疑問も持たなかった時代でした。この頃は、エズラ・ヴォーゲルが著した「ジャパン・アズ・ナンバーワン」に象徴されるように日本経済の黄金期でありました。そして、より先端的な科学技術開発を目指すために、基礎研究所設立のブームが起き、社内に設立された基礎研究所において少し先の製品の開発を目指しました。この時期に日本は急速に科学技術レベルを上げることができたと思いますが、基礎研究ブームは長く続かず、バブル経済の崩壊により基礎研究所は縮小されました。これ以降、日本の景気が低迷するにつれて研究開発にも勢いがなくなりました。
その後、新学部の創設とともに大学に移りました。大学は教育と研究の場であり、企業で研究開発をしていた環境とは異なっていました。研究テーマは自由に選べたことから、自分が関心を持つテーマについて少ない予算でしたが研究ができました。しかし、学生に論文を書いてもらう必要があり、大胆な研究ができませんでした。また、企業からの依頼で製品開発にも携わりましたが、製品開発にはもどかしさがありました。自前主義に陥っていたように思えます。
大学を定年退職してからは、技術調査をしていてオープンイノベーションを知りました。この定義は、「組織内部のイノベーションを促進するために、意図的かつ積極的に内部と外部の技術やアイデアなどの資源の流出入を活用し、その結果組織内で創出したイノベーションを組織外に展開する市場機会を増やすことである」(オープンイノベーション白書、2016年)とされています。企業を取り巻く競争環境が厳しくなっており、自社だけではイノベーションを起こすことは不可能になっていることから、世界中の技術資源を活用するオープンイノベーションは企業にとって今後の成長を確実にするための重要な戦略といわれています。しかし、日本ではまだ6割程度の企業は自前主義の傾向が強い現状です。
米国のシリコンバレーはオープンイノベーションで有名ですが、最近、イスラエルではベンチャーキャピタルなどからの投資により多数の先鋭的なベンチャー企業が創出されています。これらのベンチャー企業は開発した技術や製品をM&A(合併や買収)などにより素早く市場に出しています。企業だけでなく大学も含めてオープンイノベーションを遂行すれば、自前主義に固執して企業活動の停滞を招くことなく、体質改善されて、大きな飛躍を遂げることができると思われます。
日本でも大学発のベンチャー企業が設立され成果をあげていますが、リスクが大きいため若い人が起業に躊躇するのではないかと想像されます。しかし、多くの企業がオープンイノベーションにより先鋭的なベンチャー企業を支援すれば、企業からスピンアウトしたベンチャー企業や大学発のベンチャー企業の創設が活発になるのではないでしょうか。ここで生まれたベンチャー企業によって、以前のように我が国の産業が世界をけん引するエネルギーを生み出すように思えてなりません。
著者紹介 東洋大学名誉教授、東洋大学バイオ・ナノエレクトロニクス研究センター(客員研究員)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 24 2月 2017
生物工学会誌 第95巻 第2号
近藤 恭一
本会の賛助会員の1/3は発酵・醸造関係の企業ですが、筆者は、その一つの清酒メーカーで入社後20年間を研究部門で過ごした後、複数の異分野を経て現在に至っています。本会会員の40%は企業に所属しているとのことですので、現在は研究職や技術職でも、いずれ筆者のように研究に直接携わらない方も出てきます。そのような立場から、研究と経営について独り言を呟いてみます。
大小を問わず、多くの日本企業は、超高齢化社会への対応など、経験したことのない難局に直面しています。経営者は、猛スピードで変化していく環境下、企業の将来に向けて、国内外のトレンドや技術と市場の進化を見極めながら難局に立ち向かわねばなりません。現在の延長線上にはない明確な目標を掲げて、その実現のための計画を実行することが必要です。少なくとも10年先を見据えた「自社のありたい姿」を描き、経営計画に展開します。近年、経営計画の策定に関連するセミナーが頻繁に開催され、大盛況とのことです。企業の関心の高さと同時に、経営計画を策定する人材や将来の経営幹部の育成に腐心していることの表れでしょう。
企業の経営職は、入社以来の分業体制の中できちんと仕事をこなし、立派な成果を上げ続けてきた優秀なマネジャーから選ばれるのが一般的でしょうが、優秀なマネジャーといえども、必ずしも経営に適しているとは限りません。経営の勉強をする機会のないままに経営職に就けば、さらに状況を悪化させます。自分の守備範囲にこだわり、部分最適に邁進する「取締役担当者」に思い当たりませんか?そこで、キャリア形成の途中に経営の勉強の機会を与えることが増えているそうです。大企業の多くで「次世代経営幹部の育成」制度があるとのことですが、育成には長期間を要し、対象者をフォローし続けるのは困難だと予想できます。制度は、うまく機能しているのでしょうか?
このところ我が国の伝統的な企業であっても、MBAを取得したいわゆるプロの経営者にトップを委ねるケースが増えています。今までのような経験による経営ではなく、知識と視野の広さによる経営が求められるからといわれます。また、トップに理系の出身者が増えている気もします。製造業に限らないことから、目標達成のプロセスを論理的に構築する訓練がされているというのが理由のように思われます。研究でも目標を達成するには、現状や将来への洞察力と広範な知識に裏付けられた研究計画が必須です。そして、結果の保障がない新しい目標に向けて突き進んで行く勇気と数年間に及ぶ粘り強さが求められます。その点で研究と企業経営には相通じる点があり、研究は経営職の育成に有効なキャリアとなり得ると思います。企業で研究や技術部門に所属し、将来は経営を担いたいと考えている若い方や次世代の経営幹部をこれらの部門からも選抜しようと考えている立場の方に申し上げたいと思います。
モノ余り社会の中で自社製品の差別化のための技術開発に熱心に取り組んだ結果、皮肉にも品質の高いレベルでの均質化と否応なしの価格競争(低収益状況)を生み出してしまっています。企業経営の目的は、持続的な利益の確保であるにもかかわらず、戦略なき戦術の至るところです。顧客満足の向上のために品質や性能やデザインを改善することは、日々の事業にとって大切です。研究も改良やコストダウンなどのリノベーション的なテーマが多くなりがちです。しかし、難局からの脱出に求められているのはイノベーションです。これからの経営に役立つ、見えない未来に挑んでいく力を研究を通じて身につけるには、イノベーションとは言わないまでも、どこかにオリジナリティーを意識して取り組むことを薦めたいと思います。先行論文の補完的なテーマや、やれば結果が付いてくるようなテーマでなく、ささやかであっても洞察力が試されるような経験を積み上げていただきたいと思います。後輩諸氏のご活躍を祈念します。
著者紹介 白鶴酒造株式会社(取締役常務執行役員 経営企画室長)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 1月 2017
生物工学会誌 第95巻 第1号
川面 克行
皆さま明けましておめでとうございます。平素から学会活動にご尽力いただいている会員各位の皆様に心より御礼申し上げます。2013年に園元会長が掲げられた活動方針、すなわち3つの行動、7つの課題を着実に推進実行して参りますので皆様方のご支援を宜しくお願い致します。とりわけ学会財政基盤の盤石化は喫緊の課題でありご協力のほどお願い申し上げます。
さて2016年は英国のEU離脱、米国のトランプ大統領の選出、韓国の朴政権の混乱等々、世界の潮流が大きく変化しているように見受けられました。いずれも内向き優先の考え方に端を発した出来事であり、人の心の本質を問われる選択であったのではないでしょうか。このような難しい選択は個人としても社会の一員としても、いや応なしに迫られます。何かを決断する時はまずデータを集め、人の進言を受け、できる限り広範囲の情報を集め、その中から何かを選択して実行に移すわけですが、昨今はこのような選択を人工知能(AI)に頼るようになってきているそうです。
たとえば2016年11月7日付けの日経新聞に次のような記事が掲載されていました。外国為替市場で英ポンドがわずか2分間で6%急落し31年ぶりの安値となったそうです。その要因と考えられるのがAI対AIの自動取引だといわれています。AIに取り込まれた各種情報を瞬時に分析したうえで、どのような影響が出るのかを推定し、売るのか買うのかを決断して実行する、これがAIによる自動取引です。こうなるといかに優れたAIを保有するかがすべてであり、トレーダーと呼ばれる人達の代理戦争をAIがやっているようなものです。ここでいう優れたAIとは、ハード、ソフトは言うに及ばず、いかに正しい情報を大量に蓄積させることができるか否かだと思われます。株式取引のAI情報の中には各企業トップの能力データが保持されており、CEOはAIの評価の下に格付けされています。とてつもなく悲しい話ではありますがAIの世界はここまできてしまいました。
あるいはこんな話もあります。このあいだテレビを見ていると、長年胡瓜栽培を続けてきた農家にAIが導入されたというのです。収穫した胡瓜の等級を9種類に選別するうえで、熟練のおばあさんが一瞬にして判断する人間の能力をAIに移植したそうです。数千枚の等級分けされた胡瓜の写真を撮り、選別された理由をおばあさんの目を通したカメラからその着眼点を探り、大量の画像をAIに蓄積させたうえで検査対象となる一本一本の胡瓜と画像を比較して選別処理するそうです。こうして選別された胡瓜の等級分け正解率はまだ70%程度だそうですが、検査を重ねていくうちに間違いなく、おばあさんを追い抜いていくものと想像できます。
このように大量の画像や判断基準の観点になるようなデータをどんどん積み重ねることをAIの世界ではディープラーニングといいます。さて、ここで一つハッキリしてきたことがあります。ディープラーニングの部分でAIと記憶力を競ってみても無駄なことです。新たな着眼点や新たな発想こそがまだ人間に与えられているAIより強い領域なのです。そして人間の深層部分はこれからも未知の領域であり、まだまだAIには理解できないのではないでしょうか。
アメリカの大統領選挙の事前データに、人間の深層部分が反映されていなかったので、あのような誤った予想結果となったのでしょう。ホーキング博士は「強力なAIの登場は人類にとって最高にもなりうるし最悪にもなりうる」と警鐘を鳴らしています。ディープラーニングのデータを与え続けるのは人間、そしてその結果を利用するのも人間。しかしAIがリテラシーを持ち始めて独自でデータ集めが可能な状態になる前に人間はAIを手なづけておく必要があります。いよいよ日本でも創薬用AIを50社が共同使用し世界の製薬会社と戦う時代がやって来ました。いつの時代も、我々のように科学の進歩に携わっている者は正しい倫理観が求められていることを忘れてはなりません。
著者紹介 前アサヒグループホールディングス株式会社(代表取締役副社長)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 22 12月 2016
生物工学会誌 第94巻 第12号
古川 憲治
英タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)誌の2015年のアジアの大学ランキングによると、上位100校に入った日本の大学は19校で、21校の中国に首位の座を譲った。大学ランキングは研究者による評価や論文引用件数、留学生数や外国人教員の比率(国際化)などから算出される。日本の大学が国際化に乗り遅れていることが、ランキングを落とす原因になっている。大学が国際的に高い評価を得るには、教員がIFの高い学術誌に掲載される論文を沢山書くことはいうまでもない。海外から留学生を呼ぶには、国際的な情報発信に加えて、国際交流のネットワークの構築が必要になる。
ここで、私と中国・大連理工大学楊楓林教授との国際交流を紹介してみたい。
熊本大学大学院自然科学研究科博士後期課程の董飛君(現在、トヨタ中央研究所研究員)が、私の提供する科目を履修したことがことの始まり。彼から、中国の大学は全寮制で、寝食を共にした部屋仲間は、卒業後も兄弟と同様の付き合いをしていると聞いた。彼の部屋仲間は張興文君(現在、大連理工大学環境生命学院副教授)と劉志軍君(現在、大連理工大学教授・教務処長)で、3人とも楊教授の教え子。楊教授は大連理工大学化工学院の院長を長く務めた後、環境生命学院を設立した大物教授。2001年に董君の案内で大連理工大学環境生命学院を訪問し、楊教授と、張君、劉君、加えて楊教授の教え子で新進気鋭の全燮教授と出会った。共通の専門が排水処理工学ということもあり、意気投合し、交流が始まった。
楊研究室の劉毅慧講師を客員研究員として招聘したことをきっかけに、楊研究室から多くの先生方、学生が私の研究室に入室することになった。最初の博士後期課程の学生として成英俊さん(現在、大連市資源保護環境保全処・処長)、国費外国人留学生として喬森君(現在、大連理工大学環境生命学院副教授、第2回生物工学アジア若手研究奨励賞(The DaSilva Award)を受賞)、中国政府派遣の国家建設高水平大学公派研究生として馬永光君(現在、遼寧省機械研究院)、前述の劉先生が中国政府派遣のポストドクとして、楊教授の実験助手・徐暁晨君(現在、大連理工大学環境生命学院副教授)が博士後期課程の学生として研究室に入室した。彼らには研究室の主要研究テーマであるアナモックスや、付着固定化に関する研究に従事してもらい、研究室の発展に貢献していただいた。
楊教授との交流を通じて、楊教授から日本人以上に人との繋がりを大切にする人的ネットワーク作りの極意を教わった。私の方も楊先生にしていただいたことにお応えするよう力を尽くした。
楊研究室との付き合いがきっかけで熊本大学と大連理工大学の交流が活発になり、2002年には学部間交流協定を、2006年には大学間交流協定を締結した。また2011年には、楊先生の尽力もあり中国で2か所目になる熊本大学大連オフィスを開設することができた。
話は変わるが、2010年夏に韓国・釜山国立大学土木環境学院の金昌元教授から、研究室の学生に研究室を見学させていただけませんかとの申し出があった。折角の機会なので、学生主体のワークショップ(WS)をしませんかと提案し、釜山国立大学と熊本大学との間でWSがスタートした。金教授と情報交換するなかで、偶然にも金教授が大連理工大学の全教授と親交のあることを知り、第3回目のWSからは大連理工大学も加わることになった。その後、北里大学の清和成教授の研究室も加わり、四大学の学生WSに。私が、熊本大学を退職した後は大阪大学の池道彦教授に代わっていただき、2016年7月には、第9回のWSが大阪大学で開催された。今回から山梨大学の森一博研究室も加わり、益々活発なWSに発展しそうで、これも楊先生の取り持つ縁と思っている。
今回紹介したような楊教授のようなキーパーソンとなる研究者と信頼される人間関係を構築することが国際交流では必要となる。いきなりキーパーソンに辿り着くのは難しい。普段の出会いを大切に心のこもった交流を積み重ねることが早道である。
著者紹介 熊本大学顧問・名誉教授、古川水環境コンサルティング株式会社代表取締役
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 11月 2016
生物工学会誌 第94巻 第11号
広常 正人
日本で最近、オープンイノベーションが盛んに取り上げられるようになったのは、2003年のハーバードビジネススクール出版の「Open Innovation」からだそうである。これまでの組織内の研究者だけで技術開発を行い外部に商品を出すClosed Innovationに対し、外部の技術やアイデアを意図的に活用して得られた組織内部の革新技術を外部の新しい市場に向けて商品を出すのがOpen Innovationと定義付けている。
日本の企業のオープンイノベーションへの取組みは、欧米に比べて遅れているといわれている。グローバル企業であるP&G社が、2001年からオープンイノベーションを世界的に展開し、多くの実績を上げていることはよく知られている。日本企業にオープンイノベーションが馴染みにくいのは、独自技術の改善を積み上げて来たという歴史からかもしれない。しかし市場の急激な変化に対応し、また新分野の技術開発をスピードアップするには非常に有効な手段である。
企業のオープンイノベーションとして重要な位置を占めるのは、大学や公的研究機関との共同研究や委託研究である。しかし企業からは、研究が進展しても実用化の段階を迎えると、大学の産学連携本部やTLOといった組織との交渉に時間を取られて商品化が遅れる、といった声を聞くことも多い。技術の商品化のスピード感は、やはり最近注目されている大学発ベンチャー企業が勝っているように思われる。産学連携本部やTLOには大学で研究された技術の、将来の発展を見越した柔軟な対応をお願いしたい。
最近のオープンイノベーションでは、個々の技術を導入するだけでなく、モジュール化あるいは他の技術(たとえばIoT)との組合せによって、従来なかった市場を創造することが求められる。一つの分野の技術に異なる分野の技術を加えることによって、新しい顧客体験が実現でき、新たな市場が形成される。したがって、これからのオープンイノベーションの推進には専門領域を超えた、いわゆる「目利き」が必要とされる。
オープンイノベーションに取り組みにくい理由としてよく言われる企業の自前主義の他に、ニーズを公開すると開発の方向性を同業他社に知られる、その企業の技術開発レベルが明らかになってしまうという問題がある。
以上の課題への対応として、企業に対する非公開(Closed)のオープンイノベーション(Open Innovation)を支援する機関が数年前から各地にでき始めている。筆者は今年度から、その一つである公益財団法人のオープンイノベーション支援事業のお手伝いを行っているが、社名を公開しニーズ情報をWebサイトに掲載する本来の(オープン型)オープンイノベーションよりも、非公開でニーズ情報を支援機関の技術コーディネーターに限定する(クローズ型)オープンイノベーションが増えている。主に大企業のニーズと、中小企業または大学・研究機関のシーズをヒアリングして、マッチングするのが支援機関の技術コーディネーターの役割である。
非公開オープンイノベーションの欠点として、マッチングが技術コーディネーターの知識、経験や人脈に負う部分が大きいことがあげられる。しかし、各支援機関のコーディネーターは、多様な分野の公設試験機関や企業の実績のあるOBで構成されており、さらに各地の機関と連携して広域のマッチングを行うので、製品開発だけでなく新しいビジネスモデルやサービス提供を実現する、これからの日本のオープンイノベーションに適しているのかもしれない。
企業側の技術課題ニーズだけでなく、実用化直前のシーズ技術があれば、各地の経済産業局や公益財団法人のオープンイノベーション・ソリューションサイト(たとえば、大阪産業振興機構:https://www。mydome。jp/open-inv/、関西文化学術研究都市推進機構:https://kri-open-inv.jp/needs/など)で一度、最新のオープンイノベーションを調べてみることをお勧めする。
著者紹介 大関株式会社総合研究所(シニアアドバイザー)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 24 10月 2016
生物工学会誌 第94巻 第10号
根来 誠司
研究に対する価値観は研究者によって異なるが、「新規性・独創性」と「社会貢献」を判断基準にするという点では共通しているであろう。しかし、ここでは見方を少し変え、研究における「個性」という面から考えてみたい。定年を間近に控え、思いがけず、今回、執筆の機会をいただいた。これから研究室を立ち上げる方や、研究者を目指す若い方への提言としてお読みいただければ幸いである。
学生に同じテーマを出しても、その後の発展の経過は、直接、その研究を行った学生の「個性」により、大きく変わる場合がある。実験の上手下手も個性の一つと言えなくもないが、期待した結果が得られなかった時に、その研究を中止するのか、あるいは、新たな方向性を見いだすのかは個人レベルでの判断になる。潜在的に重要な事実を含んでいるにもかかわらず、見過ごされる場合も多い。特にその分野を取り扱う研究者が少ない時には、その研究を行っている本人が気付かなければ、永遠に埋もれたままになる可能性がある。一方、見落としてしまいがちな些細な現象に気付き、その研究を発展させて、人類に大きな福音をもたらす可能性もある。フレミングが、カビが生育したシャーレの周辺でバクテリアの増殖が抑えられるという現象からペニシリンを発見したという話は有名であるが、これは後者の例であろう。
さて、研究テーマは自由に選択できるはずであるが、実際には多くの制約の中で選ばざるを得ない。卒研生としてある研究室に配属されれば、その時に出された数個のテーマから一つを選び、研究活動の第一歩を踏み出すことになる。企業の研究開発では、その制約はより強いと思われる。私事であるが、40年ほど前に、大阪大学・岡田弘輔教授の研究室で卒業研究のテーマとして与えられた課題は、ナイロン工場廃棄物を分解する酵素の一つを精製するというものであった。
当時は、遺伝子工学の黎明期であり、抗体遺伝子の構造など画期的な成果がNature、Science、Cellなどに続々と掲載されていた時期であった。私の場合、卒研テーマとして与えられた酵素の精製がうまくいったことから、大学院では、「微生物の環境適応や酵素進化を理解するためのモデル系」という意味と、「遺伝子工学の研究室への技術導入」という目的から、その酵素の遺伝子組換え実験を始めることになった。その後、同じ研究室で助手・助教授として在籍させていただき、現在の大学に移った後も、テーマを中止する必然性がなかったことから、結果的に現在に至るまで、この流れの研究を続けることになった。研究内容として「立体構造に基づく触媒機構と熱安定化機構の解析」「加水分解酵素の逆反応を利用したアミド合成」「ナイロンポリマーの分解と再資源化を考慮したポリマーの探索」へと展開し、現在、「非天然アミノ酸の代謝工学に関する研究」を始めているが、最初の一歩がその後の研究を方向付けることになった訳である。
環境・エネルギー問題、医用材料・新薬・新機能物質の開発などにおいて、すでに中心的課題として認知されているものについては、多額の競争的資金が投入され、共通の目標に向かって多くの研究グループがしのぎを削っている。この中でも新規性と独創性が重要であることはいうまでもないが、現在注目されている分野は、これを注目させた先人の研究に基づくものである。一歩先んじた研究者は、個人の業績評価のみならず、産業化につながる場合、市場確保の面で優位になるが、その研究者でなくても別の誰かが同時期に成功するとすれば、社会全体から見れば、同等の恩恵を受けたことになる。一方、その研究者がいなければ、その分野が展開できないような研究もある。研究領域が細分化した現在では、独自性の高い題材を見いだすことが困難になりつつあるが、将来を担う研究者には、後者がイノベーションの原点であることを心に留め置いていただきたいと願う。
著者紹介 兵庫県立大学大学院工学研究科応用化学専攻(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 23 9月 2016
生物工学会誌 第94巻 第9号
松井 和彦
「思えば遠くへ来たもんだ」とは、1978年(昭和53年)に発売された武田鉄矢氏が率いる海援隊の楽曲のタイトルである。1980年には同名の映画の公開に合わせて再び発売され、1981年にはテレビドラマ化され、主題曲にもなったので、ノスタルジックなメロディーをご記憶の方も多いのではないかと思う。この曲の中に、「思えば遠くへ来たもんだ この先どこまでゆくのやら」という印象的なフレーズがある。
1981年に味の素(株)に入社以来、35年余の会社生活の中で、何度かこのフレーズが頭の中に浮かんできたことがあった。担当する研究開発テーマが大きく変わり、研究開発の方向性を見いだすべく、七転八倒した後で、また、新たな職場環境に慣れ、新たな役割期待にも応える自信がある程度芽生えてきたころに、あるいは、海外でジョイントベンチャー設立を命じられ、赴任地の生活環境にも慣れ、設立したベンチャー企業の基盤がようやくできあがったころに、「思えば遠くへ来たもんだ この先どこまでゆくのやら」というこのフレーズが頭を過ったものである。これから自分はどこへ向かうのか?と思い悩むのである。今、自分のキャリアを振り返ると、こういう時に新たな道に進むきっかけを与えてくれた人が自分の周囲にいたように思う。進む道の選択には不思議と縁というものがあったような気がする。思いのまま、「随意」とはいかないが、「随縁」、つまり縁に従ってきたのではないかと思う。
「人事を尽くして天命を待つ」ということわざがある。目標に向かって努力をするが、その結果は天にまかせるという意味である。このことわざの順序を逆に変えた「天命を待って人事を尽くす」という山村雄一元大阪大学総長の言葉の方が企業に勤める私には好ましく思える。第6回生物工学産学技術研究会で講師を務めていただいた江崎グリコ(株)の栗木隆氏も同じことを言っておられた。天から与えられた機会をとらえて、それを十二分に活かすように能動的に取り組むということのようだ。企業では研究開発の現場に新人として配属された方が、ずっと研究開発の最前線で活躍し、会社生活を終えるというケースは多くないと思う。ある日突然研究開発以外の部署への異動を命じられ、新たな職場で、これまでのキャリアにない役割期待に応えることが求められることがある。周囲が対象者のキャリアパスを検討したうえでの異動であることは想像に難くないが、自らが期待した通りであるとは限らない。しかしながら天命と捉えることで新たな業務に前向きに取り組めるように思える。
人事を尽くして天命を待つと、どうしても天命を自分の都合の良いように期待してしまう。期待通りにいかないと、自らに原因があったとしても、誰かを恨むことになるかもしれない。大学を卒業後、研究開発の現場で会社生活をスタートし、35年余の間にさまざまな職場や業務を経験させていただいた。思えば遠くへ来たもんだと実感するが、この先どこまでゆくのやらとも思う。新たな天命を待って人事を尽くしたい。
日本生物工学会は生物を研究対象として、実学、知・技の実用化を志す者が集う、切磋琢磨の場であると思う。ここ数年、徐々に年次大会への参加者が増え、また産学官の交流の場が増えてきたように感じる。生物工学産学技術研究会の懇親会で、ある学生の方から、就職活動がうまくいかず落ち込んでいた時に生物工学産学技術研究会に参加して産業界の方と意見交換し、もう一度就職活動に取り組もうという前向きな気持ちになり、幸いにしてその後就職することができたということを聞いた。会員の方々にとって、年次大会や本学会主催のさまざまな交流の場は、情報収集や研究ネットワーク拡大の場としてだけでなく、自らのキャリアを振り返り、新たな道に進むきっかけの場にもなっているのだと思った。本学会を介してさまざまなステークホルダー間の交流が活発になることを期待している。
著者紹介 味の素株式会社(上席理事)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 8月 2016
生物工学会誌 第94巻 第8号
田谷 正仁
皆さんは、実験ノートのデータや論文の図表を眺めながら、あれやこれやと想像を巡らし、それがある程度かたまって仮説となり、新たな具体的アイディアとなっていったという経験をお持ちではないだろうか。筆者は昔からこの想像を巡らすひと時が好きだった。
先日駅構内にある本屋さんをぶらついていたところ、受験シーズンということもあり、各種教科の受験対策本が積まれていた。何となくその中から現代文対策本を手に取りパラパラと頁を繰った途端に、遥か45年以上も昔の記憶がまざまざと蘇った。「本文中の傍線部分について作者の考えとして正しいものを次のから選べ」という設問である。高校生だった筆者は、現代国語の授業中に教科書の文章を題材にして、「作者の気持ちはこうだ」と先生が説明されたのがどうしても納得ができず、教科書の出版社を通じて作者に手紙を書き、自分が感じた「作者の気持ち」と先生の解説とどちらが近いか尋ねたことがある。若気の至りで今思い出すと赤面ものである(ちなみに返事は来なかった)。ただ、今でもこの類の受験問題が出されていることに多少の違和感を覚えた。つまり、ある文章を読んで何を感じるかは個々人で異なって当然であり、極論すれば正解などなくても良いと思うからである。件のような設問は、これから色々なことにチャレンジする若者の自由な発想(想像)を阻害するとさえ思えるのである。
日本には読み手・聞き手の想像をたくましくさせる伝統的な文芸がある。その代表が俳句であろうか。作者の世界がわずか17文字の中に凝縮されているため、読み手側の想像をかき立てる。「古池やかわず飛び込む水の音」―古池の場所は山里か/古刹の裏境内か?季節は(蛙の季語を気にしなければ)夏/秋?時間は昼下がり/夕暮れ時?蛙はガマガエル/トノサマガエル?そもそも飛び込んだのは1匹なのか/複数匹なのか?自分の過去の経験を重ね合わせ、どのような情景を想像してもどれも間違いだとは言えないように思う。一方、聞き手と一体となって物語を創る芸に落語がある。落語家は一人でナレーターから登場人物まですべてを演じなければならないために、細部にわたる描写には限界がある。したがって聞き手の想像に頼る部分がある。名人と言われる落語家ほど聞き手に想像する余地を残し想像を促す間の取り方がうまい。水を打ったようにシーンと静まり返った会場で、聞き手一人ひとりが想像を巡らしているのを確かめているかのようである。同じ演目を聞いても、各人異なった感想をもつことが落語の楽しいところでもある。
浅田次郎氏のエッセイ中で、次のような一文が目に留まった。―小説に限らず、あらゆる文学は人間の想像力を涵養する。そして、想像は創造の母である。近代アカデミズムにおいて、もっとも非生産的な分野にちがいない文学が、他の学問に伍して尊重された理由はこれであろう。人間が文学を非生産的なるものとして軽侮すれば、想像力は衰え、あらゆる文化は新たな創造ができずに停止し、退行する。このごろ問題とされている、「読書ばなれ」の真の弊害は、実はかように重大なものであると思われる(浅田次郎:つばさよつばさ、JALグループ機内誌スカイワード9月号、p. 109–112、2015より)。
氏の言うあらゆる文化の中に科学技術も含まれることは言うまでもない。大学の文系を中心とした学部再編成が取りざたされている昨今、「想像」と「創造」の関係性について考えさせられた。1のものを2に作り上げるのは比較的容易かもしれないが、ゼロから1を生み出すには想像力が必要であろう。皆さん、せいぜい想像に関する感性を磨き創造力を養おうではありませんか。本稿脱稿後、JT生命誌研究館館長の中村桂子先生が想像と創造について同様の話をしておられるのを知り、意を強くした(週刊文春6月16日号、p. 100–114、2016)。
著者紹介 大阪大学大学院基礎工学研究科(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 7月 2016
生物工学会誌 第94巻 第7号
高見澤 一裕
科学技術基本法が成立してから20年が経過し、科学技術基本計画も5期目に入った。これと連動してか、教育基本法と学校教育法が数回改正された。大学は、人材養成に加えて、社会との関わりをより強くすることを要求されるようになった。さて、この間、大学と社会との関わりはどのように変化したのか、産官学連携データ集2014–2015を中心に調べた。大学発ベンチャー数は、2246社でここ数年は漸増である。2003–2006年度では毎年200–250社が設立されたが、2010–2013年度では毎年47–69社しか作られていない。ベンチャー設立の機運はしぼんでいる。特許権実施収入は約22億円、特許出願件数は約9300件である。仮に特許権実施収入が売り上げの1%とすると、日本の大学全体で2200億円の経済効果を上げたことになる。
アメリカではスタンフォード大学やマサチューセッツ工科大学のように1大学で年間50億円を超える特許権実施収入がある大学が多くあり、国全体での大学の特許収入は2000億円を超えるといわれている。同様に計算すると経済効果は20兆円である。ところで、特許取得総件数の国別ランキングでは日本が34万3484件で、2位のアメリカ(22万8918件)に大差をつけてトップとなっている。民間企業を見習って大学にも頑張ってもらい、科学技術立国を実現したいと考える向きが多いのであろう。科学技術立国日本と叫ばれてからかなりの年数が経過している。2016年度からの第5期科学技術基本計画では、未来の産業創造という目標が入った。
私は、2003–2004年の大学発ベンチャー設立を社会的に強く要求された時期に、バイオレメディエーションを正しく普及するための組織を学内の同僚とともに、NPO法人岐阜大学環境技術研究会として立ち上げた。そして、その実施母体として株式会社コンティグ・アイに参画し、一つの事業部門を作った。関連特許を7件出願して、DNAマイクロアレイによる塩素化ハロゲン分解菌数の計測、添加栄養物の決定、地下水流動解析に基づく栄養物の注入位置の設計を主として事業展開を行った。幸い、当初は順調に業務展開でき、数名ではあるが新規雇用につなげることもできた。
しかし、10年も経過すると、社会情勢が変わり、さらに、まったく別の観点からの新たな技術開発も加わって、事業を維持することで精一杯である。第2の柱として、ソフトバイオマスからのバイオエタノール生産の業務を始めているが、なかなか社会情勢が伴わない。次に、プールやスーパー銭湯の新たな殺菌方法を開発して事業展開している。このように3本の柱を軸に社会貢献しているが、実情は、かろうじて維持できているということである。次々と新たな事業展開をしないと雇用は維持できない。教授兼社長ではなく、実務の先頭に立つことはないが、大学発ベンチャーの限界も感じている。技術には賞味期限・消費期限があり、ベンチャーにも賞味期限がありそうだ。
ところで、科学技術基本法が成立してからの人口当たり全分野の国別論文数を調べると、日本は、2014年は37位で1982年の12位からだんだん低下している。同様に全論文数も伸びず、漸減している。特許出願数の増加や特許権実施収入の増加と相反する現象である。単純に、社会実装を大学に求められるようになって論文数が減ったとは考えにくいが、気に留めておく必要のある事実である。科学技術基本計画では、大学には、極端に言えば、ノーベル賞級の研究成果を上げ、特許権実施収入でも数十億から数百億円を稼ぎ、ベンチャーのエンゼルになるようなスーパー教授を輩出することが望まれているようだ。しかし、これはあまり現実的ではなく、大学では、専門分野と研究者に応じた時間軸で基礎研究と応用研究に邁進し、その成果を主として人材育成に還元することが基本である。急がば回れ、大志を持った優れた人材の活躍によって社会が発展する。
著者紹介 岐阜大学名誉教授、放送大学岐阜学習センター客員教授、愛知文教女子短期大学非常勤講師、
NPO法人岐阜大学環境技術研究会副理事長、株式会社コンティグ・アイ取締役
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 24 6月 2016
生物工学会誌 第94巻 第6号
水光 正仁
今年の3月で定年退職を迎えることになり、最終講義を行った時、今までの研究を振り返ることになった。講義のタイトルを「基盤研究から国際共同研究そして地域創生研究へ」とした。ある若手の先生からは、私に対して「先生は世話焼き人生を送ってこられたから、そのやり方を教えてほしい」とリクエストがあった。
科研費(基盤研究)の申請、採択、活用を通じての「世話焼き」を紹介したい。思い起こすと、宮崎大学赴任当時から、常に科研費を意識し、年の初めの1月には、1年間の論文投稿の計を立てて、必ず9月までに掲載またはアクセプトにもって行くようにし、最新年度の論文をより多く見せることに努めてきた。また、申請書は、必ず身近な研究者に読んでもらうようにし、さらに研究室の学生にも読んでもらった。時々学生のシビアな指摘に肝を冷やしたことも思い出した。言われればなるほどという経験も数多くした。結果的に、ほぼ毎年何らかの科研費を獲得することができた。その科研費で購入する機器などは、私以外の人も利用できるものとすることに徹した。実は、これが研究室や周りの研究者とうまくやる「世話焼き人生」のスタートだったかもしれない。
国際共同研究に関しては、留学した際のボスであるロックフェラー大学ノーベル賞学者Lipmann教授とポスドクであったLiu博士(現、オハイオ州トレド大学薬学部教授)との出会いがきっかけとなった。実は、Lipmann教授が亡くなる前、ノーベル賞受賞金で購入されたニューヨーク近くの山荘で、「今後は水光とLiu博士は共同で「硫酸化」の研究をしてくれ」とお願いされ、その後すぐに亡くなられたので、それが、遺言となった。私達は、そのことを忠実に守り、30年間、国際共同研究を続けている。夏になると、学生を連れて、Liu博士のいるオクラホマ大学、テキサス大学そして現在のトレド大学へ行き実験を行い、また、ビールを飲みながら将来の研究計画を語ってきた。米国へ連れて行った学生は23名にもなっていた。これらの実績が、文部科学省主催の「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」へとつながり、今も活発に研究を展開している。
地域創生研究に関しては、まず、基盤研究の応用として宮崎県、企業と連携し大型研究プロジェクトを立ち上げた。2004年、JST主催の「宮崎県地域結集型共同研究」(食の機能を中心としたがん予防基盤技術創出)に採択され、5年間13億円の研究費を頂いた。今まで、購入できなかった遺伝子、タンパク質解析機器そして生理活性物質分離装置が、地方の宮崎に入り、100名もの地域の研究者の基盤技術を構築した。
南九州の風土病といわれるウイルス性の成人T細胞白血病(ATL)とC型肝炎ウイルスによる肝臓がんの発症機構解明と食による予防技術の開発を行った。特に、ただ1度の実験で、10項目の食品の機能性を推定する技術開発は、きわめて優れた成果となった。その推定実験から、ブルーベリー葉の熱水抽出物に両ウイルス原因病に対して予防効果を確認し、その活性物質も特定できた。この研究は、農学と医学そして工学分野が連携した、世の中に貢献する究極の研究であったと思っている。また、食の安心・安全を目指し、宮崎県と連携した農産物の残留農薬分析を基盤技術とした「(一般社団法人)食の安全分析センター」の設置も地域に貢献する事業となった。
これらの一連の研究は、研究技術はもとより、研究管理技術の能力が要求され、人の輪が最終的にもっとも重要であることも勉強した。さて、研究室の整理をしていると、懐かしい本・文献が山ほど出てきた。つい内容を読んでしまい、クラシックな技術も重要、そして最先端の技術はなお重要であることを感じた。多くの卒業生の知の結集は、卒業論文、修士論文そして博士論文となっている。これだけは、捨てられないでいる。
がむしゃらにやってきた36年間の大学での研究生活は、あっという間に過ぎて、まだまだやり残したことは多くあるが、次の世代に任せたい。次の世代の人たちも、研究を面白がってやって頂きたい。好奇心とは、すべてを発展させる原動力である。社会に送り出した多くの卒業生の活躍と学会などでできた多くの友人のご活躍を祈って筆を置きたい。
著者紹介 宮崎大学理事・副学長(研究・企画担当)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 5月 2016
生物工学会誌 第94巻 第5号
勝亦 瞭一
周知のように、大村智先生が他2名とともに2015年度ノーベル生理医学賞を受賞されました。受賞業績は放線菌起源の抗寄生虫薬イベルメクチンの開発ということです。この研究は生物工学会のテリトリーである発酵学・応用微生物学分野に属するものであり、我が国の当該分野の研究者にとって大きな喜びであり、若手研究者には大きな励みとなりましょう。発酵学分野では、1945年にペニシリンの発見者たちが初めて受賞してから70年ぶりということですが、1952年のストレプトマイシンの発見者の受賞を合わせると、この分野から3件が受賞したことになります。
一方、この同じ期間に、微生物を研究題材として生命真理の解明に寄与した基礎科学の業績での受賞は十数件ほどではないかと思います。発酵学が有力な科学であることを再認識させられます。上記の三つの受賞研究は、探索研究、すなわち自然界の微生物を探索して所望の生理活性物質を生産する微生物を見つけ出すことによって成果を収めたものです。1980年代以降も日本で行われた探索研究によって、コレステロール合成阻害剤スタチンや免疫抑制剤タクロリムスなどの医薬が開発されており、探索研究がいかに価値あるものであるかを教えられます。大村先生は、「探索研究に駆り立たせるのはロジックではなく、こういうモノを見つけたいというロマンだ」というようなことを述べておられます。
我が国発の発酵学の金字塔として知られるグルタミン酸発酵が、1950年代後期に協和発酵(現協和発酵キリン)の研究者たちによって開発されたのをご存じの方も多いかと思います。初めてアミノ酸発酵という分野を切り開いたこの研究も、自然界を探索し、有望な生産菌(Corynebacterium glutamicum)を分離することによって生まれたものです。私は、その開発グループのリーダーであった故木下祝郎博士からグルタミン酸発酵の開発経緯を詳細にうかがっています。その当時、微生物がアミノ酸を細胞外に大量に産生するなどという知見はなく、「そんなことは微生物にとって自殺行為だから起こるはずがない」というのが一般常識とされていたのですが、「変わり者の微生物もおるかもしれない」と考えて探索を行い、非常に短期間のうちに生産菌を見いだしたということです。続いて実業化されたリジン発酵は、グルタミン酸生産菌からいろんな栄養要求性変異株を誘導し、その中からリジン生産株を探し出すことによって開発されたものです。
今日、教科書にはリジン生合成の代謝調節機構がわかりやすく図解されていますが、それは生産株を解析して後からわかったことです。ロジックより先に目標技術ができていたわけです。アミノ酸発酵もロジックではなくロマンによってもたらされたものであるといえます。
発酵産業は社会に提供する有用物質を徐々に増やしながら発展してきました。その発展は探索研究の成果に支えられてきたのではないかと思います。しかしながら、近年の発酵学の研究をみると、ゲノム情報や遺伝子技術を使った微生物細胞の機能解析や既存物質の組換え生産菌の作製などに多くの力が注がれており、そこから新しい産業シードが出てくるのは期待し難いように感じます。それを期待できる探索研究は少なくなっており、発酵産業はこの先伸びるのだろうか不安を覚えます。探索研究はリスキーとみられがちですが、一概にそうともいえないのではないでしょうか。前述のようにグルタミン酸生産菌はごく短期間に取得されています。また、上記のスタチン生産菌やタクロリムス生産菌は約6,000~10,000株の微生物を探索して得られたといいます。決してリスキーではないように思えます。
今一度、底知れぬ微生物の潜在機能を発掘する探索研究に目を向けるべきではないでしょうか。発酵学・応用微生物学と発酵産業のさらなる発展のために!
著者紹介 東北大学名誉教授
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 4月 2016
生物工学会誌第94巻 第4号
土戸 哲明
北里大学大村智先生の地道な微生物からの探索研究によって発見された化合物が、企業の協力を得て薬となり、アフリカの多くの人々を失明から救うという偉業が評価され、2015年のノーベル医学・生理学賞が授与されました。このニュースは、微生物やバイオテクノロジーに携わる科学者・技術者はもちろん、広く日本国民のみなさんに喜びと夢をもたらしました。
ところで、バイオテクノロジー、ここでは単にバイオとしますが、これには工学系でいわれる生産や製造に関わる、「ものづくり」バイオのほかに、安全や保全を目指す「ものまもり」バイオがあると思います。ここで言う「もの」を広い意味にとり、材料・製品や構造物など姿形のあるものだけでなく、環境や健康、人命なども含めるとすると、「ものづくり」と「ものまもり」とはつながったり、部分的にオーバーラップすることになります。たとえば、大村先生らが成し遂げられた研究は、微生物を利用した「ものづくり」によって健康を、さらには人命を守る「ものまもり」バイオでもあるといえるでしょう。しかし、生産・製造業界での用語としての「ものづくり」における「もの」は、通常、物理的に構造や形態のあるものと解釈されています。そもそもバイオテクノロジーという用語は生物を利用する技術を意味し、その利用の手段となる生物は当然、人にとって有用な生物です。
一方、ここで言う「ものまもり」バイオで対象となる「もの」を「ものづくり」と同様なものとし、それを何から守るのかを考えると、それは人にとって有害な生物と言えます。「ものまもり」バイオは、人類の生活や産業活動における有害生物による被害の防止、保全を図ることをミッションとする分野といえるでしょう。つまり、「ものづくり」バイオは有用生物による利用生物工学に、そして「ものまもり」バイオは有害生物を対象とする制御生物工学(ここでの制御の用語は抑制と同義です)に含まれるといえます(これら2つの生物工学の概念はかつて本誌〔77巻、p. 224、1999年〕に紹介したことがあり、当初はpositiveとnegativeとしていましたが、その後それぞれutilizationとcontrolに変更しています)。
「ものまもり」での作用要因の対象を生物に限らず広くとった場合には、自然の力や人的な要因によって発生する劣化や破壊、価値の低下などの変化、またそれが甚大な影響をもたらす事故や災害などの物理的・化学的作用も含まれることになります。私たち日本人が今まで当たり前のように思いがちな「ものまもり」への認識は、あの3.11の東日本大震災とその後の原子力発電所事故を境に大きく変化したように思います。今や世界的にテロ事件が多発し、国内でも食品や医療、建築や工業製品などで安全にかかわる問題が頻発しています。安全・安心の重要性は、いろいろな分野でますます強く認識されるようになってきています。
筆者は「ものまもり」バイオの立場から、基礎研究をベースに食品、医療、環境、工業材料や文化財の保全・保存の研究に従事してきていますが、医療や環境での衛生分野だけでなく、生産・製造業界においても企業の方々とお話する中で微生物学的安全性に直結する製品の品質保証や工程管理など、有害微生物に対する汚染の対策とそのシステム、リスクアセスメントなど、ここで言う制御生物工学の諸問題への意識の高まりを感じます。またそれとともに、そのミッションを担う人材の育成の必要性を感じます。バイオの中ではごく小さい分野ながら、一見単純そうに見えて実は奥の深い、生物の生死に関わる難問にチャレンジし、これらのニーズに応えて世の中の安全・安心に貢献できる「ものまもり」バイオを目指す若人が、一人でも多く現れてくることを期待したいと思います。
著者紹介 関西大学名誉教授・大阪府立大学21世紀科学研究機構微生物制御研究センター(客員教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 3月 2016
生物工学会誌 第94巻 第3号
芳本 忠
北里大学特別栄誉教授大村智博士のノーベル医学生理学賞受賞は、日本の生命科学関係では、利根川進博士、下村脩博士、山中伸弥博士の受賞に続く快挙である。特に抗生物質の研究であり、生物工学会の会員には身近な分野である。
ところで、私は40年ほど前、大阪市立大学理学部の微生物酵素研究室(福本寿一郎教授)で学部、修士課程を修了し、短い期間であったが製薬会社に勤務した。開発能力が高いとして知られる会社で、薬の開発現場を見ることができたことは、以後の私の教育研究に非常にプラスとなった。恩師の鶴大典先生が長崎大学薬学部の教授として赴任され、私も講師としてお供した。当時は、それまでの化学一辺倒だった薬学教育と研究において生物学の必要性が高まった頃であった。微生物酵素の研究から始め、鶴先生のご定年退職後、後任となり研究を続けた。奈良の土壌から得たP. putidaの酵素による腎機能診断キットは日本中の健康診断に用いられ、DPP4酵素の研究はそれまで治療薬のなかった2型糖尿病の治療薬(グリプチン)の開発に役立った。
一方、医療の世界では、1980年代、医師の医療ミス(薬剤誤投与)が続き、薬剤師の役割が問題になった。世界の薬学教育は6年制で薬剤師を養成するのに対し、日本だけが、明治以来4年制で創薬に重点を置いた教育であった。薬学部長になりこの問題に直面した。私は理学出身であり、薬学の創薬研究の環境は居心地良いものである。しかし、薬学部はやはり職能教育として薬剤師の教育が必要で、医師とともに医療に携る役割の重要性を感じ、修士課程に臨床薬学独立専攻を設置し4 + 2の薬剤師教育の場を作った。これが後に現在の6年制の薬剤師教育となっている。自分の首を絞める結果となったが、これでよかったと思っている。
以上、私の経歴を書いたのは、本会の会員には薬学の関係者が少なく、薬学教育の変遷と現状を知っていただくためである。大村先生のノーベル賞受賞はまさに創薬研究での成果で、多くの人々を寄生虫感染による失明から救ったことによる。戦後、抗生物質の医療への役割は大きく、各製薬会社こぞって抗生物質を求めたが、私が会社に入った1970年頃はすでに放線菌をスクリーニングしても既知物質ばかりで、古典的な方法として開発から撤退する企業が多かった。むしろ、化学的方法で誘導体を合成するとか、最近では遺伝子組換えや構造生物学に目が行き、大学でも学生がスクリーニングや培養液からの精製などを、泥臭いとしていやがる傾向になっている。そのなかで微生物生産物のスクリーニングを続けられた大村先生を心から賞賛したい。
同様に、微生物からの新規化合物の発見は、放線菌からの免疫抑制剤・タクロリムス(FK506)(藤沢製薬)や、カビからの抗コレステロール剤・スタチン(第一三共)など日本発のビッグドラッグとなっている。薬学の先生には申し訳ないが、これら発見者は薬学以外の生命科学系の研究者である。もはや薬は薬学と考えず、多くの本会員の創薬研究が望まれる。簡単ではないが、ヒトが病気で苦しむのを救えるのは素晴らしいことである。生物工学会のシンポジウムや学会発表で創薬の話がもっと出てきても良いように思われる。
長崎大学薬学部を定年退職した後、摂南大学の理工学部に生命科学科を立ち上げた。理学としてバイオの基礎研究と理工学部としての応用が目的で、食品、環境に加え創薬もポリシーに入っている。若い教員が多い構成で活発な研究が行われているが、私はあえてローテクの研究を選んだ(与えられた期間が短いとは言い訳で、最先端の技術についていけないのが正直なところである)。移ってからの研究で、歯周病菌のキー酵素となるプロリルトリペプチジルペプチダーゼ(PTP)の阻害剤を米糠に見いだし、鹿児島での生物工学会大会で発表した。ターゲットを工夫すれば、まだまだ知られていない有用物質が天然に存在すると感じている。ついつい、講義で「人真似でない独自の研究が重要である」との話をまたくり返している自分に気付き、年を取ったと感じるこの頃である。
著者紹介 摂南大学理工学部生命科学科(教授)、長崎大学薬学部(名誉教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 2月 2016
生物工学会誌 第94巻 第2号
福田 秀樹
日本生物工学会80年史に記述されている名称変遷の歴史をみると、大正12年(1923年)に大阪高等工業学校醸造科の醸造会を源流として発足された「大阪醸造学会」が設立されて以降、醸造、発酵の分野に生物化学工学という新しい研究を取り入れるため、昭和37年(1962年)に「日本醗酵工学会」へと改組改名されたとされている。さらに平成4年(1992年)には、微生物に加えて広く動植物をも取り扱う学会として成長発展することを期して「日本生物工学会」と改称され、学問領域の拡大に伴って学会は大きく変貌をとげ発展してきた。現在の学問領域は、発酵工学、生物化学工学、生体情報工学、環境工学、酵素工学、動植物細胞工学、生体医用工学となっており、生物科学分野の基礎学問の発展と工学や医学などの学問分野との連携によって育まれる学際分野への展開に大きく寄与している。
さて、最近の国立大学法人においては、さまざまな議論をベースに「大学の機能強化」が強く求められ、各国立大学法人は特徴のある改革を推進している。神戸大学は、明治35年(1902年)創立以来の理念である「学理と実際の調和」を実践するため、新たな学際分野の創出とそれらによって生み出される成果の社会への普及を図るため、分野横断型組織を積極的かつ戦略的に構築してきた。
平成19年(2007年)には、理学、工学、農学、海事科学の4部局から構成される大学院自然科学研究科をそれぞれ独立した研究科組織に再編成すると同時に学際分野を発展させるため、選抜された戦略的研究チームが核となって構成される「自然科学系先端融合研究環」を設置した。本研究環は、学際性と総合性の調和を考慮した教育研究を推進する組織である。
学長に就任して以来、平成23年(2011年)には、人文・人間科学系、自然科学系、社会科学系、生命・医学系の分野に所属する教員メンバーにより構成される「統合研究拠点」を神戸ポートアイランド地区に設置し分野横断型の先端的融合研究の推進を図った。本拠点では、バイオリファイナリーや先端膜工学のグリーンイノベーション分野、創薬や健康学のライフイノベーション分野、惑星科学や宇宙開発のフロンティア分野、そして計算科学分野に係わる総計10チームによる先端融合研究プロジェクトを発足させた。
そして、平成24年(2012年)には、経済、経営、法学などの分野に所属する社会科学系5部局の教員メンバーから構成される「社会科学系教育研究府」を設置した。本教育研究府は、学際的理論研究だけでなく産学連携で事業創造に関連した研究や臨床型のフィールド研究も行う実践型の教育研究を実施する組織である。
このようなさまざまな分野横断型組織においては、異分野の研究者間でのコミュニケーションが促進され学際領域における研究成果が数多く創出されている。
ところで、近年我が国ではエネルギー問題や地球環境問題などグローバルな難題を克服し日本の国際競争力を高めるために、科学技術イノベーションを自ら創出できる力を持った理系人材の育成が急務とされている。このような社会的ニーズに対し、神戸大学では経済学、経営学、法学などの社会科学分野と医学、工学、農学、理学、システム情報学など自然科学分野の構成員が一体となった「科学技術イノベーション研究科」を設置することとした(平成28年度設置予定)。本研究科は、神戸大学がフラッグシップ研究と位置づける重点4分野(バイオプロダクション、先端膜工学、先端IT、先端医療学)と事業創造に焦点を当てたアントレプレナーシップとの融合による日本初の文理融合型の独立大学院であり、産業界のさまざまな分野から求められているイノベーションを推進するリーダーとして活躍できる理系人材の養成を主眼にしている。
このように、学問の深化と領域の拡大を促す新たな学際領域の構築は、組織基盤の強化につながるものと思われる。
著者紹介 神戸大学名誉教授
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 1月 2016
生物工学会誌 第94巻 1号掲載
五味 勝也
私が会長を拝命してからほぼ半年が過ぎました。その間の10月末に鹿児島で開催された年次大会では、過去最高の一般発表数と参加者数を数えました。天候にも恵まれ成功裡というよりも、大成功のうちに終了しました。私の力が及ぶところではないとは言え、本当に嬉しい限りでした。大会を企画し、滞りなく開催運営に当たられた九州支部の会員の皆様方と、特にご苦労の多かった鹿児島大学をはじめとする地元の皆様方には心より御礼申し上げる次第です。申すまでもなく、年次大会は学会のもっとも重要な活動の一つです。大会が多くの会員の参加を得て盛況に行われることは、私たち本部役員一同、強く望んでいることです。しかし、実際に開催運営するとなると、担当いただく支部の皆様のご努力に頼らざるを得ない状況にあります。
今回の大会に関しては、開催地が各地からの交通の便に必ずしも恵まれているわけではなく、私の場合でも、自分が住んでいる仙台から鹿児島までの直行便がありませんでした。また、企業の採用選考開始が半年ほど遅くなり、もっとも成果が出始める修士2年の学生が、学会要旨の申込時期に、就職活動に時間を費やさざるを得ませんでした(私の研究室でも修士2年の発表はありませんでした)。これらの要因が発表数にどのような影響を及ぼすのか、少し不安に思っておりました。しかし、いざふたを開けてみれば、このような不安はまったくの杞憂に終わりました。大会の成功はひとえに会員の皆様方の学会へのご協力の賜物と感謝申し上げる次第です。
さて、大会の成功を喜んでいるばかりではなく、会長として大会や学会運営の将来像も考えておくことが必要と感じております。ここ数年の年次大会では、一般講演はポスター発表で行われていますが、この発表形式については会員の皆様にも賛否両論あるかと思います。国内外の学会では、ポスター発表が一般的になってきていますが、学生のプレゼンテーション能力の向上など、教育的な面を考えると口頭発表という形式も重要です。口頭発表は受動的で聴いているだけで、内容が理解できるという利点があります。その一方で、発表が一過性で、聞き漏らしや不十分な理解につながる恐れもあります。また、質疑応答時間が限られていることや、質問があまり多く出ないケースもあり、必ずしも十分な討議が行えていないこともあると思います。一方、ポスター発表では、参加者が積極的に内容を読み込む必要がありますが、詳細なデータをじっくり検討することができます。また、発表者との緊密な質疑応答が可能であるなどの利点もあります。実際に学生に大会での発表を勧めると、ポスター発表を好む傾向があります。したがって、年次大会でポスター発表の形式をとることは、発表数増加の一因になっているかと思います。大会での発表数、ひいては参加者数の増加は、学会の財政事情も考えると重要な点であります。このようなポスター発表の利点を活かしていくことは大事だと思いますが、口頭発表の良さも活かせていける方策があると良いと思っています。発表数が800件を超すという中規模以上の大会に発展してきた中では難しいのかもしれませんが、学生などの若手研究者を対象にし、いくつかのトピックスをショートトークのような形式で発表してもらうという方法も検討する価値があるのかもしれません。
今回の大会では、主には学生かと思いますが、多くの若手研究者からの発表がなされました。ここ数年の会員数の推移をみると、学生会員数がやや増加する一方で、正会員数はやや減少傾向にあるように見受けられます。学生に限られるわけではありませんが、大会で発表するだけのために会員になるのではなく、会員としてのメリットを感じてもらえる、会員になって良かったと思えるような学会の在り方を考えていくことが重要だと思っています。これは本学会に限られたことではなく、簡単にできることでもありません。会員の皆様のニーズをしっかり把握し、少しでもそのよう学会の方向性が見いだせれば嬉しいと、今回の大会の盛況ぶりを見ながら感じた次第です。
著者紹介 東北大学大学院農学研究科(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 24 12月 2015
生物工学会誌 第93巻 第12号
中西 一弘
今から四十数年前の学生の時、筆者は、京都大学工学部で触媒反応工学の研究に携わっていた。この頃、すでに大学のポストを見つけることは難しかったが、幸運にも農学部食品工学科の農産製造学研究室の助手として採用された。実質的に新設の研究室であったので、研究テーマを探すことから始めたが、長年にわたり試行錯誤の日々が続いた。ようやく、研究が軌道に乗り始めたころに、岡山大学工学部に新設された生物応用工学科の教授として赴任したが、一期生がまだ2年生であり、学科の建物ができるまで3年近く待たねばならなかった。ここでも本格的に研究できるようになるまでに随分年月が経過した。
二つの新設の研究室で苦労したことは、研究者であれば誰しも同じではあるが、研究テーマと研究費である。筆者が助手のときには自由に申請できる研究費は科研費のみであった。現在では、さまざまな競争的資金制度や民間の助成金制度が利用できるので隔世の感がする。研究費の面からは、昔よりはるかに研究しやすい環境になっている。一方、教育やいわゆる雑用に取られる時間が増え、研究時間が減っていることも事実である。特に、雑用に対する取組み方を工夫して、研究に必要な時間を確保することが求められる。
さて、研究は、ナンバーワンを目指す研究とオンリーワンを目指す研究に大別される。ナンバーワン研究では、同じ分野で多くの研究者が競って頂点を目指す。通常、多額の研究費が使われる。オンリーワン研究では、それまでは注目されていなかった分野で独創的な研究に挑む。研究テーマ選択の自由度は高いが、リスクは大きいと言える。ただし、ナンバーワン研究でも、その過程では新規性を追求する必要があることは言うまでもない。どちらがよいかは研究者の置かれている立場や考え方により異なる。
上述した事情などにより、筆者は、一貫してオンリーワン研究を志向した。しかし、通常、オンリーワン研究の糸口を探すことは簡単ではない。文献調査、学会・シンポジウム、研究者との交流、あるいは企業との共同研究などを通して得られるさまざまな情報に基づいて納得がいくまで考え抜くことが肝要である。一方、研究室で得られた実験結果、特に、当初の予想とは異なる結果からオンリーワン研究が生まれる場合もある。さらに、同じ研究室に留まるのではなく、機会があれば複数の研究室を経験することもよい。
筆者の場合は、助手のときに留学したミュンヘン工科大学で行った研究が、オンリーワン研究の糸口の一つになった。雑用がまったくない環境で、自分の思うように研究を行えたことは幸運であった。与えられた研究テーマは、スキムミルクの濃縮に使用した限外ろ過膜の水洗浄速度の解析という食品工学分野のテーマであった。初めての分野の研究であったが、最終的に、膜面上に付着しているタンパク質の構造・状態が、洗浄速度に支配的な影響を及ぼすことを示し、一段落をつけることができた。本研究の過程で、付着あるいは相互作用が関与する事象に興味を抱くようになった。このような体験が糸口となって、後日、微生物菌体懸濁液のろ過、糸状菌の膜面液体培養、さらには、物質の固体表面への吸着・脱離現象、有機溶媒系での固定化酵素反応、相互作用を伴う酵素反応、配向制御固定化など多くのオンリーワン研究が生まれた。いずれのテーマにも共通するキーワードは付着・相互作用である。
オンリーワン研究も自己満足で終わるのではなく、学会などで認められると喜びも一入である。筆者の場合、当時はオンリーワンを目指した研究を行っていると自負していたが、今、振り返ると、本物のオンリーワン研究を行っていたと言えるのかどうか、ニッチな分野の研究を行っていただけではないのかと思うことがしばしばである。本会の特に若手の会員諸氏には、本物のオンリーワン研究に挑んで、功をなしていただければと期待しております。
著者紹介 中部大学応用生物学部(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 11月 2015
生物工学会誌 第93巻 第11号
菅 健一
1960年代、我が国の高度経済成長に伴って発生した深刻な公害問題、この危機を克服した技術、さらに1990年代に入り、地球規模での環境保護で大きな課題になっている地球温暖化、その原因と考えられる温室効果ガスの削減など、我々が得た経験や技術を発展途上国に広く導入できれば、地球の環境破壊を最小限に抑えることができるかもしれません。このことを踏まえて、日本が経験した公害の歴史とその対策を振り返ってみたいと思います。
戦後70年という言葉が新聞紙上を賑わしていますが、敗戦から10年足らずの1956年(昭和31年)、政府は高度経済成長を促進させるため、四日市に石油コンビナートを建設し、さらに全国に同様のコンビナートを建設するなど、経済の飛躍的な成長政策を打ち出しました。昭和33年度版科学技術白書によれば、この当時、日本は先進国から科学技術を輸入して近代化を図ることに汲々とし十分な研究能力を持つ余裕がなかったようです。また、これらの技術には排ガスや排水処理に対する考慮がなされていなかったため、1960年代、各地で大気汚染、水俣病、イタイイタイ病などのいわゆる公害が発生することとなりました。当時はまだ公害の深刻さに対する政府の認識が甘かったこと、さらに、日本の国際競争力が弱かったこともあって、公害対策に力を入れれば、経済の発展が立ち遅れるという考えがあったといわれています。
しかし、高度経済成長の中、各地の公害問題の発生に加えて、自動車の排ガス、光化学スモッグ、河川、湖沼、湾岸地域などの水質汚染などが発生して、国も本格的に公害対策を講じる必要が生じるようになりました。こうして、1970年のいわゆる公害国会で公害防止のための法律、公害対策基本法が成立し、さらに、1971年、公害対策本部に代わって環境庁を設立させ、本格的に環境問題に取り組む体制が誕生しました。大学関係の研究者の間でも環境問題解決に向けて関心が高まり、公害関連問題をいろいろな角度から総合的に研究するため1970年代に「科学研究費補助金特定研究」という共同プロジェクトが発足しました。私どもも市川邦介教授、前田嘉道先生(現・姫路工大名誉教授)の下、東京大学農学部有馬啓教授を研究代表者として1974年に発足した「微生物による環境浄化」という特定研究に参加しました。本研究室では富栄養化の原因となる窒素、リンの除去について研究しました。このころ環境問題の持つ総合科学的な性格と、対象とする分野の広がりから、その解決のために新たな科学を構築することが必要という認識も生まれ、環境問題に対する科研費はその後「環境科学特別研究」として1977年から10年間続き、全国の大学の研究室が参加し、既存の学問領域を越えて環境科学を体系づけることとなりました。
日本ではこのような公害に対する取組みによって、大気中の二酸化硫黄の濃度については大幅に改善がなされ、水質汚濁についても有害物質濃度は環境基準を達成するようになっています。このように日本は70年代においてさまざまな公害に悩まされましたが、その経験から、現在では高いレベルの汚染防止技術が築かれました。
一方、1980年後半から人間の社会、経済活動によって増加した地球上の温室効果ガスによって、平均気温が上がり、海水面が上昇、生態系の変化が生じるという温暖化問題が生じてきました。地球温暖化は人類の生存基盤を直接脅しかねない問題であり、早急な対策が必要であります。この問題は先進国と開発途上国の双方がともに取り組むべき問題でありますが、途上国においては、高度経済成長に伴う大気汚染や水質汚濁などの深刻な環境汚染問題を抱えているため、地球温暖化と環境汚染対策を同時に行うことは困難です。公害対策先進国である日本はこれまで獲得してきた技術やノウハウ、さらには新しい省エネ技術やバイオ技術を活用して、途上国を技術支援し、世界全体の温室効果ガス削減に益々貢献して欲しいものです。
著者紹介 大阪大学名誉教授
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 02 11月 2015
生物工学会誌 第93巻 第10号
浅野 泰久
講演会に付随したパネルディスカッションに何度か出演させていただいたことがある。あらかじめ、座長と大まかな到達点について話し合うのだが、傍から思うほどはっきりと結論を決めて臨むものではなく、ありとあらゆる発言が可能なアドリブの世界である。滔々と自分の意見をうまく述べる演者もあり、また予想しなかったような発言もあって、異なった方向に展開していく場合もある。全体の意見を踏まえ、その流れに沿うように、また自分からの新しい視点を入れるように、瞬時に協調点などを探って発言しなければならず、表現に慣れていない者は大変冷や汗をかくものである。自己の発言記録を読むと、論理が整然とせず紆余曲折しているなど、記録とするには大幅に修正を要することが多い。このように、パネルディスカッションは、研究と似ていて、瞬間のきっかけで局面が展開する芸のようにも思える。
数年前、アメリカで開催された産業用酵素の講演会で、私は、各国における酵素の産業利用についてのパネルディスカッション要員として乞われて壇上に上がった。テーマ以外の打ち合わせはまったくなかった。外国人として口下手は当然なので、ある種の気楽さもあったが、まったく準備がない状況で窮地に陥り、最後の瞬間に自分が思いついた話題は、以下のようなものだった。
「私は幸運にも比較的長く研究に従事する機会を得ました。発見・発明について言えば、たとえば1000の発明をして特許を取ったとしても、3つさえ産業化のきっかけにもならないそうだ。日本の酵素応用技術が世界を先導してきたことは周知のとおりである。そのプロセスの多くは、発見を伴った発明であったことに気づいて欲しい。発明だけしようとしてもコピーになることが多いのではないか。発見についてたとえ話をさせていただきます。発明に先立つMr.発見君は、いわばものすごいスピードで駆け抜けてゆくので、彼が通る瞬間は、普通の人間はほとんどわからないそうです。彼を見た人は少ないが、前髪だけに毛が生えているが、頭の後ろはのっぺらぼうであり、とても変わった姿であるらしい。人間は発見・発明をしようといつも待ち構えており、彼を捕まえようとするのだが、なかなか捕まえられない。なぜなら彼が駆け抜けた後に彼を捕まえようとしても、後頭部がのっぺらぼうだから、つるりと逃げられてしまうのだ。まれに捕まえることができるのは、彼が真正面から走ってきたときであり、そのときだけ前髪をがっちり捕まえることができるのである。」会場は大爆笑となり、この短いスピーチで難を切り抜けた。実は、これは私が在籍した(財)相模中央化学研究所に伝えられていた、有機化学上の発見に関する怪談の一つであった(注)。
豊富な自然の中で遊びながら育った私が、実験科学に魅せられ大きく研究の方向に進路を転換させていただいたのは、有機化学を専門とする研究室で卒業研究の機会を得た時のことである。さらに、大学院では応用微生物学を専門とする研究室に所属し、ご指導をいただいた優れた先生や先輩方のおかげで、実験室での実験生活の楽しさと、自然の中での幼年期の遊びとをいわば重ね合わせることができた。ありとあらゆる実験と数限りない失敗を重ねることを許していただいた、先生方の大らかなご指導に感謝している。
自然は永遠であり、人間はそのほんの一部を解明してきたに過ぎない。これまでの研究人生の中で、はたして彼がMr.発見君だったのかどうかは釈然としないが、偶然と思われる生物現象の発見に何度も遭遇した。一方、自分の自然に対する洞察力のなさを痛感し、悔しい思いをすることもあった。それらの発見を、発明として形にし、産業化へと導いていただいたのは、やはり優れた先生方、同僚、学生諸君、そして企業の研究者の皆様であった。分子生物学が発展し、研究がデジタル化されている現在であっても、私は自然界を超高速で走るMr.発見君の気配を以前にもまして大きく感じている。過去のアナログ的な時代の研究だけにMr.発見君が潜んでいるのではないと思う。彼になかなか巡り合えない苦しみも大きいが、別のMr.発見君を正面から捕まえてみえたいものである。
(注)「「幸福」が来たら、躊らわず前髪をつかめ、うしろは禿げているからね。」『レオナルド・ダ・ヴィンチの手記(上)』(杉浦民平訳、p. 40、岩波文庫)に由来していると考えられる。
著者紹介 富山県立大学工学部生物工学科(教授)、JST、ERATO浅野酵素活性分子プロジェクト研究総括
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 9月 2015
生物工学会誌 第93巻 第9号
高木 博史
筆者が支部長を務めている関西支部では、昨年度から産学官の若手人材の国際化を目的とした活動を始めている。たとえば、今年度は支部に所属する産学官機関から選抜した若手研究者に、タイバイオテクノロジー学会主催の国際シンポジウムにおいて、口頭発表の機会を与えるとともに、現地の企業と研究機関を訪問し、見学・討論を行うことで、タイを中心とする東南アジアにおけるバイオテクノロジーの現状を学ぶ機会を提供する。
こうした取組みは、本学会の重点化課題(国際交流・国際展開の推進)に支部として貢献できることの一つとして、今後も積極的に実施していきたい。また、学会としては「アジアの生物工学を先導する学会」を目標に、リーダーシップを発揮しながら、アジア諸国における関連学会との連携強化や若い研究者・技術者の顕彰などを行っている。一方で、おもに国内の大学で修学し、その数が増えている留学生についても、大学だけでなく、学会として彼らの育成・支援を組織的に行う時期が来ているかもしれない。
そこで、学術・経済の両面で発展が著しい東南アジアからの留学生について、所属大学で学生のキャリア支援を担当している立場も含め、最近感じていることを纏めてみた。
- 優れた留学生を育成する国(大学)に、高い意欲や能力を有する留学生が集まる
現在、留学生の受入れは2008年に政府が発表した「留学生30万人計画」に基づき、急速に進んでいる。そのリクルート活動は以前の欧米や中国・韓国から東南アジア地域にシフトし、優秀な留学生確保のための競争が激化している。筆者もある国の首都のホテルで同じ目的で滞在している別の大学の知人と偶然会い、なぜか気分が凹んだ。大型の競争的資金として、大学の国際化を推進する国費留学生優先配置プログラム、スーパーグローバル大学等事業などで、数値目標の達成に苦労されている教職員も多いと思う。
- 最先端のコースワークと研究指導、およびキャリア支援が重要である
筆者の所属大学では、活発な教育研究交流を展開している東南アジア4か国の連携大学から毎年10名程度の学生を選抜し、博士前期または後期課程に受け入れている。そして、英語による最先端バイオ分野のコースワークと研究指導を行い、博士号を授与している。在学中の経済的支援は十分に保証しているが、彼らの高い目的意識(学位取得)と教員へのリスペクトは多くの日本人学生も見習ってほしい。加えて重要なことは、個々の留学生のニーズに対応したキャリアパス教育と支援を通して、アカデミアや企業において東南アジアと日本との良好な関係の構築に貢献できるリーダー人材の育成である。今後は、アカデミア以外の出口支援も重要であろう。
- 留学生を研究室に受入れることで、日本人学生の国際化教育を実践できる
留学生は日本人の学生へもさまざまな影響や刺激を与えている。筆者の研究室では、ミーティングやセミナーに日本人学生と留学生が一緒に参加し、ほとんどの場合英語で行っている。日本人学生にとって、欧米のnative speakerではなく、東南アジアの留学生と英語で会話することにそれほど抵抗はない。また、英語での実験指導や研究討論を行う能力が養われるだけでなく、相手国の文化や歴史を学ぶこともできる。こうした研究室活動や教育カリキュラムを通して、国境や国籍を意識せず、人類共通の価値観を認識する「グローバル人材」に必要な能力を身につけることができる。
大学としては、留学生に最先端の教育を提供し、学位を取得させた上で、日本での就職(アカデミア、企業を問わず)を支援することが優秀な留学生の獲得に直結するであろう。そのためには、大学・企業・国が密に連携し、国には留学生が国内で就職できる制度を充実していただき、企業には大学が育成した人材の就職機会を増やしていただければ有り難い。現在、本学会に所属している留学生は概数で100名弱である。関西支部も具体的な活動を通して学会組織と協力し、国際交流・国際展開の活性化に貢献したい。
著者紹介 奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 8月 2015
生物工学会誌 第93巻 第8号
森原 和之
終戦後から1950年代にかけて日本の多くの製薬企業は抗生物質の発見に狂奔していた。しかし、抗菌作用によるスクリーニング方法には限界があり、成果は乏しかった。その間、画期的な業績をあげたのは三共研究所の遠藤章氏だった。彼はラットの肝臓抽出液を用いてコレステロール合成阻害剤を探索、1972年、青カビの生産するスタチンを発見した。スタチン製剤が動脈硬化や心臓病の特効薬として世界で広く使用されているのは周知のことである。同様に劇的だったのは米国NIHに在籍中の満屋裕明氏であろう。彼は免疫細胞を用いて多数の化合物を検索、エイズ治療薬AZTを発見する(1985)。AZTは逆転写酵素阻害剤であった。同種阻害剤のddIやddCもエイズ治療薬として認可される。
翻って、私自身の半世紀に及ぶ研究の大半は酵素関係であった。最初に与えられた研究テーマは緑膿菌プロテアーゼ(エルギノリシン)の結晶化だった。3年かかってやっと成功した。1955年、まだ日本が貧しい頃の話である。酵素の活性部位に関する研究はフィリップスによるX-線解析から始まる(1965)。リゾチーム-基質類似オリゴマー複合体の解析により、酵素と基質との結合部位(活性部位)の構造が分子のレベルで明らかとなる。それを酵素的手法でアプローチしたのはイスラエルのシェクターとバーガーであった(1967)。彼らはサブサイトマッピングという手法を考案、パパインの活性部位のサイズを測定した。私達はその手法を利用して多数のプロテアーゼについて検討し、数々の成果をあげた。たとえば、ズブチリシン(枯草菌プロテアーゼ)の活性部位指向性阻害剤を発見する(1970)。同阻害剤で失活したズブチリシンのX-線解析をクラウトら(米)が行い(1971)、我々のサブサイトマッピングの結果(1970)とよく一致することを認めた。
私達はサブサイトマッピングの研究をアスパルティックプロテアーゼにも拡げた。ペプシンや黴酵素を対象とし、有効なヘキサペプチド基質を発見した(1973)。1976年初頭、米オクラハマ大で開催されたアスパルティックプロテアーゼに関するワークショップに招待される。もっとも関心を集めたのは、梅沢らの発見したペプシン阻害剤ペプスタチンの阻害機構に関する同会主催者タン教授の発表であった。ペプスタチンを構成する新アミノ酸残基がペプシン触媒における遷移状態アナログと認定、それを同阻害剤の示す強力な親和性(抗原―抗体反応に匹敵する)の理由とした。タン教授と台湾大學で同級だったというメルク社のリン博士と親しくなる。彼はレニン阻害剤の研究をしていた。ユーゴスラビアのヴィトー・トルク博士とも親しくなり、彼との親交はその後も続く。
1987年の年末、トルクは突然私の研究所を訪ねた。これは内緒だがと断りながら、エイズプロテアーゼはアスパルティックプロテアーゼで、その阻害剤はエイズ治療薬になる可能性があるから、君は早急にその研究を始めるべきだと言って帰っていった。しかし諸般の事情でその研究に着手できなかった。エイズプロテアーゼ阻害剤に関する第一報は、1990年、サイエンス誌に発表される。同阻害剤は遷移状態アナログとサブサイトマッピングの知識をフルに活用して構築された化合物であった。同酵素の立体構造も同薬の創生に貢献した。メルク社ではレニン阻害剤の研究がその後押しをした。その後、同プロテアーゼ阻害剤を含む多剤併用療法が始まり、エイズ死亡者数は激減する。
今や、くすり探しの主流は、スクリーニングではなく、病気発症に関与する酵素の発見、結晶化、X-線解析、活性部位指向性阻害剤構築の時代に入っているようである。時代の変遷とともに進化する研究の有り様を赤裸々に描いた「ザ・科学者、企業体研究員奮闘記」(文芸社、七百円)を最近出版した。ご一読願えれば幸いである。
著者紹介 東亜大学大学院(元教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 7月 2015
生物工学会誌 第93巻 第7号
松下 一信
微生物学の授業を担当される方は、はじめに微生物学の成り立ちの話をされることと思います。私自身、Leeuwenhoekに始まり、Pasteurの発酵学、Kochの細菌学、そしてBeijerinckとWinogradskyの土壌(環境)微生物学が生まれ、その後の発展を通して生化学・分子生物学が生まれ、現代の生命科学(微生物学)へと発展したと説明しています。これらの微生物学は、現在それぞれ産業微生物学(応用微生物学)、医学微生物学(病原微生物学)、農業微生物学(土壌微生物学・環境微生物学)へと展開しています。一方、欧米では、これら微生物学全体を統合した微生物学会が生まれ、ASM(1935年発足;前身Society of AmericanBacteriologists、1899年)、SGM(1945年;前身Society of Agricultural Bacteriologists、1931年)、FEMS(1974年;前身1968年)などとして活動しています。しかし、日本を見てみると、同様に古い歴史をもちながら、発酵微生物は生物工学会(1992年;前身1923年)や農芸化学会(1924年)、病原微生物は植物病理学会(1918年)や細菌学会(1927年)、環境微生物は土壌微生物学会(1998年;前身1954年)や微生物生態学会(1985年)などに細かく分かれ、それぞれの学会がほぼ独立して活動を進めており、全体を統括するような微生物学会は生まれていません。
私自身は、酢酸菌を中心に発酵微生物、つまり応用微生物学の研究を進めてきました。しかし、最近の研究の中で、「発酵微生物とは」と考えてしまうことがあります。酢酸菌の分離源に遡れば、植物上で他の多くの微生物と競合しており、酢酸発酵にしろ、カカオ発酵にしろ、自然発酵系の中にあっては酵母、乳酸菌、その他多くの微生物とともにその発酵系を形成しています。最近では、昆虫の腸内にも数多くの酢酸菌が発見され、しかも昆虫の生育に重要な働きをしていることもわかってきました。動物の体内に生育し病原性を示すものまで見つかっています。それ故、酢酸菌に限らず大腸菌と言えども、人工的な発酵槽の中での生理学だけでは大腸菌を理解することはできず、自然環境の中での他の微生物との競合、植物・動物との相互作用なども含めて、その進化や生理学を見て行くことが必要となっています。微生物学全般に目を向ければ、ゲノム解析技術の急速な発展と相まって、腸内フローラの研究、根圏微生物群の研究、自然発酵・環境浄化(バイオガス生成)系のメタゲノム解析など、病原微生物・環境微生物・発酵微生物の垣根はどんどんなくなってきているように思えます。
自身の話で恐縮ですが、私は現在、山口大学の中高温微生物研究センターに所属しています。このセンターは、東南アジアなどの研究者との共同で見つかってきた耐熱性微生物を中心に研究展開するために組織されたものですが、メンバーは本学の理系全学部(農・獣医・工・理・医)から参加しています。発酵・環境・病原微生物それぞれを研究対象とするグループが交流しながら研究を進めているため、垣根を越えた共同研究も生まれてきています。
最近、生命科学研究の中で微生物学の位置付けが相対的に低下してきているように感じているのは私だけでしょうか。国内の学会は上述したように多岐に分かれていますが、昨今の微生物学研究はさまざまな分野(発酵・環境・病原・農学・工学・ゲノムなど)が相互に密接に関係して展開するようになってきていると思います。いくつかの微生物関係の学会(研究会)では共催で学会を開催することも増えているようですが、今後、国内の微生物関連学会がもっと交流を深め、時には一つの課題で連携を進めるなど横の繋がりを深めて、生命科学における「微生物学」の役割を高めるべく努力する時期にきているのではないかと思っています。
著者紹介 山口大学農学部教授(特命)・山口大学中高温微生物研究センター長
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 5月 2015
生物工学会誌 第93巻 第5号
正田 誠
2014年のノーベル物理学賞は3名の日本人に与えられた。受賞者ならびに関係者の喜びは大変なものであろう。私自身も、2000年に白川英樹先生がノーベル化学賞を授与されたときのことを思い出した。先生は私が奉職していた研究所において伝導性ポリマーを発見し、その功績で受賞されたが周囲の盛り上がりは大変なものであった。重厚なメダルを直接拝見でき、受賞にまつわる各種のエピソードが披露された。中でも先生は自分が必ずしも優秀な学生でなかったことを独白され、これが多くの若い研究者や大学院生に研究意欲を高揚させたことも確かである。
最近のノーベル賞受賞者は、他の追従を許さない程に群を抜いた秀才タイプというよりも、粘り強く一つのことをやり遂げるタイプの人が多い。今回の青色LEDも2000年の伝導性ポリマーも、実用化に非常な困難がともなっていたが、諦めずに20年近く奮闘した成果である。こうした努力の報いとして「幸運の女神がほほえんだ」ことも共通している。
今後も日本において研究の発展と成果が期待されるが、いくつかの課題もある。思いつくまま列挙してみる。まず今までのノーベル賞受賞者は必ずしも研究環境に恵まれていたとは言えない。むしろ逆境の中で出された成果である。現在は科学技術基本法が成立して以来、数十兆円の税金が使われ、研究費および研究環境も充実して恵まれた状況と言える。こうした良い研究環境からノーベル賞が輩出されることが望まれるが、研究費の分配方法や費用対効果などについて批判があることも事実である。日本の科学技術政策の方向性について、厳しい議論がなされる必要がある。
日本人は新たな問題を提起したり、仮説を立てることが苦手である。海外の情報と動向をいち早く察知して、類似の課題を提案したり、いち早く仮説を証明してきた。海外のノーベル賞受賞者から「感謝」されている研究者も多い。こうした体質は、実質がなくても、プレゼンテーションがうまい人が目立つという結果を生む。今後は大きなブレークスルーを生み出す新しい概念や方法を提示する能力が望まれる。研究を推進する上で若い人の力が必須である。実は次の時代を担う優秀な高校生が日本の大学を選択しなくなっている。日本人の海外留学者数が全体としては減少しているが、それは「安心、安全」を重視する内向な若者が増えたことと、海外の厳しさが分かってきたことによろう。しかし、トップクラスの若者にとって今後20–30年間、日本が人生を賭けるに値する国であるのか疑問視しているとすると、今後の日本の科学技術の発展に大いに影響するであろう。すでに優秀な野球やサッカーの選手が海外に出て活躍しているし、海外の国籍を取得して活躍している研究者もいるが、今後は若い優秀な頭脳が流出し続けることが心配である。
日本人の頭脳流失を補うために、海外から優秀な若者を受け入れることにした結果、大学が主にアジアの国に事務所をおき、宣伝活動を活発化するに至っている。果たして優秀なアジアの若者が日本を目指してやってくるであろうか。障害の一つが日本語という言葉である。仮に日本語が堪能であっても日本の企業には就職しにくいばかりか、将来の昇進に関して必ずしも平等ではない。私の研究室を出て、日本で職を得た外国人は、日本社会のflexibilityの少なさへの不満を国内外に発信している。私自身、海外の大学に授業に出かけ、授業後のfree talkingにおいて学生の本音を聞き出すと、彼らは欧米志向であることを正直に言う。特に優秀な学生は日本に関する正確な情報を持ち合わせており、彼らが日本を遠ざけているこうした要因を是非改善すべきである。
最近は火山噴火などの自然災害の予想も頻繁に報道されているが、こうした情報が外国人学生に対して、留学先としての日本の魅力をさらに失うことになるのではないかと危惧している。
著者紹介 東京工業大学名誉教授、エイブル株式会社顧問
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 24 4月 2015
生物工学会誌 第93巻 第4号
関口 順一
信州大学での28年間、当初の21年間は講座制の下で過ごし、次の5年間は研究室制にかわり、定年後の2年間は特任教授として留学生と数人の学生を指導したが、その移り変わりの中で感じた研究室の体制について述べてみたい。
講座制の規模は大学によりさまざまだが、私が所属した信州大学繊維学部応用生物科学科は教授1、助教授1、助手1が基本であった。学生数は十数名で、半数以上は大学院生が占めており、1–2名の博士課程の学生と企業からの技術者を含めた規模の講座であった。一方、私が育った大阪大学工学部醗酵工学科では、講座の規模はその倍はあり、そのうち学部、修士の時代は週1回の雑誌会と年数回の研究発表会の折、指導教授にお会いする程度で、研究ディスカッションは助手の方にすべて任されていた。博士課程になって岡田弘輔教授の研究室に代わり、講座の規模も中程度になり、気さくな雰囲気の先生の下、研究ディスカッションの機会も増え、その後の研究に対するものの見方、考え方が確立できたように思える。このことからも指導教授と接する機会を増やすことの大切さを感じた。
さて信州大学での話に戻せば、教授として週1回の雑誌会とグループごとの週1回の研究ディスカッション、月1回の全体での研究発表会を実施していた。その中で週1回の研究ディスカッションには直接指導にたずさわる教員にも参加いただいて、詳細に実験方法、結果、今後の展開について話し合った。ノートを持ってこさせるので、理研で問題になった実験の不記載などはまず起こらない。グループ別なので、私はほぼ毎日午前中をこの仕事に充てることになったが、実験結果を評価したり、研究の展開を考える上で有意義であった。もっとも、ディスカッションに参加する学生諸君にとっては息つく暇もない学生生活だったと思うが、それでも卒業生から、あの時の経験が今の職場での仕事を支えていると言われると満更でもない思いである。研究テーマについて、助教授の専門のテーマ以外は私から提案することが多く、助手の方々とのディスカッションを通して、それらの研究テーマを展開した。
ポスドクシステムが不十分な日本では、研究の遂行は若手教員と大学院生に頼らざるを得ず、講座制は研究テーマを高度化し、成果をあげるに好適であった。研究費は赴任後10年近く大学からの運営交付金がほとんどで、たまに財団から外部資金を得ていた程度で、苦しい研究室運営であった。しかし50歳に近づいた頃から、科研費が貰えるようになり、生涯のテーマとなる枯草菌細胞壁溶解酵素の研究を続けることができた。途中、特定領域研究やNEDOのプロジェクトに参加したこともあり、枯草菌ゲノム解析の技術や情報の取扱いなどがわかるようになり、異なる視点から細胞壁溶解酵素の機能解明を行った。まさに新しい実験手法の導入と共同研究に積極的であり続けることの重要さを感じた。さらに論文を精力的に書くことが共同研究者の実績をあげるためにも必須で、共同研究の成功の大きな要素となった。
定年が近くなり、研究室制に移行していったが、その時でも数人の若手教員を交えての研究ディスカッションは続き、雑誌会では異なる分野の教員から多くの知識をもらい、自分だけでは足を踏み入れることがない新分野も体験できた。ところで、私は若手の研究者の方が強く主張した研究テーマを「没」にしたこともあった。個人の自主性を尊重するアカデミアの世界では非常に稀かもしれない。これは自由にテーマを選び、活発に研究をしてもらう雰囲気が大切であることは重々存じているが、一時の面白さを重視するより、それまで培ってきた学問的な位置づけを認識し、より深く掘り下げた研究を持続する方が大切であると感じたためであった。生涯学生諸君には個々のテーマごとに研究の面白さを伝えることに務めてきたつもりだが、このような私の体験談が、新たに研究室を主宰することになる若手研究者や学生諸君の参考になれば幸いである。
著者紹介 信州大学名誉教授
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 3月 2015
生物工学会誌 第93巻 第3号
江崎 信芳
2013年11月に文部科学省から「国立大学改革プラン」が示された。今後10年で世界大学ランキングトップ100にわが国の10大学をランクインさせるという。世界の動きに遅れまいとする文部科学省(以下、文科省)の切迫感が滲み出ている。しかし、そもそも世界大学ランキングの意義を疑問視する声や、仮に意義を認めるとしても到底達成できないのでは、という声が多く聞かれる。文科省と意見交換する機会の多い大学執行部メンバーはまだしも、教育研究現場の教員の多くは戸惑っているのではないか。こうした、文科省(あるいは大学執行部)と現場教員の間の乖離は年々大きくなってきているように思われる。
筆者は2008年10月から6年間、京都大学の理事を務め、企画、評価、人事制度などの業務に携わるなかで、こうした乖離に起因する多くの問題に直面し、距離を縮めることの難しさを実感した。待ったなしなのかもしれないが、乖離が拡大していくとこの先どうなるのか、心配でならない。
国立大学は2004年4月からそれぞれ個別の国立大学法人になった。この間、国からの運営費交付金の配分額は毎年1.0 ~1.6%削減されている。京都大学の場合、2014年度の運営費交付金は、10年前の法人化直後の配分額の約85%に減額されている。一方、2014年度の人件費予算は運営費交付金総額の94%を占め、運営費交付金のほとんどが人件費に使われる。このまま減額が続けば、間もなく運営費交付金で人件費を賄うことができなくなるであろう。ほかの国立大学の状況も似たり寄ったりではないかと思われる。これだけをみれば、国はとんでもないことをしているようにみえる。
しかし、文科省は実は懸命に頑張っている。2014年度、全国86の国立大学に配分する運営費交付金の総額は1.1兆円に上り、この金額は実は前年度に比べてほとんど減額されていない。上記の運営費交付金は年々減額するが、それとは別に、大学ごとにメリハリをつけて配分する、いわゆる「袋予算」を別途確保しており、この「袋予算」分を含めると、国全体の運営費交付金の総額は昨年度に比べてほとんど減っていない。「袋予算」の中身としては、「国立大学改革強化推進事業(2014年度138億円)」などであり、配分されれば、学長のリーダーシップのもとで基盤的なことに使ってよい、といわれるものである。これをうまく使えれば、上述の縮減分を補填できるはずである。
ところが、こうした「袋予算」の資金配分を受けるためには、いろいろな条件が付されている。その顕著なものは、教員への年俸制導入であろう。2014年度と2015年度の2年間に全国立大学の1万人の教員に年俸制を導入し、研究大学では20%、それに準ずる大学では10%の教員に年俸制を導入してほしいという。この機会に、しっかりとした教員個人評価制度を確立するとともに、教員の流動性を高めてほしいという。しかし、研究大学とそれに準じる大学とは具体的にどの大学なのか、また、なぜ20%あるいは10%なのか、明確な説明がないので、教員は戸惑うばかりである。
今後、運営費交付金で人件費を賄えなくなると、たとえば1人の教員の人件費を2つの大学で折半するような必要性に迫られるかもしれない。その場合、年俸制教員でないと、人事制度上、折半はきわめて難しい。こうした年俸制導入の意義は頭では理解できても、自分と無関係な形で進めてほしいと願う教員は少なくなかろう。国立大学はそれぞれ法人組織になっているので、文科省としてできることは、「袋予算」の配分を通して各大学に考えてもらうしかないのかもしれない。
とはいえ、現場教員の理解と協力がなければ、中身のある改革は期待できない。そのためには、目標を具体的な数字で示す際に、なるほどと腑に落ちる理由を説明できるかどうかが鍵になるのであろう。
著者紹介 京都大学名誉教授
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 2月 2015
生物工学会誌 第93巻 第2号
永井 史郎
厚労省(2013年度)は全国医療機関に支払われた医療費が39兆3千億円であり、2014年度には40兆、国家予算の40%に達すると予想しています。一方、国際糖尿病連合(IDF)は、2013年度の世界糖尿病人口(20~79歳)が3億8200万人であり、2003年度(1億9400万人)から倍増したと報告しています。経済成長に伴い、糖尿病は中国、インド、アフリカでも年々深刻化しており、メキシコ、フランスなどでは高カロリー食品(加糖飲料など)への課税が導入され、USAでも検討中であるとか。日本での糖尿病患者(予備軍を含む)も2050万人になるようです(神戸新聞2014/9/2付)。
古い話ですが、1970年頃、廃糖蜜を原料にしたパン酵母生産(好気)でエタノール発酵の併発を防ぐ培養法を検討していました。ブドウ糖濃度を一定に保つことのできるケモスタット培養法で調べた結果、ブドウ糖濃度が100 mg/Lを超えると酸素供給が十分であるにも拘らず、エタノール発酵の併発が認められミトコンドリアの活性低下が示唆されました。
2000年、ブドウ糖を増殖制限因子(70%)にした酵母の培養では十分に与えた場合に比べ酵母の出芽回数が20回から28回に増えること、すなわち酵母の寿命が延びることが発見され長寿遺伝子(サーチュイン)と命名されまし1)。ヒト細胞でも確認されました。
基本的な特徴は、①NAD+依存性脱アセチル酵素が活性化し、DNAの複製が安定化する(長寿)。②核内転写因子(FOXO1)が活性化し、ミトコンドリアで抗酸化酸素(SOD、カタラーゼなど)の生成を促し、ミトコンドリアで発生している活性酸素種(reactive oxygen species, ROS)を無害化(水に)するなどです。
現在の飽食時代、血糖値(標準:60~110 mg/100 mL)が高くなる場合が多くあります。この場合、ミトコンドリアではNADH > NAD+になり過剰電子はROSの発生を加速し、細胞に酸化障害を与え「病」の根元となるようです。さらに高血糖ではブドウ糖(還元糖)は非酵素的にタンパク質と反応し(メイラード反応)、糖化物(advanced glycation end products, AGEs)をつくります(シッフ塩基、アマリド化合物など)。これらのラジカル反応はROSも発生する以外、血管内皮細胞のタンパク質の糖化を促進、血流障害の原因となり、脳、心疾患の要因となっています。高血糖はROSによる酸化(サビ)とAGEsによるタンパク質の糖化(コゲ)で万病の元となっています。ちなみに、哺乳動物の血糖値は、ネコ(肉食):71~148、イヌ(雑食):120~140、ブタ(雑食):70~120、マウス(雑食):75~115、ヒツジ(草食):60、ウサギ(草食):135など、一定範囲に保たれているようです2)。
人類(ホモ・サピエンス、20万年前)が生活してきたアフリカでは飢餓との戦いでした。その結果からか、高血糖を下げる手段はインシュリンの分泌しかありません。そのため、ご存知の通り、インシュリン分泌が不調になると血糖値を下げることは困難になります。逆にブドウ糖が不足すると、貯蔵グリコーゲン、糖新生アミノ酸、グリセリン、乳酸などから補給できます。これらがなくなると脂質からケトン体でエネルギー生産が可能になるといったように、「多様的」に対応できます。稲作民族である私達は米麦を主食に生き抜いてきましたが、過酷な労働が伴うためエネルギー消費が大きく、庶民の高血糖は少なかったと思われます。
最近は健康維持のためカロリー制限によるダイエットも盛んですが、カロリー制限は糖質、タンパク質、脂質の燃焼熱を基準にして計算されています(生理的根拠が曖昧である)。一方、糖質制限は糖質のみを食事から減らす方法であり簡単です。先にも述べましたが、生活習慣病の原因は糖質過剰によるミトコンドリアの不調が主原因でミトコンドリア病とも呼ばれています3)。体重の10%はミトコンドリアで占められているようです。糖質制限とウォーキングなどの運動(ミトコンドリアの活性化)で健康長寿を目指したいものです。
1) NHK「サイエンスZERO」取材班,今井眞一郎編著:NHKサイエンスZERO 長寿遺伝子が寿命を延ばす,NHK出版 (2011).
2) 夏井 睦:炭水化物が人類を滅ぼす 糖質制限からみた生命の科学,光文社新書 (2013).
3) 近藤祥司ら:Newton, 12, 44 (2012).
著者紹介 広島大学名誉教授
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 1月 2015
生物工学会誌 第93巻 第1号
倉橋 修
新年明けましておめでとうございます。会員の皆様をはじめ、これまで学会活動にご参画、ご協力頂きました多くの皆様に、改めて御礼を申し上げます。
園元会長が2013年に掲げられた活動方針、重点課題(3アクション+7テーマ:学会HP参照)は、学会を取り巻く社会の環境変化に対応しつつ、創立100周年、さらにはその先に向けた学会の基盤作りを目指すものです。そのためには、学会および学会員がこれまでの考え方や行動を能動的に変えていくことが求められています。
少々古いデータになりますが、日本経済大学の後藤俊夫教授が2009年に発表された調査結果によると、日本には創業200年以上の歴史を有し、老舗と呼ばれる会社が3937社も存在するということです。最も長い歴史を有する会社は神社や寺を建立する金剛組で、なんと西暦578年に創業しています。世界各国の調査結果も示されており、2位以下は、ドイツ1850社、英国467社、フランス376社と続き、アジアでは中国75社、インド6社、韓国1社とのことです。米国企業は平均30年の短い寿命で衰亡していると言われていますが、老舗の多寡は必ずしも各国・各地域の歴史の長さとは相関しないように思えます。我国に老舗と呼ばれる会社が突出して多いのは、その地政学的な特性に加え、独自の文化、自然、風土、思想などが色濃く反映された結果ではないでしょうか。
日本のバイオインダストリーも例外でなく、長い歴史を誇る会社が多々存在します。醤油製造を生業としたヒゲタ醤油は1616年に、ヤマサ醤油は1645年、酒造りを生業とする月桂冠は1637年、大関は1711年、酢の醸造を生業とするマルカン酢は1649年に創業しています。我国の伝統的な発酵食品の会社以外でも、武田薬品工業は和漢薬の仲買商店として1781年に創業し、アサヒビールとサントリーは1889年に、キリンビールは1907年に創業しています。筆者の属する味の素は1909年に創業しており、100年を超える歴史を有していますが、各社ともバイオテクノロジーをコアコンピタンスとして経営の多角化を図りながら、事業規模を拡大しています。このように長期間に亘り存続できたのは、時代の変化を機敏に捉えつつ、新たな社会的価値、お客様価値を創造し続けてきたからこそであり、伝統は革新の連続であると言われる所以です。
東洋には自然に生かされているという思想があり、日本のバイオインダストリーは自然に謙虚に対峙し、自社の基盤に外からの異質な文化を鷹揚に取り込み、混ぜ合わせ、発酵、熟成させて自らの基盤を発展、拡大し、魅力的なものに変えてきたからこそ長期間に亘り、存続し得たのではないでしょうか。
さて、日本生物工学会は2022年に創立100周年を迎えます。本学会創立の端緒となった1910年の大阪高等工業学校醸造会の設立から数えれば、既に100年を超える歴史があり、国内の学会の中では伝統ある学会と言えます。1923年に大阪醸造学会として設立されて以来、1962年には日本醗酵工学会に、1992年には日本生物工学会へと学会名称が変更されると同時に学会の基盤を発展、拡大してきました。大阪醸造学会から日本醗酵工学会への改称は、同窓会的性格を併せ持つ学会が純粋学術団体へと大きく変貌を遂げるものでしたが、先輩諸氏が学会会員の声に真摯に向き合い、リスクを取って変革にチャレンジされたことが今日の発展に繋がっているものと推測します。日本生物工学会は、これからも原点を見つめながら、学会のステークホルダーの声に耳を傾け、能動的に自らを変えていくことが必要であると考えます。
一方で、決して変えてはならないものもあります。日本生物工学会の定款にはその目的が明確に示されていますが、筆者は日本生物工学会とは、日本独自の基盤(文化、自然、風土)に根ざし、生物を研究開発対象として実学(役に立つ知、技と新たな社会的価値の創造)を志す研究者が集い、学会本部・支部役員と会員の皆様、特に次世代を担う若手会員の皆様との双方向コミュニケーションによる切磋琢磨の場と考えています。これこそが本学会の変えてはならない原点ではないでしょうか。
日本生物工学会が、これからも社会的価値を創造する学会として発展し続ける事を願いつつ、年頭のご挨拶といたします。
著者紹介 味の素(株)(常務執行役員)
バイオ・ファイン事業本部(副事業本部長)、バイオ・ファイン研究所(所長)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 24 12月 2014
生物工学会誌 第92巻 第12号
大竹 久夫
私ごとですが、来年2015年3月をもちまして大学を定年退職になります。1968年に大学に入学しましてから、じつに50年近くも大学に居続けたことになります。振り返ってみますと、自由が取り柄の大学と言いましても、やはり言いにくいことはいろいろとありました。たとえば、立派な研究発表を聞かせて頂いた後で「だから何なの」とはなかなか言えません。そもそも発表された方に「だから何なの」などとお聞きするのは、意地が悪いし大変失礼なことです。発表者が研究成果を中心に話すことは当然ですから、「だから何なの」などと聞くのは発表内容に直接関係ありませんし、なにより貴重な質疑応答の時間を無駄にしかねません。しかし、そう頭では分かっていましても、やはり「だから何なの」と聞きたくなる衝動にかられることが、とくに最近増えているように思います。単に、私が偏屈で人間ができていないだけのことであればよいのですが。
研究の発表を聞かせて頂いて「だから何なの」と聞きたくなるのは、研究の縦割りならぬ横割りの弊害が見え隠れする時が多いように思います。基礎研究、応用研究と産業化の間に、展開研究や実証研究などが飛び箱のように積み重ねられ、出口に向かわない応用研究やビジネスモデルのない実証研究があちこちで行われていると感じているのは、はたして私だけでしょうか。応用研究や実証研究では、目的が達成されなければ意味がありません。研究の横割りがひどくなりますと、応用研究は出口について語らなくなり、実証研究も社会実装を棚上げにしがちです。研究の横割りの最大の弊害は、だれも責任をとらない大型研究プロジェクトが、国で堂々と行われてしまうことでしょう。
どうみても先の見えないプロジェクトの研究費申請書を読まされても、「うそでしょう」とはとても言えません。基礎研究ならともかく、応用研究や実証研究では研究の到達目標や期待される波及効果について書かなければ、研究費はもらえません。たとえ出口に向かうロジックや波及効果の説明に「ありえない」と思っても、「うそでしょう」とはなかなか言えません。しかし、「ありえない」ことは「ありえない」と言わなければ、何でもありの空想の世界に入り込んで、役に立たない研究ばかり増えてしまいます。若い研究者が信じきって取り組む場合は微笑ましく、ひょっとしてとんでもない結果がでるのではないかと期待するのも楽しいことです。しかし、明らかに苦し紛れの方便としかとれない場合は頂けません。もちろん、言いにくいことを口に出すには、それなりの覚悟が必要です。ある会議で、巨額な国費を投入した割にビジネスモデルが出てこないバイオ燃料に苦言を呈したとき、お役人から「そんなことは総理大臣になってから言ってくれ」と叱られたこともありました。そう言うお役人も、きっと役所で同じことを言わたことがあるのでしょう。研究の横割りがひどくなりますと、ありえない話や方便がまかり通ってしまいます。自分の持ち場のことだけを語っていればよくなり、先のことには責任をもつ必要がなくなるからです。研究の横割りを避け、ありえない話がまかり通らないようにするには、技術の開発から社会実装に関わる利害関係者を一堂に集め、シームレスな議論をすることです。それにはお金も時間もそれほどかかりません。利害関係者を一堂に集めたシームレスな議論において、ビジネスモデルも波及効果も明らかにならなければ、少なくともお金のかかる大型研究プロジェクトはやめるべきでしょう。
私は、これまで50年近い大学生活のほとんどを工学部と工学研究科で過ごしてきました。最後に振り返って、工学者である限りパス回しよりも、もっとしつこくゴールに向かってシュートを打ち込むべきだったと思います。若い生物「工学者」の皆さん、一日も早く自分のゴールを見定めて、ぜひ強力なシュートを打ち続けて下さい。
著者紹介 大阪大学大学院工学研究科(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 11月 2014
生物工学会誌 第92巻 第11号
久松 眞
若いころは面白そうと感じて行った直感的な行動や、あるいは経験を積んで独創的な計画を立て、ここは勝負と決断して行った直観的な行動でも、予想を超えた結果に出会うことがある。研究にも感性はあると思っているが説明が難しいので、とにかく体験を紹介する。
研究者として駆け出しの阪大産研時代、水溶性多糖類、サクシノグリカン(以後SGと略記)の研究をしていた。生合成の研究が行き詰り、ストレスを発散させるつもりで当時目新しかったHPLCでSGから抽出した有機酸の分析をした。すると、コハク酸のほかに大きなピークを検出、これがピルビン酸の発見となった。ピルビン酸のみを外したSGをメチル化分析し、糖結合情報を調べるガスクロ分析にかけると、構造がイメージできる見事なチャートが現れた。SGの構造解析はボス原田篤也教授(故人)の目標の一つであったので研究室一丸となって取り組んだ。研究室の同僚にも恵まれSGの構造解析で学位が取れた。SG産生微生物は、植物の遺伝子組換えに使われるアグロバクテリウムと同属であったことから、この多糖類の構造解析は我々の実績になった。
未完成となった生合成の研究も、多くの植物病原菌が産生するb-1,2-グルカンが重合度20程度の環状グルカンであることを証明するのに役立った。この時、共同研究者で糖分析でも先駆者の小泉京子先生(故人、武庫川女子大学薬学部教授)から分析哲学を教わった。糖の分離でやるだけやって困ったらNH2よりODSの方が頼りになる、均一溶媒(アイソクラテック)でこのカラムの超能力は発揮されるが、溶媒の作り方が重要と教えられた。53%のAB混合溶媒を作る場合、50% A液7部と60% B液3部で混合すること、そうすれば1%ずつ溶媒濃度を変えてHPLC分析を再現性よく行え、ベストな分離パターンが得られると。
米国ジョージア大学は、コロラド大学のアルバーシャイム教授と彼の研究室のメンバーを丸ごと引き抜き、最新分析装置を備え世界から注目される複合糖質研究拠点(CCRC)を立ち上げていた。三重大学に移ったころ自分の能力を試してみたくて、彼に受け入れを伺う手紙を出したところ、提示した雇用条件なら受け入れられるとの返事が届いた。キシログルカンのセルラーゼ分解物には重合度20前後のオリゴ糖が複数存在する。そのうちの1個、1 mg程度を分離する研究がCCRCの仕事となった。1年と短い滞在期間で結果を出すには、ある程度の成果が見込める実験方法をデザインする必要があった。そこで思い出したのが小泉先生の教え。はじめはゲルろ過で分け、次にNH2で分け、最後に溶媒濃度の選択を熟慮しODSで分取すれば何とかなると直観した。計画は大当たり、キシログルカンオリゴ糖を6種類純化でき構造解析も全部完了、CCRCのメンバーをうならせた。
21世紀に入ると改組や大学法人化など次から次と大学運営が変わり始めた。独自性がある基礎研究(シーズ)に加えて社会のニーズにも応えられる研究が求められる時代になった。そこで、残飯からバイオエタノールを生産する研究を選んだ。老化した澱粉や調味料として加えられた塩や油の影響で残飯は生澱粉と比べると酵素分解は容易でない。古い技術ではあるが硫酸糖化を選択し、硫酸が入った酸性下でエタノール発酵ができるストレス耐性酵母の研究を始めた。しかし、遅すぎた新分野への参入と産学官の連携型で研究する新しい体制には不慣れであったことと、会議が多くなり自分で研究しなくなったことなどから実験中に次の手を想像しにくくなった。若かったころと比べると研究の勘は鈍った。
研究できる若い時期こそ感性を磨く貴重な時期である。たくさんの経験の中に勘も入れてほしい。社会のニーズとマッチングさせることを頭に入れながら自分流の型が育ってきたころに大きな果実が転がってくるはずである。
著者紹介 三重大学名誉教授、三重大学社会連携研究センター伊賀研究拠点(副所長・特任教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 10月 2014
生物工学会誌 第92巻 第10号
越智 幸三
「趣味の園芸」という言葉があるように、何事も趣味でできるなら、これ程楽しいことはない。つくばの国立研究所を停年退職し、目下地方の私立大学で教鞭をとっているためか、幸いにも「趣味の研究」に思いを巡らせることが多い。研究がこれ程楽しいものであることに気づいたのは、実に齢60を過ぎてからということになる。遅すぎた目覚めというべきか。
ヒトは26,000余りの遺伝子を保有しているが、その多くは一生使われることなく(つまり発現することなく)生を終えると考えられている。このような通常発現しない遺伝子を「休眠遺伝子」と呼ぶが、ヒトでは“サーチュイン遺伝子”がよく知られている。数年前にNHKのサイエンスZEROで2度も放映されたので、記憶されている方も多いであろう。このサーチュイン遺伝子(SIRT1)は1999年に酵母で発見され、酵母の寿命延長効果を示すのみならず、その後の研究で線虫、ショウジョウバエ、ヒトにも存在することが判ってきた。この遺伝子を覚醒できればヒトの寿命は20才伸びると言われている。長寿遺伝子と呼ばれるゆえんである。ただし、最新の追試実験ではサーチュイン遺伝子と寿命延長の間には因果関係がないとされている。
サーチュイン遺伝子の真偽はともかく、微生物にも多数の休眠遺伝子が予想をはるかに越えて数多く存在することが判ってきた。これは昨今のゲノムプロジェクトの進歩によるもので、放線菌、カビ、ミクソバクテリアには一株あたり通常20~40の二次代謝産物合成遺伝子クラスターが存在することが明らかにされている。ところがいずれの菌株でも二次代謝産物としてせいぜい3~5物質しか発見されていない。明らかにこの事実は、約8割を占める大半の二次代謝遺伝子は通常培養条件下では発現しておらず、それ故これまで発見されることがなかったことを示している。換言すれば、膨大な二次代謝産物の探索源が手つかずのまま現在まで残されていたことになる。この宝の山をいかにして発掘するかは応用微生物学における焦眉の課題の一つであり、私どもの「リボゾーム工学」「転写工学」「希土類元素の利用」も含め、「遺伝子強制発現」「エリシターの利用」などさまざまな方向から強力なアプローチが始まっている。
50年前は生命原理の探究において微生物が主役であったが、現在もそうであるとは言い難い。一方、天然物を探索源とする創薬は、新物質の発見に至る確率が低下したため、困難の度を増している。すなわち、将来における微生物学の繁栄のためには、微生物がいかに“役立つ”ものであるかを示し続けることが必要であり、「休眠遺伝子覚醒技術」がこれに多少とも貢献できることを願っている。
ところで、なぜそんなにも多くの二次代謝遺伝子が休眠状態のまま眠っているのであろうか?ごく特殊な環境下では目覚めて、自分自身または周囲の菌に役立っているのだろうか?二次代謝産物の代表は抗生物質であるが、抗生物質は周囲の菌を殺して、栄養源を独り占めすることにその生理的意義があるとされてきた。しかし、土壌など自然界で殺菌力を示すほどの多量の抗生物質が産生されているとは到底思えない。実験室でさえ高レベルの生産は難しいのである。もし生理的意義があるとすれば、それは極微量で作用可能なものであるはずだ。
これに関して私どもは最近、最少致死濃度(MIC)の1/100~1/1000という極微量の抗生物質添加により、放線菌の休眠遺伝子が強力に目覚めるという非常に興味深い事実を見いだしている。これは、抗生物質の本来の姿は周りの菌を殺すことではなく、むしろ抗生物質という“微生物のことば”を使って互いにCell-to-Cellコミュニケーションを図っていると考えるべきであろう。とすると、目覚めた休眠遺伝子産物は逆に相手方菌になんらかの効果(当然好ましい効果であろう)を及ぼしているのだろうか?もし大半の休眠遺伝子が目覚めるとすれば、そのように多様な二次代謝産物を一度に生産する意義は何なのだろうか?それぞれの二次代謝産物は異なったことばを意味するのだろうか?ここまでくると、趣味を通り越して「道楽の研究」であろう。それだけに楽しさもひとしおなのである。最後に、抗生物質が微生物のことばであるならば、なぜそのリセプターが“リボゾーム”でなければならないのかという命題を提起しておきたい。
著者紹介 広島工業大学生命学部(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 29 9月 2014
生物工学会誌 第92巻 第9号
河合 富佐子
研究者は研究だけに専念できることが理想であるが、人間社会ではそうもいかない。影響するものは研究環境、個人環境、時代背景といろいろあるが、私自身は、特に女性に対する時代の考え方との闘いにかなりのエネルギーを費やした。それでも何とか生き残れたのは私より以前の女性群に比べると時間の経過が助けてくれたおかげだろう。従姉の一人が京大女子学生一期生であったが、ほぼ一回り年齢の違う自分と彼女を比較すると時代の違いを実感する。さらに自分より5年下くらいから、どの分野でも数はともかくとして女子学生が存在するようになった。女性問題という言葉が最近ではあまり取り上げられないのも、時代の変遷を反映している。また、個人というものは確固とした考え方があるようでいて、いかに時代に影響されるものであるかを実感する。私の学生時代の指導者世代から以降、私と同年代およびかなり下の世代でさえ、女性への視点には問題があったが、ある意味ではその時代の考えに従っていたに過ぎない。それらの世代がすっかりいなくなったわけではないのに、気がつくといつの間にか女性の活用が叫ばれているという風潮には、とまどう思いもある。しかし、研究生活の最後にこのような変化を見届けられたのは嬉しいことである。では何が変えたかというと、個々の闘いの蓄積と時代の流れが合うようになった結果だと思う。
残念なことに、最近の理研のSTAP細胞の騒ぎをみていると、研究者としてどこかおかしいという気がする。ミスというより作為的な詐欺行為が露見しないと思っていたのか、あるいは露見したらと不安に苛まれることはなかったのだろうか。大きくアピールすることは、内容がなければ大きく墜落することでもある。光と影は常に表裏一体である。研究テーマに拘らず、成功の確率は研究者自身の判断と責任である。大きな果実を得られるかは賭けであり、努力の結果でもある。理研では理事長が未熟な研究者と断罪したが、その未熟な研究者を選んだ責任と今後の対応策が最終的にどうなるか注目している。この事件を受けて、女性研究者への影響という意見もあったが、あんなことで志望や進路を変える人はいないだろうし、世間の女性研究者への評価に影響することはないと信じたい。そもそもジャーナリズムの取り上げかたは、ゴシップ週刊誌並で違和感があった。あのスタイルで真に実験ができるのかということと、いまだに見かけの評価が女性研究者にはつきまとうという両面の違和感である。最近では、女性リーダーが大きな研究を牽引していることが珍しくなく、日本も国際化したと感じていたのと真逆の印象を受けた。論文疑惑の問題は男女を問わない研究者マインドの確立と存在に関わる。研究倫理以外に生き方の問題でもある。東大の論文疑惑では教授の辞職以外にも、同研究室出身者についても同様の疑惑が生じたようである。断固として虚偽を否定する人はいなかったのだろうか。いたとすればその方達に何が起こったかを知りたい。何グループかを競わせていたということだが、優秀な人材ならば別の世界もあったと思われる。どの組織に籍をおくかは研究費の獲得や学会の序列のようなものに影響する。しかし、それ以外でも研究者としての生き方はあるというのが、文系公立大学の教養からスタートして地方国立大学研究所で定年を迎えた私の実感である。
研究者の闘いの第一の対象は研究そのものであるが、それ以外にも闘わなければならないことは常に存在する。時代に求められるものはとよく言われるが、時代に求められるものに合わせるだけでは迎合に過ぎない。時代がくる前に時代を作ることに貢献するとか、来るべき時代を読み取ることが大切だろう。それではまったく無視できるかというとそうでもない。まったく無視するのはただ頑固、偏狭さを示すにすぎないこともある。自分は研究者としてどう生きるかを考えながら、時代の流れの中にヒントなり取り入れるべきものがないかを探ることから姿勢なり背骨ができ上がっていくのだろう。時代に流されても駄目、下手に竿をさしても抵抗が大きい。時の流れに身をまかせ、かつ先をみることが必要なのだろう。長期的には努力は報われることが多い、だから見る目を磨いて、めげず進みましょうというのが、若い世代へのエールである。
著者紹介 京都工芸繊維大学繊維科学センター(特任教授)、岡山大学名誉教授
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 8月 2014
生物工学会誌 第92巻 第8号
恒川 博
筆者は大阪大学醗酵工学科修士課程を修了後、酒類メーカーの医薬・化学品事業部門に入社し、2013年6月に定年退職するまで抗生物質などの医薬品原体の発酵生産に従事した者です。この間、先輩・同僚・後輩のご支援のお陰で経営にも参画する機会を頂戴し、企業研究者として恵まれた会社人生を全うさせていただきました。在職当時の経験を踏まえて、企業で活躍されている、あるいはこれから活躍したいと考えておられる若い生物工学研究者の皆様に一言述べさせていただきます。
企業研究者にとってもっとも大きな喜びとは、会社という組織を通して自身の研究成果や技術を活かして社会に役立つ新しい商品を生み出すことであると筆者は考えています。新商品の開発は一人の優秀なスペシャリストの能力だけで達成されることはありません。発酵生産という技術面だけを取り上げても種母調製から本発酵、回収精製、品質分析、設備機器類の維持管理、さらには原料調達から出荷輸送まで含めた品質保証などの単位プロセスから成っており、それぞれのプロセスのスペシャリストを統合して技術課題を解決する人材が必要です。また、新商品開発には法的規制などの多くの問題点が発生しますが、組織内外にまたがるこれらの諸問題を調整し、それらを技術課題に落とし込める人材も不可欠です。要は、専門的な知識・技術を持ち、かつ専門外の人との円滑なコミュニケーションを図れるゼネラリストの存在が新商品開発には必須と言えます。
それではゼネラリストになるにはどうすればよいのでしょうか。筆者自身も若い時は目前の研究課題に没頭し、実験に明けくれた毎日を過ごしましたし、特別なゼネラリスト養成教育を受けた記憶もありません。ただ、歳を経てゼネラリストとしての職務を果たすにあたり、次の点を意識するようになりました。第一は、自分が万能ではなくわからないことが多いという自覚です。この自覚があれば不得手部分を素直に他の人に任せることができますし、場合によっては社外の先生方に教えを請うことも可能となります。ただし、信頼して任せたとしても最後の責任を自分で取る覚悟は必要です。第二は、自分は人とは変わっていることの自覚です。人は得てして自分以外の誰それは変わっているということを簡単に意識できますが、自分自身が人と変わっているとは意識しないものです。特に同じ組織に長くいるとお互いの慣れのために皆が同化したように思いがちで、言葉にしなくても自分の考えは伝わっていると勘違いしてしまいます。自分は変わっているという意識を持っていれば、自らの考えを理解してもらうためには常に徹底したコミュニケーションが必要だということも理解できるはずです。そして第三は、プロジェクトを成功させるのは自分以外の誰でもないという強い主人公意識です。筆者の経験では、組織の上下関係とは無関係に主人公意識を明確に持った人物がプロジェクト内にいた場合はそのプロジェクトが成功したように思います。もちろん、その人が主人公意識を振りかざすのではなく、円滑なコミュニケーションを通して諸課題を解決するゼネラリストに徹した場合ではありますが。
以上、取り留めもなく述べましたが、大学という学問の場を離れ企業研究者の道を選ばれた皆様が、専門性に裏づけられたゼネラリストとして大きく羽ばたかれることを期待してやみません。
著者紹介 日本マイクロバイオファーマ株式会社(元取締役副社長)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 26 7月 2014
生物工学会誌 第92巻 第7号
藤井 隆夫
研究者、技術者で大切なことは、研究対象に強い興味を持てること。つぎに、対象を自分の五感を動員してよく観察すること、それをよく吟味し、自身の経験や知識を駆使して考えること。対策や仮説を立て、積極的に実験(トライ)を繰り返し、本質を見極め、成果を出すことだろう。くわえて、まだ競合者が少ない、誰も考えつかなかったテーマに巡り会うなど研究のタイミングがよければ、成果を出せる確立がさらに高くなる。これらは当たり前の事柄だが、どこか恋愛と似ている気がする。
私の場合、嫌気性アンモニア酸化(anammox)というテーマに出会った。anammoxは、1990年代中盤に発見された、アンモニアと亜硝酸の酸化還元、脱窒反応であり、新発見のanammox菌と呼ばれる一群の細菌が行う化学独立栄養のエネルギー代謝である。当初、発見者のオランダ、デルフト工科大学のグループ以外に誰もanammox菌を培養できなかった。anammoxに関する解説を読んだ記憶があり、興味をそそられたが、すぐに手を出せるような状況ではなかった。ところが、90年代末に、古川憲治先生(熊本大学教授)がanammox菌の集積培養に日本で初めて成功し、先生から、anammoxの研究を、まさにグッドタイミングで、勧められたのがこの研究に入った契機であった。
anammoxの発見時から窒素含有廃水の処理の革新が期待された。熊大でのanammox菌の集積培養成功によって、廃水処理へのanammoxの適用をめざした日本の研究、開発が始まった。自分は、酸化還元酵素を長く取り扱っていたこともあり、競合者も少なかった生化学的側面からanammoxを攻略することにした。一方で、anammox菌は単離できない細菌で混合微生物系の汚泥状態でしか機能しない。純化できなければ、生化学の研究の対象にはならない不安もあった。ところが、扱ったリアクターの汚泥はanammox菌KSU-1株が60%程の割合で優占していた。メタゲノム解析や遺伝子による菌叢解析などの分子生物学的技術の進歩もあり、純化細菌と同じように、汚泥からタンパク質を精製できた。さらに、精製タンパク質の反応解析、結晶化、構造解析も通常の方法が適用できた。言ってみれば、私の研究履歴とanammoxは相性が良く、こちらのアプローチに応えて、相手が微笑みを返してくれたようなものであった。
研究を進めていくと、エネルギー代謝系のほとんどの酵素や電子伝達のタンパク質に多種類のc型ヘムタンパク質が関与していると考えられ、事実、多種類のヘムタンパク質が発現していた。なかには、データベースのタンパク質と相同性がなく、未知なヘムタンパク質も複数ある。どこに導くのかわからない、未知のものの持つ魅力が益々私達を引きつける。一方で、過去の知識がほとんど参考にならない。相手を理解し、全貌を自分のものにすることの難しさ。本質を掴みかけるが、自分の掌からするりと逃げてしまうもどかしさ。解決策を求めてもがき苦しむ日々を過ごしている。ゴールはまだ見えない。
私の拙い「未完成の」anammox研究の経験を書いてしまったが、冒頭に書かなかった一番大切なことがある。それは、自然や研究対象に対する感性(センス)である。自分の感性に共鳴しないような相手には好意をもてないだろうし、どだい感じるもののない対象に興味など湧くはずもない。年を重ねる程に総じて鈍感になってくる。これは、次々生じるさまざまな事柄に必要以上に動揺しなくなり、冷静に対処できる良い点もある。しかし、若い時は多感で一見些細なことと思えるものにさえ感動できる特権がある。研究者や技術者をめざす人、これから未来を切り開かれる人、若い間に是非感性を磨いて欲しい。そうすれば、日々の研究、実験の中で感動する場面に多く出会うことができ、ひいては大きなチャンスに巡り会えるに違いない。
著者紹介 崇城大学生物生命学部(学部長)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 6月 2014
生物工学会誌 第92巻 第6号
山根 恒夫
バイオマス(澱粉や砂糖などの作物系、草本系および木質系リグノセルロース、藻類)からの燃料生産関連の研究が盛んです。正確な数字ではありませんが、本学会年会での口頭発表でも、1/4から1/3位の発表件数はこの分野の研究のようです。そこで、エタノールなどのバイオ燃料の研究開発について、少し長い目で日本の歴史を振り返ってみたいと思います。
まず、今から70年前(1945年、昭和20年)の太平洋戦争末期の出来事です。マリアナ諸島陥落により、東南アジアからの石油運搬も難しくなると、軍艦や戦闘機の燃料をどのように調達するかが大問題となりました。戦争末期、海軍省軍需部では、本土内で得られる原料から燃料を生産しようとする「新燃料戦備」計画が査定されました。計画では、最初は、松の切り株から取れる「松根油」、次はブタノール発酵をエタノール発酵に転換、そして最終的にもっとも期待したのは、全国各地に多数存在する日本酒蔵元の燃料用エタノール工場への転換でした。国内で得られる原料としてはサツマイモに絞られました。準備は順調に推移し、1945年10月から本格生産に入る計画でしたが、戦争は8月に終わり、幸か不幸か、この計画は実行されませんでした。この太平洋戦争末期が近代日本における最初のエネルギー危機と言えましょう。
戦後、経済が復興し、1955年頃から日本は高度経済成長期に入り、その後およそ18年間発展を続けました。
そして、1973年から始まった石油危機(石油ショック)に巻き込まれました。それまで1~2ドル/バレルであった原油価格が最大で40ドル付近(1980年)まで急上昇したのですから、大変でした。1973年から1985年位までは、2回目のエネルギー危機と言えましょう。このころは、日本でも蔗糖やブドウ糖などの糖質原料からのアルコール発酵の研究が盛んに行われ、学会(当時は日本醗酵工学会)の年会でもアルコール発酵の発表が沢山あったことを覚えています。特に、1979年とその翌年に発表された田辺製薬(当時)の
固定化増殖酵母による連続アルコール発酵技術は大きな反響を呼びました。筆者らもこの時代、固定化酵母用バイオリアクターや凝集性酵母によるアルコール発酵について、3報発表しました。日本は、相当インフレとなりましたが、エネルギー源の多様化、省エネルギー技術、産業構造の転換などでこのエネルギー危機を乗り切りました。原油価格も1986年には10ドル/バレル位まで下がっています。それとともに、アルコール発酵の研究もしぼんでしまいました。
さて、時代は進み、21世紀に入ってから現代に至る潮流です。原油価格は2007年に30ドル/バレルから再び急上昇し、2008年5月には146ドル/バレルまで上昇しましたが、これはサブプライムローン問題と深く関係して、投機的な思惑で一時的に急騰したためであるとされ、数年で沈静化しました。しかし、それでも、現在100ドル前後で高止まりしています。日本だけに限れば、現在は円安になって、リーマンショック時と同じぐらいです。2005年以降、アメリカではブッシュ政権の政策もあって、トウモロコシからのバイオエタノール生産のブームが加速しましたが、「食糧とエネルギーとの競合」が問題となりました。この頃から、再びバイオマスからのエタノール生産の研究が盛んになってきたように思います。真っ只中に生きているとかえって実感できにくいですが、日本は、現在第3のエネルギー危機にあると思います。
以上のことから、「エネルギー危機時にはエタノール発酵関連の研究が盛んになる」と言えましょう。
しかし、現在の日本のエネルギー危機とバイオ燃料を取り巻く環境は複雑です。1)電力事情(原発の停止)、2)化石燃料の使用による地球温暖化の進行、3)バイオ燃料はカーボンニュートラル、4)再生可能エネルギー(太陽光、風力、地熱、バイオマス発電etc)の推進、5)LCAの進歩、6)北米のオイルサンドやシェールガス&シェールオイルの開発、7)非可食性バイオマスの糖化技術は進歩しましたがそれでも日本では依然としてコスト面で難点あり、8)遺伝子工学、代謝工学、合成生物学の進歩は著しいが、大規模な工業的実施にはカルタヘナ法の制約あり、9)多量のエネルギー作物(エリアンサスやネピアグラスなど)をどこで栽培するか、など正負の要因が複雑に絡まって、容易に解決策が見いだせない状態となっています。
日本について時代を超えて変わらない真実は、「石油や天然ガスをほぼ100%輸入しているエネルギー資源小国であり、エネルギー問題はアキレス腱である(さらに言いますと、ウラン鉱石や鉄鉱石を始めほとんど総ての鉱物資源も同様です。)」ことと、「台風(とそれに伴う高潮と高波)や地震(とそれの伴う津波)に、毎年あるいは間欠的に必ず襲われる天災大国である」、という2点です。叡智を集めて、多少不安定でも安心安全で持続可能かつ十分なエネルギーを確保したいものです。
著者紹介 名古屋大学名誉教授、中部大学元教授
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 26 5月 2014
生物工学会誌 第92巻 第5号
高木 敦子
本稿では、「ヒトの遺伝子の解析」の倫理に関わる手続について書くことで、ヒト遺伝子解析はDNA配列決定と変異の機能解析だけではないことを、自分の経験から述べたいと思います。
循環器疾患は日本人の死因の第2位であり、独立行政法人国立循環器病研究センター(国循)においても、その克服のための努力が続けられています。高トリグリセリド血症も循環器疾患である心疾患の危険因子の一つであり、この病因の解明や予防、治療は、心疾患の危険因子を減らすことにもなります。私は、本症の病因を調べるため、血清中のトリグリセリド代謝に関わる酵素であるリポタンパクリパーゼ(LPL)と肝性トリグリセリドリパーゼの活性測定系、タンパク質測定系を開発し、これら酵素で異常値を示す患者様の遺伝子解析を行ってきました。こういった経緯で、施設内部以外に、日本国内の他の病院などからも、高トリグリセリド血症者の遺伝子解析の依頼を受ける事もあります。
施設内外に拘らず、ヒト遺伝子解析研究では、2001年4月以降、行政指針の『ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針』(2013年2月全部改正)に基づいて、倫理審査申請書を作成し、倫理委員会で倫理審査を受けます。倫理審査申請書は研究計画書、説明文書、遺伝子解析の解説文書、同意文書、試料などの取扱い(破棄・変更)依頼書などから成ります。研究計画書には、研究計画概要、研究協力の任意性および撤回の自由、問題発生時の対応、予測される危険性、被験者の利益および不利益、費用負担に関する事項、知的所有権に関する事項、倫理的配慮、試料などの種類・量・保存の有無および保存場所、インフォームド・コンセントのための方法、個人情報保護の方法、遺伝情報の開示に関する考え方、遺伝カウンセリングの体制などが記載されます。
他施設からの依頼の場合には、指針に沿うように、国循では次のような手続きをとっています。まず、他施設の主治医が、その施設での倫理委員会での審査を申請し、承認を受け、それら申請書と承認書のコピーが当方に送られます。私は、「脂質代謝異常を示す患者および家族の遺伝子解析:他施設からの検体を用いる研究計画」の課題名で、国循の倫理委員会からの承認を得ていますが、新たな施設からの依頼ごとに、施設追加の変更申請を行っています。このとき、追加施設を書き入れた新たな研究計画書、他施設からの申請書と承認書のコピーおよびその施設の個人情報保護方針を提出し、変更申請をします。施設追加のような軽微な研究計画の変更の場合には迅速審査が適用され、倫理委員会でのプレゼンは省略されますが、新規申請や軽微でない変更の場合には、迅速審査が適用されず、委員会でのプレゼンも行います。迅速審査を行っても良いか、また、申請書に不備はないかなどに関し、倫理委員会の前に予備調査もなされます。承認後、依頼施設の主治医に連絡し、同意書(個人情報を黒く塗りつぶし、匿名化番号を記載したもの)とともに検体(血液)を郵送いただき、晴れて、解析を行うことが可能となります。毎年、実施状況の報告も倫理委員会に提出します。このような倫理申請を行うためには、臨床研究に関する倫理研修の受講が必須で、国循でも、年に数度、倫理研修が開催されます。倫理研修は、2010年設置の研究倫理研究室を前身とする医学倫理研究室(2013年~)の室長、室員の先生が担当されています。また、本研究室では、倫理コンサルテーションも受ける事ができ、私も、昨年度は3回相談させていただきました。
ところで、1990年代前半頃まで、上記のような指針は施行されていなかったとは言え、疾患遺伝子の原因変異部位が決まった場合、たとえば、LPL遺伝子の原因変異部位に、「Cys239→stop/TGC972 →TGA;LPL○○○(○の所に患者様の住所の都市名を入れる)」といった標記が論文にも見られました。私自身も、この頃の論文では、同様の記載をしていました。しかし、今にしてみれば、これは患者様など被験者に配慮した対応とは思えません。被験者の立場に立って考えることができていなかったと感じます。もちろん、被験者の立場に立って考えているつもりでも、自分の経験不足、知識不足などから、倫理にかなっていないことをする可能性があります。このようなことを回避するために倫理研修を受け、また、医師、研究者以外の立場の方も含まれている倫理審査委員会での審査を受ける事が必要ですが、臨床研究において、第一歩は「被験者の立場を意識する」ではないかと思います。
以前、研究費の審査に関わったときに、研究計画調書にヒト由来検体を使用すると書かれているのに、その検体を使用することの倫理的配慮に関しての記載のないものを何度か見ました。今回、自分のわずかな経験を踏まえ、「被験者の立場を意識する」重要性を紹介させていただきました。
著者紹介 (独)国立循環器病研究センター研究所分子薬理部(室長)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 4月 2014
生物工学会誌 第92巻 第4号
岡部 満康
アンチエイジング治療とは、より美しく老いたいという願いもこめ、人間の本来の姿、本来の寿命、至適な状態に心身ともに持っていく事を目的とする医療である。秦の始皇帝はアンチエイジングの妙薬を探し求めたが結局その夢は叶わなかった。しかし後漢時代(25–220)にはいると『神農本草経』に不老不死の霊薬として霊芝(マンネンタケGanoderma lucidum)を珍重していた事、また我が国の卑弥呼(邪馬台国)から献上されていた事などが記されている。
美しく老いることへの障害物はガン、高脂血症、糖尿病、アルツハイマー病などがあるが、目下のところ最大の難敵はガンで、我々高齢者のアイドルであった島倉千代子さんの例にもあるように、最近有名人のガンによる死亡がマスコミを賑わしている。我が国には元々シイタケ、カワラタケ、ヒメマツタケなどのキノコをよく食べる人はガンになりにくいという民間伝承があったので医学、薬学および農学分野でキノコは絶好の研究テーマになり、遂にシイタケから免疫機能を有する多糖が分離精製され、この有効成分がβ-(1,3)(1,6)-グルカン(以下β-グルカンと略称)であることが明らかとなった。これは1985年抗悪性腫瘍剤(レンチナン)として認可され、現在もさらに改良されて使用されている。なお、β- グルカンには高脂血症や糖尿病などに対しても何らかの予防・治療効果があると報告されているが、基礎、臨床両面から研究が鋭意進められている。β- グルカンはその後キノコ以外にパン酵母細胞壁などに含まれることが明らかとなったが、昨年そのパン酵母細胞壁β-グルカンの免疫機能に関わる分子生物学的研究がカリフォルニア大学などの研究グループによってNatureに発表された。
最近バイオの最先端技術を駆使して分子標的治療薬(モノクロナール抗体)なる抗ガン剤が開発されたが、副作用も強く、なるべく投与量を下げる必要性が出てきた。補体と結合したガン細胞と好中球や単球などのエフェクター細胞との結合をβ-グルカンがさらに強化する事により、薬効(補体依存性細胞傷害など)を高め、結果的に副作用を抑える事が可能な事がルイズビル大学などの研究結果から明らかとなり、複数の分子標的薬とβ-グルカンとの併用治療法が現在米国でそれぞれ臨床実験に入っている。
アメリカではβ-グルカンがアンチエイジング治療のエースとして食品添加物やサプリ、さらには保湿性が高く、しかも免疫機能を有する事から化粧品原料としても大量に製造販売され始めた。従来β-グルカンの供給源はキノコやパン酵母細胞壁に限られていたが、これらを前記目的に利用するためには固形物からの分離精製が必要となり、その過程でアレルギー物質などが混入する可能性が高く、またキノコ栽培が大量生産になじまないなどの背景もあり10年ほど前から黒酵母菌(Aureobasidium pullulans)による発酵生産法の開発が始まった。同菌による醗酵生産はさまざまな理由からスケールアップが非常に困難であったが、いわゆる当学会18番(オハコ)の発酵工学的手法により、抗生物質やアミノ酸同様に商業用大型発酵タンクでの培養が可能となり、キノコやパン酵母細胞壁由来と機能的にも品質的にも勝るとも劣らない発酵β-グルカンの生産が可能となった。しかし、その培養は大変奥が深いものであり、今後も絶え間ない技術革新が必要である。そのためにも当学会の果たす役目は大きい。今後、よりよい培養方法が確立され、β-グルカンの用途の多様化と拡大が進み、いつまでもより美しく、より健康でありたいという始皇帝以来の人類の究極の夢の実現に一歩でも近づくことを希望してやまない。
著者紹介 静岡大学名誉教授・日本生物工学会功労会員 工学博士・技術士(農芸化学)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 3月 2014
生物工学会 第92巻 第3号
小埜 和久
自然科学を探求することで、自己の考え・思いを具現化する「学術・研究」生活を卒業し、次世代を担う人材を育てる「教育」生活に身を転じた。生活スタイルの劇的変化に伴うカルチャーショックによる戸惑を感じつつも、今までの生活では得られなかった多くのことを学び楽しんでいる今日この頃である。これを機に、アメリカで研究する機会に恵まれた経験を基に、当時感じた日米の教育格差の一端を回想しつつ、人材育成としての「教育」のあり方についての思いを述べてみたい。
渡米後、はじめに驚いたことは、博士課程(博士課程後期)の学生が高度な講義を受けていたことである。しかも、講義資料には、当時の代表的な生化学の教科書がすべて引用され、教科書出版後の研究の進捗にも対応して、速報版Current Contentsに収録された論文の研究内容も瞬く間に収録され、常に最新の知識が提供されて学生に刺激を与えていた。ここに博士研究員の段階で大きく伸びる要因の一つがあり、まさに“抗体産生機構”を連想させて人材育成としての基盤となる「教育」の重要性を感じた。
次に、“独創的な研究”を高く評価する土壌があることである。ヴェクトルは“いかに独創的な研究ができるか”が研究者に求められていたのである。生化学分野の発展に貢献した研究業績から、日本人では岡崎令治、八木國夫、早石修、利根川進博士がよく知られていたが、日本ではどうだろうか?アメリカの糖質関連のある研究者の一例であるが、当時29歳にもかかわらず論文数98報もあり、将来この分野の指導的な役割を担うだろうと日本では目されていたが、助教授から准教授への昇任は認められなかった。理由は明快で、1)彼の全論文に先行論文があり、それぞれに類似しているために研究のoriginalityが低い、2)彼が雇用した博士研究員が独立した研究者として育っていない、というものであった。日本ではどうだろうか?と衝撃を受けた。これも、個性(=独創性)を大切にして、これを伸ばす「教育」ができるかどうかが、人材育成を担う研究者・教育者としての評価の底流にあるように思えた。
一方で、アメリカに滞在していた間に、日本でも独創性の高いものを見抜く目や独創性を育む教育環境を創成する努力があることを知った。Current Contentsの裏表紙に、当時、もっとも引用された文献の著者によるコメント欄があり、東北薬科大学の箱守仙一郎先生が開発された糖水酸基の完全メチル化法についての投稿秘話が書かれていた。そこには、J. Biochem.にFull paperとして投稿してrejectされたが、当時、Editorをされていた山川民夫先生から“独創的な研究”と内容で評価され、Noteで出すことを勧められたと書かれていた。山川先生が評価されなければ、一世を風靡した箱守法は陽の目を見なかったかもしれない。また、早石修先生がMiami Winter Symposiaでの招待講演後、懇親会で「自分の弟子、あるいは孫弟子の段階で、ノーベル賞が受賞できる研究者を育てたい」と述べられておられた。早石先生もまた、今でいうiPS細胞研究所のような独創的な研究を推進する機関を想定され、そこでノーベル賞級の研究者を多く輩出したいと考えられたのだろう。
中教審答申で「学習」から「学修」へと大学教育の質的転換が強調されている。現実に戻って、“学生の主体的学びを促して将来性豊かな人材を育てたい”と考えていた時に、「学生の主体的学びを促す学修ポートフォリオによる授業改善」という講演を聞く機会に恵まれた。教員のための「ティーチング・ポートフォリオ」と学生のための「ラーニング・ポートフォリオ」を上手に組み合わせた「学修ポートフォリオ」が授業改善に効果的であるとのことであった。次々と多用される「ポートフォリオ!?」とは何ぞや?と感じる固い頭に悩まされながら、素晴らしい可能性を秘めた、次世代を担う個性(=独創性)豊かな人材が大学教育の質の向上によって育つことを夢見つつ、日々、試行錯誤を繰り返している。
著者紹介 広島工業大学生命学部食品生命科学科(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 2月 2014
生物工学会 第92巻 第2号
西野 徳三
世の中がいわゆるバイオブームで沸いていた昭和63年、バイオ系の研究者や研究機関の数としては西高東低と言われた(それ以降は耳にすることは少なくなったが、当時はそのように呼ばれていた)東北の地にも生物化学工学科が東北大学工学部化学系の学科改組で誕生した。時を同じくして当時の通産省の肝いりで全国にできたバイオテクノロジー団体の一つ「東北地域バイオインダストリー振興会議」(通称TOBIN)もバイオ団体としては東北地域唯一の組織として発足し、私も当初から副会長のかばん持ちとして関与することとなった。
TOBINの発足時は東北大学の農学部と工学部が主となり三つの部会を擁する大きな組織でバイオテクノロジーの情報発信や啓蒙活動を行ってきた。しかし、時代の波に乗って目新しさにひかれて会員になったものの、企業にとっては成果が得られるのに時間がかかると見切りをつけて早々に退会する企業が続出した。その後は小人数ながらも活動して多くの人的ネットワークを構築しながら現在につながっている。しかし、今でいうところのコンソーシアムを作るとか、コーディネーターとしての機能を持つまでには至らなかった。
私自身工学部に移り地域への貢献が必要となると同時に、TOBINの活動とも相まって多くの地元中小企業との接触が増え、専門以外の雑多な相談や質問を受けることになった。たとえば農水産物業者から残渣の有効利用や排水処理、さらに生ごみ処理の新規微生物探索に関して、飲食業界の排水中の油分解に関して、種々の健康食品・機能性食品の製造法や機能に関してなどの相談、また、養豚業者や堆肥施設での臭気対策、特殊土壌菌の評価の依頼、はたまた美白化粧品の製造法などの話が集まるようになった。インターネットのまだない時代にそれらに応えるため、その都度情報収集に奔走し、当時は新たな挑戦の日々であった。そのような交流の中から人と人の輪ができ上がり、新しい製品や改良につながったものも多く、産と学との連携において、さらに官との関連において人の果たす役割を痛感した時代であった。
中小企業からの質問・相談に対する討論にあたっては学からの内容を理解してもらう困難さを再三実感した。バイオとは直接関係のない異業種の中小企業の社長さんが相談に見えた時などはなおさらであり、間入って双方の溝を埋めるか通訳(?)をしてくれる人がいないもどかしさを味わいながら努力したものである。
その後しばらくしてから方々にリエゾンオフィスが設置され、さらに母体の異なる種々のコーディネーターが組織化されてそれらの役割を果たすようになり、それまでの産から学への個人的な方向だけでなく、確実かつ的確なパイプで意思の疎通ができるようになり喜ばしいことと感じた。さらに学から産への情報の流れも加速されるようになり、ニーズ指向よりシーズを広める方向に変化していき、さらにその上研究シーズの発掘も手助けしてくれるように変化してきたことは大きな進歩と思われる。それに加えて、学において細々と行ってきた研究成果をも、しかるべき研究費獲得へと助言してくれ、特許申請の情報まで提供してもらえるように変化したなど、産学官の連携も様変わりしてきたように見受けられる。
しかし、すべての連携がこのように手厚い手助け・援助のもとにあるわけではなく、ベンチャー的な研究や過去からのつながりのあるものなどはやはり個と個との関係に結びついた提携も多く残っており、中小企業に対しての技術の移譲や共同研究を進めるにあたっては科学的知識が伝わるような人と人とのつながりが重要である事を改めて実感している。
著者紹介 東北大学名誉教授、公益財団法人日本化学研究会(理事)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 1月 2014
生物工学会誌 第92巻 第1号
会長 園元 謙二
30世紀の西暦2922年、惑星連邦生物工学会は創立1000周年を迎えた。惑星連邦生物工学会は、21世紀の日本生物工学会、22世紀の地球生物工学会などを経て、24世紀の星間連邦国家設立に伴って、連邦加盟惑星の生物工学に関する研究の進歩普及、人材育成の推進、産学連携の促進、人的交流の促進、星間連邦国家協力の促進を図り、もって惑星連邦の学術および科学技術の振興、福祉の発展に寄与することを目的として拡大・改組されたものである。
約300の惑星および植民星が加盟している。これまでの科学技術の進展より、21世紀では不可能と思われたSFもどきのことが30世紀では実現している。たとえば、21世紀初頭に明らかとなった物質に質量を与えるヒッグス場は宇宙空間に常に存在しているため物質を光子のように光速で動かすことができないと言われていたが、ヒッグス場を瞬間的に遠ざける技術革新によりいわゆる『ワープ』が最近可能となった。また、星間連邦国家ではいくつかの種族が独自の言語を使用しているため、高性能な宇宙翻訳機は24世紀に早々と開発されている。
一方、生命科学分野では、生物ゲノム情報の解析が進み、休眠遺伝子やジャンクDNAなどの機能が明らかになり、合成生命の誕生や合成微生物からヒト臓器の作製などが実現している。さらに、記憶の階層研究が進み、コンピュータでの情報の保存・上書きに相当するヒトでの他者の記憶の転移などが可能となっている。しかし、高度の記憶情報処理、たとえば記憶の干渉・再構成やインスピレーション力、セレンディピティなどは未開拓事例である。場面が変わり、惑星連邦下の学会では、加盟惑星の種族、年代の相違による交流の低下と次世代の育成が問題になり、連邦理事会・代議員会で議論が続いている。
“これは21世紀の学会と同じ悩みだ。学会の伝統を重んじ、かつ新たな進展を担う次世代の若手育成は30世紀の科学技術でも対処できないのだな!”と思っていると目が覚めた。前述の夢は、子供の頃、ガガーリンの人類初の宇宙飛行(1961年)、人の月面歩行(1969年)に歓喜し、テレビの『宇宙大作戦』やその後の映画『スター・トレック』で空想し、そして私自身の科学的瞑想の世界から生まれたものであった。面白い初夢を見たものだ。
ここ数年、生物工学若手研究者の集い(若手会)の夏のセミナー(泊まり込み合宿)に参加しています。他には若手会の幹部との飲み会などを通じて、次世代を担う若手を知り、交流する喜びを感じています。この過程から私は今後も次世代を担う若手が続々と出てくると確信しています。ただし、人材育成に携わる年齢になった者(シニア)が若手との交流で大事にすべきこととして、SNSでも可能な単なる“チャット(雑談)”ではなく、Face to Faceを最大限利用した会話、特に目先の課題より自らの経験・情熱などを語りかけ、彼らの興味をかき立てることから始めるとよいと思います。
シニア自身は独自の価値観を持っていますが、その範疇を飛び越える若手にも寛容である、むしろ喜びとする余裕が必要でもあると思います。望外には、彼らの夢や才能を引き出すことができ、自らも高揚できればと思います。夢を紡ぎ、次世代に繋ぐためには、若手との共感・共有からスタートし、若手に学会のことを知ってもらうことも重要と思っています。右頁の提言は、2013年7月、宮崎での若手会の夏のセミナーで講演した際の私の要旨から抜粋したものです。大学人としての私の経験と価値観が背景にありますが、若手に少しでもお役に立てればと思います(准教授、教授版もありますが、ここでは割愛します)。なお、別の機会に産での人材育成をぜひお聞きしたいとも思っています。
異色の年頭所感となりましたが、年代を超えた交流の促進が30世紀の科学技術でもなし得ない世界へ我々を導いてくれると信じて、年頭のご挨拶といたします。
≪大学の3つの階層(年代別)への提言≫
学部生、修士課程学生
- 目標とする人を持つ
- 深く考える(脳に植えつける)
- きちんと学ぶ姿勢が大事、これがないとどんなサポートをしてもダメ
- この時期は研究に没頭する時期
- エリート意識を持つ
- 実験事実は経験を凌ぐ!
- 常に問題意識を持つ(なぜ?など)、ここからInspiration, Serendipityが始まる、これがないと単なる技術習得になる
- 真面目は最大の長所であり、欠点でもあることを認識する
- 先生や年長者を恐れるな!同じ研究者として対話する、ただし、敬意は払う
博士課程学生
- こだわりは持つ、しかし諦める決断も大事(頑固と柔軟性)(独りよがり、唯我独尊に陥らない)
- 取捨選択、視点を変える
- 自分と同じ人間は居ない!先で待つ余裕、意外な(想定外の)展開と喜び
- 異分野の人とつき合う、特に世代を超えて
- 世界にはすごい研究者が居る!
助教
- バックグラウンドは大切に、しかし他分野へのチャレンジ
- 個の力と集団・組織の力(1 + 1は?)、個性か組織か? → 旗印の重要性
- 道場破りをする(新たな刺激と展開のために)
- 集中と開放:研究を離れる時を持つ、研究は人生の一部
- エリートを育てる、すべての学生?
- 世界のトップに立つことをいつも意識する、困難を伴うがチャレンジする気持ちがないとダメ
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 12月 2013
生物工学会誌 第91巻 第12号
下田 雅彦
産学官連携が、我が国の科学技術振興や地域活性化の一翼を担う重要施策と位置づけられて久しい。筆者は、九州地域の伝統醸造産業である本格焼酎製造現場でさまざまな技術課題に関わってきた。その経験を踏まえて、産学官連携における技術者視点の重要性について述べてみたい。
大分県の麦焼酎は、1970年代にろ過・精製技術の進歩や減圧蒸留機の普及に加えて、麹原料も大麦を使用し、麦麹・麦掛け仕込み(麦100%)を特徴として商品化された。その後、1980年代の第1次焼酎ブームの追い風に乗り、生産量が飛躍的に伸長したが、製造技術確立の為の研究は緒についたばかりであった。「麦焼酎に適した大麦の新品種開発」は、1企業の取組みでは不可能なテーマで、農林水産省九州農業試験場(現農研機構九州沖縄農業研究センター)、大分県農業技術センター(現大分県農林水産研究指導センター)、大分県酒造組合などを中心とした産(学)官連携の課題として1994年にスタートした。1998年には、新品種「ニシノホシ」が全国で初めて麦焼酎に適した麦として大分県の奨励品種に登録された。その後、2001年に麦焼酎「西の星」が弊社より発売され、以来、地元で焼酎原料麦として毎年1000トン以上生産されている。
この取組みは、地産地消の先端的成功事例の一つとして高く評価された。産・学・官は言うまでもなく3者が異なる「場」と「目的」を持っている。大学は「研究ニーズと技術シーズを深堀する場で、科学技術進歩への貢献と研究成果の技術移転が目的」である。産業界(企業)は「技術開発と商品化による市場競争の場であり、事業展開による企業経営が目的」となる。さらに、行政は「制度・行政による社会支援の場であり、地域振興・産業経済の活性化が目的の一つ」である。異なる「場・目的」の発想からの連携論議では、表面上の形を整えても技術シーズ移転・技術開発・商品開発・製品化はうまくつながりにくいと感じている。
その理由は、先の事例でいえば製品化までの過程で、二つのハードルがあり、そのハードル越えは「場・目的」の連携ではなく、別の捉え方である「機能・人」の連携によって成し得るからである。すなわち、第1のハードルは、「基礎研究・応用研究を担う科学者・研究者」から「技術開発・実用化を担う技術者」への連携である。そして、第2のハードルは、「技術開発・実用化を担う技術者」から「成果の普及・製品化を担う行政・経営者」への連携である。この二つのハードルはベンチャー起業における魔の川、死の谷のハードルと同様と捉えても差し支えない。その成否の鍵を握るのは中心となる次のような人材の連携と考えている。
すなわち、1)「技術者視点を持った科学者・研究者」から2)「経営者視点を持った技術者」へ、さらに、2)「経営者視点を持った技術者」から3)「技術開発に理解のある経営者・行政」への連携である。これは、麦焼酎用の大麦品種の概念が存在しなかった段階で、試験系統の麦を研究開発用に準備していただいた研究者から、求める品種特性を設定し選別する行政・企業の技術者への連携、さらに、新品種麦の栽培普及と企業への産業利用の働きかけを担う行政、商品化を弊社経営層が決断したことで実現した連携を考えると理解しやすい。
ここで、人材について2)「経営者視点を持った技術者」、3)「技術開発に理解のある経営者・行政」は理解を得られやすいが、1)「技術者視点を持った科学者・研究者」については少し補足説明したい。筆者は以前、「JABEEと企業」という拙文を本誌に寄稿する機会を得たことがある1)。その頃から、技術者教育に関心を抱いていたが、日本技術者教育認定基準にある学習・教育目標の多くは、たとえば「種々の科学・技術・情報を利用して社会の要求を解決するためのデザイン能力」など、産学官連携を推進する人材に必要な素養や能力に合致する。その意味で、技術者視点を持った科学者・研究者の存在は重要である。
最後に、麦焼酎の製造技術に関わる30年近い取組みの中で、弊社では7名が博士号を取得し、今年ようやく技術士(生物工学部門)が1名誕生した。多くが産学官連携の成果であり、ご縁をいただいた大学や公設研究機関の先生方に深謝申し上げる次第である。
1) 下田雅彦:生物工学、82, 331 (2004).
著者紹介 三和酒類株式会社(専務取締役)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 11月 2013
生物工学会誌 第91巻 第11号
浅野 行蔵
技術士(Professional Engineer)という制度がある。産業分野のほぼすべてをカバーする21の技術部門に 専門が分かれており、生物工学部門もその一つである。私は企業経験があったこともあり、紹介されて技術 士試験を受験し、幸いにも技術士となれた。現在は学生に技術士(補)になることを大いに勧めている。
私どもの学生のほとんどは修士課程に進み、修了後は産業分野へと巣立ってゆく。技術士(補)であると、 社会へ出てからの技術ネットワークを拡大しやすいことに気がついてからは、積極的に学生に受験を勧めて いる。
技術士とは国による資格認定制度(文部科学省所管)で、国によって科学技術に関する高度な知識と応用 能力が認められた技術者という位置づけになっている。
発端は、第二次世界大戦後、吉田茂首相からの荒廃した日本の復興に技術者の奮起を促すことへの強い要 請を受けたことにあり、「国の復興に尽力し、世界平和に貢献するため、社会的責任をもつて活動できる権 威ある技術者」を資格化するため、米国のコンサルティングエンジニア制度を参考に「技術士等の資格を定め、 その業務の適正を図り、もって科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的」とした技術士法が制 定された(1957年)。生物工学部門は、18番目の部門として新設された(1988年)。
私が学生に技術士(補)になることを薦めている理由は、生物工学部門の活発な活動の中に入ることで得 るものが大きいからである。第2土曜日には、会員同士の発表会、外部講師の講演会などを開き、発表後の 多様な質疑応答では、参加者の知識と経験の幅の広さを感じることができ、発表が2倍おもしろくなる。年 に1度は、見学会でいろいろな地域の会社や研究所を訪問している。運営は、それぞれ職を持ちながらのボ ランティアで、多様な企画を進めている。もっとも活発なのは東京だが、地方でもそれぞれ活動している。 北海道も人数は少ないが定期的な集まりを開いている。
生物工学部会は、1990年に合格者8名によって活動グループとして発足し、技術士121名、技術士補179 名(2013年現在)に成長した。若い技術士補が多いのも特徴である。出版活動も熱心で10周年記念「バイ オの扉」(2000年)、「もう少し深く理解したい人のためのバイオテクノロジー」(2007年)、「翻訳 バイオエ レクトロニクス」(2008年)、「新 バイオの扉」(2013年)と上梓している。
生物工学分野はどんどんと発展しており裾野も広がっている。学会では出席しないような分野の話を聞い て、新たな発想が浮かぶことも多い。社会へ出てからは、会社を超えて同業あるいは近い分野での気の置け ない友人を作るチャンスが少なくなる。切磋琢磨できる友人を得られることが、私が学生に技術士(補)を 薦める大きな理由である。種々の会の後には懇親会があり、情報と熱い気持ちの交流となっている。その中 で互いの技術の機密部分は尊重するマナーも学ぶ。
技術士1次試験に合格すれば、公益法人日本技術士会に登録することによって技術士補となる(登録料 と年会費が必要)。技術士補から技術士へは、2次試験を合格する必要があり、合格率は10~30%程度である。
シニアの方も技術士になられることをお勧めします。技術屋の長年の目的として定年とともに受験される すばらしい方々もおられます。若い人と飲むのも楽しく、若い人にご自身の知恵と経験を伝えるのも喜ばれ、 そして若い人と意見が合わないこともあり、その中から新しいアイデアもわいてきます。シニアも楽しめる 技術士生物工学部門です。
著者紹介 北海道大学農学部応用菌学(技術士)(生物工学/総合技術管理部門)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 28 10月 2013
生物工学会誌 第91巻 第10号
林 英雄
今では死語に近い「学園紛争」の時から45年間を過ごした大学における教育研究活動を終え、私は3月末に定年退職した。学園紛争におけるスローガンの一つが「産学連携反対」であったように記憶している。今では想像もできない時代であった。本稿では大学、特に国公立大学における教育研究に関して気になる点を記載したいと思う。
私は興味の赴くままに研究室の教員と共同研究を行ってきた。その一例としてアーバスキュラー菌根菌(AM菌根菌)と植物の共生に関する研究を取り上げてみたい。研究室を主宰することになった1996年に、新たに採用した助手と新しい研究課題「菌根共生」に取り組むことにした。4.6億年前に始まった菌根共生は80%以上の陸上植物に見られる普遍的な現象であり、共生がどのようにして起こるかは興味深い課題であった。しかしながらAM菌根菌が絶対共生菌であるためその取り扱いが難しいこともあり、当時天然物化学の研究対象ではなかった。AM菌根菌の取扱いに習熟した後、宿主認識シグナル物質の同定を目指した結果、2005年にシグナル物質がストリゴラクトン(SL)であることを世界に先駆けて明らかにした1)。SLは根寄生雑草の種子発芽刺激因子として知られている物質群であった。後にSLが植物の枝分かれを制御していることが明らかにされ、これらの研究成果が認められ、2012年にトムソンロイター社から第3回リサーチフロントアワードを4名の研究者とともに受賞した。研究成果が得られるにつれて研究費は得やすくなったものの研究開始当時は当然ながら乏しい研究費であった。
大学教員の研究費は科研費に多くを依存している。2012年度学校基本調査報告書によると国立大学および公立大学、私立大学の本務教員数はそれぞれ62,825名および12,876名、101,869名である。また、文科省資料によると2013度における新規採択と継続分を合わせた科研費の採択件数は国立大学および公立大学、私立大学それぞれ39,101件および5207件、18,002件である。2013年度の教員数も2012年度と同じであると仮定して、重複して採択されている教員あるいは研究分担者として科研費の配分を受けている教員を考慮に入れると国立大学では6割、公立大学では4割程の教員が科研費の補助を受けているのではないかと想像される。また、1課題あたりの配分額の平均は222万円余りである。分野別の採択件数が生物系49.2%、理工系28.3%、人文・社会系19.0%であるのに対し、配分額は生物系47.9%、理工系36.3%、人文・社会系12.4%であるから、理工系は平均額以上の配分を受けているものと思われる。ここで私が特に注目したい点はかなり多くの教員が科研費の配分を受けていない点である。
校費として配分される基盤的教育研究費減少し、社会貢献として産官学連携を促進することによる
外部資金を獲得することが教員に求められている。さらに、教員は科研費以外の競争的資金の獲得を目指さなければならない。このような研究費を目指すためには自ら研究テーマを研究費獲得に有利なものにせざるを得ない。本来、いつ社会のために役立つかは不明であっても、未知の現象を明らかにする研究が大学においてのみ可能な研究活動ではなかっただろうか。研究費獲得のためとはいえ、研究テーマの設定が影響される事態は憂慮すべきものと考える。
現在、種々の巨大プロジェクトが動いている。これらにも参画していない多くの教員は乏しい教育研究費で日々の活動をしており、彼らの研究室で活動している学生諸君もまた劣悪な環境に置かれていることが容易に想像される。前述の報告書によると2012年度の在籍学部生数は国立大学618,134名、公立大学145,578名、私立大学2,112,422名である。また、大学院の修士課程および博士課程に在籍する学生数は全体でそれぞれ74,985名および15,557名である。何割の学生が充分な経費を用いて研究実験をしているのであろうか。
社会で役立つ課題解決能力を習得するための教育研究を充実させるとともに、教員および学生にとって大学における最低限度の教育研究を行うことができる基盤的教育研究費の整備が強く望まれる。なぜなら、このことが日本の活力を下支えすることにつながるものと思うからである。
1) Akiyama, K. et al.: Nature, 435, 824 (2005).
著者紹介 大阪府立大学名誉教授 兼 (株)ファーマフーズ技術顧問
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 26 9月 2013
生物工学会誌 第91巻 第9号
大島 泰郎
間もなく「ヒトゲノム解読終結宣言」10周年の日を迎える(この稿が出るころは記念日は過ぎているだろう)。ヒトゲノム解読を頂点とする生体分子に関する構造および機能の解析に関する研究は、ヒトゲノム計画が始まるほぼ100年前、ブフナー兄弟が発見した「生命なき発酵」が切り拓いたin vitro実験法に依存してきた。やがて、タンパク質など生体分子を単離、精製する実験技法が確立し、純粋な系、たとえば単一の酵素とその基質、補酵素のみからなる「反応液」を用いて生体分子の構造や機能が解明されてきた。今日の分子医療、創薬、バイオテクノロジー、環境技術のすべてが、in vitro実験から得られた成果に基礎をおいていると言っても過言ではあるまい。
いまでは一般向けの科学雑誌やテレビの科学番組でも使われるほどになっている「イン・ビトロ」であるが、果たして生体内の環境を反映しているだろうか?
この疑問は好熱菌の研究をしていると避けられない。抽出してきた酵素タンパク質は安定であるが、基質や補酵素が生理的な温度では速やかに分解し、酵素活性が測れない。たとえば、キナーゼ類ではATP、糖代謝では三炭糖のリン酸エステル、これらは好熱菌の生理的な温度である60°C以上の温度では速やかに分解するので、多くの場合、好熱菌研究者は非生理的な低い温度で酵素活性を測定している。
また、好熱菌でなくても、酵素などタンパク質自体の安定性は、生きている細胞内ではもっと高濃度なので無細胞抽出液で観察されるよりずっと安定と一般に信じられている。生化学・分子生物学研究者の深層心理には、in vitroが細胞を再現していないという「うしろめたさ」があったはずである。
ある有名な教科書には、細菌の細胞内のタンパク質など高分子成分の重量パーセントは26%と書いてある。その大部分がタンパク質であろうから、細胞内のタンパク質濃度はおおよその見当として25%くらいと考えてよいであろう。われわれの技術では、こんな濃度のタンパク質溶液は作れないが、無理やり濃くした5%タンパク質溶液はすでに粘稠であるから、細胞内はトリモチ(若い人には死語かな?)のようなどろどろの状態であろう。こんな中にあるATP は、60°Cでも90°Cでも水に出会う機会すら少く加水分解も起こらないかもしれない。タンパク質もギュウ詰めで、よく議論される「X線構造解析の結果は、“溶液”中のタンパク質と違う」という結晶構造学者に対する非難めいた議論も逆で、細胞内のタンパク質は身動きもできない結晶内と似ていて、結晶構造解析の結果は細胞内のタンパク質の挙動をよりよく反映しているのかもしれない。
1897年、ブフナー兄弟の「生命なき発酵」の発見以来、生命科学の研究手法の中核であった“in vitro”実験は、細胞内の生体反応を忠実に再現しているとはいえない。最近、より細胞内環境に近い「無細胞抽出液」を作ろうとする研究が始まってきた1)。このような研究は、これまでの希薄溶液で得られてきたkm、kcatなど酵素反応のパラメータ、コンフォメーション変化などの動的な挙動、それらに基づいて作られてきたタンパク質の概念とは違った新たなタンパク質研究の世界を拓くのではないだろうか。
われわれは、細胞内のタンパク質の構造も機能も正しくは理解していない。細胞内のタンパク質を正しく理解できれば、そこから生まれる新しい知識が、新しいバイオテクノロジーを拓くであろうことは言うまでもない。
1) Fujiwara, K. and Nomura, S.: PLoS one, 8, e54155 (2013).
著者紹介 共和化工(株)環境微生物学研究所(所長)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 28 8月 2013
生物工学会誌 第91巻 第8号
高木 昌宏
生物工学会が関連する分野で昨年一番の話題と言えば、やはり山中伸弥先生のノーベル生理学・医学賞の受賞であろう。
賞の決定に関する「ある新聞」の報道は、以下の通りであった。
「スウェーデンのカロリンスカ研究所はこのほど、2012年のノーベル生理学・医学賞を、再生医療の実現につながるiPS細胞を初めて作製した京都大学教授の山中伸弥iPS細胞研究所長と、ジョン・ガードン英ケンブリッジ大学名誉教授に贈ることを発表しました」
一般の方々はもとより、本誌のおもな読者である生物工学会会員の皆さんですら、この報道内容に対して多くの疑問を持たないと思う。しかし正式な授賞理由は、この報道とは少し異なっている。授賞理由は、“for the discovery that mature cells can be reprogrammed to become pluripotent”(分化後の成熟細胞であっても多分化能細胞へ再プログラムすることができることの発見)である。「再生医療の実現につながるiPS細胞」は、応用面での可能性について言及しているに過ぎず、正式な授賞理由と若干のかけ離れがある。しかし新聞報道の読者である一般の人に、「成熟細胞」や「多分化能」といった馴染みの薄い生物学の専門用語を用いたところで、理解を得られないであろう。「それ何に役立つのですか?」という質問が飛んでくるに違いない。「再生医療の実現につながるiPS細胞」は、確かに分かりやすい説明である。
天然資源の少ない日本は、「科学技術創造立国」を目指さなくてはならない。このことに疑問を挟む余地はない。ところでその「科学技術」とは、いったい何なのだろうか? 周囲の何人かに「科学技術とは、技術なのか?」と尋ねてみると、多くの場合「技術ですよ」と返ってくる。英語のtechnologyの日本語訳を科学技術としている辞書もある。一方、私の所属する大学は「先端科学技術大学院大学」であるが、その「科学技術」の英語訳は“science and technology”である。これは直訳すると、「科学と技術」になる。「科学技術」に対するイメージが、日本語と英語で微妙に異なっている。
そのつもりで調べてみると、「科学・技術」と中黒を入れるべきだとの議論もあり、「中黒問題」と言うらしい。しかし、科学と技術は不可分な側面もあるので中黒で区切るのにも、私には違和感がある。学術会議会長を務められた金澤一郎先生は、中黒肯定派である。「科学技術」と書くと、技術が主役で、科学が修飾語になることを懸念する有識者の一人である。サイエンスライターの元村有紀子氏は、マスコミを中心とする科学報道の視点が「役に立つ」に傾きがちで、それが国民や政策決定者の意識に影響を与えている可能性があるとも指摘している。昨年のノーベル賞報道にも通じるコメントである。「役に立たない」を理由に、基礎科学が切り捨てられては、科学技術創造立国など実現できる訳がない。
こんな議論を、かつてしたことを思い出した。進路に悩んでいた高校生のころに、工学と理学の違いについて青臭い議論を仲間と交わしたことである。その当時の理学部進学者は、ほとんどみな博士後期課程へ進学した。しかし聞くところによると最近では、理学部でも博士後期課程進学者が減り、就職希望者が多数なのだそうである。「科学が修飾(就職)?」とは、ダジャレのようだが、これも中黒問題の影響であろうか?
簡単には結論が出そうにない。科学と技術、そのどちらもが大切で、その両者は微妙に対立している側面もありつつも、またオーバーラップもしている。そんな背景が、この問題を複雑にしている。
「科学か、技術か」の二元論ではなく、それぞれの科学者、技術者、そして研究テーマに、比率こそ異なっていても「科学」と「技術」の両方が混在しているはずである。まさに、Science and Technologyなのである。かつては学生達に、「何に役立つか考えましょう」と指導してきた。しかしこれからは、「どこがサイエンスで、どこがテクノロジーなのか考えましょう」と指導するつもりである。「何かに役立てたい気持ち」、そして「役立たなくても分かりたい気持ち」、そのどちらも大切に育めないだろうか? それはたとえば、就職活動が、うまくいっても、うまくいかなくても、充実していたと満足できる学生生活をおくって欲しいと思う気持ちに近い。
「成熟」と「多分化能」の両立は困難である。しかし、そこに価値を見いだしたい。
著者紹介
北陸先端科学技術大学院大学マテリアルサイエンス研究科(教授)
日本生物工学会理事・英文誌(JBB)編集委員長
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 26 7月 2013
生物工学会誌 第91巻 第7号
石埜 正穂
ノーベル賞を受賞した山中伸弥教授の一連のiPS細胞研究の成果に関して、最近、一定効果の期待できる特許が登録されはじめている。だがここに至るまで、京都大学iPS細胞研究所では、専門家によるフォローに恵まれながらも、知財確保のために多大な苦労を費やしてきた。実際、大学などにおけるバイオ医学分野の基礎・先端研究成果の有効な権利化には課題が多く、困難を伴うのが常である。
こういった中で、米国のホワイトヘッド研究所は、「外来性に導入された、少なくとも一つの制御配列に動作可能に連結されたOct4タンパク質コード核酸を含む単離された初代細胞を含む組成物」というクレームを有する特許の登録に米国で成功している(US8071369)。同研究所が、このような、iPS細胞の標準的作製法のいわば中間産物を対象としかねない権利(解釈次第ではあるが)を成立させ得たのは、Oct4がES細胞の樹立を促進できることをいち早く示した同研究所のイエーニッシュ博士らの成果に着目し、きわめて初期の段階で特許出願を行い、しかもそれをうまく生かしたからである。これは、基礎・先端的研究の現場に密着した知財面でのフォローの重要さを物語っている(因みに当該出願は、日本の現在の大学発知財の支援環境では、無用な「スクリーニング発明」と断じられて日の目を見ずに終わりかねない類のものである)。
イノベーションの創出においては、自由な発想の基礎研究から出てくる知財の種をいかにうまく掬い上げるかが肝要となる。残念ながら、大学の研究現場における知財の作り込みには課題がある。企業と大学が基礎研究段階から共同で研究を進めるようなプロジェクトも走っているが、出口を意識するほど目的が具体化されイノベーションから遠ざかる側面もあって難しい。いずれにしても、イノベーティブな技術であればあるほど、実用化に際して制度・インフラの改革が要求される。したがって大学は、その役割として、知財にビジネスモデルも加えた新しい価値を自ら率先して世の中に提案していく必要がある。 医療分野であれば、医学研究者の見識を存分に生かしつつ、治療や診断の将来像の観点から、来るべき医療環境の革新に照準を合わせた特許を作り込みたいところである。
そう考えたとき、もっとも根源的な課題は、大学の研究者の大多数が、知財の視点を欠いたまま研究を遂行している現状にあるように思う。そもそも論文を書くとき、「成果が出ました。では論文を書きましょう。」ということにはならない。実際には、成果に至る最初の知見(きっかけ)を得てからも、仮説をたててストーリーを頭に描きながらその後の検証的研究を進めて論文を作り上げている。特許においても同様で、「発明が出ました。では特許を書きましょう。」というものではなく、効果的な特許の構築に向けた研究戦略が必要である。社会が大学の研究成果の知財化を求める以上、大学研究者が論文作成に必要なプロセスにしか精通していないのでは理に適わない。
つまり、知財管理体制の強化も重要だが、研究者自身の知財に関する知識・意識の向上こそ、イノベーション創出に必須ではないだろうか。そのためにまず欠かせないのは、裾野の広い知財教育の浸透であると思う。
たとえば、中学生の社会科などの中で医薬開発における特許の意味や重要性を教えるなど、義務教育における知財のイントロダクションの在り方も重要となる。イノベーション創出に向けた医学研究者のリテラシー教育という面では、特許の構造のみならず臨床研究の知識も必要だし、工学などの他分野の技術についての教育も有効であろう。
教育とは地道な作業であり、忍耐が必要である。大きな予算をともなう短期的なプロジェクトは、時に起爆剤となることはあっても、ある意味箱モノに共通した危うさがあり、教育がこれに依存するのは適切でない。医療イノベーションの創出のためには、長期的な視野に立った知財教育を戦略的に構築する必要がある。
著者紹介 札幌医科大学(教授)、医学系大学産学連携ネットワーク協議会(運営委員長)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 5月 2013
生物工学会誌 第91巻 第5号
木田 建次
諸先輩の教えに従い、依頼があればほとんどお引き受けしてきました。しかし今回の執筆にあたり文才もなく浅学の私は、ご依頼を受けるべきではなかったと反省しつつ、中国での現状と日常生活も含め記載させていただきました。東アジアでの共同研究の有り様の一助になればと思っております。
私は、1997年に学部間交流協定が締結された後、客員教授として四川大学(以後、川大と呼ぶ)を年1~3回訪問してきました。2011年5月に学部間覚書(熊大、研究室のバイオマス関連の機器の移設;川大、移設費と研究室の提供)の形で両大学の共同ラボを川大に設立することになりました。私は、長年の積み重ねと成都には4人の卒業生(会社会長1名、川大教授2名、企業研究者1名)が居りますので、定年後の2012年4月から川大建築与環境学院に赴任いたしました。環境学院の5階研究室(450 m2)はほぼ立ち上げることができ、研究も少しずつ始めています。現在、ベンチスケールで実証試験などを行うために、中規模実験棟(床面積1580 m2 うち約650 m2)に機器を設置し、その立ち上げに熊大中国人ドクター2人(うち1人、現、川大ポスドク)を含む学生さん達と一緒に頑張っております。当初、なぜ大学で実証試験が必要かと思ったのですが、中国では大学でもベンチかパイロット規模での実証試験を行わないと信用されないことがわかり納得したわけです。
さて日常生活ですが、自宅は望江校区の傍の川大職員住宅に住んでおり、130 m2と広くとても近代的に作られています。朝食は自宅で、昼食は学食で、夕食は自宅近くの食堂でとり、時々肩こり解消のためにマッサージに行きます。自宅から大学のシャトルバスで約40分かけて共同ラボのある江安キャンパスに通っており、構内が広くお陰で毎日1万歩程度歩いています。正月は成都に滞在する学生さん達がわが家に集まり、手作りの本場四川料理を味わいながら団欒しました。
共同ラボの正式名称は『環境生物技術中心』で、私の夢はバイオテクノロジーを駆使して四川省に賦存するバイオマスからのエネルギー創出、環境対策および環境調和型プロセスの研究開発を行い、資源循環型まちづくりを目指していくことです。最大の懸案事項は、人口の70%を占める農村部において環境調和型新農村を造ることです。具体的には昨年5月に川大のホームページに掲載されましたように、金堂県(成都市東北部人口84万人)と共同して新農村をつくることでした。このプロジェクトが前に進めば私の夢も一歩前進かと思っていたのですが、それにはまだまだ時間が必要と判明しました。なお、中国の行政区分は{省>市>県>鎮}の順になっています。
新農村に関して四川省環境保護庁の処長と懇談した後、別の県を視察しました。洪雅県(四川省眉山市人口35万人)の主たる産業は材木、お茶そして酪農(牛乳の生産だけ)です。成都市民(1000万人強)が飲む牛乳は、すべて洪雅県で製造されており、現在、飼育頭数は40,000頭にものぼり、その家畜糞尿による環境汚染が大きな問題となっています。洪雅県環境保護局から、川大の『環境生物技術中心』と共同して酪農地域で家畜糞尿のメタン発酵とコンポスト化を行い、さらに有機栽培した農産物を成都市に循環していく環境調和型農村造りを行おうとの提案を受けました。当初、研究から始めるものと思っていたのですが、そうではなく四川省に申請し、200頭あるいは400頭の家畜糞尿を利活用するプラントを造り、さらに堆肥を用いて有機栽培を行っていくというものです。このモデル事業終了後、中国政府に申請し洪雅県の酪農地域すべてを環境調和型にしていくという壮大な計画です。四川省環境保護庁も支援しており、その行動力にはまったく驚かされております。
わが国ではプロジェクト申請時には新規性が要求されますが、常温・常圧反応のバイオプロセス開発にはほとんど新規性はない、また新規性の多いプロセスほど実用化されにくいものと、私自身思っています。外部資金を獲得するために新規性を出そうとする傾向は、優れた技術を有していても産業化で後塵を廃する結果を招いているように思います。今後は文科省以外のプロジェクトでは実用化開発に予算を投入し、その実績を携えて中国や韓国と歩調を合わせ、よい意味での開発競争に打ち勝っていくことが、健全な国際協力につながっていくものと思う次第です。(2013.1.6投稿)
著者紹介 四川大学(教授)、熊本大学名誉教授
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 24 4月 2013
生物工学会誌 第91巻 第4号
野村 龍太
公益財団法人実験動物中央研究所(実中研)は60年の歴史を持った民間の公益法人の医学研究所です。医療技術・医薬品の開発には医療の現場のニーズから考えた最善の動物実験システムの開発が必要です。そのために実中研は、最適な動物実験システムを実現するための最良な実験動物作出システムを構築し、世界で他にない最先端の実験動物を開発、さらに実用化することによって最終的に人類の健康に貢献することを目的として活動しています。
創立者の野村達次は、当時の実験動物の低品質が医学研究の成果に影響しては医学の発展がないと考え、恩師安東洪次教授と実中研を設立しました。実中研の歴史の2/3に近い40年はこの再現性のある実験動物作りの技術と供給システム確立に注力しました。その結果、現在の技術が確立され、世界中で使用される実験動物やシステムが生み出されました。
これらの技術を使い、実中研では安全性試験分野での世界標準を作るべく努力しています。我々は、日本のみならず、世界中の行政当局と連携して長い時間をかけて、世界に認められる仕事をしてきました。
たとえば、ポリオの生ワクチンの神経毒力の検定に使われている遺伝子改変Tg-PVR21マウスは、都立臨床研におられた野本明男教授が作られたマウスをポリオ研と実用化を目指し、その後、実中研で大量生産技術が確立されたものです。さらに、このマウス30、000匹を米国FDAに無償で供給して、従来使われていたサルとの比較試験によってその優位性を実証することができ、最終的にWHOのポリオ撲滅世界プログラムの正式検定動物に認定されました。欧州の局方ではこのマウスを使った試験法が収載され、現在では世界の主だったポリオワクチンメーカーへ供給されるようになり、アジア・アフリカを含め世界中の子供たちの命を救うことに貢献できるようになりました。ここに至るまでに25年以上かかりましたが、これこそ実中研の仕事だと考えています。
このほか、新規医薬品開発時に使用される短期がん原性試験用の遺伝子改変マウスTg-rasH2マウスも国立医薬品食品衛生研究所などと開発し、FDAなどの規制当局と60社近い製薬企業が米国の公的機関ILSI・HESIの主導のもと20年以上の検証によって、漸く世界標準になりつつあります。これを使うとがん原性試験を2年から6カ月に短縮でき、世界の医薬品や医療機器を開発する企業に大きく貢献しています。
実中研のもう一つの仕事は、世界最先端の実験動物を生み出し、動物実験システムを構築して、医薬品の開発や新たな医療技術の開発を大学・研究機関・製薬企業などと共同で行うことです。その代表的な動物が超免疫不全マウスのNOGマウスです。この動物を使った研究から新たな抗体医薬やエイズ薬などの薬が開発されていますが、さらにこのNOGマウスを改良したヒトの臓器をマウスの体内に持つ、ヒト化マウスを利用することにより、医薬品の代謝や毒性試験がヒトの環境でできるようになってきました。これにより、動物実験がよりヒトの安全性を見ることができるシステムに近づいたと言えます。
また、実中研では世界で初めての小型霊長類の一つであるコモンマーモセットの遺伝子改変の作出に成功しており、現在は、パーキンソン病やアルツハイマー病の病態モデルを作出すべく尽力中です。
2012年には山中教授がiPS細胞でノーベル賞を受賞されました。インタビューでは実用化に向けて安全性の証明が何より重要と話しておられましたが、実際に安全性の検証では、いくつものプロジェクトでNOGマウスが使われています。現在では、国立医薬品食品衛生研究所と、世界の標準試験法の確立に向けて共同研究を開始しています。一方で脊髄損傷の治療や心筋を再生させる技術の開発・実用化の研究がマーモセットを使って行われています。このように実中研の最先端実験動物は、iPS細胞を使った技術の実用化やその他の幹細胞を利用した再生医療など、医薬品開発における新たなシステムとして世界中で使われてきています。
実中研は2011年7月に川崎市の殿町地区に移転しました。その後、この地域が国際戦略総合特区に認定され、新たな技術を世界に発信していくライフサイエンス拠点に位置することになりました。世界の人々が殿町に来て研究がしたい、技術を習いたいと思う研究所になっていくことを目指してこれからも頑張っていきたいと思います。
国際戦略総合特区に魂を入れていくことこそ我々の役割だと考えます。
著者紹介 公益財団実験動物中央研究所(理事長)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 3月 2013
生物工学会誌 第91巻 第3号
五十嵐 泰夫
日本生物工学会は創立90周年を迎え、昨年10月末には、記念式典・祝賀会に続き、記念大会が神戸において開催された。また、この行事の一環として、グリーンバイオテクノロジー関係の国際会議も開催され、さらに韓国の関連学会KSBBとの交流など、国際色豊かな記念大会となった。大阪大学の国際交流センターの活動と協働したアジアでの活発な活動が、生物工学会を特徴づけるものであることはいまさら言うまでもない。このような国際的な展開、特にアジア諸国との連携が、閉塞感漂うわが国の今後の歩むべき方向であることを強く感じた。この点で日本生物工学会は、日本の中で一歩も二歩も先をいっているということであろう。
わが国に色濃く漂う閉塞感、そしてそれを何とか打破して新たな時代を築かねければならないという焦燥感・危機感の中、私はこの3月末で大学を去ることになっている。以下の私の文章は、記念大会で歴代会長のことばとしてポスター掲示、および2号に掲載されたものと一部重複するが、定年を迎える研究者からの若い研究者へのエールの意味も込めて、敢えてまたここに書かせていただきたい。
現在、日本は老齢化社会を迎えている。私たち団塊の世代が年取ってなお元気でいれば、上をふさがれた若い人たちの閉塞感は益々深まるだろう。すでに時限雇用の博士研究員の数はバイオ分野だけで6000人程度に達しているといわれている。この数字は、パーマネントジョブについている団塊の世代が定年を迎えたとしても、とてもさばききれる人数ではない。企業の海外進出の必要性が叫ばれて久しいが、研究者もいよいよ海外、特にアジア地域へ本格的に進出することを本気で考えるときが来ているのではないだろうか。
しかしここでひとつ考えなければならないことがある。それは私がアジア諸国と関わりを持ち始めた30年前と今とでは、状況が大きく変わっているということである。アジア諸国は、現在、経済的にも学術的にも大きく発展・進歩している。以前のように「行ってやる、教えてやる」などという態度は、これからは通じにくくなる。すでに早くに経済的発展を始めたいくつかの国では、自前の科学研究費で独自に物事を進めようとする傾向が強まっている。もともと文化には優劣はない。あるのは違いだけである。基本的には対等の立場で接し、その中でどのようにイニシアチブやリーダーシップをとっていくか、このことが今後の大きな課題になると考える。
そのためには、何が必要であろうか。特に若い人たちに望みたいのは、自らの発想で自らの研究の道を切り開いていこうという気概である。もちろん自ら行なうことのできる研究には枠というか可能な範囲がある。どんなことでもやろうと思えばトライできるなどという境遇にある研究者はまずいないだろう。しかし、たとえグループの中で研究全体の一部を担当していようとも、自分自身の研究をしているという自覚を持って課題に立ち向かっていって欲しい。与えられた枠の中でいかに自分のオリジナリティ、個性を発揮するか、このことを若いうちから常に考えていて欲しいと思う。
たとえ、年を重ね、経験を重ねても、自分の自由な発想が持てないことは、研究者として不幸なことと考える。研究者にとって、常に自分の立ち位置、自分の存在意義をしっかりと認識していることが大切だと思う。そのアイデンティティを持つことによって初めて、閉塞感を打破し、研究者として多難な時代を生き抜く力を得ることができると信じている。オリジナリティやリーダーシップもそのような気概の中から生じてくるものだと思う。
ここに書いたことは、未完のまま終わろうとしている私の「集団微生物学・微生物社会学」から得たひとつの教訓でもあります。若い研究者の皆さんの奮闘を望むとともに、皆さんに明るく楽しい未来が待っていることを、心よりお祈りいたします。
著者紹介 東京大学農学生命科学研究科(教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 28 2月 2013
生物工学会誌 第91巻 第2号
塚本 芳昭
近年、組織の外部で生み出された知識を社内の経営資源と戦略的に組み合わせる、もしくは社内で活用されていない経営資源を外部で活用することによりイノベーションを引き起こす、いわゆるオープン・イノベーションに注目が集まっている。製薬をはじめとするライフイノベーションの分野では、大学やバイオベンチャー由来の新薬が増えており、大手製薬企業を中心に自社の求める技術領域などを対外的に公表し、アカデミア、バイオベンチャー、他の製薬企業などからの技術導入、共同研究の形成などを活発に行うようになってきている。バイオマスから燃料・化学品などの生産を目指すグリーンイノベーションの分野でも、最近はバイオベンチャーと大手化学企業、大手化学企業同士の提携により、その実用化を早める動きが活発化しつつある。
なぜ今オープン・イノベーションが注目されるのか? 従来、日本の多くの企業の研究開発は、初期の段階から自社で取組み実用化を目指すという自前主義が多かったように思われる。一方、今日のバイオ関係企業のおかれた環境は、関連のサイエンスの進展のスピードが速く、また実用化に至るまでの投資資金の増大により事業リスクが拡大しており、企業単独の努力のみでは世界との競争に勝てないという現実がある。加えて社内で実用化されずお蔵入りしている技術を他社に移転すれば時には収益に寄与することも考えられないわけではなく、こうした動きは財務面からも高まっていくものと思われる。
一般財団法人バイオインダストリー協会は日本製薬工業協会などバイオ関係団体とともに、毎年10月にBioJapanと称するイベントを開催している。同イベントは1986年から開催されているもので、初期はバイオテクノロジーの普及啓発に重点がおかれていたが、近年はビジネス創造にイベントの重点をシフトしてきている。特に昨年は世界水準のビジネスマッチングソフトを開発・導入したこともあり、アジア最大のビジネスマッチングの場に変貌した。対象領域は製薬、診断、医療機器、バイオフューエル・リファイナリー、機能性食品、植物工場などバイオの出口全般にわたる。技術移転・導入、共同研究、事業提携などを真剣に求めるバイオベンチャー、アカデミア、大手・中堅企業群が参加し、3日間の期間中に3400件のビジネスミーティングが行われた。その後多くの成果事例が出つつあり、オープン・イノベーションを実現する場となったわけである。
仕事柄欧米の国々の方々と面談する機会が多いが、近年特に懸念していることは欧米からの調査団が中国、インド、韓国などを訪問するものの日本を素通りするケースが多いということである。市場の発展のスピードを考えるとやむを得ないとも思うが、イノベーションを引き起こすパートナーとしてはアジアでは日本がアカデミア、企業ともに群を抜いているはずである。ただし、これらアジアの国々のバイオ関連産業の育成に注ぐ熱意と資金は並はずれたものがあるうえ、欧米での留学経験者などの帰国により、日本が優位性を保持するには相当の努力が必要であろう。我々バイオ産業界としては、アジアでイノベーションのパートナーを探すには日本に行かないと見つけられないと世界の人々に再認識されるようにBioJapanの活動をさらに本格化させ、我が国バイオ産業の本格的発展に結びつけることを考えている。日本生物工学会所属のアカデミア、企業の方々には本年10月に横浜で開催予定BioJapan2013に是非ご参加いただき、ともに日本のバイオ産業の発展と雇用の創出に向けて活動いただければ幸いである。
著者紹介 一般財団法人バイオインダストリー協会(専務理事)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 1月 2013
生物工学会誌 第91巻 第1号
副会長 柳 謙三
皆様新年おめでとうございます。昨年の創立90周年記念大会にご参加戴いた方、ご寄附を戴いた方、大会を表裏に支えて戴いた方、皆様誠に有難うございました。学会も次の100周年を視野に活動する新しい年となりました。振り返ればCPUの2000年問題に始まった21世紀も早や最初の10年を終え、2nd Decadeも3年目に入りました。この十数年間世界の政治経済や社会は大きくChangeしている中、日本は停滞、相変わらずの相対的な後退状態と世界から見られています。
18世紀後半から19世紀に英国で起こった産業革命はベルギー、仏、独、米国、日本へとグローバルに伝播し、その恩恵で、マクロに見れば20世紀の世界は19世紀の人々の「願いや思い」が実現した世紀でした(ただし、戦争を除けば)。空を飛びたい、宇宙へ行きたい、より早く移動したい、病気をなくしたい等々、人々の熱い思いや意志がまず有ったことが、数々の革命的な科学技術の発展につながっていると考えます。もちろん、物事には光と影の様に両義性があり、手放しで社会に貢献したものばかりとは言えませんが、総じて、 世の中に役に立ち、人々に享受され、我々は先人達のその努力の恩恵を、強く受けていると言えます。さて、 この21世紀はどのような世紀になるのでしょうか?
20世紀後半に生まれた第二の産業革命といえるMicroprocessorの発明を含め、さまざまな発明や応用により、現在グローバル化やスピード化が急速に進んでいます。ある経営学部の先生の言では、スマートフォンなどはまるでブラックホールだと。つまり、電話機、計算機、ウォークマン、録音機、ゲーム機といったものがすでに絶滅危惧種になるほど次々に吸い込んでいってしまうと。それだけ革命的な技術と言えます。バイオの世界ではiPS細胞の発明もこのようなコアになる技術でしょう。生命科学や健康・医療の世界だけでなく、バイオエネルギーや環境バイオも、またナノテクやナノバイオのバイオミメティクス(生体模倣)技術も大きな可能性を秘めていると言えます。これらは21世紀の人々の「夢や願い」を適えるために大いに期待されていると言えるでしょう。その実現を支えるのは現在およびこれからの研究者・技術者であると確信しています。ただ、現在でも生命とは何か?物質とは?宇宙とは?の根源的未知な問題、現象は存在するがメカニズムは未解明な事柄は未だ多く、科学技術はまだまだ未熟であるとの基本的な認識が必要でしょう。
やるべき事、可能性は沢山あるということです。その上で、21世紀のこれから、ますます異分野間の連携や融合が必要であり、自然や生物・微生物に学ぶことがその未熟さの解明の戦略となると言われています。その際、バイオテクノロジーと生物工学を標榜する本学会が、学と学、産と学、学と社会との出合い、研究者と技術者の出合いや切磋琢磨を一つの場として提供できる学会として社会に貢献していくこと、それが学会のミッションの一つであるのではないでしょうか?
100周年に向かって、国際化、産学連携、若手育成などの基本方針に沿い、この10年間に試行錯誤はあっても、具体的戦略・戦術を立てて、一歩一歩実行していくことが肝要です。中でも若い研究者・技術者の育成・成長や努力こそが不可欠であり、これからの学会にとって必要なものでしょう。これからを担う人に言いたい。21世紀は皆様のもの、大いに「WillとVision(意志と発想)」を持って多いにWorkして戴きたい。ど真ん中も大事だけどニッチの世界にも目を向け 「No.1よりOnly 1 !」。明日は好むと好まざるとの拘わらず、いずれ現実となります。さらに乱暴に言えば「自信溢るる自己流は確信なき正統流に優る」と。大いに自信を持って進んでもらいたいものです。21世紀の人々の為、国際社会の為、これからの日本の為、学会の100周年の為、これからの10年が有意義なものとなる よう、危機感と大いなる努力と期待を持って進みましょう!
著者紹介 元サントリーホールディングス常務取締役、前サントリー生命科学財団理事長
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 25 12月 2012
生物工学会誌 第90巻 第12号
奥田 徹
ドイツ中央に位置するアイゼナハは、中世の古城、ユネスコ世界文化遺産のワルトブルク城があるところとして名高い。この城は11世紀に建設されたとされ、13世紀には、ヴォルフラム・エッシェンバッハなど吟遊詩人たちが歌合戦で活躍するが、伝説的な聖女エリザベートが登場するのもこの頃だ。この歌合戦を題材にしたオペラがワーグナーの『タンホイザーとワルトブルクの歌合戦』である。ワルトブルク城には壮麗な祝宴の間(歌合戦の間)があり、現在コンサートホールとしても使われている。実は19世紀初頭、ドイツ統一の機運が高まり、荒れ果てた中世の城が、1838年に再建され、祝宴の間には19世紀の目で見た理想的な中世が再現された。1867年、バイエルン国王ルートヴィヒ2世は、ワーグナーの助言に従ってこの部屋を見学し、そっくり真似た歌合戦の間をノイシュヴァンシュタイン城内に作った。ワーグナーは、19世紀の視点で、『タンホイザー』を作曲したわけである。
さて、分子系統学のおかげで生物の系統進化の理解は革命的に進歩し、生物の系統樹は大きく変わった。1968年のWhittakerの5界説では、バクテリアなどを含むモネラ界の上に原生動物界があり、そこから動物界、植物界、菌界が「進化」したとなっていたが、現在では、Woeseらによるバクテリア、アーキア、真核生物の3ドメイン説が定説になり、かつては「下等生物」と呼ばれたバクテリアや原生動物も、ターミナル・クレード(terminal clade)に位置する生物で動物・植物・菌類と同等と評価されている。つまり現存する生物はいずれも、現時点での進化の最終産物であり、動物や植物が現在のバクテリアや原生動物から進化したわけではない。
系統樹の過去の分岐点の生物の、一部の機能は推定できても、化石に形態の一面が残ることはあるだろうが、過去の生物の姿そのものを見ることはできない。現存生物はあくまで現在の姿である。さらに、分子系統学によって、系統樹のクレードの隙間が大きいところと密なところがあるのも判明した。事実、隙間を埋める大きな新分類群も次々と発見されつつあるが、大きな隙間には、培養できない微生物も存在するかもしれないし、絶滅した分類群が該当することもあるだろう。生物の理解には、現在という一断面だけではなく、時間的評価が必要である。
三中信宏は「進化生物学がたどってきた歴史を振り返るとき、私たちはある1つの学問領域を支えてきた思想的基盤が、もっと現実的な人脈ネットワークや組織体制、さらには時代背景や社会・文化までせおっていることを痛感する。(中略)生物の系統樹と同様に、学問もまた伸び続ける一本の『樹』であるとみなすならば、ある時空的断面で切ったときの『切り口』はそのつど違って見えるはずだ」と述べている。生物学教育においても、最新の技術的側面だけではなく、そこに至った歴史的過程を理解しなければ、付け焼き刃にしかならず、生物の真の理解には至らない。
生物の理解とは、生物そのものの姿・形+機能+遺伝子情報と置き換えてもよい。昨今わが国の生物学教育の分野では、「もはやメンデルから語らなくても、遺伝はDNAで説明がつく」と極論され、歴史的背景なしで、技術面のみが重視されようとしている。また海外では生物多様性条約ならびに生物資源がますます脚光を浴びているが、2010年の名古屋における締約国会議を境に、わが国におけるこの問題は下火になっている。
さらに、昨年の植物命名規約の大幅改訂に関連して、オランダ、アメリカ、そして中国では微生物データベースの重要性が高まっているにもかかわらず、わが国は官民問わず興味がなさそうである。わが国の強み、他国には真似のできない緻密なバイオ産業の協業システムを新しい形で構築するには、予算を湯水のように使うようなアメリカ追従ではなく、生物学の歴史的断面と生物の総合的理解を目指した細やかな教育と研究が必要である。
昨年来のバイロイト音楽祭の『タンホイザー』は、ワーグナーが文明批判、科学技術批判を行ったことがあるということを受けて、巡礼は炭鉱(?)労働者、舞台は大きなバイオガス・タンクの並ぶ化学プラントという演出だ。音楽の美しさ・壮麗さとは打って変わって、歌詞と歌手の演技が正反対であるという矛盾や奇妙さはあったが、主張の妥当性はともかく、産業革命による大気汚染、新しい鉄道交通網による自然破壊など19世紀の目を現代の目に投影させることには成功していた。
著者紹介 玉川大学学術研究所菌学応用研究センター(教授・主任)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 26 11月 2012
生物工学会誌 第90巻 第11号
島田 裕司
三人寄れば文殊の知恵、三人にして迷うことなしといった諺にもあるように、古くから連携の有効性は認識されている。実際、ものづくり産業界でも、さまざまな素材を使って材料が作られ、その材料を使って部品が作られ、いろいろな部品を集めて製品が作られるというピラミッド型の供給網が整備され、連携体制が構築されている。また、委託加工や委託生産も積極的に進められ、最近では流通業界まで巻き込んだPB商品も作られるようになり、生産効率を高めるための連携は定着してきた感がする。一方、最先端技術や高付加価値製品などの開発を目的とした連携は、行政施策の下で積極的に進められているものの、企業、特に連携をもっとも必要としている中小企業には意外と浸透していない。
最近のものづくり産業界では新製品の開発に必要な技術はますます専門化する一方、ボーダーレス化という、相反する方向にも進んでいる。当然、開発にかかる経費は飛躍的に上昇し、そのリスクも大きくなっている。この経費とリスクの低減化を図るために、大学や公的研究機関が活用されているが、連携事業の推進も有効なツールである。同じ専門領域の人が集まって高度な技術を作り出す縦の連携と、異分野の人が集まって新しい技術を作り出す横の連携が組み合わさったときにもっとも大きな効果が期待できる。
新技術、新製品の開発を目的とした連携事業は行政の下でたくさん企画されているものの、ものづくり企業における開発研究の観点からみると大きな成果は挙がっていない。その原因は、とにかく連携という体制を作っておけばよいというトップダウン型の課題設定とコンソーシアムの構築にあったと思われる。連携事業が成果を挙げるために一番大切なことは、明確で具体的な目標を定めた課題の設定である。次いで、連携を構築するパートナーの構成が重要である。
通常、一つの組織だけで目的を達成することができないから連携を求める。そのパートナーとして、目的の達成に必要な技術や材料を持っている企業を探す。当然より高い技術、より優れた材料を持つ企業が選択される。ところが、もし対象となる技術や材料を保有している企業が1社だけであるなら、選択の余地なくその企業がパートナーとして選ばれる。したがって、研究開発の一手段として連携というツールも考えるなら、他社にはない独自の技術を持ち、ナンバーワン、オンリーワンの材料や部品を提供できる企業を目指すことが重要となる。
このように考えると、組織においてどのような人材を育てるべきかが見えてくる。広い視野に立ち、かつ最先端の知識、経験、技術を持った人材が理想的であることはいうまでもない。しかし、連携を研究開発の一つのツールとするなら、限定された分野を得意とする人達を集めることによっても目的を達成できる。つまり、この分野では誰にも負けない、この技術は私しか持っていないといえる人材、加えてチームでも力が発揮できる人材を育てることも必要となってくる。
大量生産、大量消費に支えられた科学技術の発展は人類に大きな豊さと繁栄をもたらした半面、化石資源の浪費、地球環境の破壊という負の遺産も残してしまった。今後は持続可能な社会の構築を目指さなければならず、自然エネルギーの活用、省エネルギー、未利用資源の活用、廃棄物の減量と再資源化、長寿命化などをキーワードとした研究開発が求められている。また、生物工学の分野においては、環境調和型、再生可能な資源(生物資源)の活用、再生可能な製造・加工技術(生物反応)の確立が強く求められている。ものづくり産業界に共通したこれらの課題については連携体制も構築しやすく、研究開発の一つのツールとして連携事業はより一般化してくるように思われる。この大きな流れに乗り遅れないためにも、今後の企業の在り方を考慮しながら人材育成に取り組む必要があると感じている。
著者紹介 岡村製油(株)取締役 商品企画開発室長・前(地独)大阪市立工業研究所理事長
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 27 10月 2012
生物工学会誌 第90巻 第10号
中西 透
昨秋、ある文化系の英才に「バイオで無から有ができるか」と言われた。この問いには、喧伝されているバイオへの期待と、(新産業が出てこないという)少々の失望が含まれていた。「バイオ産業勃興のタイムラグである。バイオ医薬品の創出、農業用植物の育種では成果が出ている」(JBA・大石会長就任挨拶)。ほぼ同感する。
今から50年前、戦中から続いていたアルコールとアセトン・ブタノールの発酵生産、後者は、戦後17年で石油化学製造法に切り替わった。しかし、アルコール、パン酵母、有機酸、抗生物質、抗がん物質、生理活性物質、酵素類、続いて、戦後、日本で発明されたアミノ酸発酵、呈味核酸発酵が、次々と工場で実施され、発酵タンクと関連設備は、数、容量共に拡大を続けていた。正に盛況であり、我々は、微生物による発酵工業に大きな可能性を感じていた。現在は、バルク物質の生産の多くは海外で行われている。わが国では、医薬品、機能性食品など、量的には少なくて比較的に高価なものの生物発酵生産が実施されている。
筆者は、上の質問に「できる」と答えた。相当するのは(価値のかなり低いものから価値のあるものをつくる)、光合成・炭酸固定、食品・有機廃棄物処理、バイオマスなどである。炭酸固定では、五十嵐・石井先生らの報告があり、今後の進展が待たれる(五十嵐泰夫:微生物炭酸固定の多様性とその進化生化学的理解(科学研究費補助金研究成果報告書2010年5月28日現在))。
光合成については当会に研究部会があり、本誌2011年3月号には特集があった。これによると光合成生物のいろいろな分野での応用が述べられている。現今、もっとも勢いがあるのは、「微細藻類によるバイオ燃料の生産研究」であり、今では多くの企業がパイロットプラントで研究を進めている。友人の話によると、プラントでは、対二酸化炭素収率や光の効率向上を含めて、エンジニアリングが非常に重要であるとのこと。微生物学者と化学工学者との協力によって、はじめて生産研究が進展すると共感する。世界各国でも盛んに研究が行われているが、米国が先行している。現在では日本も光合成微細藻類の能力のある面では、米国を凌駕しているようである。早く実用化されることを望む。なお日本では、二酸化炭素からだけではなく、有機廃棄物から微細藻類が炭化水素を効率良くつくる研究もある。
光合成微生物からは、DHA、アスタキサンチン、5-アミノレブリン酸など、生理的に有用な物質が実用生産されている。燃料を収穫した後の微細藻類菌体は、飼料や食品としての利用が当然考えられる。しかし「藻類」からは、まだまだ実効のある機能性食品、抗がん物質、医薬品などが見いだされる可能性があり、夢がある。
食品廃棄物、有機廃棄物の高度利用、そして特にバイオマスについては、本会の先生方は活発に研究しておられる。まだまだ研究することはあるにしても、我が国の実情に応じて、どのようにして実用に移行するかが課題であろう。昨年の本学会大会発表の26題のトピックスは、いずれもすばらしかった。このような研究成果同士の融合からより大きな発明が生まれてくるかもしれない。
これまで、バイオ産業での大発明の多くは、その端緒は少数精鋭によってなされた。企業は、これをスケールアップして工場生産するために多くの人を投じた。今後も大きな発明で、個人の力量、感性、そして努力は、大変大切である。しかし現在、バイオ研究も巨大化し、専門化してきた。今後の大発明は、従前よりも多い人数の精鋭の研究員同士のチームワークによって、より早くなされると考える。すなわち良い組織をつくり、これを創造的に機能させることである。当然、組織の中で、リーダーの役割は重要である。構成員は同質の研究員同士よりも、テーマによっては専門分野の多少異なる研究員間の組み合わせがよい場合もあろう。
第三者にバイオを「分からせる」のは非常に難しい。筆者の言う「分からせる」には、二通りある。1つは、バイオ各分野での研究員同士の相互理解である。バイオも専門化しきたので、たとえば代謝生理学の研究員が生物情報工学の最先端の報告をすぐに理解するのは困難であろう。この場合、報告する方にも、一工夫をしていただき、理解する側も合理的に努力されることである。もう1つは、市民に対する「分からせる」である。メディアなどを通じての「現代のバイオ」のやさしい解説があればと思う。そうすれば、バイオに対する世論もよい方向に盛り上がってきて、研究も進めやすくなると考える。
著者紹介 日本クエン酸サイクル研究会副会長
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 27 9月 2012
生物工学会誌 第90巻 第9号
杉山 政則
我が国では「食品」による健康維持や疾病予防への関心がかなり高く、2011年3月の東日本大震災が発端となった放射性物質による汚染問題もあって、安心で安全な食品や保健機能性食品を求める意識が強くなっている。一方、世界最長寿国である日本の医療費は増加し続けており、予防・未病医療への機能性食品の活用を通じて医療費を抑制しようとする動きもある。
第2次小泉内閣当時に提出された中央教育審議会の答申、「我が国の高等教育の将来像」は、大学のめざす方向に大きな変化を与えることとなった。その背景としては、大学が地域の要望に耳を傾け、地域と連携し、得られた成果を大学自身の教育研究活動に活かそうとする考えを持たない限り、社会から遊離してしまうとの危機感を持ったからであろう。そのため、この答申では、「教育と研究」に加えて,「社会貢献」を大学の第三の使命とした。
文部科学省は、関連する施策として「知的クラスター創成事業」を立ち上げ、産学官連携で地域産業を活性化するためのプロジェクト研究を公募した。広島県が提案した「広島バイオクラスター」計画は2002年に採択され、植物乳酸菌の基礎研究とその有効利用技術の開発をめざした「杉山プロジェクト」は2003年からスタートし、2007年3月まで実施された。
本プロジェクトにおいて、「酒粕中に植物乳酸菌増殖促進因子を見いだした」ことがきっかけとなり、植物乳酸菌の保健機能性と醗酵技術を活用して10種類程度の機能性食品が商品化された。この実績を踏まえ、さらに、2008年4月から2011年3月まで文部科学省・都市エリア産学官連携促進事業(発展型)・杉山プロジェクトが推進された。そこでは、600株を超える新規植物乳酸菌の探索分離と、有用植物乳酸菌の機能解析およびその活用による保健機能性製品の開発に加え、我が国の醸造産業に不可欠な「麹菌」が持つ新たな生物機能の発見などを通じ、生活習慣病の予防改善をターゲットとした保健機能性製品を創出するための技術開発を目標とした。すでに広島大学を出願人として複数の特許を申請し、そのうちの幾つかに関して特許を取得している。
一方、杉山プロジェクト参加企業との産学連携製品の販売に係るアライアンス戦略として、大学と企業との産学連携製品であることを示すとともに、それを販売に生かす方策として、『BioUniv.(ビオ・ユニブ)』ブランドとロゴマークを定め、広島大学が出願人となって、そのロゴマークを商標登録した。これを踏まえ、都市エリア事業のミッションの1つとして創立した大学発ベンチャー『(株)植物乳酸菌研究所』では、植物乳酸菌の有効利用技術の開発に加えて、杉山プロジェクトの研究成果から生み出された特許やノウハウ技術の実施許諾、およびBioUniv.ブランドの使用権許諾および管理などを業務内容としている。
初代の代表取締役社長には、広島の製パン会社の元専務取締役を迎え、プロジェクトの研究代表者である著者は、代表権を持つ研究開発担当の取締役に就任した。現在は、マツダ株式会社の元副社長で、広島バイオクラスターの事業総括を務めた高橋昭八郎氏を二代目代表取締役社長として迎え、海外展開を含めた事業化を戦略的に進めている。さらに、食品の保健機能性を臨床評価するための『臨床評価・予防医学プロジェクト研究センター』を大学院医歯薬保健学総合研究科内に設置し、今や3500名を超えるボランティアと広島大学病院の医師の協力のもと、食品のヒト臨床試験を受託している。
放線菌の分子生物学的な研究は、40年近く進めてきた筆者のライフワークとして、新たなパラダイムの創出をめざしている。一方、植物乳酸菌と麹菌の生物機能開発は、事業化に直結した研究であり、酒どころ広島の醸造・食品産業の活性化にも結びつけられるので、きわめて意義深いものと感じている。最近、韓国、シンガポール、タイ、台湾、米国などの企業からも、植物乳酸菌の保健機能性に興味を持っているとの連絡を受け、広島大学社会連携推進機構の協力の下、その具体化に向けた施策を練っている.筆者自身、教育研究活動はもちろんのこと、大学の第三の使命を果たすためにも、新たなバラダイムの創出と研究成果の社会への還元を努力目標として、微生物の特異的機能の解明と有用微生物の活用技術の開発をバランスよく進めていこうと思う。
なお、植物乳酸菌に関する研究で、平成20年度の科学技術賞(文部科学大臣表彰)と栄養科学分野の国際論文賞(第14回John M. Kinney賞:2012年)を受賞した。
著者紹介 広島大学大学院医歯薬保健学研究院(薬学部長・教授)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
新着情報
Published by 学会事務局 on 26 8月 2012
生物工学会誌 第90巻 第8号
牧野 圭祐
昨年は東日本における大震災、大津波、原子力発電所事故等々で深刻な被災が発生しました。被災された方々には一刻も早い復興を心からお祈りするばかりでありますが、最近では温暖化による影響も深刻さを増し、たとえばゲリラ豪雨や突然の竜巻による大規模な被害が報道されており、人類の生活環境の変化がもたらした自然災害による深刻な事態はいつも気になるところです。研究者としては3年余り前に定年を迎えましたが、持っております知識が何か社会に役立つことができればと心から思っております。
今の仕事は京都大学における産学連携事業の遂行です。ここでは、この事業を司る「産官学連携本部」の内容について紹介します。本学では、2001年、他大学に遅れながら当該本部前身の国際融合創造センターが誕生しました。「事業の基礎は組織なり」の鉄則に従い、今日の組織に至るまでに数回の脱皮を繰り返し、走りながら考えてきました。準備周到に我が国の産学連携活動のお手本を作られた諸先輩大学とは異なる点です。本学は、古くは産学連携の苦手なあるいは嫌いな大学として誤解されがちでしたが、この10年でずいぶん様変わりし、今では立派に先頭グループの一員になったと思いますので、我々の産学連携の最近の動向やこれからの計画を紹介することにします。
いうまでもなく、産学連携事業は、教育・研究に次ぐ大学第三番目のミッションである「社会貢献」の主な事業の一つとして、多様な分野における研究成果をもって社会に貢献することを目的としており、同時に活動が教育・研究に相乗効果をもたらすことが肝要であります。大学が研究結果によってビジネスを行うことは論外であり、産官学連携本部の業務は大学の研究成果を広く社会で活用していただくための橋渡しであろうと考えております。10年余の試行錯誤の中で得た結論として、産学連携事業は、基本特許の開発・育成・ライセンス契約あるいは譲渡・ベンチャー起業と育成、そして産業界との共同研究の推進、の二つに絞られる、と考えます。
前者に関しては、昨年度知財ライセンス収入などが250万ドルを超え、米国の優秀な大学の収入と比較できる額に達したことが特筆すべきことかと思いますが、今後の努力目標としては、当然のことですが、本学発の基本特許によるベンチャー起業・育成があげられます。この点は他の国々に比べて我が国のもっとも苦手とする課題ですが、これに関しては国際連携ネットワークの活用がもっとも効果的な手段であると考え、試行錯誤して案を練り実行に移そうとしております。またこれにも増して重要なことは、ベンチャー起業に興味をもつ若い世代を育てることと特に我が国には少ないentrepreneur(事業家)の投資への興味を引き起こすことであると考え、ここ数年地道に教育システムの充実に努めてきました。数年前には数名の学生しかいなかった起業に関する授業が今や500名余の受講生を抱えるようになり、学生諸君の就職に対する意識改革が進んできたと考えています。加えて色々な試みを行っておりますが、詳しくはまたの機会に紹介したいと思います。
後者に関しては、私どもがこの4年の間に全力を挙げて注力してきた国際連携ネットワーク作りが功を奏し始めたのでしょうか、国内の企業に加えて欧米の大企業からの大型プロジェクトに関するアプローチが急増してきたことが特徴かと思います。中国や韓国に目を奪われていた欧米が我が国の大学の技術開発力に再度注目し始めており、このような新しいトレンドが生まれつつあるのでしょう。彼らと話をする中で、「グローバリゼーション」と「オープンイノベーション」が急速に進展していると実感しております。
日本企業の強みであった基礎・応用研究の一体化した開発力に急速な陰りが見え、団塊の世代に続く企業人の自力での開発力の低下が目立つ昨今、大学の持つ基礎研究力の応用は今後の国家存亡のカギを握っており、大学の第三のミッションを現実のものとすることこそ社会への最大の貢献であるかと思っております。
著者紹介 京都大学産官学連携本部(本部長)
►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧
⇒生物工学会誌90巻8号
新着情報
Next »


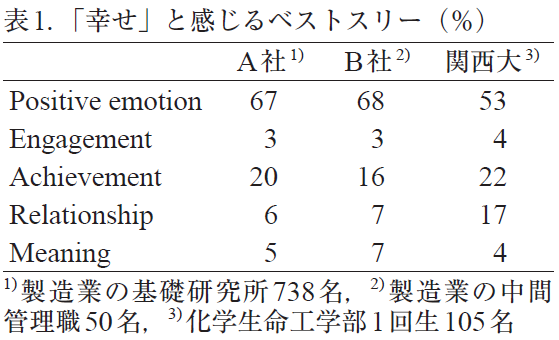 これらに加えて、私たち研究者・技術者は一般の人たちに比べてMeaningを得る機会に恵まれていることにお気づきでしょうか。自分の強みを活かして誰もが価値を認める安全・安心・健康・福利に貢献することができるからです。成果を論文化したり製品化したりすることだけで満足せず、自分の経験・知識・スキルで何に貢献できるかを考えてみませんか?そうすれば、皆さんの幸福度は間違いなく高まるはずです。筆者のMeaning?それは本稿によって皆さんの気づきに貢献できることです。
これらに加えて、私たち研究者・技術者は一般の人たちに比べてMeaningを得る機会に恵まれていることにお気づきでしょうか。自分の強みを活かして誰もが価値を認める安全・安心・健康・福利に貢献することができるからです。成果を論文化したり製品化したりすることだけで満足せず、自分の経験・知識・スキルで何に貢献できるかを考えてみませんか?そうすれば、皆さんの幸福度は間違いなく高まるはずです。筆者のMeaning?それは本稿によって皆さんの気づきに貢献できることです。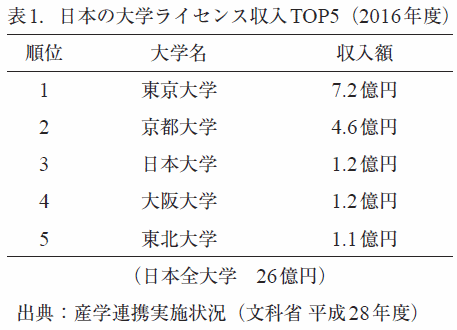
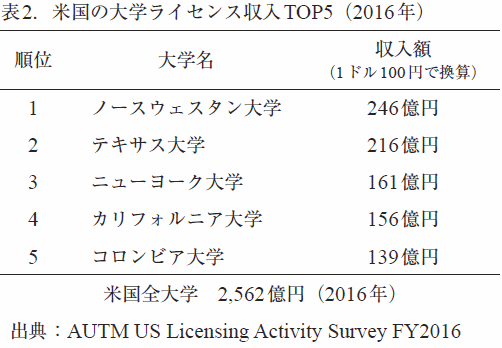
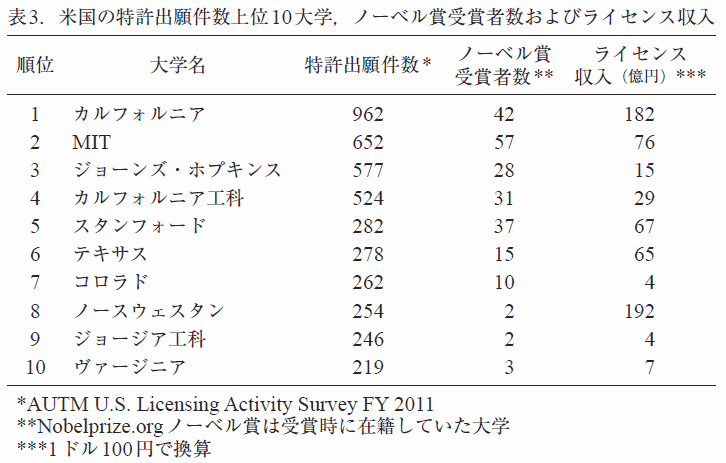


.gif)